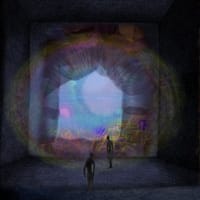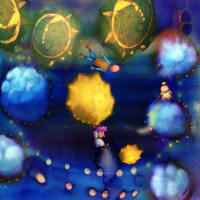「染み入れ、我が涙、巌にーなみだ石の伝説」第2回
作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所
第2回
僕は、いま 1975年ー昭和50年ーの思い出の中にいる。
正直にいうと実は、「なみだ石」を一つ持っているのだ。
東京へでてからの僕は人づきあいの悪い人間だった。
特異な風貌、まるで禁欲的な僧侶にみえた。
なみはずれた長身、それにどことなく体から発する毅然たる態度。
こんな僕でも恋はする。
その彼女、香月和子こうつきかずこに出会ったのは、去年1974年の十二月。仕事の関係で知り合った。
彼女の眼をみた僕ははっととする。
同じ種類の入間だ。
僕は彼女に必死で話しかけ、最後には彼女が同じ頭屋村の出だとわかった。幼ない頃、村を出た僕が知らないはずだった。
彼女と知り合い、それ以後私は彼女にひかれていた。
ずっと昔から彼女を愛しているように思えた。
それからの僕の行動は、あらゆることを投げすて、彼女に会うこと、
それがわびしかった生活をなぐさめる生きる力。
けれども、彼女にはどこか近づきがたいところがあった。
外見は20才くらいにみえるのだが。
僕と話をすると、僕がたちうちできほいほどの知識をもっていた。
まるで何百年もいきているように感じられた。
「あなたと同じようが寂しい眼をしている人々、この世の中
そう地球といってもいいわ、でやさし過ぎて生きてはいけない人々
をさがし、そんな人達を幸福にみちびいてあげるのが私なの」
ある時、彼女は私の眼をじっとのぞきこみながらいった。
「でも残念ながら、あなたは私達の仲間にはなれない」
「仲間だって」
「そう仲間よ。一緒に長い旅にてる仲間」
「旅?」
「私達、旅立つ日が近づいている」
彼女はさびしそく言う。
「二度と、、、
「会えなくなる」
「そんな」
「悲しい?。そう、、これをあげる」
彼女が僕にわたしてくれたのは、ちっぽけな石。
「これは何」
僕は立ちあがった彼女を見上げながらたずねた。
「なみだ石」
彼女は去っていった。
「なみだ石」 僕はつぶやく。
きらきら光るそのなみだ石をじっとながめる。
彼女のあとは追いかけなかった。
なみだ石、
聞いたことがある。その時はっきり思いだせなかった。
そうだ、ときずいた僕はさっそく下宿にとんでかえる
。もう一度、なみだ岩伝説の事を読みかえす。
そして、決心した。涙岩をみよう。
ふるさとへ帰ろう、、と。
そうそう,僕、日待明の道ずれについて話すのをわすれていた。
知り合いといっても最近知り合ったばかり。
彼。名前は滝光一郎という。いわゆるフリーターだと本人は言っている。
知り合いになった理由は、ほんの偶然で「なみだ石」をみせてしまったからなのだ。
滝はとてもおもしろい奴だったが、こと、なみだ石のことではしっこく聞き、とうとう一緒に「涙岩」を見るために、頭屋村までついてくることになった。
僕は滝を連れてきたくなかった。
他の地域の人間には見せたくないのだ。
が、滝は、不思議にあまりに執拗に食い下がった。
何があるのだ。
唯一の知り合いなので、無下にことわることができない。
「おい、日待よ、明よ。「カンタチ」駅、この駅じゃないのか」
色んなことを考えているうちに、やっとお目当ての駅にたどりついた。
駅の出札口で、駅員(といっても契約社員か)が、私達に話をしかけてきた。
「あんたら、東京の方からきなすったかね」
「ええ、そうですけれど」
僕が、答えた。
「いやな。感でいうたんだが、近頃、このーカ月の間に、このカンタチ駅で降りる人がたくさんふえてね。それであんたら神立山カンタチヤマの方へやっぱりいくかね」
「ええ、、、やっぱりの口ですな」
そらなという表情で
滝は答え、僕の顔を見てニヤリと笑った。
「へえ、仲間がいっぱいか。涙岩のことが知られているのか。雑誌でも紹介されたかな、さては」
僕は、僕でやはり、こない方がよかったかなあ、それにこの滝も、、と後悔しはじめる。
「いや、そんなことはないはずだよ。涙岩が、どんな新聞、雑誌にも記事になたったことがない。滝、君の方がよくしってるだろう」
「そうだな。神立山の方で他に何か祭事があるのか。まあ、いいや。あ、どうやらあそこがパス停らしいぞ。レンターカーはない?なにのだな。人口がないから、、商売にならんから、、か」
滝は、しゃべっている間、しきりにズボンの内ポケットの中に手をつっこんでいじりまわしている。
「滝、何を、そういらいらいじくりまわしている」
「いや何も」
こんどは、ジャケットの内ポケットに手をつっこんでいる。
「日待よ。これは俺の個人的な性癖ってやつだ。あまりつっくっ子無と友達なくすぞ。って俺しかいないか友達は、なあ明クンよ」
探し物か?僕はいぶかしく思った。内をそわそわ。
つまりは、僕の存在より、カンタチヤマへの手がかりとして僕に近づいてきた。という疑念が僕におこる。
とはゆえ、バスは、十人ほどの近くの村人達をのせて走りだす。
僕は彼女に頭屋村で会えそうな気がしてきた。
彼女に会いたい。
一目でいい。
あの人は頭屋材出身だといっていた。
駅員が神立山の方へ行く人がふえたと言っていた。ひよっと
してその中に彼女がはいっていないだろうか。
いや絶対に帰っているに違いないと僕は思った。
僕の、自分でいうのも何だが、このロマンスというか、純真さが後で大惨事を起こすとは。思っちゃいなかった。そして僕の人生も変えてしまうとは。
それは、この田舎バスから始まったのだ。
バスは、そう考えにふけっている僕を乗せ、
神立山へむかって坂を下りたり峠を上たり、森林を抜け走る。
あちこちに点在した人家がたまにみえる。しかしめづかしく、でこぼこ道だ。
あまり乗りごこちはよくない。
「日待、何かへんな気分だな。僕の方をみているようだ」
と、滝は、僕、日待明ひまちあきらの名前を気安く呼ぶ。
「気にするなよ。僕らのかっこが目立つからだろう・・」
「しかしだな。テレピというものがあるだろう。こいつら、テレビで東京の人間を見たことがないか」
「滝、いいわすれていたけれど、神立山の方は日本でめずらしく電気がとおっていない。だからもちろん、
テレビもみずらい。新聞・郵便物は1週間にまとめてだ」
「へえーー、まるで日本の秘境か、まだ日本にあったか、、だな」
滝がしゃぺった。
「あんたらも、神立山の方へいくだか」
後の座席から、急に声がしてびっくりした。後ろには、市外地の途中のバス停で降りたらしく、もう4人しかいない。
滝がふりかえって答えた。「ええ、そうですけれど」
僕も後を見る。後の方の座席に80才くらいの男の老人がちょこんと腰掛けて、僕たちの方をにらんでいる。
「僕は、頭屋村トウヤムラの出なんです。頭屋村へかえるんです」
僕が答えた。
「へえ,、そうかいね。,頭屋村のもん近頃、ようバスにのっとるで。また危ない」
「また頭屋村で人がようけいてなくなるやろらだろう・・」
「あんた、そのこというたらいかんがね」
老人の隣にいる老婆が、きつい調子でたしなめた。
「そうやったな。あのこと、を、しゃべったら、それも他の村のものがいうたら、タタリがあるの
やなあ。クワバラ、タワバラやは」
「おじいさん、ひょっとしたら涙岩伝説のことと違う」
滝がしゃぺった。
老人達は、しわい顔をしてだまりこむ。パスの中は、異様なふんいきだった。
やがて、老婆が訟もいきったようすでいった。
「そっちのにいちゃは、頭屋村の人だけど、いま、あのことをいったにんちゃは。村の人と違う
ようだね。そのことは、口にせん方が身のためだ」
「これや、これ」
今度は、老人の方が老婆をたしなめた。いっているのが聞こえてくる。
「ちえっ、しったことかいな」 滝が後を見ずに悪態をつく。
その老人達は、次のパス停で降りていった。残りの2人も山の中に点在するバス停で逃げるよう降りていった。
奥深い山の中を走るパスの中には僕たち二人だけ。
年の若いニキピづらの運転手が、バスを止め、座席から振り返り話しかけてきた。迷惑そうに、たづねる。
「あんたら、キクけどさ。本当に頭屋村までいくの?」
(続く)
作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所