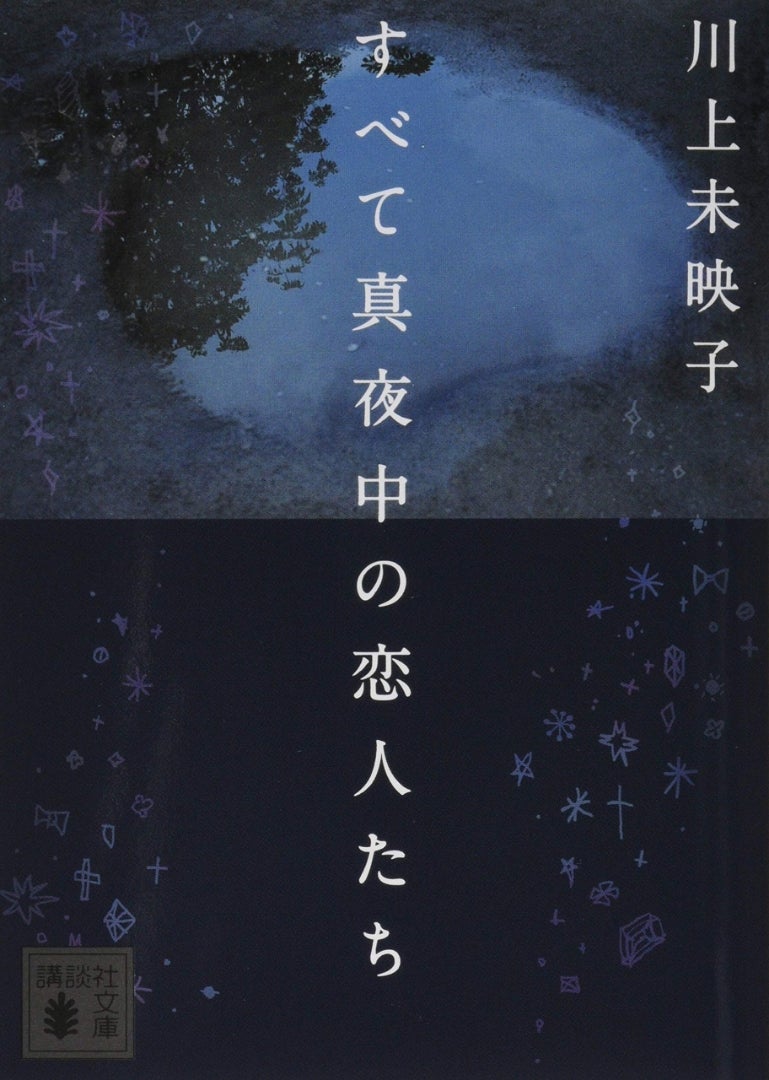『市役所で市民課長を務める渡辺勘治は、かつて持っていた仕事への熱情を忘れ去り、毎日書類の山を相手に黙々と判子を押すだけの無気力な日々を送っていた。市役所内部は縄張り意識で縛られ、住民の陳情は市役所や市議会の中でたらい回しにされるなど、形式主義がはびこっていた。』
『ある日、渡辺は体調不良のため休暇を取り、医師の診察を受ける。医師から軽い胃潰瘍だと告げられた渡辺は、実際には胃癌にかかっていると悟り、余命いくばくもないと考える。不意に訪れた死への不安などから、これまでの自分の人生の意味を見失った渡辺は、市役所を無断欠勤し、これまで貯めた金をおろして夜の街をさまよう。』
『そんな中、飲み屋で偶然知り合った小説家の案内でパチンコやダンスホール、ストリップショーなどを巡る。しかし、一時の放蕩も虚しさだけが残り、事情を知らない家族には白い目で見られるようになる。』
『その翌日、渡辺は市役所を辞めて玩具会社の工場内作業員に転職していようとしていた部下の小田切とよと偶然に行き合う。何度か食事をともにし、一緒に時間を過ごすうちに渡辺は若い彼女の奔放な生き方、その生命力に惹かれる。自分が胃癌であることを、とよに渡辺が伝えると、とよは自分が工場で作っている玩具を見せて「あなたも何か作ってみたら」といった。その言葉に心を動かされた渡辺は「まだできることがある」と気づき、次の日市役所に復帰する。』
『それから5か月が経ち、渡辺は死んだ。渡辺の通夜の席で、同僚たちが、役所に復帰したあとの渡辺の様子を語り始める。渡辺は復帰後、頭の固い役所の幹部らを相手に粘り強く働きかけ、ヤクザ者からの脅迫にも屈せず、ついに住民の要望だった公園を完成させ、雪の降る夜、完成した公園のブランコに揺られて息を引き取ったのだった。新公園の周辺に住む住民も焼香に訪れ、渡辺の遺影に泣いて感謝した。いたたまれなくなった助役など幹部たちが退出すると、市役所の同僚たちは実は常日頃から感じていた「お役所仕事」への疑問を吐き出し、口々に渡辺の功績を讃え、これまでの自分たちが行なってきたやり方の批判を始めた。』
『通夜の翌日。市役所では、通夜の席で渡辺を讃えていた同僚たちが新しい課長の下、相変わらずの「お役所仕事」を続けている。しかし、渡辺の創った新しい公園は、子供たちの笑い声で溢れていた。』
★★★★★