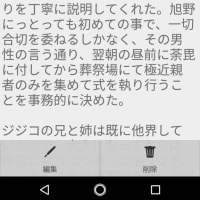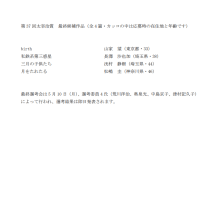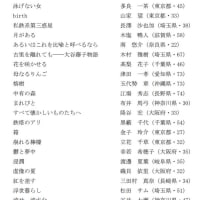僕は小さめのボストンバッグを右肩に掛けて約束の場所へと急いだ。駅前のトラファルガーストリートを5分ほど西へ,クイーンズロードを左に折れて更に5分ほど行くと右手に貴族の紋章の様な釣り下げ看板が目に入る。扉は開け放してあるから,通りにもバンドの生演奏の音が響き渡っていて,歩道の人も一瞬興味深げに中を覗き込んで確認する。自分も最初にここを訪れた時は同じような感じで,正直に言うと,ホーヴにあるブランズウィックというパブに比べれば居心地はよろしくない。それでもKing&Queenは大盛況の賑わいを見せていた。僕は約束通り彼らは来るのだろうかと半信半疑で身体半分入店させた状態で,まだ7時前だというのにパイントグラスを片手にご機嫌に語り合う人混みの中に2人の姿を探した。響き渡るサキソホンのフレーズに注意を奪われた途端,バンドの右手前のテーブルに陣取っているマシューが左手を高く上げて微笑みかけているのが目に入った。薄暗い店内で,マシューの丸眼鏡が,オレンジ色の照明を反射して白っぽく煌めいている。僕はバッグが誰かとぶつからないように精一杯の努力をしながら彼の方へ真っ直ぐ進んだ。もうひとつブランズウィックと明らかに違う点は,このパブには椅子付きのテーブルが何脚か並べてあって,のんびりとバンドの演奏を楽しむことができる様になっていることだ。僕はマシューの左横に雑に並んでいた椅子に腰掛け握手を交わしてから騒がしい音を嫌うようにマシューの耳元で尋ねた。
「ベンは?」
マシューは呆れた表情で肩をすくめがら,既に1/5程しか残っていない黒ビールを少しだけ口に含んだ。
バンドの女性ボーカルがドラムのハイハットのリズムに会わせて小刻みに身体を揺らしている様子が,スローな曲とギャップがありすぎて気になって眺めていると,突然肩をパンと小気味良く叩かれて身体を捩らせた僕の左側にベンが軽やかに座った。
「ソーヤン,大事な話があるんだ」
ベンはのっけから真剣な表情で切り出した。
「日本語で,“You’re so beautiful”って何て言うんだ」
「あぁ,それは“きみはきれいだ”だよ」
「きみわ・・・きれいだ」
「そうそう」
「OK」
ベンは,まるで戦車に爆弾でも落としに来た戦闘機みたいに,すぐさま立ち上がって通り側の隅の方へいそいそと姿を消した。
「いつもあんな感じ」
「あんな感じって?」
「女だよ。日本人が好きなんだ,アイツはね。特に日本人の女」
「あぁ,なるほど」
そもそも英語を学びに来たんだという思いで,学校で日本人を見つけても関わらない様にしていたこともあったが,僕のニックネームのせいか,どうやら日本人学生は僕の事を同胞とは思わないらしく,僕自身も常にアジャやイーゴたちと連んでいたから,その時まで余り日本人のことなんか気にならなかったけど,折しもその年は“JAPAN FESTIVAL”という催し物が全国的にあって,何だか日本人の存在感が急激に強まっている様な雰囲気もあった。
ぐるりと見回してみても,そこかしこに日本人らしき若者の何と多いことか。ここで「日本人らしき」と僕が言っているのは,これも海外留学すると実感することなのだが,服装や髪型,醸し出す雰囲気で中国人や韓国人と直感で区別できるということであって,それにはそれほど高い正確性が伴わないからだ。
すぐ後のテーブルに座るグループにも日本人が何人かいて,所謂“Japalish”(Janglishとも言うかもしれない)で一生懸命に会話をしている。
「なぁ,ソーヤン。アイツら何語話してるんだ?英語にも聞こえるけど・・・」
真剣な眼差しでその一行を観察するマシューの様子に僕は思わず吹き出した。そんなことには気も留めず,必死で英単語をカタカナで並べる日本人と,眉を顰めながらじっと凝視しているマシューの姿がこの上なく滑稽に見えたので僕は涙が出るほど笑って胸が苦しいほどだった。
「あれは英語だよ。英語」
「そんなばかな。全然わかんないぞ。オレってイギリス人だよな?」
マシューのジョーク,もしかすると真剣な感想だったのかもしれないが,僕は更に笑いが止まらなくなって死にそうなくらい大笑いした。そのうちマシューも愉快になってきたのか,2人で笑っていると,またベンが僕の肩を叩いた。
「“I love you”って何ていうんだ」
「ああ,それは・・・」
僕はアジャたちがイギリスを去って,円山さんが姿を消して以来,こんなに愉快に笑い転げた記憶がなくて,本当に何もかもがどうでもいいくらいに愉快で爽快な気持ちになっていたから,その時思いがけず悪戯心に支配されて,彼が真面目な顔で復唱する姿に笑いを堪えながら言い尽くせないほどの卑猥な日本語を3つ程教えて見送った後,マシューにそれを教えるとマシューも呼吸できないくらいに笑って,2人でベンの様子を観察しようと後を追いかけた。
ベンが向かったテーブルにはおとなしそうな日本人女性が2人座っていて,ベンはその前に立ちはだかると,なぜか人差し指で天井を指して僕が教えた禁止用語を大きな声で唱えたものだから,僕はマシューと一緒に肩を組んで爆笑した。女性たちが呆気にとられてニコリともせずベンを睨み付ける様子に異変を察したベンがゆっくりと僕たちの方を見た時の情けない顔といったら。僕たちは声を枯らして笑い続けた。すると僕たちの周りにいた見知らぬ人達までもが「何があったんだ」と言うほどの騒ぎになってしまい,マシューが気さくに説明するとあちこちで笑いが連鎖して,それに促される様にその日本人女性たちも笑った。僕は何だか煽られたみたいに再び笑いが混み上がってきて,ベンに謝りながら笑い続けると,ポカンと口を開けたまま自分が置かれている状況を把握できないかといった表情でアピールするベンの姿に観衆は笑いをそそられるのだった。
たかだか5分ほどのエピソードだったが,多くの人たちの幸福そうな笑顔と声と熱気に,深手を負った僕の傷心が癒やされていくのを一瞬でも感じることができたのは幸いだった。それに,この出来事のおかげで,ベンとマシューはその日本人女性たちと付き合うことになったし,マシューに至っては翌年に結婚まで漕ぎ着けたのだから,ベンに嘘を教えたことに対する罪悪感などは微塵も感じる必要はなかったんだ。