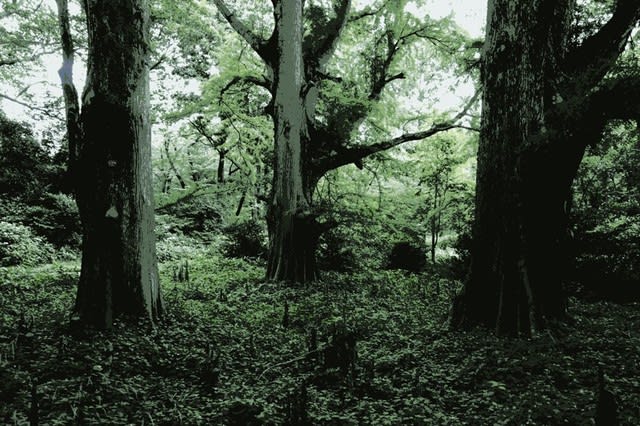
ラクンショウの森(新宿御苑)
このほど、黒川検事長が賭け麻雀で辞任して退職し、検察官の定年延長法案は廃案となり、この問題はもう過去のことになりつつある。しかし、菅官房長官は記者会見で「さまざまな意見があったことを踏まえ、再提出に向けて検討していきたい」と言っている。つまり、これで終わったわけではない。したがって、この問題について考えることは無駄ではないと思う。
この法案の要旨はつぎの通り。
① 検察官の定年を65歳に引き上げる。
② 次長検事と検事長は、63歳以降はヒラの検事になる。
③ 次長検事と検事長は、内閣が定めた事情がある場合、1年以内の期間、引き続き次長検事または検事長として仕事ができる。
④ さらに、1年後も引き続き内閣が定めた事情がある場合、引き続き定年まで次長検事または検事長として仕事ができる。
⑤ これらのことは内閣または法務大臣がそれぞれ決定する。
最も重要な点は、③、④、⑤である。その理由を以下に述べる。
まず、つぎのような事実(憶測ではない)を確認しておきたい。
森友、加計問題では、安倍首相がどのように、どこまで関与していたのかは証拠が隠滅されてしまったのでよってよくわかっていないが、つぎのことははっきりしている。
- 籠池泰典氏や加計孝太郎氏が大きな利益を得たこと。(籠池氏はその後、別件で逮捕され、有罪となって当初の利益を失った)
- 安倍昭恵夫人が森友学園が作る予定だった瑞穂の國記念小學院の名誉校長になっていたこと。
- 加計孝太郎氏は安倍首相がアメリカに留学していたときに知り合った「30年来の腹心の友(安倍首相の表現)」であったこと。
- 公文書の改ざんがあったこと。森友問題での、赤木俊夫さんの自死は、それが事実であることを自らの命でもって証明したとも言える。
桜を見る会での以下のようなことも否定できない事実である。
- 桜を見る会(「各界で功労・功績のあった方々を慰労する」首相主催の公的行事)で、山口県の安倍晋三後援会のメンバーなど安倍首相の支援者が大量に招待されていたこと。
- ホテルニューオータニで、上記支援者を中心に、会費5,000円/人で、前夜祭が行なわれたこと。(今でも、ホテルニューオータニは5,000円/人のパーティーなど受け付けない)
- 招待者名簿を野党が開示請求したところ、即刻廃棄処分したこと。
さらに、河井元法相夫妻の件を別にしても、安倍首相が任命した大臣たちについてつぎのようなことがあった。
- 甘利明氏(当時、内閣府特命担当大臣<経済財政政策>、経済再生担当、社会保障・税一体改革担当の国務大臣、TPP担当の国務大臣)が建設業者から現金(総額1,200万円)を受け取ったこと
- 建設業者が甘利氏に口利きを依頼し、その依頼が実現したこと。(上記金額には実現後に業者が渡した謝礼金も含まれる)
- 下村博文氏(当時、文科大臣)が加計学園から政治資金パーティー代として200万円を受け取り、それを政治資金収支報告書に記載していなかったこと。
- 甘利氏、下村氏共に、この件について説明すると約束しながら、いまだに何の説明もしないこと。
- 小渕優子氏(当時、経済産業相)が、関連政治団体の不明朗な収支を巡る問題の責任を取って辞任したこと。
- 松島みどり氏(当時、法務大臣)が、地元選挙区で討議資料として「うちわ」を配布した問題で辞任したこと。
- 菅原一秀氏(当時、経産相)が、公設秘書が選挙区内での支援者の通夜で2万円入りの香典袋を受付に手渡した問題で辞任したこと。
これらの事実は、公文書管理法違反、公職選挙法違反、あっせん利得処罰法違反、政治資金規正法違反、公金横領、その他の犯罪に関わるものであり、きちんと捜査をし、関係者を法律に従って処罰すべきものである。しかし、検察は、すべてを不起訴とし、裁判にかけることもしていない。その根拠は、起訴するに足る十分な証拠がないとのこと。つまり、裁判所にかける前に検察の判断だけで「無罪」とされたことになる。ここで、元検察官の郷原弁護士のつぎのようなことばが重みを持ってくる。
検察には検察のダイナミズムというものがあります。捜査によって証拠というものが動いていくんですね。ですから、検察がやるべき事件でもこれはやらない方向にしようと思えば、やるべき捜査をやらないで事件が立たないような消極的な証拠を集めればいいし、それでもし不起訴が不当だといって検察審査会に申し立てをされても、検察審査会の人も消極的な証拠を見たら、不起訴でもしょうがないなというようになる。これは、伊藤詩織さんが訴えた強姦の被害、どう考えても不起訴になるとは思えない事件でも、不起訴になってしまう。検察審査会の判断も「不起訴相当」でした。それは検察のアクションの中で、不起訴というものが相当だということが塗り固められていたからです。そのくらい、検察というのは、方針を決めれば最終的な判断を自分たちの思い通りにできる。それが検察の絶大な権限なんです。
現政権の応援団は、「批判するなら証拠を出せ!」とうそぶく。刑事事件のルポを数多く書いているノンフィクション作家の佐木隆三氏は、「『証拠を出せ!』と言うのは、犯罪者の常套句」という意味のこと言っている。たとえば、桜を見る会の件で、適切な人を招待していると言うのなら「招待者名簿」を提出すればよいだけの話である。ところが、野党からその提出を求められると即刻破棄してしまう。つまり、証拠を隠滅し、その後で「証拠を出せ!」と言うわけである。
たしかに「証拠」は重要である。だからこそ、その証拠を固めるため、検察には大きな権限が与えられている。証拠隠滅を防ぐため、迅速な家宅捜索、証拠品の押収、身柄確保、取り調べなどである。ところが、疑惑を追求している側(野党、マスコミ、その他の組織から個人まで)には、そのような権限がない。国会で、事件にとって重要な人物を証人として呼び、喚問しようとしても、疑惑を持たれている側(自民、公明)に拒否されてしまう。そして、「証拠がない」と言うのである。犯罪者が証拠を隠滅するのは当然と言えば当然である。
だから、検察がその本来の職分を果たさなければ、どれほど疑念があろうと、国民は黙って見ているほかないのだ。検察の不作為の前に、どんどんと証拠が隠滅されてゆくのを止めようがないのだ。政府側は、国会で連日疑惑を追求されても、文書の改ざん、廃棄によって証拠を隠滅し、情報開示請求にも請求者が知りたい部分を黒塗りして対応し、都合の悪いことは記憶にないことにし、すべて「法律に基づいて適法、適切な処理をした」と答弁するのみである。それで説明責任を果たしたことにしている。いまでは、後で追求されないように、議事録など決定過程の記録そのものを取らないというところまで来ている。そして、「文句があるなら証拠を示してみろ」と言うわけだ。これが、この国の現状である。
そして、今回の黒川検事長問題である。この検察の不作為に対して、黒川氏がどれほど関与しているのかはよくわからない。黒川氏が辞任した後、すぐに河井元法相夫妻が逮捕されているが、黒川氏の辞任とこの逮捕がどう結びついているかもよくわからない。しかし、黒川氏は検事長として検察内部では大きな権限を持っていたことは間違いない。また、数々の疑念が持たれている現政権は、黒川氏を「余人を以って代えがたい人」と評価し、前代未聞(法律違反:法相がその根拠を説明できない)の定年延長をしたが、そのことを考えれば、検察の現状に対して、「余人を以って代えがたい」影響力を持っていたのだと想像できる。
仮に、黒川氏がこの検察の不作為の原因だとするならば、この度の辞任によって問題は解決するはずである。彼の辞任によって、現政権のさまざまな疑惑についての捜査が開始され、関係者は起訴され、裁判にかけられ、処罰を受けることになる。果たしてそんなことになるのだろうか。河井元法相夫妻の逮捕がどういう力関係の中で実現したのかよくわからないのだが、たぶん本丸に捜査が及ぶことにはならないように思われる(予想がはずれれば嬉しいが)。黒川氏が辞任しても相変わらずだとすれば、いまの検察には、政権の不祥事を起訴しないことで何らかの利益を得る構造がすでにできている可能性がある。黒川氏もそういう構造の中で生まれてきたのかもしれない。だから、彼がいなくなっても彼の代わりに「余人を以って代えがたい」人をすぐに作り出せるのかもしれない。だから、形を変えて法案の再提出を検討しているのかもしれない。
黒川氏のことはおいて、そもそも、内閣が法律に基づいて堂々と検察人事を左右することができるようになってはならないこと、これははっきりしている。そんなことをすれば、その人事は内閣にとって有利な人事になることは火を見るよりも明らかである。「内閣が必要と認めたときは、その役職を延長できる」ということは、「必要かどうかは内閣が決める」ということである。疑惑だらけの政権がそのような法律を作ろうとしているならば、なおさら問題は大きい。検察組織に「役職を延長してまで留め置く必要がある特別な人」を作り出してはならないというのは検察組織の鉄則である。元検事の山尾しおり議員がつぎのように言っている。
検事時代、私は先輩から「検察組織は金太郎飴」と教わった。切っても切っても同じ顔が現れ「替えがきく」ことこそが検察庁の強みで、属人性がないことが検察庁の正義だと。
検察としての判断が、担当検察官の個人的属性によって変わるということは、起訴されるか不起訴になるかが担当検察官個人の思想信条によって変わるということになる。それは、検察制度そのものを、そして、法治国家そのものの根幹を揺るがす問題である。「法治国家」は、そして「法の下の平等」は、法の適用に当たり、法を運用する「人」の個人的な性質を排除することで成り立つ。同じ法律を適用するにあたり、どの検察官であっても、その判断は同じでなければならないのである。
黒川氏の定年延長にあたり、その理由として政府は「東京高検管内で遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応できない」からだと説明した。しかし、そういう事態が生じているということは、検察内部が不調になっているということであり、そのときに必要なことは、その不調を正し、もとの状態に戻すことである。病気を治すことである。そうであるのに、政府は「内閣が必要と認めたときは、その役職を延長できる」という法案を提出し、検察組織の病的状態を引き延ばせるようにしようとしたのである。すなわち「内閣が必要とする状態」を引き延ばせるようにしようとしたのである。この法案は、いったん廃案になったが、冒頭で紹介したように、菅官房長官は、「再提出に向けて検討していきたい」と言っている。だから、彼らはそうすることをあきらめてはいないのである。
検察は行政機関なのだから、行政機関を統べる内閣がその人事に関与するのは当然だと言う人もいる。しかし、検察は行政機関の不祥事をもみ消し、行政機関を守るための機関ではない。たとえそれが総理大臣であれ、違法行為を行えば、逮捕し、起訴し、裁判にかけるというのが検察の仕事である。それが法治国家における検察の役割である。もし、法律に基づいて内閣がその人事に関与し、自らにとって都合の良い人事ができることになれば、内閣の犯罪を、いったい誰が捜査し、起訴して裁判にかけることができるのだろう。「国民が選挙で」という言い方もできる。しかし、先に述べたように、国民に(新聞社やテレビ局も同じ)捜査権はなく、関係者を取り調べることもできないということを忘れてはならない。
検察がときの政権の犯罪を捜査し、起訴して裁判にかけることができなくなれば、その国は法治国家として成立しなくなる。いまの日本はすでにそうなりつつあるように見える。このような問題に目を向けることなく、単なる形式論として「検察は行政機関なのだから、行政機関を統べる内閣がその人事に関与するのは当然」と言って、現状を肯定していいのだろうか。
いったいこの政権は、どこまでこの国を壊してゆくのだろう。この政権からは、よくもまあつぎつぎと問題が出てくることか。つぎつぎと問題を起こし、それを常態化することによって、国民は過去の問題など忘れてゆくだろうという戦略があるのかもしれない。この政権はこの国をいったいどんな国にしたいのだろう。見えるのは、パソナ(竹中平蔵元経済財政担当相がその会長)や電通などの連中とつるんで、国から甘い汁を吸っている姿である。たとえば、いま話題となっている「サービスデザイン推進協議会」(このサイトがその実態について詳しい。実に怪しい組織である)は、2016年から5年間で、経済産業省から1,576億円の事業委託を受けている。新型コロナウィルスという国家的危機の渦中でも、政権と政商がつるんで大儲けを企んでいるように見える。この危機にあたっては、短期間に数十兆円、あるいはそれを上回るお金が動くので、たっぷりとうまい汁を吸えるということか。
官僚たちも、そんな彼らに協力すれば退職後も含めてよりよい地位、収入が得られるので、文書改ざん、隠蔽、廃棄、そして忖度などを平気でやるのだろう。赤木俊夫さんのように、まっとうな人はそれに耐えられず、自死を選んでしまったのだろう。彼らは、甘い汁をより吸い取りやすいように憲法、法律、制度を変えて吸い尽くし、この国が彼らにとって役に立たなくなれば、捨ててどこかに行くのだろう。彼らの財産の多くは国外のタックスヘイブンにあるという。タックスヘイブンは脱税のためだけではなく、国民を裏切って大儲けをした連中の国外逃亡用資金をプールしておくためにあるのかもしれない。そういう彼らが「お国のため」にどうだこうだと言うとき、気持ち悪さを越えた不気味さ恐ろしさが増すばかりである。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます