リエマニアさーん
いつも本当にありがとうございます
せっかくなので『私と歌とフルート』のことを
ご質問に対してのお答えとあわせて、ちょっとお話させていただきます
クラシックとジャズのフルートの違いですが、
まず、1ついえることは、気持ちの部分では、まったく境がありません


でも、「奏法」というか「表現の仕方」となると、
まったく変わってきます
というのも、ジャズというのはやってて思うのですが、
『スウィングしなけや意味ないね』のデューク・エリントンではありませんが、
かっこいい「ノリ」があってなんぼの音楽なんですね
そして、その「ノリ」というのは、リズム感とかはもちろんですが、
いろいろなもので成り立ってくるもので、
私の意識の中で分かりやすくいうと、
楽譜には記しきれない音符の長さや休符の長さ、裏拍、
もっといえば時には『味』になる程度の音程のズレ、
スラーやスタッカートなどのアーティキュレーションと呼ばれるものなど、
こういった色々な要素をどう表現するかが、
また「ノリ」につながっていくんだと思っています
メロディーさえも、アドリブによって、個人のプレイヤーが勝手に、
というか自由に解釈しても良い、とされている、
そういう意味ではすごく、ジャズはおおらかな音楽だと思うのです
それに対してクラシックというのは、譜面があって、
その楽譜通りの音符の長さ、休符の長さをきちんと守って、
スラーやスタッカートなども、基本的には書いたとおりに演奏する、
または、指揮者などの考えであえて変更されるものはあるにしても、
約束事が多いのはクラシックのほう。
オーケストラでも、基本はみんなでそろえる。
弦楽器の弓の動かし方すらも、そのときのコンサートマスターや
リーダーに合わせるほどですから
じゃあ、どっちがいいの?というのは、
「私と仕事と、どっちが大切なのよ!」というのと同じ?で(笑)
もちろん決められないことで、どちらにも良さがありますからね
でも、「郷に入っては従え」というやつで、
ジャズのときとクラシックのときと、
その辺を自分できちんと整理できた上で演奏しないといけないと思います
それが、その音楽を演奏させてもらう上での礼儀だと思うから
だから、クラシックとジャズを見事に融合させたガーシュインって、
本当にすごいなぁ~、と思います
あと、日本の偉大な音楽家で武満徹さんという方がいらっしゃいます
武満さんは大のジャズ好きでも知られていて、しかも
『デューク・エリントン』の大ファンだったのだとか
それも筋金入りで、奨学金でアメリカ留学するときに
「むこうで誰に師事したいか?」と聞かれ、当然、
質問したほうはクラシックの専門家の名前を挙げるだろうと
思っていたら、まじめな顔をして
「デューク・エリントンに習いたい。」
と答えられたんですって
その逆で、ジャズの大家も、
『ジャズ以外の音楽を聴かないで、ジャズが演奏できるか!』
と言って、クラシックや別の音楽を
たくさん聴いていたそうですし
だから偉大な音楽家ほど、「ジャンルなんていうのは便宜上のもの」
としてとらえていて、それぞれのジャンルや色々な国で生まれた
音楽に敬意を持って、そこに自分なりのエッセンスをどう薫らせるか?
ということに力を注いでこられたのかなぁ?なんて思います
1つの分野の音楽を深く掘り下げることは素晴しいことです
でも、「ジャズも好き!」「クラシックも好き!」「ポップスも好き!」と、
それぞれの音楽の持つ良さを、たくさん感じて受け入れられれば、
それも人生を豊かにすることなんじゃないかぁ~?とも思います
あと、ヴィブラートはそう言っていただいて本当に嬉しいです
実は私もいわゆる縮緬ビブラートは好みではありません。
でもジャズがお好きな方の中には「あれこそがジャズだ!」と
おっしゃられる方もいらっしゃいますが、私はそうは思いません。
好みの問題も大きいと思います
私は前にも書かせていただいたかもしれませんが、
クラシックのフルーティストで「マルセル・モイーズ」の本で、
『ヴィブラートというのは、音に命を吹き込むもの』というような
内容を読み、とても感動して、意識するようになりました
それによると、「ヴィブラートというのは感動する部分、
緊張する部分などでは、あたかも心臓の鼓動が激しくなるように
ヴィブラートも変化させなければならない。」のだそうです。
考えてみれば当たり前のことなのかもしれません。
どんな場面でも同じヴィブラートというのはやはり不自然だと思うのです。
ゆったりしているところであまりに速い振動 はやっぱり不自然ですし、
はやっぱり不自然ですし、
逆に速いパッセージでゆっ くりした波のヴィブラートも
くりした波のヴィブラートも
やっぱり不自然ですし
だから、ヴィブラートは立派な表現方法だと思っています
そしてそれは、歌でもフルートでも、ジャズでもクラシックでも、
変わらない考えです。その音楽に合った、その曲に合った
方法で、自分なりに、演奏しているつもりです
長くなってしまいましたが、そういった意味で、
気持ちの上では、たとえどのジャンルでも基本的なものは変わらないし、
でも、奏法などは変わる、という理由です!
それにしても夕方5時でも明るい
日が伸びましたねー?
3連休、ETCで明石海峡、渡ってみたいなぁ~(笑)

いつも本当にありがとうございます

せっかくなので『私と歌とフルート』のことを
ご質問に対してのお答えとあわせて、ちょっとお話させていただきます

クラシックとジャズのフルートの違いですが、
まず、1ついえることは、気持ちの部分では、まったく境がありません



でも、「奏法」というか「表現の仕方」となると、
まったく変わってきます

というのも、ジャズというのはやってて思うのですが、
『スウィングしなけや意味ないね』のデューク・エリントンではありませんが、
かっこいい「ノリ」があってなんぼの音楽なんですね

そして、その「ノリ」というのは、リズム感とかはもちろんですが、
いろいろなもので成り立ってくるもので、
私の意識の中で分かりやすくいうと、
楽譜には記しきれない音符の長さや休符の長さ、裏拍、
もっといえば時には『味』になる程度の音程のズレ、
スラーやスタッカートなどのアーティキュレーションと呼ばれるものなど、
こういった色々な要素をどう表現するかが、
また「ノリ」につながっていくんだと思っています

メロディーさえも、アドリブによって、個人のプレイヤーが勝手に、
というか自由に解釈しても良い、とされている、
そういう意味ではすごく、ジャズはおおらかな音楽だと思うのです

それに対してクラシックというのは、譜面があって、
その楽譜通りの音符の長さ、休符の長さをきちんと守って、
スラーやスタッカートなども、基本的には書いたとおりに演奏する、
または、指揮者などの考えであえて変更されるものはあるにしても、
約束事が多いのはクラシックのほう。
オーケストラでも、基本はみんなでそろえる。
弦楽器の弓の動かし方すらも、そのときのコンサートマスターや
リーダーに合わせるほどですから

じゃあ、どっちがいいの?というのは、
「私と仕事と、どっちが大切なのよ!」というのと同じ?で(笑)

もちろん決められないことで、どちらにも良さがありますからね

でも、「郷に入っては従え」というやつで、
ジャズのときとクラシックのときと、
その辺を自分できちんと整理できた上で演奏しないといけないと思います

それが、その音楽を演奏させてもらう上での礼儀だと思うから

だから、クラシックとジャズを見事に融合させたガーシュインって、
本当にすごいなぁ~、と思います

あと、日本の偉大な音楽家で武満徹さんという方がいらっしゃいます

武満さんは大のジャズ好きでも知られていて、しかも
『デューク・エリントン』の大ファンだったのだとか

それも筋金入りで、奨学金でアメリカ留学するときに
「むこうで誰に師事したいか?」と聞かれ、当然、
質問したほうはクラシックの専門家の名前を挙げるだろうと
思っていたら、まじめな顔をして
「デューク・エリントンに習いたい。」
と答えられたんですって

その逆で、ジャズの大家も、
『ジャズ以外の音楽を聴かないで、ジャズが演奏できるか!』
と言って、クラシックや別の音楽を
たくさん聴いていたそうですし

だから偉大な音楽家ほど、「ジャンルなんていうのは便宜上のもの」
としてとらえていて、それぞれのジャンルや色々な国で生まれた
音楽に敬意を持って、そこに自分なりのエッセンスをどう薫らせるか?
ということに力を注いでこられたのかなぁ?なんて思います

1つの分野の音楽を深く掘り下げることは素晴しいことです

でも、「ジャズも好き!」「クラシックも好き!」「ポップスも好き!」と、
それぞれの音楽の持つ良さを、たくさん感じて受け入れられれば、
それも人生を豊かにすることなんじゃないかぁ~?とも思います

あと、ヴィブラートはそう言っていただいて本当に嬉しいです

実は私もいわゆる縮緬ビブラートは好みではありません。
でもジャズがお好きな方の中には「あれこそがジャズだ!」と
おっしゃられる方もいらっしゃいますが、私はそうは思いません。
好みの問題も大きいと思います

私は前にも書かせていただいたかもしれませんが、
クラシックのフルーティストで「マルセル・モイーズ」の本で、
『ヴィブラートというのは、音に命を吹き込むもの』というような
内容を読み、とても感動して、意識するようになりました

それによると、「ヴィブラートというのは感動する部分、
緊張する部分などでは、あたかも心臓の鼓動が激しくなるように
ヴィブラートも変化させなければならない。」のだそうです。
考えてみれば当たり前のことなのかもしれません。
どんな場面でも同じヴィブラートというのはやはり不自然だと思うのです。
ゆったりしているところであまりに速い振動
 はやっぱり不自然ですし、
はやっぱり不自然ですし、逆に速いパッセージでゆっ
 くりした波のヴィブラートも
くりした波のヴィブラートもやっぱり不自然ですし

だから、ヴィブラートは立派な表現方法だと思っています

そしてそれは、歌でもフルートでも、ジャズでもクラシックでも、
変わらない考えです。その音楽に合った、その曲に合った
方法で、自分なりに、演奏しているつもりです

長くなってしまいましたが、そういった意味で、
気持ちの上では、たとえどのジャンルでも基本的なものは変わらないし、
でも、奏法などは変わる、という理由です!
それにしても夕方5時でも明るい

日が伸びましたねー?
3連休、ETCで明石海峡、渡ってみたいなぁ~(笑)












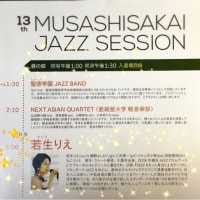




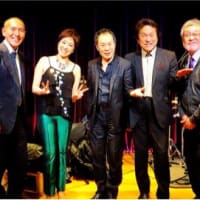

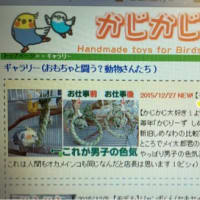




よおーくわかりました。
何が良くわかったって、りえさんがどれほど
音楽を大切にし、フルートを愛し、その上で
ジャンルを超えて、楽曲と真摯に向き合って
いるということが。
ファンの一人として、とても嬉しい、りえさんのお気持ちが伝わるコメントでした。
丁寧にコメントしていただいて本当に
恐縮です。
これからも応援していきます。
どうぞ体に気をつけて、どんどん
ご自身の世界を切り開いていってください。