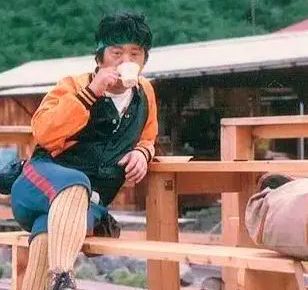食糧自給率の問題は、数十年前から「このままではダメだ」と指摘されていましたが、政府は有効な対策を打ち出さないままに推移し、40%を切るという危機的な状況にしてしまったのです。(勝手になったわけではありません。政治の責任です。)
そのうえ、TPPへの参加で、さらに自給率が低下すると予想されています。なにかあれば、日本人の多くが「餓死」するという状況が、いわば「目の前」に来ているのです。
政府は、TPPから撤退するとともに、食料自給率のアップのために、重点的に力を入れるべきだと思います。
【Food】先進国の中で最も低い自給率 世界に依存する日本の食は、異常気象に耐えられるのか? http://eco.goo.ne.jp/life/futsugou/04.html
食糧の約7割を輸入食材に頼っている日本。温暖化によって海外に“不都合”が多発すれば、食卓はたちまち食糧不足に直面する。
◎海外の異常気象がもたらす、"食糧不足"という危機
マズい食べ物と言われて思い出すのは、15年前の出来事。人々は輸入米のマズさにへき易し……。いや、日本米の旨さを再認識し、全国各地 で小さな"米騒動"が起こった。しかし、単純な冷害が原因だったこの米不足はすぐに終息し、輸入米のマズさもやがて笑い話となった。ところが、だ。「あの時すぐにおいしい米が食べられるようになったのは、我々にとって不幸だったかもしれない」と思える食の問題が、いま、温暖化問題によって浮き彫りになっている。日本の"食糧自給率の低さ"という問題だ。下の統計を見てほしい。ほとんどの人が「自分の食生活は海外の食材に支えられているのか」と納得するはずだが、この現実が、"日本の国内事情とは関係のない理由で、ある日突然、食糧が輸入されなくなる可能性がある"というリスクを抱えている点を見逃すわけにはいかない。
「食糧は安全保障品目ですから、どこの国も国内の需要に供給が満たない場合は、対外的な契約を破棄してでも国内需要を優先します。だから、何かあった時にアメリカやオーストラリアや中国が食糧を出してくれるという保証はまったくないのです」(農と食の環境フォーラム代表・牧下圭貴氏)
「何かあった時」の具体的な例として、今まさに温暖化による気候変動が取り沙汰されているわけだが、その「何か」は戦争の可能性だってある。いずれにせよ、我が国の"食糧調達に関する無作為のツケ"を、かなり致命的な形で実感することになるわけだ。
「戦後の農業政策においては、米を過度に保護した一方で小麦や大豆は作らなくてもいいと指導するなど、生産者に経営の自由を与えてきませんでした。つまり、この約40年間、自立した農業生産が行われてこなかったわけです。そこに貿易の自由化や食生活の急激な変化がからんできて、小麦や肉の需要が増しました。さらには日本の経済力が低下し、少子高齢化も顕在化。社会全体の過度な自由化も進みました。そしてついには、温暖化も重なった。こうした諸問題が、ほぼ同時に限界に達しようとしているのです」(牧下氏)
あの"米騒動"の数年後にまた不作が起こっていれば、自分たちの食べ物をどこからどう調達するかを、みんなが真剣に考えていたかもしれない。が、そんなものは空しい仮説だ。
ちなみに、あの時は日本がタイから米を輸入したあおりをイランやアフリカ諸国が受けたが、次に同じことが起これば、日本があおりを食う可能性も充分にある。中国、インドが急激に人口と経済力を伸ばしているため、相対的に日本の調達力が落ちているからだ。忘れてならないのは、世界はつながっているという事実。そして、いま世界は同じ温暖化の中にある。
コピーはここまで。
上記のURLをクリックして、全文をお読みください。
そのうえ、TPPへの参加で、さらに自給率が低下すると予想されています。なにかあれば、日本人の多くが「餓死」するという状況が、いわば「目の前」に来ているのです。
政府は、TPPから撤退するとともに、食料自給率のアップのために、重点的に力を入れるべきだと思います。
【Food】先進国の中で最も低い自給率 世界に依存する日本の食は、異常気象に耐えられるのか? http://eco.goo.ne.jp/life/futsugou/04.html
食糧の約7割を輸入食材に頼っている日本。温暖化によって海外に“不都合”が多発すれば、食卓はたちまち食糧不足に直面する。
◎海外の異常気象がもたらす、"食糧不足"という危機
マズい食べ物と言われて思い出すのは、15年前の出来事。人々は輸入米のマズさにへき易し……。いや、日本米の旨さを再認識し、全国各地 で小さな"米騒動"が起こった。しかし、単純な冷害が原因だったこの米不足はすぐに終息し、輸入米のマズさもやがて笑い話となった。ところが、だ。「あの時すぐにおいしい米が食べられるようになったのは、我々にとって不幸だったかもしれない」と思える食の問題が、いま、温暖化問題によって浮き彫りになっている。日本の"食糧自給率の低さ"という問題だ。下の統計を見てほしい。ほとんどの人が「自分の食生活は海外の食材に支えられているのか」と納得するはずだが、この現実が、"日本の国内事情とは関係のない理由で、ある日突然、食糧が輸入されなくなる可能性がある"というリスクを抱えている点を見逃すわけにはいかない。
「食糧は安全保障品目ですから、どこの国も国内の需要に供給が満たない場合は、対外的な契約を破棄してでも国内需要を優先します。だから、何かあった時にアメリカやオーストラリアや中国が食糧を出してくれるという保証はまったくないのです」(農と食の環境フォーラム代表・牧下圭貴氏)
「何かあった時」の具体的な例として、今まさに温暖化による気候変動が取り沙汰されているわけだが、その「何か」は戦争の可能性だってある。いずれにせよ、我が国の"食糧調達に関する無作為のツケ"を、かなり致命的な形で実感することになるわけだ。
「戦後の農業政策においては、米を過度に保護した一方で小麦や大豆は作らなくてもいいと指導するなど、生産者に経営の自由を与えてきませんでした。つまり、この約40年間、自立した農業生産が行われてこなかったわけです。そこに貿易の自由化や食生活の急激な変化がからんできて、小麦や肉の需要が増しました。さらには日本の経済力が低下し、少子高齢化も顕在化。社会全体の過度な自由化も進みました。そしてついには、温暖化も重なった。こうした諸問題が、ほぼ同時に限界に達しようとしているのです」(牧下氏)
あの"米騒動"の数年後にまた不作が起こっていれば、自分たちの食べ物をどこからどう調達するかを、みんなが真剣に考えていたかもしれない。が、そんなものは空しい仮説だ。
ちなみに、あの時は日本がタイから米を輸入したあおりをイランやアフリカ諸国が受けたが、次に同じことが起これば、日本があおりを食う可能性も充分にある。中国、インドが急激に人口と経済力を伸ばしているため、相対的に日本の調達力が落ちているからだ。忘れてならないのは、世界はつながっているという事実。そして、いま世界は同じ温暖化の中にある。
コピーはここまで。
上記のURLをクリックして、全文をお読みください。