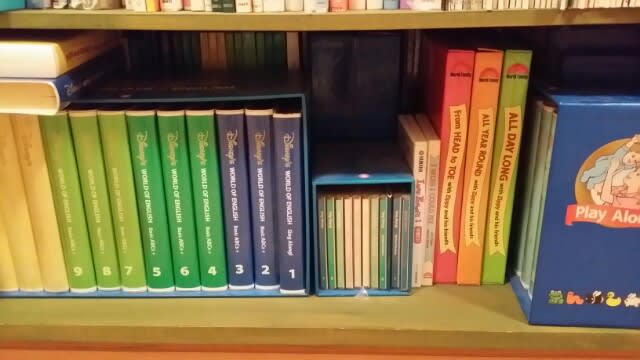東京の大学へ進学した我が子。
夏休みということで只今帰省中。
G.Wに帰省した折りは大学選びを失敗したかなぁ?と言ってたので心配しておりましたが、「学校はどう?」と聞くと、「まぁまぁ、楽しくやってるよ。」との返事に安心しました。
なんでも、文理や学部学科の隔てなく好きな学問を学べるリベラルアーツ教育に魅力を感じ志望した大学なのに、前期は必修が多く、なかなか希望する講義が選択できなくて嫌になってたそうです💦
しかも、思いの外課題が多くて、入ってからも点取り競争。楽~に単位をとって卒業とはいかない仕組みに、思い描いていた大学生像とのギャップを感じたそう。
ただ、後期からは少し必修が少なくなって選択できる講義が増えるようで、楽しみにしている様子。
さて、我が子の受験歴、中学は私立大学系列の中高一貫校と国立大学付属中学の2校。国立は付属高校がないので、進学後は高校受験が必要です。
どちらにも合格をいただいたのですが、国立大学付属中学に進学しました。
私立中学は、やはり手厚い学習指導や英語教育に力を入れ修学旅行が海外だったり、高校受験がなく6年かけて大学受験までじっくり学習に取り組めるのが魅力でした。ただし、進学実績は地元県立上位校より下がります。有名私立大学への推薦枠があるのは魅力。
一方、国立大学付属中学は2/3ほどは小学からの内部進学。親は地元会社経営者や役員、医者、大学関係者、教員、公務員が多い。サラリーマン夫の同僚の息子さんも同級生になりましたが。
こちらは半数以上が県立の地元トップ高校へ進学します。
大学教育学部の付属校ということで、先生方も研究授業や実習生の対応に忙しく、学習面も生活面も割りと生徒の自主性を重んじて深入りすることがないので、面倒見はあまりよくありません。それでも、家庭環境のせいでしょうか、面倒を起こす子も少なく通塾率や習い事をしている子も多く、学力も相対的に高く個性的な子が多かった。ここだったら良い刺激になるのではと思い進学しました。ここで成績TOP層であれば、そのまま地元高校TOP層に食い込むことができます。夫は小学からの内部進学組ですが、やはり同じ学校に入れたかった様子。
中3の時に高校受験対策はしたものの、模試で県内上位の成績がとれていたので、学校でもこの成績でいままで落ちた人はいません、ということで、塾では中3冬から東進衛生予備校で高1の難関大学受験に向けた講座の受講を始めました。
東京の大学への進学を希望していたので、高校から東京という事も考えましたが高校選びや受験対策に遅れをとったので断念。地元で頑張ることに。
今、通っている大学のクラスメイト達の出身校を聞くと、やはり有名中高一貫校が多く、いろいろな意味で余裕のある人が多いとの事。伸び伸びとした印象を受けるそうです。それでいて、多趣味で趣味の範囲を越えて、玄人はだしの子も多くいると言っていました。
自分も首都圏にいたら中高一貫校で6年かけて好きなこと見つけたかったなぁ、子供にはそうさせたいなぁ、と言っています。
中学受験、高校受験、大学受験と続くのは、なかなか好きなことにじっくり取り組むには大変だと言ってました。部活や趣味もそれなりに楽しんでた様子でしたが、常にどこかで受験を意識せざるおえない感じだったそう。
決して偏差値の高い大学に行くために中高一貫校を目指すのではなくとも、受験に追われずじっくりと物事に取り組める環境ということでは良いのかも。
そういう意味でも、最近、大学付属校が人気あるのかなぁ。
思春期の多感な時期に、余裕があるっていいものね。
夏休みということで只今帰省中。
G.Wに帰省した折りは大学選びを失敗したかなぁ?と言ってたので心配しておりましたが、「学校はどう?」と聞くと、「まぁまぁ、楽しくやってるよ。」との返事に安心しました。
なんでも、文理や学部学科の隔てなく好きな学問を学べるリベラルアーツ教育に魅力を感じ志望した大学なのに、前期は必修が多く、なかなか希望する講義が選択できなくて嫌になってたそうです💦
しかも、思いの外課題が多くて、入ってからも点取り競争。楽~に単位をとって卒業とはいかない仕組みに、思い描いていた大学生像とのギャップを感じたそう。
ただ、後期からは少し必修が少なくなって選択できる講義が増えるようで、楽しみにしている様子。
さて、我が子の受験歴、中学は私立大学系列の中高一貫校と国立大学付属中学の2校。国立は付属高校がないので、進学後は高校受験が必要です。
どちらにも合格をいただいたのですが、国立大学付属中学に進学しました。
私立中学は、やはり手厚い学習指導や英語教育に力を入れ修学旅行が海外だったり、高校受験がなく6年かけて大学受験までじっくり学習に取り組めるのが魅力でした。ただし、進学実績は地元県立上位校より下がります。有名私立大学への推薦枠があるのは魅力。
一方、国立大学付属中学は2/3ほどは小学からの内部進学。親は地元会社経営者や役員、医者、大学関係者、教員、公務員が多い。サラリーマン夫の同僚の息子さんも同級生になりましたが。
こちらは半数以上が県立の地元トップ高校へ進学します。
大学教育学部の付属校ということで、先生方も研究授業や実習生の対応に忙しく、学習面も生活面も割りと生徒の自主性を重んじて深入りすることがないので、面倒見はあまりよくありません。それでも、家庭環境のせいでしょうか、面倒を起こす子も少なく通塾率や習い事をしている子も多く、学力も相対的に高く個性的な子が多かった。ここだったら良い刺激になるのではと思い進学しました。ここで成績TOP層であれば、そのまま地元高校TOP層に食い込むことができます。夫は小学からの内部進学組ですが、やはり同じ学校に入れたかった様子。
中3の時に高校受験対策はしたものの、模試で県内上位の成績がとれていたので、学校でもこの成績でいままで落ちた人はいません、ということで、塾では中3冬から東進衛生予備校で高1の難関大学受験に向けた講座の受講を始めました。
東京の大学への進学を希望していたので、高校から東京という事も考えましたが高校選びや受験対策に遅れをとったので断念。地元で頑張ることに。
今、通っている大学のクラスメイト達の出身校を聞くと、やはり有名中高一貫校が多く、いろいろな意味で余裕のある人が多いとの事。伸び伸びとした印象を受けるそうです。それでいて、多趣味で趣味の範囲を越えて、玄人はだしの子も多くいると言っていました。
自分も首都圏にいたら中高一貫校で6年かけて好きなこと見つけたかったなぁ、子供にはそうさせたいなぁ、と言っています。
中学受験、高校受験、大学受験と続くのは、なかなか好きなことにじっくり取り組むには大変だと言ってました。部活や趣味もそれなりに楽しんでた様子でしたが、常にどこかで受験を意識せざるおえない感じだったそう。
決して偏差値の高い大学に行くために中高一貫校を目指すのではなくとも、受験に追われずじっくりと物事に取り組める環境ということでは良いのかも。
そういう意味でも、最近、大学付属校が人気あるのかなぁ。
思春期の多感な時期に、余裕があるっていいものね。