
http://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:ZeolitesUSGOV.jpg
このゼオライトと言う鉱物、「効果がどうなのか?」「簡易実験を行い」官邸でも確認すべきであろう、、、。
確認出来れば、農業では土壌のセシウムを吸着させ、その吸着したゼオライトを回収する事によって土壌汚染はかなり軽減化出来るのではなかろうか?、、、。
更には、数回繰り返せば、元の状態に近づける事も可能かもしれない、、、。
放射線土壌汚染の基準値以下になれば、野菜栽培も可能になる。
漁業も同じである。
早急な対応により、漁業の復活も早いかもしれない、、、。
しかし、その前に、「何よりも原発の問題を処理しておかないと意味が無くなる」、、。
重要な部分は、セシウムが吸着したゼオライトを確実に回収し、放射性廃棄物としての処理を「確実に行う必要がある」と言う事が言える。
最終処分場に持って行くべきだ。
*汚染した原子炉の冷却水の処理は決まったのか?、、、。
純粋に水分を極力無くし、残った放射性物質をガラス固化体でも良いので、それを製造し、早急に最終処分場に持って行くべきだ。
官邸のメンバーはストーリー(作業工程)をシッカリと考えているのか?、、、。
「今後どうして行くのか?」、、、。
東電、原子力保安委員会、官邸も説明していないので、そろそろ国民、及び世界に向かって「説明する必要がある」。
クリントン長官も「日本政府の対応」に「やきもき」している事であろう、、、。
記事参照
汚染水浄化、仙台産ゼオライトが有望…学会有志
福島原発
東電福島第一原発のタービン建屋地下などにたまる高濃度の放射性物質を含む水の浄化に、仙台市青葉区の愛子
(あやし)産の鉱物「天然ゼオライト」が有望であることを、日本原子力学会の有志らがまとめ、7日発表した。
研究チームは、同学会に所属する東北大など5大学と日本原子力研究開発機構の計59人。福島第一原発で、難航する高濃度汚染水の処理の一助になればと、自主的にデータを集めた。
実験の結果、表面に微細な穴の多い「天然ゼオライト」10グラムを、放射性セシウムを溶かした海水100ミリ・リットルに入れて混ぜると、5時間で約9割のセシウムが吸着されることを確認した。愛子産ゼオライトは大量にすぐに入手できるため、有望な材料と判断した。ほかにも放射性ヨウ素を効果的に吸着する材料として、活性炭などを挙げる。
(2011年4月7日21時32分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20110407-OYT1T00767.htm
沸石
http://ja.wikipedia.org/wiki/沸石
RO逆浸透膜による水処理装置や排水再利用装置等水処理プラントはゼオライト
http://www.zeolite.co.jp/
天然ゼオライトの新東北化学工業 - ゼオライトとは
http://www.s-zeolite.com/zeolite.html
日本ゼオライト株式会社
http://www.japan-zeolite.com/
放射線分布図
NEVER 全国放射線量情報
http://www.naver.jp/radiation
2011年03月17日 18時32分07秒
放射性物質による汚染を除去する「除染」の具体的な方法まとめ
by euthman
「除染」とは、放射性物質による汚染を除去するということなのですが、その詳細な実践方法について説明します。 実際にどのような処置を行うべきなのか、また洗剤を使う場合はどのような種類が適切なのかといった点について、放射性物質を扱う研究者向けのガイドライン書籍を参考にまとめてみました。
一般人が行うのはかなり難しいと思われる処置などもありますが、一歩踏み込んだ専門的な方法を知っておくことで、「除染」と一口に言っても汚染された物によってさまざまな処置方法があることが分かり、いざという時の心構えができるはずです。 除染の具体的な方法まとめは以下から。
<除染する際の注意>
◆汚染を生じたらできる限り早目に除染するのが原則
汚染直後であれば、一般に水による洗浄で容易に除染できる場合が多いです。ただし、汚染してからの時間が経過すればするほど、除染はしだいに困難となってきます。
これは汚染が器具表面の微細な割れ目や傷口に入り込んだり、あるいは表面の材質と化学反応をしたりするため。
このような汚染物へは、活性度の大きい除染剤を使用することになります(除染剤についてはさらに下記具体的手順で後述、いろいろな種類があります)。
◆汚染している部位を広げないようにする(汚染の局所限定)
多量の除染剤を使用したり、また汚染の箇所を確実に把握しないで不必要な部分までも除染処理を行うと汚染の面積が広がり過ぎてしまいます。
たとえば、皮膚面や床面を汚染したときは、まずろ紙や布片で拭き取ってから除染剤を用いるようにします。
また、汚染を空気中に舞い上がらせないように、なるべく湿式除染(乾燥させない状態で除染すること)をこころがけるようにします。
また、使用した除染剤や資材は「放射性廃棄物」になるので、これらをあちこちにばらまいて二次被害を出さないように気をつけ、所定の容器へまとめて捨てましょう。
<人体の除染>
by gfpeck ◆皮膚の除染
除染中に爪の中に放射性物質が入り込まないよう、爪は短かめに切っておきましょう。
ひだ、毛髪、爪の間、指の股部、手の外縁などの部位は除染しにくいので、ネイルブラシやハンドブラシを使って特に注意して洗います。
この時使うブラシはプラスチック製ではなく動物毛製の物を使用するのが望ましいです。 顔の除染をする場合、眼と唇に汚染水が入りこまないように注意して行います。
<軽い汚染の場合>
アルカリ石けんは使わず、粉末状中性洗剤(ソープレスソープやアルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)をかけて、ぬるま湯でぬらし、ネイルブラシなどで軽くこすりながら流水中で洗い流します。
この時、有機溶媒は皮膚から浸透することがあるので除染剤として使用しないでください。 除染によって皮膚が荒れてしまったら、ハンドクリームなどを十分にすりこんで、傷口を作らないよう保護しておくことが大切です。
<やや汚染度が高い場合>
酸化チタンペースト(アナタース型の酸化チタン100gを0.1mol/lのHCl60mlでペースト化)を十分な量だけ塗りつけ、2~3分放置した後、湿った布でこすりとってしっかりと水洗いします。
<汚染度がかなり高い場合>
粉末状中性洗剤:キレート形成剤の割合が1:2となる混合物をかけた後、ぬるま湯で湿らせてから、ネイルブラシなどでこすりつつ水洗します。
キレート形成剤にはさまざまな種類がありますが、Na-EDTA、クエン酸、クエン酸ナトリウム、酒石酸ナトリウム、リン酸ナトリウムが適しています。
<汚染度が非常に高い場合>
KMnO4の飽和溶液と0.1mol/l H2SO4溶液を同量ずつ混ぜた混合液をかけて、ネイルブラシなどで軽くこすりながら水で洗い流すという手順を3回くり返します。
その後、10%NaHSO3を使って脱色します。混合液を作る作業と、NaHSO3を水に溶かす作業はこれらを使う直前に行ってください。
この方法は皮膚に対する作用が強いので、髪の除染には使いません。
(2)に続く、、、。
このゼオライトと言う鉱物、「効果がどうなのか?」「簡易実験を行い」官邸でも確認すべきであろう、、、。
確認出来れば、農業では土壌のセシウムを吸着させ、その吸着したゼオライトを回収する事によって土壌汚染はかなり軽減化出来るのではなかろうか?、、、。
更には、数回繰り返せば、元の状態に近づける事も可能かもしれない、、、。
放射線土壌汚染の基準値以下になれば、野菜栽培も可能になる。
漁業も同じである。
早急な対応により、漁業の復活も早いかもしれない、、、。
しかし、その前に、「何よりも原発の問題を処理しておかないと意味が無くなる」、、。
重要な部分は、セシウムが吸着したゼオライトを確実に回収し、放射性廃棄物としての処理を「確実に行う必要がある」と言う事が言える。
最終処分場に持って行くべきだ。
*汚染した原子炉の冷却水の処理は決まったのか?、、、。
純粋に水分を極力無くし、残った放射性物質をガラス固化体でも良いので、それを製造し、早急に最終処分場に持って行くべきだ。
官邸のメンバーはストーリー(作業工程)をシッカリと考えているのか?、、、。
「今後どうして行くのか?」、、、。
東電、原子力保安委員会、官邸も説明していないので、そろそろ国民、及び世界に向かって「説明する必要がある」。
クリントン長官も「日本政府の対応」に「やきもき」している事であろう、、、。
記事参照
汚染水浄化、仙台産ゼオライトが有望…学会有志
福島原発
東電福島第一原発のタービン建屋地下などにたまる高濃度の放射性物質を含む水の浄化に、仙台市青葉区の愛子
(あやし)産の鉱物「天然ゼオライト」が有望であることを、日本原子力学会の有志らがまとめ、7日発表した。
研究チームは、同学会に所属する東北大など5大学と日本原子力研究開発機構の計59人。福島第一原発で、難航する高濃度汚染水の処理の一助になればと、自主的にデータを集めた。
実験の結果、表面に微細な穴の多い「天然ゼオライト」10グラムを、放射性セシウムを溶かした海水100ミリ・リットルに入れて混ぜると、5時間で約9割のセシウムが吸着されることを確認した。愛子産ゼオライトは大量にすぐに入手できるため、有望な材料と判断した。ほかにも放射性ヨウ素を効果的に吸着する材料として、活性炭などを挙げる。
(2011年4月7日21時32分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20110407-OYT1T00767.htm
沸石
http://ja.wikipedia.org/wiki/沸石
RO逆浸透膜による水処理装置や排水再利用装置等水処理プラントはゼオライト
http://www.zeolite.co.jp/
天然ゼオライトの新東北化学工業 - ゼオライトとは
http://www.s-zeolite.com/zeolite.html
日本ゼオライト株式会社
http://www.japan-zeolite.com/
放射線分布図
NEVER 全国放射線量情報
http://www.naver.jp/radiation
2011年03月17日 18時32分07秒
放射性物質による汚染を除去する「除染」の具体的な方法まとめ
by euthman
「除染」とは、放射性物質による汚染を除去するということなのですが、その詳細な実践方法について説明します。 実際にどのような処置を行うべきなのか、また洗剤を使う場合はどのような種類が適切なのかといった点について、放射性物質を扱う研究者向けのガイドライン書籍を参考にまとめてみました。
一般人が行うのはかなり難しいと思われる処置などもありますが、一歩踏み込んだ専門的な方法を知っておくことで、「除染」と一口に言っても汚染された物によってさまざまな処置方法があることが分かり、いざという時の心構えができるはずです。 除染の具体的な方法まとめは以下から。
<除染する際の注意>
◆汚染を生じたらできる限り早目に除染するのが原則
汚染直後であれば、一般に水による洗浄で容易に除染できる場合が多いです。ただし、汚染してからの時間が経過すればするほど、除染はしだいに困難となってきます。
これは汚染が器具表面の微細な割れ目や傷口に入り込んだり、あるいは表面の材質と化学反応をしたりするため。
このような汚染物へは、活性度の大きい除染剤を使用することになります(除染剤についてはさらに下記具体的手順で後述、いろいろな種類があります)。
◆汚染している部位を広げないようにする(汚染の局所限定)
多量の除染剤を使用したり、また汚染の箇所を確実に把握しないで不必要な部分までも除染処理を行うと汚染の面積が広がり過ぎてしまいます。
たとえば、皮膚面や床面を汚染したときは、まずろ紙や布片で拭き取ってから除染剤を用いるようにします。
また、汚染を空気中に舞い上がらせないように、なるべく湿式除染(乾燥させない状態で除染すること)をこころがけるようにします。
また、使用した除染剤や資材は「放射性廃棄物」になるので、これらをあちこちにばらまいて二次被害を出さないように気をつけ、所定の容器へまとめて捨てましょう。
<人体の除染>
by gfpeck ◆皮膚の除染
除染中に爪の中に放射性物質が入り込まないよう、爪は短かめに切っておきましょう。
ひだ、毛髪、爪の間、指の股部、手の外縁などの部位は除染しにくいので、ネイルブラシやハンドブラシを使って特に注意して洗います。
この時使うブラシはプラスチック製ではなく動物毛製の物を使用するのが望ましいです。 顔の除染をする場合、眼と唇に汚染水が入りこまないように注意して行います。
<軽い汚染の場合>
アルカリ石けんは使わず、粉末状中性洗剤(ソープレスソープやアルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)をかけて、ぬるま湯でぬらし、ネイルブラシなどで軽くこすりながら流水中で洗い流します。
この時、有機溶媒は皮膚から浸透することがあるので除染剤として使用しないでください。 除染によって皮膚が荒れてしまったら、ハンドクリームなどを十分にすりこんで、傷口を作らないよう保護しておくことが大切です。
<やや汚染度が高い場合>
酸化チタンペースト(アナタース型の酸化チタン100gを0.1mol/lのHCl60mlでペースト化)を十分な量だけ塗りつけ、2~3分放置した後、湿った布でこすりとってしっかりと水洗いします。
<汚染度がかなり高い場合>
粉末状中性洗剤:キレート形成剤の割合が1:2となる混合物をかけた後、ぬるま湯で湿らせてから、ネイルブラシなどでこすりつつ水洗します。
キレート形成剤にはさまざまな種類がありますが、Na-EDTA、クエン酸、クエン酸ナトリウム、酒石酸ナトリウム、リン酸ナトリウムが適しています。
<汚染度が非常に高い場合>
KMnO4の飽和溶液と0.1mol/l H2SO4溶液を同量ずつ混ぜた混合液をかけて、ネイルブラシなどで軽くこすりながら水で洗い流すという手順を3回くり返します。
その後、10%NaHSO3を使って脱色します。混合液を作る作業と、NaHSO3を水に溶かす作業はこれらを使う直前に行ってください。
この方法は皮膚に対する作用が強いので、髪の除染には使いません。
(2)に続く、、、。













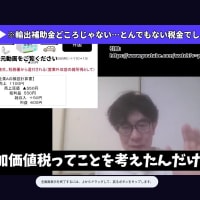
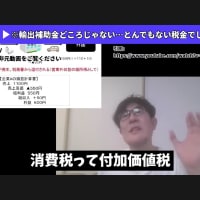
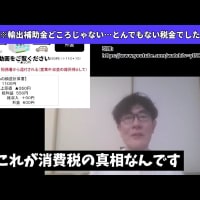

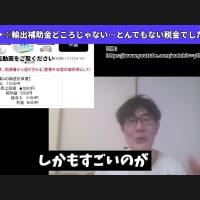

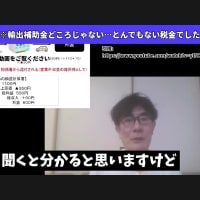
日本国土開発の土壌洗浄工法は、ツイスター工法と言うようだが、この技術を元に、粉砕した土壌を、セシウムをよく吸着する「プルシアン・ブルー溶液」と混ぜ、その液体を、電気泳動で電極に集め、クリーンな部分と、汚染物質の集まった部分を分離し、汚染している部分を抜き取る(様々な方法があると思う)。
水が透明になれば浄化した事になり、その「透明な水」は、戻しても良い。
「着色している汚染水」を回収し適切に処理する。
日本国土開発株式会社
http://www.n-kokudo.co.jp/index.shtml
日本国土開発の地盤環境技術・震災復興対策技術
http://www.n-kokudo.co.jp/soil_environment/index.html?gclid=CODh87zo6KwCFUdNpgod30XKJg
土壌汚染浄化
優れた混合能力のあるツイスター工法で土壌汚染浄化を安価にサポートします。
http://www.n-kokudo.co.jp/soil_environment/soil_purifying/index.html
回転式破砕混合装置(ツイスター工法)
破砕と混合を同時に行う仕組み、機械の種類を紹介します
http://www.n-kokudo.co.jp/soil_environment/twister/index.html
「上記の技術と下記の技術」を組み合わせると、成功する。
独立行政法人 産業技術総合研究所 広報部 報道室
プルシアンブルーを利用して多様な形態のセシウム吸着材を開発
-汚染水や土壌などさまざまな環境に適用可能-
2011年8月24日 発表
ポイント
安価な顔料であるプルシアンブルーを利用し、優れたセシウム吸着能力を持つ吸着材を開発
用途に応じて、布状、液状、ビーズ状など多様な形態のセシウム吸着材が使用可能に
放射性物質漏洩事故などにおける環境中の放射性セシウムの除去に期待
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2011/pr20110824/pr20110824.html
独立行政法人 産業技術総合研究所 広報部 報道室
土壌中のセシウムを低濃度の酸で抽出することに成功
-プルシアンブルーナノ粒子吸着材で回収し放射性廃棄物の大幅な減量化へ-
2011年8月31日 発表
ポイント
土壌から酸水溶液でセシウムイオンを抽出し、抽出したセシウムイオンを吸着材で回収
抽出したセシウムイオンはプルシアンブルーナノ粒子吸着材でほぼ全量を回収可能
放射性セシウムに汚染された廃棄土壌などの大幅な減量化に期待
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2011/pr20110831/pr20110831.html
*昨日の夜、NHKで「福島の水田の土壌洗浄について」の放送をしていたが、番組を見ていると、途中で、水田に「プルシアン・ブルーの溶液」を放水していたようだが、「セシウムと吸着させたプルシアン・ブルー溶液」は、その後どうなったのであろうか?。
水田の左右両側に巨大な電極を配置、「適切な量の電流」を流し、「セシウムと吸着させたプルシアン・ブルー」を回収する必要がある。
「プルシアン・ブルーの溶液」を放水したままだと、「セシウムとは吸着」するが、そのセシウムは、その水田の中に留まる事になり、結果的には、その場所の「セシウム濃度は下がらない」と言う事が言える。
その状態で稲作、又は別の作物でも良いが、そのまま育てれば「米も汚染する」と言う事が言える。
稲は水を吸う事になるからだ。
重要な事は、水田の両側に電極を配置し、セシウムを強制吸着させた、「汚染したプルシアン・ブルー」を「回収する」と言う事が最も重要な事だ。
水が透明にならなければ、浄化したとは言えない。
水田の水が透明になれば、「その水田の「水」については「OK」」と言う事だ。
土壌洗浄については、掘り返し、その泥や土を洗浄しなければならない。
福島や近隣県の場合、水田近くの山林が汚染しているので、暫くすると雨水が地下水となって下流に流れ出す。
水田は「再汚染」と言う事になる。
どちらにしても、「セシウム濃度が下がるまで「セシウム吸着」・「汚染したプルシアン・ブルー」の「回収作業」を繰り返す必要がある」と言う事は言える。
根気のいる作業になる。
東電は当然だが、原発を推進した原発推進の経済団体・企業の「人的・資金的援助」は欠かす事は出来ない。
それを行う事が「原発を推進してきた関係企業の責務」である事を忘れてはならない。
セシウムを十分に吸収し成長した「マツバイ」は、適切な処分を行う必要がある。
刈り取った「マツバイ」を適当な場所に放置すれば、その場所が再汚染すると言う事になる。
記事参照
除染の味方「マツバイ」 セシウムをスピード吸収
2011年11月23日3時1分
関連トピックス
• 原子力発電所
福島県農業総合センター内の水田で実施したマツバイ栽培実験。黒いコンテナケースの中にあるのがマツバイ=福島県郡山市(榊原教授提供)
http://www.asahi.com/national/update/1123/images/OSK201111220207.jpg
用水路や池などに生えている水草「マツバイ」が、土壌中の放射性セシウムを効率よく吸収することを愛媛大大学院の榊原正幸教授=環境岩石学=らが明らかにした。
マツバイは簡単に入手でき、薬品などを使わないため安全。
福島第一原発事故の放射能で汚染された水田の除染などの有力な手段の一つになりそうだ。
今回の研究は、日本地質学会の東日本大震災復興支援プロジェクトの一つ。
マツバイはカヤツリグサ科の多年草で、カドミウムや亜鉛など重金属類をよく吸収する性質がある。
福島県郡山市の県農業総合センターの協力で、マツバイが放射性セシウムをどの程度吸収するのかを確かめた。
• 関連リンク
• 汚染土蒸し焼き、セシウム分離 飯舘の焼却施設で実験(10/26)
• 新種の藻類に除染能力 山梨大・東邦大など確認(10/19)
• ヒマワリは除染効果なし 農水省が実験結果公表(9/14)
• 厄介者、実は環境対策の優等生? 驚きの吸収力で土浄化(10/10/8)
http://www.asahi.com/national/update/1123/OSK201111220203.html
関連記事
厄介者、実は環境対策の優等生? 驚きの吸収力で土浄化(1/2ページ)
2010年10月8日
マツバイがぎっしり詰まった容器を調整池に敷き詰める愛媛大学の学生たち=中国地方の銅鉱山跡地
田んぼの用水路などに根を張る雑草「マツバイ」が、重金属類を効率よく吸収して葉や茎に蓄積することに愛媛大大学院の榊原正幸教授(50)らが着目し、土壌改良に役立てようと研究を続けている。
実用化されれば、薬品を極力使わず安く簡単に土や水の浄化が可能になるという。
厄介者でしかなかった雑草が、環境対策の「優等生」としてにわかに注目を集めている。
マツバイはカヤツリグサ科の多年草。全国の用水路やため池などに生えている。
マツに似た細長い10~15センチの葉が特徴で、芝のように密集して生える。
繁殖力が強く、用水路や田んぼで群生すると水を流れにくくしたり稲の生育をじゃましたりするため、農家から嫌われてきた。
榊原教授は、マツバイの仲間が重金属類をよく吸収するというメキシコの研究者の論文を読み、「マツバイにも応用できるのでは」と2004年ごろから研究を始めた。
国内の廃鉱跡から取ってきた汚染土にマツバイを植え、2~3カ月後に葉に含まれる重金属類の量を計ったところ、乾燥させた葉1キロあたり、最大で銅20.2グラム(汚染されていない土壌で育った場合は約9.9ミリグラム)、亜鉛14.2グラム(同105ミリグラム)、ヒ素1.74グラム(同0.5ミリグラム)、カドミウム239ミリグラム(同0.2ミリグラム)が蓄積されていた。
重金属類は葉や茎の微粒子に取り込まれ、いったん吸収されれば、マツバイが枯れた後も土や水に戻りにくいことも分かった。
水辺の植物のため、弱点は豪雨の際に流されやすいこと。
そこで、いかだのようにひもで結んだプラスチック製のかごにマツバイを入れ、水中に浮かせて育てる手法を考案した。
http://www.asahi.com/kansai/kouiki/OSK201010080054.html
厄介者、実は環境対策の優等生? 驚きの吸収力で土浄化(2/2ページ)
2010年10月8日
マツバイがぎっしり詰まった容器を調整池に敷き詰める愛媛大学の学生たち=中国地方の銅鉱山跡地
今年9月からは、中国地方にある銅鉱山の跡地に約180キロを植えて観察を続けている。
培養地は、ヒ素が環境基準(土壌1キロあたり150ミリグラム以下)の6倍超含まれる汚染土。
ここでヒ素の濃度を10%ほど減らすことができれば成功だという。
鉱害防止事業に取り組む独立行政法人「石油天然ガス・金属鉱物資源機構」(川崎市)によると、全国には約7千カ所の休廃止鉱山があり、うち約450カ所では何らかの鉱害防止事業をしているか、その必要性があるという。
通常だと、坑道をふさいだり中和処理をしたりしなければならず、多額の費用がかかるが、安く簡単に植えられるマツバイは利点が多い。
榊原教授は「カドミウム米などが問題になっている国内各地の田畑や鉱山跡地、土壌水質汚染のより深刻な海外で早く実用化したい」と意気込む。
マツバイには、インジウムやガリウムなどの希少金属(レアメタル)をよく吸収する性質もある。
榊原教授は「特定のレアメタルを蓄積させて取り出す『植物鉱山』としても利用できるかもしれない」と夢を膨らませている。(藤家秀一)
http://www.asahi.com/kansai/kouiki/OSK201010080054_01.html
その他の土壌洗浄に関する関連記事。
新種の藻類に除染能力 山梨大・東邦大など確認
2011年10月19日19時6分
粒状に加工した藻類バイノス
http://www.asahi.com/special/gallery_e/view_photo_feat.html?jisin-pg/TKY201110180709.jpg
100分の1ミリの緑色の藻類がセシウムやストロンチウムなど放射性物質を効率よく取り除くことを、山梨大と東邦大が確認した。
大量に増やすこともでき、来月に福島県伊達市の住宅地で土壌を洗ったり、建物の壁、道路に塗ったりして、除染に使えないか実験をする。
この藻類は、ベンチャー企業の日本バイオマス研究所(千葉県柏市)の湯川恭啓社長が5年前にめっき工場の廃液処理施設で見つけた。
単細胞で葉緑素を多く含む新種で、バイノスと名づけられた。
バイノスは生命活動が活発で色々な物質を取り込むことから北里研究所の伊藤勝彦博士が除染に利用できないかと提案し、山梨大医学部の志村浩己助教らが福島県内で取った汚染水で実験した。
すると、10分間で放射性ストロンチウムを8割、セシウムを4割取り除くことができた。
バイノスが細胞のまわりに出す分泌物が放射性物質を吸いつけて離さないとみられる。
湯川社長によると、バイノスは細胞分裂の速度が速く、培養すれば容易に増やせる。
乾燥すると重さが10分の1ほどになるため、除染後の廃棄物の量を減らすことも期待できる。
今後、他の企業と協力して放射性物質の汚染水処理や、農地や住宅地の除染に活用したいという。
住民が簡単に使えるよう、壁や道路に、塗料のように塗りつけて乾いたらはがして、除染できないか調べる。(編集委員・浅井文和)
こんな記事も
• 除染対象、福島全土の7分の1 専門家が最大値試算(9/15)
• ヒマワリは除染効果なし 農水省が実験結果公表(9/14)
• 放射能汚染土、水洗いで除染に効果 東北大が開発(9/6)
• 特集:東日本大震災
• 東日本大震災・原発関連ニュースはこちら
• 社会・話題その他記事一覧
http://www.asahi.com/special/10005/TKY201110180703.html
汚染土蒸し焼き、セシウム分離 飯舘の焼却施設で実験
2011年10月26日23時34分
1キロあたり3580ベクレルの土を蒸し焼き装置に入れる日本原子力研究開発機構の職員=26日尾、福島県飯舘村の飯舘クリアセンター、杉本崇撮影
http://www.asahi.com/special/gallery_e/view_photo_feat.html?jisin-pg/TKY201110260422.jpg
東京電力福島第一原発の事故で汚染された土を蒸し焼きして放射性セシウムを分離する実験が26日、福島県飯舘村で公開された。
除染で出る土壌などの廃棄物からセシウムを除ければ元の場所に返すことも可能で、処分する廃棄物の量の減少につながるという。
日本原子力研究開発機構と農業・食品産業技術総合研究機構が、ごみ焼却施設「飯舘クリアセンター」で実施した。こうした実験は国内初という。
実験では、飯舘村の農地の土10キログラムを電気ヒーターを使い、セ氏800度で10時間、蒸し焼きする。
セシウムは約640度を超えるとガスになるため、特殊な布のフィルターと、原発でも使われているガラス繊維のフィルターでガスをこしとる。
原子力機構の大越実・技術主席は「土に含まれるセシウムが数分の1になれば、廃棄物にしなくて済む。農土として再利用できるか検討したい」と話す。
同機構などは、汚染された植物を焼いて減量する実験もしている。
こちらはヒーターの温度を600度に抑えるため、セシウムを取り込んだまま植物を圧縮できる。
ヒマワリで実験したところ、量を数分の1程度に減量できたという。(杉本崇)
キーワード:
農業・食品産業技術総合研究機構
こんな記事も
• 汚染土仮置き場に「国有林提供」 細野原発相、再度表明(10/22)
• 福島の除染土、進まぬ仮置き場確保 2町村どまり(10/8)
• 浄水場の汚染残土、2カ月で倍増 14都県、厚労省発表(9/29)
• 中間貯蔵施設8都県に 汚染土壌・焼却灰 環境省要請へ(9/29)
• 東日本大震災・原発関連ニュースはこちら
• 東日本大震災
• ニュース特集一覧
• 社会・話題その他記事一覧
http://www.asahi.com/special/10005/TKY201110260418.html
記事参照
【社会】 福島・郡山の土 セシウム99%除去 京大など実験成功
2011年11月13日 朝刊
放射性物質で汚染された土を水で洗ったり、ふるい分けたりして、放射性セシウムを99%除去し固化する実験に京都大農学研究科の豊原治彦准教授と土壌改良ベンチャー「アース」(仙台市)が成功した。田んぼなどの粘土状の土では除去が難しいが、公園の表土など、粒が大きい土砂では効果が高いとしている。
この実験結果を応用し豊原准教授らは、一億~三億円かけて約十メートル四方と約二十メートル四方の大きさの二基のプラントを製作しており、今後自治体などと実験を進めたい考えだ。プラントを使った場合、一トンの汚染土壌が約五十キロまで減らせるという。
実験に使ったのは福島県郡山市の一キロ当たり三〇〇〇~五〇〇〇ベクレルの土で、粘土の重さは全体の4%。一回当たり二百グラムの土を、マイクロメートル(マイクロは百万分の一)サイズの極めて細かい網目のざるに入れ、数回にわたって水を流しながらステンレスたわしで洗うと88%のセシウムが水に移った。
さらに12%のセシウムが残った洗浄土を乾燥させ、目の細かいふるいで粘土を取り除いたところ、大半のセシウムが吸着していた。粘土はセシウムとの結び付きが強く、離れにくいとみられる。これで汚染土壌から計99%のセシウムを取り除けた。
水や粘土中のセシウムは、マグネシウムを含んだ鉱物を使った吸着、沈殿剤を利用することで固化も可能になった。豊原准教授は「除去したセシウムを土に埋めても、固化されていれば地下水に溶け出さない」と話している。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2011111302000030.html
*余談。
除染作業をする時には、必ず、防塵マスクを着用してください。
最近、除染作業を行った人々の体調不良、リンパ腺が腫れるなど、が発生しているようです。
(メディアは、新聞社やニュース報道で報道してください)。
おそらく、これは、土壌の掘り返しや草むしりなどの際に、放射性物質が、空中に再度、巻き上げられ、人体内に入り込んだ可能性があると言う事になります。
通常のマスクの場合、そのままだと防塵性が低いので、水で濡らして、使用した方が効果的です。
乾かないように湿らせておく事が重要です。
*処で、放射能瓦礫の処理、東京などの処理場で処理しているが、放射性物質のまき散らし対策はしっかりしているのであろうか?。
東京の場合、国より制度、体制はしっかりとしていると思うが、、、。
その部分、多少気になったところだ。
関連する投稿
細野原発担当へ~大量な土壌汚染の洗浄法~酸とプルシアンブルーで対応可能。
2011年09月11日 09時33分33秒 | 政治・自衛隊
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/745155c1db8206685ba712e939259691
記事参照
ヒマワリの土壌除染、ほぼ効果なし~農水省
< 2011年9月14日 19:12 >
放射性物質による農地の土壌汚染を減らすためにヒマワリなどは効果があるのか、農水省が14日、実証実験の結果を公表した。
農水省によると、実施した複数の実験のうち、ヒマワリなど植物が育つ過程で放射性物質を吸収させる方法は、ほとんど効果が認められなかった。
一方、5000ベクレル以上の高い濃度の放射性物質に汚染された土壌の場合、ブルドーザーなどを使って表面を取り除く方法が最も効果的で、約75%を取り除くことができたという。
しかし、この方法では汚染された残土が大量に発生するため、農水省は、土から放射性物質だけを取り除く方法を引き続き検証する方針。
注目ワード
放射性物質 方法 土壌除染 効果的 土壌汚染
※「注目ワード」はシステムによって自動的に抽出されたものです。
• 過酸化水素を用いた新除染技術
• 大気社の過酸化水素による腐食が生じない 安全確実な除染技術を提供します
• taikisha.co.jp
【関連記事】
2011.09.15 01:45
土壌除染に期待のヒマワリ、効果表れず
2011.09.09 16:22
除染後土壌の仮置き場、国有林活用を検討
2011.09.07 23:09
学校のプール「除染の手引き」を公表
2011.08.30 01:16
農地汚染地図、福島40地点で作付け制限超
2011.08.29 21:34
土壌の放射性物質の濃度分布マップを公表
http://www.news24.jp/articles/2011/09/14/06190618.html
記事参照
独立行政法人 産業技術総合研究所 広報部 報道室
土壌中のセシウムを低濃度の酸で抽出することに成功
-プルシアンブルーナノ粒子吸着材で回収し放射性廃棄物の大幅な減量化へ-
2011年8月31日 発表
ポイント
土壌から酸水溶液でセシウムイオンを抽出し、抽出したセシウムイオンを吸着材で回収
抽出したセシウムイオンはプルシアンブルーナノ粒子吸着材でほぼ全量を回収可能
放射性セシウムに汚染された廃棄土壌などの大幅な減量化に期待
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2011/pr20110831/pr20110831.html
同義記事
土壌のセシウム除去法を開発 低濃度の酸水溶液利用
2011/08/31 20:33 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201108/CN2011083101001013.html
“新技術でセシウムを除去”
8月31日 21時23分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110831/t10015281421000.html
放射性セシウム:土壌からほぼ全量回収可能…新技術を開発
毎日新聞 2011年8月31日 22時27分
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110901k0000m040119000c.html
土壌セシウムの除去法開発=廃棄物減少に期待-産総研
(2011/08/31-22:45)
http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&k=2011083100923
産総研、土壌中セシウムを低濃度の酸で抽出することに成功
2011/08/31
http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=290240&lindID=5
*この技術、「食べ物」にも利用できそうだ!。
例えば、「セシウム汚染していそうな、怪しいキュウリ」など、穀物酢などで「ピクルス」にすれば、酢にセシウムが溶け出し、完全ではないかもしれないが、汚染度を軽減できそうだ。
*この場合、利用した酢は「セシウムが溶けているので再利用はしてはならない」。
個人的には最近、キュウリのピクルスを良く作っている。
あくまでも個人的な作り方。
キュウリをよく洗う(個人的には中性洗剤を多少付け、キュウリが「キュキュッ」と鳴るまで、洗浄している)。
適当な大きさに切り分ける。
ピクルスの液を作る。
多少、水で薄めた穀物酢に醤油、砂糖、塩、唐辛子(大まかに切ってある一味唐辛子)を混ぜ、沸騰させる。
辛いものが苦手な場合、唐辛子を入れないか、「花さんしょう」などが良いかもしれない。
比率は酢が1の場合、水が0.5、醤油、砂糖、塩、唐辛子は適宜、好みで変化させる。
(ピクルス液は、「甘酢」のような味の状態になっていれば良く、この味がキュウリにしみ込んでゆくのである。)
あらかじめ、切っておいたキュウリを瓶に「入るだけ」入れる。(潰してはならない)。
キュウリを入れる瓶については、「ゴールドブレンド」などの「コーヒーの瓶」を個人的には利用している。
沸騰させた「ピクルスの液」を、キュウリを入れた瓶に一気に流し込む。
蓋をして保管。(冷蔵庫でもそのままでも良い)。
ま、冷えていた方が旨い。
食べごろは2日、3日たってからが味がしみ込み旨くなっている。
関連する過去の投稿
セシウムとは/地熱発電と風力発電/その他、関連記事。
2011年07月12日 06時53分13秒 | 社会
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/ef5b009a6841261806696df73a59c80e
記事参照
汚染土壌の処理法開発=低コスト、放射能1割以下に-兵庫県
福島第1原発事故で放射能に汚染された土壌の浄化に役立ててもらおうと、兵庫県立工業技術センターなどは、凝集剤を使った新たな処理方法を開発した。
今月中にも福島県郡山市で本格的な実証実験を始める。
同センターは「従来の方法に比べコストが安い上、廃棄物が保管しやすく、大量の土壌を除染するのに向いている」と話している。
同センターによると、この凝集剤は植物の粉末と、吸着剤として除染に使われるゼオライトに似た性質を持つ鉱物で作る。
実験ではまず、福島県飯舘村の田んぼから採取した汚染土壌10グラムを水100グラムと混合。
工業用フィルターでろ過すると、土6グラムと濁り水104グラムに分かれ、土に残った放射性セシウムなどは7%に減っていた。
濁り水に凝集剤2グラムを加えて沈殿させ、さらにろ過したところ、沈殿物6グラムと水100グラムに分離。
沈殿物に残りのセシウムなどが集中し、水からは検出されなかった。(2011/08/21-15:00)
関連ニュース
• 【特集】ソーラーパワー~節電時代の救世主~
• 【ルポ】重大事故から25年、チェルノブイリは今~住民いまだ帰還できず
• 【特集】イマドキ女子が農業変えます!~「山形ガールズ農場」の挑戦~
• 【特集】原発事故は人災~佐藤・前福島県知事インタビュー
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&rel=j7&k=2011082100066&j4
溶け込んだ放射性物質分離・汚染水処理、このような方法もあるようだ!。
この分野は、やはり「京大」が強いのか?!。
記事参照
放射能汚染水、速く安く浄化 鉱山の技術応用 京大
関連トピックス 原子力発電所
放射能汚染水の安くてはやい浄化法
放射能汚染水から放射性物質を短時間で取り除く技術を、京都大が実証した。
鉱山などで古くから使われている方法の応用で、加熱の必要がなく、使う薬品も少ないため経費は安い。
福島第一原発で使われている浄化装置に比べ、除去後に生じる放射性廃棄物の量が少ないという。
京都大が14日に東京で開くシンポジウムで発表する。
京都大の古屋仲秀樹准教授(分離工学)らが実証したのは、必要な鉱物を分離する「浮遊選鉱法」の一種。
鉄やニッケルなどの化合物を汚染水に入れて、水に溶けたり、微粒子になって漂ったりしているセシウムなどの放射性物質を包んで沈める。
水と分離しやすくする薬剤を加え、下から泡を入れると、沈んでいた放射性物質が泡とくっついて浮かぶ。
上澄みの泡と一緒に集めれば取り除ける。
古屋仲さんが京都大原子炉実験所の研究用原子炉から出た低レベルの放射性廃液などで試したところ、セシウム、ストロンチウム、ジルコニウムなど5種類の放射性物質を99%以上除去できた。
一連の処理は十数分間で済むという。
• 関連リンク
• 放射能汚染水浄化装置が本格稼働 継続運転には不安も(6/17)
• 特集:東日本大震災
http://www.asahi.com/national/update/0708/OSK201107080148.html
*官邸でデモした方が良いのでは?。
なかなか良さそうな方法かもしれない!。
これでも駄目ならば、更に濾過すればかなりの浄化が可能かもしれない。
記事参照
石川のニュース 【5月27日03時02分更新】
放射性物質吸い取る細菌 タンザニアで発見
田崎和江金大名誉教授は26日までに、タンザニアの首都ドドマ近郊で、ウランなどの 放射性物質の濃度が高い土壌中に、同物質を吸着する細菌が生息していることを発見した。
福島第1原発事故後、放射性物質で汚染された土壌の処理が大きな課題となる中、「微生物が放射性物質を固定して拡散を防ぐ『ミクロ石棺』として役立つ可能性がある」とし ており、今月中に福島県で土壌調査を実施する。
2009(平成21)年3月に金大を退官した田崎名誉教授は、昨年11月にタンザニ ア・ドドマ大に赴任し、今年4月まで地質学担当として教べんを執った。
講義の傍ら、世 界的なウランの大鉱床があるドドマ近郊約50キロの町バヒで、これまでまとまった研究 がなされてこなかった土壌中の放射性物質濃度などの調査に乗り出した。
手始めにタンザニア全土の約100地点で計測し、バヒと周辺で放射性物質濃度が顕著 に高いことを確かめた田崎名誉教授は、バヒの水田土壌を採取して調査した。
電子顕微鏡による観察では、体長数百マイクロメートル(マイクロメートルはミリの1 千分の1)の細長い糸状菌の生息が確認された。菌体の周りには粘土鉱物の塊が多く付着 しており、この粘土は周りの土壌に比べて極めて高濃度のウランやトリウムなどの放射性 物質を含んでいた。
福島第1原発事故の後、現地周辺では、放射性セシウムなどが高濃度で検出された土壌 の除去、保管の方法について議論されている。
田崎名誉教授は、土壌中の微生物の生息状 況を調べるため、今月中に福島県飯舘村などへ入って調査を始める。
田崎名誉教授は1997(平成9)年のナホトカ号重油流出事故後、石川県沖における 調査で石油分解菌の海水浄化作用を確認した。
08年には北國新聞社の舳倉島・七ツ島自 然環境調査団副団長として、輪島市沖の七ツ島・大島で、大気汚染物質を取り込む微生物被膜を発見している。
福島での調査に向け、田崎名誉教授は「自然の中にはもともと大きな環境修復能力が備わっている。微生物の力を生かした汚染土壌処理の可能性を探りたい」と意気込んでいる 。
石川のニュース
• 写真の奥深さ光る 北國写真連盟 お気に入りの一枚展開幕
• アユ「大きく育って」 金沢市で園児が放流
• 作文、小論文を廃止 来春の県内公立高入試
• さい銭箱が「救援金箱」 金沢・橋場の善福寺
• 犀川の恵み、4万戸分 金沢、全国唯一の市営水力発電所
• 意欲作を飾り付け 「お気に入りの一枚」展
http://www.hokkoku.co.jp/subpage/H20110527102.htm
記事参照
原発汚染水処理能力、アレバの20倍 金沢大が粉末 毎時1000トン、東電に採用働き掛け
2011/5/22 23:47
金沢大学の太田富久教授らは、放射性物質を含む汚染水を効率よく浄化する粉末を開発した。
研究段階の成果だが、実用化すれば1時間に1000トンの水を処理でき、東京電力福島第1原子力発電所で採用された仏アレバの処理能力の20倍に相当するという。
東電などに採用を働き掛ける。
粉末は吸着剤のゼオライトや金属の凝集作用をもつ化学物質を数種類組み合わせたもので、汚染土壌用の浄化剤を改良した。
海水中の放射性物質を効率よく取り込んで沈殿する。
浄化剤メーカーのクマケン工業(秋田県横手市)と共同開発した。
放射性でないヨウ素やセシウム、ストロンチウムを1~10PPM(PPMは100万分の1)の濃度に溶かした水で実験したところ、ほぼ100%除去できた。
放射性物質の場合でも処理機能に違いはないとしている。
太田教授らはすでに大規模な処理システムを設計済みで、政府や東電に設置を提案していく。
関連キーワード
太田富久、放射性物質、アレバ、東電、原子力発電所
• 福島1号機、爆発防止用の窒素注入が3時間停止 (2011/5/22 20:21)
• 窮余の「循環注水」、実は既定路線か 福島第1原発 (2011/5/21 18:45)
• 汚染水処理の新施設、5月末にも稼働 仏アレバ、毎時50トン (2011/4/20 4:00)
• 汚染水流出250トン 福島原発3号機で (2011/5/21 15:30)
• 原発汚染水、窮余の再利用 実現にはハードル高く (2011/5/18 4:00)
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819595E3EBE2E3EA8DE0E0E2E7E0E2E3E386989FE2E2E2
ゼオライトと組み合わせると良いようだ。
セシウムを吸着したゼオライトを粉砕し水でセシウムを溶かし出す。
その後、セシウムを混入し、酸化チタンの結晶化を行う。
記事参照
セシウム安定的に閉じ込め 酸化チタンの固化体材料開発
半減期が長い放射性物質のセシウムを、長期間にわたって安定的に閉じ込めることができる酸化チタンの固化体材料を開発したと、物質・材料研究機構(茨城県つくば市)の研究チームが18日発表した。
従来のガラス固化体に比べ、外部への漏れがはるかに少なく、埋設処分のコスト削減が期待できる。福島第1原発事故で外部に放出され、水や土から回収されたセシウムを処分するのにも役立つ可能性がある。
チームは、熱や化学的変化に強い酸化チタンに着目。セシウムや酸化モリブデンと一緒に加熱して電気分解すると、直径50分の1ミリ程度の細長いチューブ状の結晶ができた。内部にはセシウムが閉じ込められており、両端以外の部分からは外部に漏れにくい構造になっていた。
材料には1立方センチ当たり1グラムのセシウムを閉じこめることが可能。高レベル放射性廃棄物の処分に使われているホウケイ酸ガラスに比べ、高温での外部への漏出量は170分の1以下だった。
2011/05/18 20:01 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201105/CN2011051801001030.html
同義記事
放射性セシウム閉じこめ材料の開発に成功 物質・材料研究機構
2011.5.18 22:32
東京電力福島第1原発事故で高濃度の放射性汚染水が海水などに流出している問題で、独立行政法人物質・材料研究機構(茨城県つくば市)は18日、放射性セシウム137を吸収し安定的に閉じこめる材料の開発に成功したと発表した。
放射性セシウム137は半減期が30年と、比較的長く水に溶けやすいため、安定した固体化合物に吸蔵して地下深くに埋設・貯蔵することが環境への拡散を防ぐのに有効とされている。
同機構の阿部英樹主幹研究員らのグループは、酸化チタンとセシウムを液体状の酸化モリブデンに溶かし電気分解した。その結果、結晶化した酸化チタンは1立方センチ当たり1グラムのセシウム137を取り込み、ほとんど溶出しないことを確認した。
角砂糖サイズの酸化チタンで、1立方センチ当たり3万7千ベクレルの放射性汚染水87トン分のセシウムを閉じ込められる。
福島第1原発事故では原子炉や燃料貯蔵プールの冷却のため注入された水が高濃度の放射性汚染水となって漏れ、事故対策統合本部では放射性物質を吸着する「ゼオライト」という物質を使って放射性セシウムを除去している。
阿部主幹研究員は「ゼオライトなどをどのように運び、濃縮するかなどの課題はあるが、セシウムを処分する最後の段階で役立つ技術」としている。
関連ニュース
• 【放射能漏れ】長野の焼却灰からセシウム
• 【放射能漏れ】「足柄茶」セシウム基準値超、計6市町村に 出荷自粛へ
• 【放射能漏れ】茨城産パセリが基準値超え セシウム、新潟で流通
• 【放射能漏れ】神奈川でも汚泥にセシウム 4下水処理場で
• 【放射能漏れ】下水道汚泥から放射性セシウム44万ベクレル 福島県「住民への影…
• 【放射能漏れ】セシウム、基準29倍に 福島沖のコウナゴ
• 【放射能漏れ】福島原発 2号機からセシウム 1、3号機、高い放射線量
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110518/dst11051822330040-n1.htm
平成17年8月11日
独立行政法人 放射線医学総合研究所 ビール成分に放射線防護効果を確認 放医研・東京理科大の研究チームがヒトの血液細胞とマウス実験で実証 放射線防護効果は最大34%にも
(本件の問い合わせ先)
独立行政法人 放射線医学総合研究所 広報室 TEL : 043-206-3026 FAX : 043-206-4062 E-mail : info@nirs.go.jp
サイトのご利用にあたって|個人情報の取り扱いについて
Copyright (c) 2007 National Institute of Radiological Sciences.
http://www.nirs.go.jp/news/press/2005/08_11.shtml
*個人的にはビールだけではなく、「酵母、酵素等の発酵した成分」が、遺伝子修復の際の「何らかの手助け」をしているような「気がします」。
根拠は無いのですが。
> フェロシアン化鉄の使用によるセシウム吸着汚染水浄化法
ttp://www.rerefa.com/archives/65670499.html
> 遠心力で分離した後、セシウムとともにフィルターでこし取る
やはり遠心力で分離ですね。
これは、(汚染土を水に入れて攪拌し、同様に処理で)土壌改善
にも使えるかもしれません。
研究者は実際に放射性物質で確認したくても、研究室の学生も
参加するのであれば、実験に難しいかもしれません。
> ビールで放射線をブロックできるかもしれないんですって
下記論文でしょうか。
ttp://www.nirs.go.jp/information/press/2005/08_11.shtml
> ビール成分に放射線防護効果を確認
1グレイ以上は人体にとっては強力な放射線量と考えられ、
(線量と時間の関係もありますが)250mSvでの白血球の一時的現象、
100mSvでの発ガン性増加率(ICRP勧告)や、下記の結果につじつまが
合わないから, 少し疑問です(その研究にケチをつけるつもりでもありません)。
ttp://www.med.nagasaki-u.ac.jp/interna_heal_j/a12.html
> 0.2グレイ以上被曝で人体に何らかの影響がでます。
記事参照
ゼオライト使用、低コストで二酸化炭素分離膜
研究内容を説明する長岡科学技術大の姫野修司准教授
長岡技術科学大(新潟県長岡市)の姫野修司准教授が、企業との共同研究で、温室効果ガスとされる二酸化炭素(CO2)だけを気体の中からほぼ分離する膜の開発に成功した。
この膜を利用して大規模なCO2回収・再利用技術を確立する研究が、国の最先端・次世代研究開発支援プログラムに採択。姫野准教授は、2015年春までの実用化を目指し、県内天然ガス田での利用などを検討していく考えだ。
開発した薄膜は、放射性物質の吸着剤としても注目される、ゼオライトと呼ばれる物質を使用。ケイ素とアルミニウム、酸素が格子状に並んだ結晶を持っており、これを薄く合成することで作られた。
非常に微細な穴が、CO2を通しやすい構造になっており、この膜を使えば、エネルギーをほとんど使わずに、低コストでCO2の回収が可能という。
現在、長さ約1メートルのレンコン状の円柱形通気材料などの開発を進めている。姫野准教授は、このサイズであれば1本で1日2トンのCO2回収が可能と見込んでいる。
国のプログラムには2月に採択され、4年間で大学が約1億5000万円の補助を受ける。企業4社とも協力して研究しており、下水処理場で汚泥などから発生するガスを用いた実証実験が進んでいる。
大型化には技術的な課題があるが、CO2回収に要するエネルギーは従来の5分の1程度で済むという。
姫野准教授は「全国最大のガス田地帯である新潟の特性も生かして実用化させ、CO2削減に貢献したい」と話している。
(2011年4月29日12時18分 読売新聞)
Powered by Fresheye
• 【M&A・企業ニュース】 温室ガス「9.5%減」…単年度では目標達成 (4月27日)
• 【環境】 09年度の国内温室ガス排出、削減目標達成(4月26日 21:49)
• 【電力】 原発再開・新設なければ、温室ガス1割増の試算(4月20日 16:25)
• 【M&A・企業ニュース】 被災・新設原発抜きなら温室ガス10%増(4月20日)
• 【地域から】 読書増やしCO2削減(2010年7月7日)
http://www.yomiuri.co.jp/eco/news/20110429-OYT1T00267.htm
(1)からの続き。
• 伝統行事「相馬野馬追」の馬、警戒区域外に (5月2日 13:37)
• 浜岡原発再開、慎重に判断すべき…首相 (5月2日 11:38)
• 女川原発内に130人避難…「他に場所ない」 (5月2日 11:30)
• 校庭の土壌処理、福島市長ら基準策定を国に要請 (5月2日 10:15)
• 小佐古参与辞任で福島知事不快感「県民が困惑」 (5月2日 10:08)
• 原発、海水利用の冷却断念…外付け空冷装置に (5月2日 03:08)
• 福島県の下水汚泥など、高濃度の放射性物質検出 (5月2日 02:34)
• 放射線量の高い土など「処理方法、国で検討」 (5月1日 21:40)
• 福島原発
関連記事・情報
Powered by Fresheye
• 【福島原発】 校庭の土壌処理、福島市長ら基準策定を国に要請 (5月2日 10:15)
• 【社会】 核燃料製造工場で廃棄物漏れ、過去に厳重注意(4月27日 23:40)
• 【科学】 汚染土壌浄化「ヒマワリ作戦」…復興の象徴にも(4月22日 14:49)
• 【福島原発】 窒素注入は米NRCの助言、水素爆発再発を警告(4月7日 21:58)
• 【福島原発】 露に供与の液体放射性廃棄物処理施設、福島に(4月5日 01:09)
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20110316-866921/news/20110501-OYT1T00472.htm
*この土を商業利用をしてはならない。
基本的には最終処分場で保管すべきだ。
セシウムの半減期、30年なのならば、60年後から100年後はかなり減っているのではなかろうか。
その頃に一度、開封してどうなっているのか?、確認し、放射線が無くなっていれば、地上に戻せば良いのだ。
別の記事だと半減するのに、200年から300年くらいかかると書いてあったが。
そう言えば、農林水産省の入り口の所に花壇があるだろ。
そこで使われているレンガ、放射性廃棄物の再利用品と言う記憶があるが、今でもそのままなのであろうか?。
ガイガーカウンターで計測すると「ピピッ」と、音が鳴るのではなかろうか。
興味のある人は調べてみると良い。
何処かの記事で、「そのように書いてあったのを記憶している」。
たしか、都内でも、色々な所でそのレンガは使用されていると記憶している。
しかし、そんなモノ、よく許可が出たものだ。
処で、とある事を、思い出してしまった。
「とある場所」に以前住んでいたが、その際、近くに(低レベル?)放射性廃棄物を集めて、埋めたらしい更地があった(放射線のマークの看板を立てており立ち入り禁止)が、その後、土地開発と言う事で、その場所に多くの家が建っているが「大丈夫なのであろうか?」。
そこで生活している人々、「健康は大丈夫なのであろうか」。
不動産屋も、当初はその事を知りつつも恍けていたが、現在では土地を転がし過ぎて、「分からなくなっている」のであろうか。
いや、恍けているに違いない。
このようなダークな出来事、数多くあると思うョ。
記事参照
ビールで放射線をブロックできるかもしれないんですって #jishin
2011.03.15 16:21 [6] [0]
http://www.gizmodo.jp/2011/03/beer_jishin.html
記事参照
平成17年8月11日
独立行政法人 放射線医学総合研究所 ビール成分に放射線防護効果を確認 放医研・東京理科大の研究チームがヒトの血液細胞とマウス実験で実証 放射線防護効果は最大34%にも
【概要】
放射線医学総合研究所 (佐々木 康人 理事長) 粒子線治療生物研究グループは東京理科大学薬学部放射線生命科学の研究チームと共同で、ビール成分が放射線を防護する効果があることをヒトの血液細胞やマウスを用いた実験で明らかにした。
アルコール飲料に放射線を防護する効果があることはすでに報告していたが、ビールに溶けこんでいる麦芽の甘味成分などに放射線により生じる染色体異常を最大で34%も減少させる効果があることをつきとめたのは初めて。
同研究グループは、広島・長崎の原爆やチェルノブイリ原発事故被害者のなかにアルコール飲料で放射線障害が低減されたという話がある事をきっかけにして研究を展開。
ビールを使った実験でビールそのものに放射線防護効果があることを明らかにしてきたが、ビールの中の何に放射線防護効果があるかは、未解明のままであった。
今回、ビール中のアルコール分(エタノール)に加え、ビールに溶けこんでいる成分にも放射線防護効果があることをつきとめ、放射線被ばくの前にビールを飲むと、放射線による障害から防護されることを示した。
今後、同研究グループは、さらに放射線防護成分の探査を行うとともに放射線をあびた後の防護効果の確認、血液以外の臓器細胞に対する効果、作用のメカニズムの解明などに研究を発展させていく。
放射線防護剤にはさまざまな薬が開発されているが、副作用を伴うものもあり、新たな薬剤開発が待たれている。今回の成果は、新たな放射線防護薬剤開発に一石を投じるものとされる。
【背景】
放射線防護剤は一般には入手が困難であり、また副作用を伴うものが多く、長期間の服用にも課題が残る。このためニンニク、朝鮮人参、味噌などの食品や食品成分による研究が進められている。
同研究グループは、エタノール、メタノール、グリセロールなどのアルコール類に放射線防護効果があることが以前から知られていることや、飲酒により放射線障害が軽減されたなどの体験談から、アルコール飲料の放射線防護効果に着目した。
今回、数多くあるアルコール飲料の中でもビールを選択したのは、入手し易く、アルコール濃度がそれほど高くない(比較的飲みやすい)などの理由による。
2001年には、ビールを摂取したヒトの血液細胞を採取し、放射線を照射してダメージを調べる方法でビールによる放射線防護効果を確認した。
だが、ビール中のどの成分が放射線防護効果をもたらすのかは、調べ切れていなかった。
今回放射線防護効果を確認した成分等は、いずれもビールに極めて微量含まれている成分だが、これらが相加もしくは相乗的に作用していることが推察できる。
【研究手法と成果】
●ビールの放射線防護効果の確認実験
ビール摂取前とビール大瓶1本を摂取後3時間後に採取した血液(血中エタノール濃度は約10ミリM*モル濃度)にX線または重粒子線(炭素イオン : 放医研HIMACでがん治療に利用されている)を1グレイから6グレイまで照射し、摂取前後での血液細胞の染色体(ヒトリンパ球染色体)異常を比較した。(図1参照)
図1. 放射線により生じた血液細胞一個あたりの染色体異常の数
(飲酒後の染色体異常の数は、飲酒前のそれより明らかに少ない)
その結果、ビールの放射線防護効果は、X線ばかりか重粒子線(炭素イオン)にもあることが確認でき、これは、マウスの骨髄死を調べる実験でも同様であった。
図2. では、ビールの効果がエタノール単独の効果よりも高いこと、ノンアルコールのビールでは放射線の防護効果が認められないことが示されており、ビール中のアルコールはビール成分の吸収に一役買っていることが示唆された。
* 生理食塩水(コントロール)
図2. ビール他の放射線防護効果比較 (ノンアルコールでは効果が認められず、エタノール(アルコール)単独よりも、ビールのほうが放射線防護効果が高い)
●ビール成分の放射線防護効果の確認実験
これらの結果、ビール成分に放射線防護作用を示す物質が含まれていることが予測された。
このことを実験的に確かめるため、ビールの微量成分であるシュードウリジン、メラトニン、グリシンベタインをそれぞれヒトの血液に添加したり、あるいはマウスに投与(経口投与、腹腔投与など)して放射線防護効果を調べた。
具体的にはX線もしくは137Csが発するガンマ線のような低LET放射線とLET50keV / μm(キロ電子ボルト/マイクロメートル)の重粒子線(炭素イオン)を用い、照射量を変化させた時の染色体の異常、マウスの生存率(照射後30日の生存確率を調べる)などを測定した。
その結果、ビールに約5μg / mL含有するシュードウリジン(注1)をヒトの血液に添加した実験では、4グレイのX線照射後のヒトのリンパ球細胞の染色体異常が無添加のコントロールに比べ34%、4グレイの重粒子線(炭素イオン)の場合には、32%減少した。(図3参照)
図3. シュードウリジン添加ヒトリンパ細胞に放射線を照射した染色体異常の数
(無添加に比べ、染色体異常の減少が明らか)
同じく、ビールに極く微量含有するすることが知られているメラトニン(注2)では、マウスを使った実験からガンマ線照射の場合14グレイから21グレイで防護効果があったが、重粒子線(炭素イオン)では全く効果がないことが認められた。(図4参照)
図4. メラトニン投与マウスの放射線を照射による陰窩*数の変化 (メラトニン投与によって、ガンマ線では陰窩*数の減少が抑えられるが重粒子線では変化が無い)
* 陰窩とは : マウスの腸管上皮直下の細胞集団で、「陰窩」と呼ばれる組織。放射線照射によって数が減少することから、放射線影響の実験に用いられる。
さらに、ビールに約80μg / mL含有するグリシンベタイン(注3)をヒトの血液に添加した実験では、4グレイのガンマ線照射後のヒトのリンパ球細胞の染色体異常が無添加のコントロールに比べ約30%(最大37%)、4グレイの重粒子線(炭素イオン)の場合には、17%減少した(図5参照)。
図5. グリシンベタイン添加時に放射線を照射したヒトリンパ球細胞の染色体異常の数
(無添加に比べ、染色体異常の減少が明らか)
また、マウス腹腔内投与した場合には、全身照射による骨髄死を明らかに抑制することが確認された。(図6参照)
図6. グリシンベタイン投与マウス放射線照射後30日の生存率
(グリシンベタイン48mg以上の投与で骨髄死を抑制)
【今後の展開】
一連の実験でビール成分には放射線防護効果があることが明らかとなった。
この防護メカニズムを明らかにしていくことや血液細胞以外の他の臓器細胞での放射線防護効果の確認、さらに他のビール成分での防護効果を探査していく。
一連の防護効果確認実験では、被ばく前にビールを飲むと防護効果は高まるという結論を得た。
だが、被ばく後に防護効果があるのかは、いぜん未解明のままであり、さらにビール成分が放射線防護効果を持つメカニズムの解明を進めてゆく。
注1. β-pseudouridine (シュードウリジン)
N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG)により誘発されるサルモネラの変異がビール添加により抑制され、その効果はビール中のシュードウリジンによることが2002年岡山大学の吉川友規氏らによって確認された(MNNGはDNAをアルキル化することによりDNA切断を起こし、染色体異常を引き起こす物質である)。
シュードウリジンは、ビールに約5μg / mL含まれているが、製品によって含有量は異なっている。
注2. Melatonin (メラトニン)
メラトニンは、脳内の松果体から分泌されるホルモンであり、体内時計を調節している。メラトニンの放射線防護効果は、1995年に Vijayalaxmiらにより初めて報告された。ビールには約50~300 pg / mLのメラトニンが含まれている。
注3. グリシンベタイン (別名 : ベタイン,トリメチルグリシン)
グリシンベタインは主に砂糖大根から分離精製されているが、エビ、カニなどの水産物や麦芽、キノコ類、果実などにも多く含まれている天然の物質であり、甘味料として利用されている。
冠動脈疾患のリスクファクターとされているホモシステインを減少させることが知られており、高脂血症、脂肪肝、肝機能障害、肥満等の改善に有効という報告がある。
また、ホモシステインをメチオニンに転換させる作用を利用してホモシスチン尿症患者への利用が報告されているほか2-chloro-4-methylthiobutaniod (CMBA)による突然変異を抑制することが報告されている。
ビールには約80μg / mL含まれているが、製品によって含有量は異なっている。
(本件の問い合わせ先)
独立行政法人 放射線医学総合研究所 広報室 TEL : 043-206-3026 FAX : 043-206-4062 E-mail : info@nirs.go.jp
サイトのご利用にあたって|個人情報の取り扱いについて
Copyright (c) 2007 National Institute of Radiological Sciences.
http://www.nirs.go.jp/news/press/2005/08_11.shtml
放射線量の高い土など「処理方法、国で検討」
枝野官房長官は1日の記者会見で、東京電力福島第一原子力発電所の事故で放射線量の数値が高くなった土などの処理について、「原発以外の所で発生する放射性廃棄物の処理にどう対応するかは、簡単に答えの出る問題ではない。
若干時間がかかるが、国として検討を進める」と述べた。
この問題では、政府は年間20ミリ・シーベルトの放射線量を上限に小中学校の校庭利用を認めた。
この基準では不十分だという意見もあり、福島県郡山市は基準以下の場所も含め、放射線量が比較的高い小中学校の校庭などの表土を除去したが、埋設予定地周辺の住民から反発が出て、処分方法が決まらないままになっている。
(2011年5月1日21時40分 読売新聞)
最新主要ニュース8本 : YOMIURI ONLINE トップ
福島原発 特集
• 岡本太郎の壁画に原発事故思わせるいたずら (5月2日 14:44)
• 福島第一1号機に換気装置6台…設置作業開始 (5月2日 14:03)
(2)に続く。
放射性セシウムを効率よく収集する方法を東工大は公表したようだ。
放射性汚染水の浄化法公開、東工大
有冨正憲 教授
フェロシアン化鉄の使用によるセシウム吸着汚染水浄化法。
2011/04/20 19:40
http://www.nikkei.com/video/?bclid=67421386001&bctid=911499863001
*上記のURLに繋ぐと、日経新聞の「映像プレーヤー」の画面になります。
ページ画面上部の黒いバーの「検索」の入力部分で、「放射性汚染水の浄化法公開」を入力。
その内容を確認出来ます。
09/08(昨日)の報道ステーションで、沸石(ゼオライト)の簡易実験を行ったようだ。
色付きのインクのような液体を、沸石(ゼオライト)の粉末?に濾過したところ、透明な液体が出てきた。
ゼオライトを扱っている会社の人も「水質改善」、「土壌汚染等」も、「効果的に処理が出来る」と述べていた!。
東電や官邸等は、テレ朝に連絡して、「その件を問うてみるべき」だ。
「効果が確認、国として証明」出来れば、汚染で困っている、農民や漁民、更には「消費者」も「納得する事が出来る」と言う事だ。
重要な事は、国としては「問題がない」、「安全だ!」、、、と述べるのなら、その「論的根拠・証拠」を国民に示す必要があると言う事になる。
国際的に「発信した国としてのコメント」も同じだ、、、。
第三者、全くその事を知らない人でも「納得させる情報提供」が求められる。
日本原子力学会の「その論文を確認したが、何処にも無い」のである、、、。
しかも、日本原子力学会は、一般社団法人日本原子力学会へ移行しました(2011年4月1日)となっている、、、。
問題が巨大化し、面倒になりそうだ!となれば、「名称変更等を行うと言う事か?!」、、、。
正に、経済産業省や、資源・エネルギー庁の「天下り団体・施設」と言えそうだ!。
何をしている団体なのであろうか?、、、。
機能している団体なのであろうか!。
ゼオライトの件も、やはり「原子力産業を守る為(ゼオライトを使えば、原子力発電は安全だ!)の「嘘工作の可能性」が出てきた!、、、。
日本原子力学会
http://www.aesj.or.jp/
理事会
■一般社団法人日本原子力学会へ移行しました(2011年4月1日)
本会は、2010年6月18日の通常総会にて一般社団法人へ移行することを意志決定し、10月19日に内閣府公益認定等委員会に対し一般社団法人への移行認可申請を行いました。
その結果、2011年3月25日に移行が認可されました。
これにより、2011年4月1日に一般社団法人としての登記を行い、本会は「一般社団法人日本原子力学会」として、新たにスタートいたしました。
会員の皆様には、本会活動への一層のご支援ご協力を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
※4月1日以降、本会の法人名は「一般社団法人日本原子力学会」となりましたので、本会各組織発行の文書等への記載法人名も「一般社団法人日本原子力学会」とするようご注意願います。
新法人名
一般社団法人日本原子力学会
旧法人名
社団法人日本原子力学会
変 更 日
平成23年4月1日
Copyright © Atomic Energy Society of Japan All Rights Reserved.
http://www.aesj.or.jp/information/shinhojin.html
*念の為に「官邸は確認すべき」だ、、、機能していない団体(税金の無駄遣い)なのではなかろうか!。
文頭の文章株に記述してあるが、、、。
「ゼオライトが含有する液体飲料を飲むと放射性物質を吸着し、体外に排出すると謳う商品があるがゼオライトそのものにそのような効果は無く薬事法違反にあたる。」と記述している、、、。
しかし、日本原子力学会の有志らは、仙台市青葉区の愛子(あやし)産の鉱物「天然ゼオライト」が有望であることを、7日発表した、、、、と記事では記述したある。
確認が必要だ。
又、おかしな商品を販売しているのならば、その会社に対しては「出荷禁止」など対応を取る必要があり、「消費者庁は調査」、「適切は処理」を行う必要がある。
記事参照
wikipediaより
沸石
この項目では、鉱物の沸石について記述しています。突沸防止用の多孔質物体については「沸騰石」をご覧ください。
沸石
沸石[1](ふっせき,zeolite)とは、アルミノケイ酸塩のなかで結晶構造中に比較的大きな空隙を持つものの総称である。
天然に産する鉱物のグループ名でもあるが、分子ふるい、イオン交換材料、触媒、吸着材料として利用されるため、現在ではさまざまな性質を持つ沸石が人工的に合成されており、工業的にも重要な物質となっている。
工業的に利用される場合は、しばしば英名のままゼオライトと呼ばれる。
成分に含まれている水とアルミノケイ酸骨格との結びつきが弱いため、加熱すると容易に水を分離して沸騰しているように見え、このことからギリシャ語のzeo(沸騰する)とlithos(石)を合わせてzeoliteと名付けられた。
ゼオライトが含有する液体飲料を飲むと放射性物質を吸着し、体外に排出すると謳う商品があるがゼオライトそのものにそのような効果は無く薬事法違反にあたる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/沸石 より
、、、(3)の続き。
2011年04月03日 23時00分00秒
未臨界量のプルトニウムの塊「デーモン・コア(悪魔のコア)」
「ちょっと手が滑っただけで大惨事となったり、科学者が素手でこねくり回していた物体が数ヵ月後に世界を死の恐怖に陥れたりするセカイ系テイストとか、世界の人々が数万人単位で死んだり、自分も死んだりする可能性があることを何とも思っていないマッドサイエンティストぶりとか、あとこの「デーモン・コア」と言うネーミングとか、この記事を書いた人は嫌すぎる」ということで、日本語版Wikipediaに先月末に新しく登場した「デーモン・コア」の項目がなかなか秀逸です。
その名の通り、各種エピソードが「デーモン・コア(悪魔のコア)」という名にふさわしいくらいにぶっ飛んでおり、再現写真もあるのでその実験内容の恐ろしさが実感できます。
中身は以下から。
「デーモン・コア」という物がある - ymitsu の日記
デーモン・コア - Wikipedia まずは全体の説明。
これだけでも相当の破壊力のある概要となっています。
デーモン・コア(Demon core)とは、アメリカのロスアラモス研究所にて各種の実験に使われ、後に原子爆弾に組み込まれてクロスロード作戦にて使用された約14ポンド(6.2kg)の未臨界量のプルトニウムの塊。
不注意な取り扱いのために1945年と1946年にそれぞれ臨界に達する事故を起こし、二人の科学者の命を奪ったことから「デーモン・コア(悪魔のコア)」のあだ名がつけられた。
ということで、まずは第一の事象から。ちなみに原発関連では昔から、安全面で問題があるかのような印象を与えるという理由から事故が起きても「事故」とは言わずに「事象」と称してごまかすことが多いことが知られています。
1945年8月21日、ロスアラモス研究所で働いていた物理学者のハリー・ダリアンは、後にデーモン・コアと呼ばれるプルトニウムの塊を用いて中性子反射体の働きを見る実験を行っていた。
プルトニウムの塊の周囲に中性子反射体である炭化タングステンのブロックを積み重ねることで徐々に臨界に近づける、と言う要旨の実験であった。
ブロックをコアに近づけ過ぎると即座に臨界が始まり、大量の中性子線が放たれるため危険である。
しかしダリアンは手が滑り、ブロックを誤ってプルトニウムの塊の上に落下させてしまった。
プルトニウムの塊は即座に臨界に達し、そこから放たれた中性子線はダリアンを直撃した。
ダリアンはあわててブロックをプルトニウムの塊の上からどかせたものの、彼はすでに致死量の放射線(5.1シーベルト)を浴びていた。ダリアンは25日後に急性放射線障害のために死亡した。
この再現写真がこれ。
これのどこが「事象」なのかよくわかりませんが、この研究者以外に犠牲者が出なかったのでなんとかぎりぎり事象レベルかもしれません。
しかし次なる「第二の事象」によってこのプルトニウムの塊は「デーモン・コア」の名にふさわしいものとなります。
1946年5月21日、カナダ出身の物理学者ルイス・スローティンと同僚らはロスアラモス研究所にて、臨界前の核分裂性物質に中性子反射体をどの程度近づければ臨界に達するか、の正確な位置を調べる実験を行っていた。
今回使われた中性子反射体はベリリウム、臨界前の核分裂性物質として使われたのは昨年ダリアンの命を奪ったデーモン・コアである。
スローティンらは球体状にしたベリリウムを分割して二つの半球状にしたものを用意し、その中央にデーモン・コアを組み込んだ。
そして、ベリリウムの半球の上半分と下半分との間にマイナスドライバーを挟み込み、手に持ったマイナスドライバーをぐらぐらさせて上半分の半球をコアに近づけたり離したりしながらシンチレーション検出器で相対的な比放射能を測る、と言う実験を行った。
挟みこんだドライバーが外れて二つの半球を完全にくっつけてしまうと、デーモン・コアは即座に臨界に達し、大量の中性子線が放たれるため危険である。
この実験はたった一つの小さなミスも許されない危険性から、ロスアラモスの人望高い研究者リチャード・ファインマンが「ドラゴンの尻尾を撫でるようなものだ」("tickling the dragon's tail")と批判し、他のほとんどの研究者も参加を拒否した悪名高い実験であったが、功名心の強い若き科学者であったスローティンは皆の先頭に立って何度かこの手の実験に参加しており、ロスアラモスのノーベル賞物理学者エンリコ・フェルミも「そんな調子では年内に死ぬぞ」と忠告していたと言われる。
現場再現写真がこれ、見ているだけでも戦慄しそうな実験です。
もちろん「事象」が起きるわけですが……。
そしてついにこの日、スローティンの手が滑り、挟みこんだドライバーが外れて二つの半球が完全にくっついてしまった。
即座にデーモン・コアから青い光が放たれ、スローティンの体を熱波が貫いた。
コアが臨界に達し、大量の中性子線が放出されたことに気づいたスローティンはあわてて半球の上半分を叩きのけ、連鎖反応をストップさせ他の研究者たちの命を守ろうとした。
彼は文字通り皆の先頭に立って実験を行っていたため、他の研究者たちへの放射線をさえぎる形で大量の放射線をもろに浴びてしまった。
彼はわずか1秒の間に致死量(21シーベルト)の中性子線とガンマ線を浴び、放射線障害のために9日後に死亡した。
スローティンの間近にいた同僚のアルバン・グレイブスも中性子線の直撃を受けたが、彼はスローティンの肩越しにデーモン・コアを見ていたため、中性子線がいくらかスローティンの体によってさえぎられ、数週間の入院の後に無事退院できた。
とはいえその吸収線量は少なくなく、慢性の神経障害と視覚障害の後遺症が残り、放射線障害に生涯苦しみぬいた末に20年後に心臓発作で死亡した。
その他の研究者たちは臨界を起こしたデーモン・コアからの距離が十分離れていたため、幸い身体的な影響は出ずに無事であった
この際の位置関係を図示したのがこれです。
今回の福島第一原発関連の会見で頻繁に出てきた「直ちに健康に影響があるわけではない」の「直ちに」というのは「今すぐ死ぬわけではないがそのうち死ぬことがあるかもしれないけれど、どこがしきい値なのかは人によって違うし、追跡する方法もない」ぐらいの意味なのですが、このデーモン・コアはまさに「直ちに健康に影響がある」レベル。
おそらくこれぐらいのレベルの「事象」が起きない限り、「直ちに健康に影響がある」ことにはならないのでしょうノノ。
・関連記事
チェルノブイリ原発事故で死の灰からモスクワを救うためにどうしたか? - GIGAZINE
チェルノブイリは事故から21年経ってどのような姿になったのか - GIGAZINE
ロシア西部の森林にある謎の巨大球体に放射能の影? - GIGAZINE
加速器によって大量の放射線を浴びた男性 - GIGAZINE
「ミリシーベルト」「マイクロシーベルト」とはどんな単位なのか、どのくらいから危険なのか?放射線量計測単位のまとめ - GIGAZINE
放射性物質による汚染を除去する「除染」の具体的な方法まとめ - GIGAZINE
汚染された水道水からヨウ素131やセシウムなどの放射性物質を除去することに成功 - GIGAZINE
2011年04月03日 23時00分00秒 in サイエンス Posted by darkhorse
http://gigazine.net/news/20110403_demon_core/
関連する投稿
「原子力発電は安全!」と述べる者、「すぐには影響は無い」と述べる者、、、放射線を「甘く見るな」!。
2011年04月05日 03時49分29秒 | 食/医療
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/318056a6f6a4de1cf75a8c9aec91f4bb
電線用トンネルの、複数の束になった「配管の直径」が重要だ。
2011年04月04日 00時53分42秒 | 社会
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/af7c706e4600fc34d26f2d2e77cc317a
放射能汚染水、外洋へ拡散!/海外各国の見方/農家の状況(飯館)(1)
2011年04月03日 03時11分27秒 | 社会
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/b274be1a799406770462d98cdd1fe3ee
福島第1原発爆発事件、米GE社の元原子炉設計者、「設計に脆弱性あると指摘」。
2011年04月02日 15時59分40秒 | 科学/ハイテク
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/55bdb830e4aa4d6976e5fd68463cf3ce
緊急!、、福島原発問題・福島県・「飯舘村」の人々は避難せよ~高濃度放射性物質検出!(IAEA)
2011年03月31日 02時20分37秒 | 社会
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/4360b4f516f8769b865416d56025453a
福島第一原発・放射能汚染問題~原発の燃料棒が精製したヨウ素の気化ガスか?!。
2011年03月26日 19時03分14秒 | 社会
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/b9cbd72953d248541045e49abffc9217
政府と東電、一部の洗脳学者は正直なれ!~原発元技術者ら告発「パニックにしない配慮、多すぎ!」(1)
2011年03月26日 11時58分07秒 | 社会
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/9588fe84f56fd4a77eb13e03e9232d21
その他、多数、、、。
、、、(2)の続き。
◆ゴム
手順1:水または薄めた中性洗剤で洗う
手順2:5%Na-EDTA+1%中性洗剤でこすり水で洗い流します
手順3:1%クエン酸ソーダ+5%水酸化ソーダでこすり水で洗い流します
◆リノリウムその他の床材
手順1:ペイントに対する方法と同じ
手順2:有機溶媒の使用は避けた方がよいですが、やむを得ない場合は、CCl4や灯油などを布につけてぬぐいとります
◆タイル
手順1:あらかじめ、その面をペイント塗装しておきます
手順2:酸化チタン+Na-EDTAのペーストでこすりぬぐい去ります
手順3:液体除染剤はあまり適していませんが、やむを得ず使う場合は、0.3%クエン酸アンモニウム、4%Na-EDTA、10%Na3PO4などを使います。
手順4:可能であればタイルをはがして取り替えます
◆コンクリート、レンガ
手順1:酸化チタン+Na-EDTAを散布してから、水でぬらした布でぬぐいとります
手順2:30%HClでぬらし、こすってから水で洗い流します。この時、作業している部屋の換気をしっかりと行います。
手順3:タガネではがしてしまうか、塗装して塗り込めます
◆木材
表面から約1cmぐらいの部分を削り取ります なお、上記に記載した除染に関する内容については、通商産業研究社発行の「放射線安全管理学」(平成20年3月25日発行の改々題第1版第1刷、2011年3月時点での最新版)から、除染方法の部分(P125~P130)を使用しています。
・関連記事 「ミリシーベルト」「マイクロシーベルト」とはどんな単位なのか、どのくらいから危険なのか?放射線量計測単位のまとめ - GIGAZINE
日本各地の放射線量がわかるサイト「放射線監視モニタまとめ」 - GIGAZINE
福島第1原発から現在地までの距離や計画停電情報をiPhoneやドコモの携帯電話で測定して表示するサイト - GIGAZINE
福島第一原発へ自衛隊がヘリからの放水を開始、地上からは機動隊が高圧放水 - GIGAZINE
2011年03月17日 18時32分07秒 in メモ Posted by darkhorse_logh
http://gigazine.net/news/20110317_decontamination/
2011年03月25日(金)18時11分
降下セシウムは核実験時代の3倍 「早く沈静化を」と専門家
福島第1原発事故で東京に降り注いだ放射性物質のセシウム137は、最大となった降雨の21~22日に、1960年代前半まで行われた大気圏内核実験で1年間に降った量の3倍近くに達したことが25日、分かった。
放射線医学総合研究所の市川龍資元副所長(環境放射能)の資料と、文部科学省の発表データを比較した。市川さんは「今のレベルなら心配することはないが、これ以上(放射性物質が)外に出ないよう、早く原子炉を冷却し、沈静化させてほしい」と話している。
市川さんによると、米国、旧ソ連、英国が63年に部分的核実験禁止条約に調印するまで、米ソは盛んに核実験を繰り返した。63年に東京で確認されたフォールアウト(放射性降下物)のセシウム137は年間1平方キロメートル当たり52ミリキユリー。
換算すると1平方キロメートル当たり1924メガベクレルになる。
文科省によると、今月18日以降、東京で降下物として検出したセシウム137は、24時間ごとの値で最大だった21日午前9時~22日午前9時は5300メガベクレルで、63年の1年間の約2・8倍になった。
降雨で降下物が多かったとみられ、翌日以降は400メガベクレル以下に減少した。
市川さんは「問題はどれだけ体に入ってくるかだ。長引くと農作物の濃度が高まりやすく、厄介だ」としている。
関連記事
powered by weblio
• 福島原発、電源復旧作業を再開 3、4号機へ放水準備(03/22)
• 茨城北部の水道水にセシウム 微量「人体に影響なし」と知事(03/20)
• 9都県で水から放射性物質 降下物は7都県、影響なし(03/20)
• 水道水から微量のセシウム検出 福島市、摂取基準には達せず(03/16)
• 福島第1原発で炉心溶融、国内初 避難拡大、半径20キロ(03/12)
用語解説:
放射線医学総合研究所 部分的核実験禁止条約
http://www.sannichi.co.jp/kyodo/news2.php?genre=Main&newsitemid=2011032501000755
2011年03月31日 12時10分27秒
汚染された水道水からヨウ素131やセシウムなどの放射性物質を除去することに成功
東日本大震災による福島第一原発の放射能漏れ事故を受けて、一部で水道水からヨウ素131やセシウムなどが検出され、ミネラルウォーターが品薄になるなどの事態が発生していますが、汚染された水道水から放射性物質の除去に成功したことが明らかになりました。
詳細は以下から。
ECOA(逆浸透膜ろ過を用いた純水造水装置)の放射性物質除去能力について |(株)寺岡精工 ニュース
「逆浸透膜ろ過」を用いて純水を作るシステム「ECOA」シリーズを展開する寺岡精工のプレスリリースによると、水道水に放射性物質が混入した事故を受け、同社に安全性について、ユーザーから多くの問い合わせがあったそうです。
基本的に「ECOA」シリーズは水道水をろ過して純水を造る装置であり、放射性物質のろ過能力については実証的な根拠は示されていませんでしたが、福島第一原発から約40kmに位置する福島県の飯舘村役場の協力を得て、放射性物質を含んだ同役場の水道水を「ECOA」でろ過する実験を行ったとのこと。
「ECOA」シリーズの製品紹介ページ。用途に応じてさまざまなモデルが展開されています。
逆浸透膜 水 自販機 純水 浄水器 ECOAシリーズ
実験では3月26日15:25と16:41、27日11:37と11:40に飯舘村役場の手洗い場の水道管に「ECOA」を接続し、水道水(原水)とECOAでろ過した水(RO水)の両方を採取。そして採取した水を放射能分析などを手がける株式会社化研の水戸研究所へ持ち込み、3月28日17:13、17:28、17:44、17:59に放射性物質の有無を計測しています。
これが測定結果。放射性ヨウ素131は原水が国の暫定規制値(300Bq/kg)を大幅に上回る「350~600Bq/kg」であったのに対して、RO水は「検出されず」となり、放射性セシウムについても原水が口の暫定規制値(200Bq/kg)を大きく下回る10~32Bq/kgで、RO水からは「検出されず」に。
この結果について寺岡精工は「ECOAによって最適に制御された原水の水圧と水流が逆浸透膜のろ過機能を効果的に引き出し、放射性ヨウ素と放射性セシウムの除去に著しい効果があったと考えられます」という見解を示しています。
なお、ECOAは逆浸透膜ろ過フィルターでろ過された不純物を膜の濃縮側から排水する構造になっており、ろ過された不純物がフィルターに蓄積されることはないほか、自動的にすべての経路の滞留水を排出する自動洗浄機能などを備えているとされています。
・関連記事
都内の浄水場から放射性ヨウ素を検出、乳児の摂取を控えるように呼びかけ - GIGAZINE
茨城県のほうれん草と福島県の牛乳の一部で食品衛生法の暫定基準値を上回る放射線量を検出 - GIGAZINE
放射能泉である「ラジウム温泉」はなぜ安全なのか - GIGAZINE
ロシア西部の森林にある謎の巨大球体に放射能の影? - GIGAZINE
2011年03月31日 12時10分27秒 in メモ Posted by darkhorse_loga
http://gigazine.net/news/20110331_ecoa_water/
(4)に続く、、、。
、、、(1)の続き。
◆眼や鼻、唇などの粘膜や傷口の除染
眼、鼻、唇といった粘膜が汚染されたら、すぐにたくさんのぬるま湯で洗い流します。 傷口の汚染もぬるま湯で洗い流して除染しますが、内部被ばくを防ぐため、汚染から15秒以内に洗浄を行います。
この時、失血が心配されるような出血の多さでなければ、傷口の周辺を圧迫して出血をうながし、汚染物質を体外に流し出します。
傷口の状態を見て、必要であれば柔らかいネイルブラシで傷口を掻くようにして洗います。 傷口に塵やグリースなどが付着している場合はすぐに手当します。
手当には液体洗剤(非イオン活性剤0.5%溶液)をしっかり含ませたガーゼを使い、傷口を静かにこすりながらぬるま湯で洗い流します。
また、傷口が非常に危険な核種で汚染された時は、汚染から15秒以内に静脈を止め、多量のぬるま湯でしっかりと洗い流し、三角布で傷口をしばります。
◆放射性物質を飲み込む、あるいは吸入した際の除染
放射性物質を飲み込んでしまったら、指をのどまで入れ、胃の中の物を吐き出してから、食塩水や水を飲みます。
放射性物質を強く吸い込んでしまったときは、何度もせきこんで物質を体外に出してから、水でうがいをするという一連の行動をくり返し行います。
<物の除染>
繊維やその他の物質、部屋の床などは、一般的には下記の方法でおおよその除染は可能です。
ただし、表面の汚染限度を超えた物を一般人が扱うのは非常に危険なため、検査で衣服や持ち物から高い数値が出た場合や、正確な除染に不安のある場合は廃棄してください。
手順1:水または中性洗剤で洗浄する。
手順2:キレート剤単独、またはキレート剤と中性洗剤の混液を使用し洗浄する
手順3:希鉱酸で洗浄する
これ以降は材質ごとによる詳細な除染方法となります。すぐに実行できる内容は少ないですが、物質によって対処法が異なることを頭に入れておくと、いざ処置することになった場合や処置される側に回った場合に役立ちます。
◆繊維類
・放射性溶液(放射性物質が水に溶けている物)で汚染された場合
中性洗剤(1%)とキレート形成剤(0.1mol/l)の混合液の温度30~40度にしてから、15分間洗浄する作業を計2回くり返します。
洗浄液は再利用せず、毎回新しい液を使ってください。その後、ぬるま湯で10分間すすぐのを2~3回くり返します。
※使用に適しているキレート形成剤にはEDTA(pH10)、ヘキサメタリン酸ナトリウム(pH3)があります。また、クエン酸は絹、ナイロン類の除染に適しています。
※pHの調整剤には塩酸、シュウ酸を使います。また、炭酸ナトリウムは木綿、レーヨンの除染に適しています。
・放射性不溶性物(固体や粉体)で汚染された場合
1%中性洗剤の液温を40度にした状態で約20分間ほど洗濯機にかけてまぜ続け、その間発生してくる泡はふたを開けておいてあふれさせておきます。
◆アルミニウム
手順1:水かうすめた中性洗剤で洗い、そのまま乾燥させずに手順2に移ります
手順2:10%クエン酸で表面をぬらして、ブラシでこすりながら水で洗い流します
手順3:10%硝酸で表面をぬぐいます
手順4:5%NaOHと1%酒石酸ナトリウム、そして1.5%H2O2の混合液に浸した後、しっかりと水で洗い流します
◆黄銅、銅
手順1:アセトンまたはアルコールを布につけてぬぐいます
手順2:紙やすりで軽くこすります。表面をぬらすことができる時は、5%クエン酸アンモニウムをブラシでなじませた後水で洗い流すか、あるいは市販されている黄銅みがきを使います
手順3:手順2をくり返します
手順4:2.5%クエン酸ナトリウムと0.2%中性洗剤の混合液(pH7)に浸してから、十分に水で洗い流します
◆鉄
手順1:水または薄めた中性洗剤で洗います
手順2:10%クエン酸と5%中性洗剤の混合液をかけてこすった後、水で洗い流します
手順3:6mol/l硝酸で除染できない所を部分的にこすったら、すぐに水で洗い流します
◆ステンレススチール
手順1:水または薄めた中性洗剤で洗います
手順2:30%硝酸でこすってから、水で洗い流します
手順3:10%シュウ酸で表面をぬらして約15分放置し、水で洗い流します
手順4:6~12mol/l HClを表面にすばやく塗りつけてから、しっかりと水で洗い流します
◆鉛
手順1:水または中性洗剤で洗います
手順2:1mol/l硝酸にひたして20分間洗います
手順3:1mol/lクエン酸に入れて20分間煮ます
◆ガラス
・大きなもの
手順1:水または薄めた中性洗剤で洗います
手順2:4%Na-EDTAまたは0.1mol/lヘキサメタリン酸ソーダを使ってブラッシング
手順3:2%フッ化アンモニウムで表面をこするか、溶液につけておきます ・小さなもの
手順1:水または稀中性洗剤で洗います
手順2:濃硝酸、または発煙硝酸ガスに数日間さらしておきます
手順3:2%フッ化水素アンモニウムに30分浸けてから、水で洗い流します
手順4:クロム酸混液で表面を処理します
◆磁器
手順1:水または薄めた中性洗剤で洗います
手順2:炭酸アンモニウムの飽和溶液で20分煮てから、水で洗い流します
手順3:5%フッ化水素アンモニウムに30分浸けてから、水で洗い流します
◆ペイント塗装面
手順1:水または薄めた中性洗剤で洗います
手順2:Na-EDTA+2%中性洗剤をふりかけてから、水でぬらしてこすり、水で洗い流します
手順3:5%クエン酸アンモニウムに浸けて、ブラシでこすります
手順4:除染後の汚染が少ない場合は塗装を上塗りし、それでもまだ高度の汚染が確認される場合はペイントをはぎとります
◆プラスチック
・アクリル樹脂
ガラスの除染方法と同じ。ただし、濃硝酸は表面をひどく損傷させます。
・アクリル樹脂以外の樹脂
ガラスおよびステンレススチールに対する方法と同じ
(3)に続く、、、。