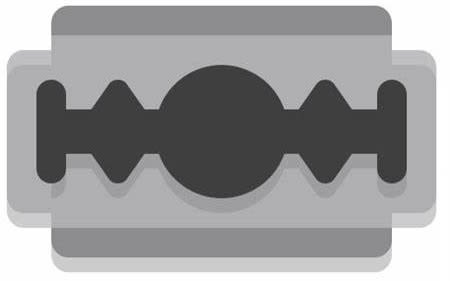長野県千曲市に姨捨山(おばすてやま)長楽寺というお寺があります。芭蕉が「俤や姥一人なく月の友(おもかげやうばひとりなくつきのとも)」という句を詠んだとかで、句碑もありますし、姨石(おばいし)という高さ15メートル、幅、奥行きとも25メートルという巨石にそって断崖に建てられた特異なお寺です。芭蕉はその姨石から眺めた絶景を詠んだものだそうです。



実際姨石に寄り添って建てられた観音堂からはこれも千曲名物の棚田を眺めることが出来ますが、すこし距離があるので、どうせならと大汗をかいて5分ほど歩いて近寄ってみました。

個々の棚田は耕作する希望者を募るという取り組みもあり、財団法人東日本鉄道なんとかという倉庫も見えましたので、JRも観光資源として投資しているようです。


さて、姨捨山という山号は長楽寺の南にある姨捨山(おばすて山、正式名冠着山(かむりきやま))から取ったというかそのままですが、やはり棄老伝説の本場ではあるようです。棄老伝説には難題型と枝折り型に分かれますが、ここは山に老いた親を捨てるために背負っていく際に、親が道すがら小枝を折っている(あるいは糠を撒いていく)のを見た息子が何故か尋ねると、「お前が帰るときに迷わないように」と答える。自分が捨てられるという状況にあっても子を思う親心に打たれ、息子は親を連れ帰る(ウィキペディア、)という枝折り型だそうです。
ついでですが、難題型とは、親を棄てきれず床下にかくまったが、その親が隣国からつきつけられたいくつもの難題を老人の知恵によって見事に解き、隣国を退散させるというような話です。
実際のところは年寄りを敬う風習がある日本で棄老という風習はなかったというのが定説で、むしろ年配者の知恵を讃えるための言い伝えというのが真相でしょう。
一方、山姥(うば)は捨てられた老婆が生き延びて、生き延びて、妖怪になったもの、という説もあります。なぜかというと女性は元来男性より生命力が強く、男だったらとっくに餓死か病死していることろ、木の実などを食べてしつこく生き残る、生きて、生きて山姥になる、そういうもんだそうです、そういえば山爺って聞かないですね、なんとなく納得です。



実際姨石に寄り添って建てられた観音堂からはこれも千曲名物の棚田を眺めることが出来ますが、すこし距離があるので、どうせならと大汗をかいて5分ほど歩いて近寄ってみました。

個々の棚田は耕作する希望者を募るという取り組みもあり、財団法人東日本鉄道なんとかという倉庫も見えましたので、JRも観光資源として投資しているようです。


さて、姨捨山という山号は長楽寺の南にある姨捨山(おばすて山、正式名冠着山(かむりきやま))から取ったというかそのままですが、やはり棄老伝説の本場ではあるようです。棄老伝説には難題型と枝折り型に分かれますが、ここは山に老いた親を捨てるために背負っていく際に、親が道すがら小枝を折っている(あるいは糠を撒いていく)のを見た息子が何故か尋ねると、「お前が帰るときに迷わないように」と答える。自分が捨てられるという状況にあっても子を思う親心に打たれ、息子は親を連れ帰る(ウィキペディア、)という枝折り型だそうです。
ついでですが、難題型とは、親を棄てきれず床下にかくまったが、その親が隣国からつきつけられたいくつもの難題を老人の知恵によって見事に解き、隣国を退散させるというような話です。
実際のところは年寄りを敬う風習がある日本で棄老という風習はなかったというのが定説で、むしろ年配者の知恵を讃えるための言い伝えというのが真相でしょう。
一方、山姥(うば)は捨てられた老婆が生き延びて、生き延びて、妖怪になったもの、という説もあります。なぜかというと女性は元来男性より生命力が強く、男だったらとっくに餓死か病死していることろ、木の実などを食べてしつこく生き残る、生きて、生きて山姥になる、そういうもんだそうです、そういえば山爺って聞かないですね、なんとなく納得です。