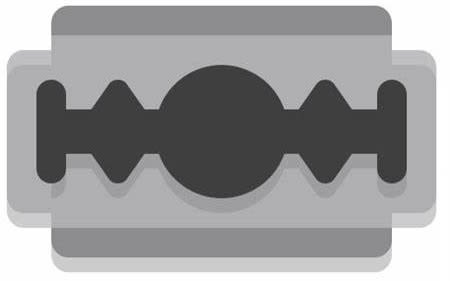注:この記事には改訂版があります。
筆者とガーネットクロウの出会いは、息子が「名探偵コナン」が好きなものですから一緒に見ているうちにテーマ曲「夢を見たあとで」が叙情たっぷり、興味を持ったのが最初でした。たまたま山野楽器で First Live Scopeを見かけたので、つい買ってしまい、ハマリました。
あまりJ-POPには興味がなく、主に洋楽、60年代から70年代のロックを聞いて育ったウッドストック世代の後半ですので、古くはジェファーソン・エアプレー ン、ドアーズ、少し前ではボストン、今も活躍のバンドではエアロスミスなどが好みなのですが、独断と偏見を恐れず言わせていただくと、ガーネットクロウのスタイ ル、ジェファーソン・エアプレーンに似ているなあ、と感じています。
私ほどの年代ではない人のために少し解説しておきますと、ジェファーソン・エアプ レーンは60年代後半から活躍したバンドで、前者はサイケデリックロックの草分け、代表作にはSomebody to Love(邦題「あなただけを」)、White Rabbitなどがあります。
ジェファーソン・エアプレーンがサイケデリックロックと呼ばれるゆえんは当時のストレートなロックンロールの中にあって異彩を放つ華麗なサウンド、華麗なハーモニー、リードボーカルのグレイス・スリックの華麗な容姿からだと思いますが、なんかこれ、ガーネットクロウにそのまま当てはまるような‥‥グレイス・スリックの派手なアクションはなしに、どちらかというと、つったったままで迫力のある低音で迫ってくるボーカルとその神々しいまでに美しい容姿。それを支える華麗かつ厚みのあるサウンド。これ、まさにガーネットクロウですよね。
さて、個人的に欧米と日本の自然観の対比に興味があるものですから、その視点からAZUKI七の詩の世界を分析してみたいと思います。
結論を先に言ってしまえば、AZUKI七の詩は生と死が重なり合った世界、また 情景が「個」の存在と重なり合う、きわめて日本的な世界だと思います。
前者の良い例はTimeless Sleepの「かろうじて憎しみに変えずいれた 私がんばれたよね?」。ここでは(多分)死者である「私」が語り手であるもう一人の「私」に直 接語りかけてきています。どう読んでみても生きていた時の「私」がもう一人の 「私」に語った思い出ではなく、いま、この場で語りかけてきている、そういう響きが感じられます。また、「夏の幻」の「君」も単に別れた「君」ではなく、死別した 「君」であるとも考えられます。一見普通の別れの歌に見えますが、途中「いつか終わる儚い夢(いのち)にただこみあげる気持ち抱いた」あたりから様子が変わり、前 半の昨日まで傍にいた「君」が永遠に届かないところに旅立った「君」に変わっていく、いいかえればAZUKI七の世界においては生と死はシームレスで連続した概念、渾然一体となり、いつの間にか死者が生者へ語りかけてくる、そういった世界です。
これは極めて日本的な世界観であり、日本的世界観においては生と死はめぐりめぐり連なりあうものと考えます。おばあさんが仏壇で死んだ亭主(このパターンが一番多いか?)に語りかけているような光景を目にしますが、これなんかそのいい例です。 これに反して欧米の世界観では、死の世界と生の世界の間には明確な線引きがあるようです。死者を懐かしみ、記念することはあっても対話することはほとんどありません。ですからお盆に死者の魂が里帰りするなどということはまったく理解できないの です。お墓参りも年1回命日の日が普通です。毎月お参りするなんて考えもつかない。
つづいて情景が「個」の存在と重なり合うということですが、これは「夏の幻」の 「海の底のような手のひらの中の街並」や「君という光」のタイトルどおりの「君という光」という表現に如実に現れています。「個」に属する「手のひら」にある町並 み(情景)。「君」という「個」=「光」(情景)。情景描写的な表現を得意とする AZUKI七ですが、頻繁に見られる情景と「個」の情景の微妙なつながり。
欧米の自然観においては、人間は自然の上に立ち、君臨するもの、また、もともと日 本と比べ過酷な自然の中で育ってきた文化ですので、自然は征服すべき対象として存在します。これに反して日本の文化においては「八百万の神」に象徴されるように森 羅万象に人格を感じる、逆に見れば人間も自然の一部であると考えます。そう考えれば「海の底のような手のひらの中の街並」や「君という光」という表現もきわめて日本的な自然観にもとづいたものだと理解できます。
こういった自然観は日本人の意識下に深く根付いており、日本人の心というか、ほとんどDNAの一部です。この辺がAZUKI七の詩が我々の心の琴線に直接触れてくるゆえんでしょう。
AZUKI七がどういう生い立ちの人なのか、一切明らかにされていませんが、よほどこういった日本人特有の感覚に敏感なのか、もしくは萩原朔太郎や中原中也など の詩などにはまった、かなりの文学少女(だった)と思われます。なぜならば、読み手、聞き手としてはDNAに任せておけばよいのですが、送り手となるとそうはいかない、意識下のものを意識の上に持ってくる作業がどうしても必要です。その点だけでも非凡な才能なのですが、彼女は得意の擬態語(「ゆらり」など)や間投詞(「ほら」など、個人的にはこの「ほら」が気に入っています)を駆使することによりやや もすれば重くなりがちな死と生のテーマや別離のテーマをさりげなく語りかけることに成功しています。
さて、日本的感覚にこだわる彼女は漢字にもこだわるようです。「生命」と書いて 「ゆめ」と読ませたり、「命」と書いて「まぼろし」と読ませたり、「過去」と書いて「とおいむかし」と読ませたり、三途の川と書いて「かわ」と読ませたり。また一方「鼓動」と書いて「リズム」とよませたりもしています。前者はそれこそ「人生わずか50年、ゆめまぼろし」の人生観、後者は書くならこちらのほうがふさわしいとい う感覚でしょう。ほとんど音の世界というよりは視覚の世界です。これは歌詞として 聞くだけではわからないことで、読まれることも想定した、詩人としてのこだわり、 仕掛けでしょう。
ご存知の方も多いと思いますが、グリムの童話が結構残酷な内容であるのと同様、日本の民謡、特に子守唄とわらべ歌は結構悲しい内容のものが多くあります。民話の世界はそういうものかもしれません。一度AZUKI七に童謡の詩を書いてもらい、 中村由利に歌ってもらいたいものです。それと「島原の子守唄」や「とおりゃんせ」 (子買いの話)、「シャボン玉とんだ」(間引きの話)などを中村由利に歌ってもらいたいものです。それらを集めたアルバムもいいですね。
筆者とガーネットクロウの出会いは、息子が「名探偵コナン」が好きなものですから一緒に見ているうちにテーマ曲「夢を見たあとで」が叙情たっぷり、興味を持ったのが最初でした。たまたま山野楽器で First Live Scopeを見かけたので、つい買ってしまい、ハマリました。
あまりJ-POPには興味がなく、主に洋楽、60年代から70年代のロックを聞いて育ったウッドストック世代の後半ですので、古くはジェファーソン・エアプレー ン、ドアーズ、少し前ではボストン、今も活躍のバンドではエアロスミスなどが好みなのですが、独断と偏見を恐れず言わせていただくと、ガーネットクロウのスタイ ル、ジェファーソン・エアプレーンに似ているなあ、と感じています。
私ほどの年代ではない人のために少し解説しておきますと、ジェファーソン・エアプ レーンは60年代後半から活躍したバンドで、前者はサイケデリックロックの草分け、代表作にはSomebody to Love(邦題「あなただけを」)、White Rabbitなどがあります。
ジェファーソン・エアプレーンがサイケデリックロックと呼ばれるゆえんは当時のストレートなロックンロールの中にあって異彩を放つ華麗なサウンド、華麗なハーモニー、リードボーカルのグレイス・スリックの華麗な容姿からだと思いますが、なんかこれ、ガーネットクロウにそのまま当てはまるような‥‥グレイス・スリックの派手なアクションはなしに、どちらかというと、つったったままで迫力のある低音で迫ってくるボーカルとその神々しいまでに美しい容姿。それを支える華麗かつ厚みのあるサウンド。これ、まさにガーネットクロウですよね。
さて、個人的に欧米と日本の自然観の対比に興味があるものですから、その視点からAZUKI七の詩の世界を分析してみたいと思います。
結論を先に言ってしまえば、AZUKI七の詩は生と死が重なり合った世界、また 情景が「個」の存在と重なり合う、きわめて日本的な世界だと思います。
前者の良い例はTimeless Sleepの「かろうじて憎しみに変えずいれた 私がんばれたよね?」。ここでは(多分)死者である「私」が語り手であるもう一人の「私」に直 接語りかけてきています。どう読んでみても生きていた時の「私」がもう一人の 「私」に語った思い出ではなく、いま、この場で語りかけてきている、そういう響きが感じられます。また、「夏の幻」の「君」も単に別れた「君」ではなく、死別した 「君」であるとも考えられます。一見普通の別れの歌に見えますが、途中「いつか終わる儚い夢(いのち)にただこみあげる気持ち抱いた」あたりから様子が変わり、前 半の昨日まで傍にいた「君」が永遠に届かないところに旅立った「君」に変わっていく、いいかえればAZUKI七の世界においては生と死はシームレスで連続した概念、渾然一体となり、いつの間にか死者が生者へ語りかけてくる、そういった世界です。
これは極めて日本的な世界観であり、日本的世界観においては生と死はめぐりめぐり連なりあうものと考えます。おばあさんが仏壇で死んだ亭主(このパターンが一番多いか?)に語りかけているような光景を目にしますが、これなんかそのいい例です。 これに反して欧米の世界観では、死の世界と生の世界の間には明確な線引きがあるようです。死者を懐かしみ、記念することはあっても対話することはほとんどありません。ですからお盆に死者の魂が里帰りするなどということはまったく理解できないの です。お墓参りも年1回命日の日が普通です。毎月お参りするなんて考えもつかない。
つづいて情景が「個」の存在と重なり合うということですが、これは「夏の幻」の 「海の底のような手のひらの中の街並」や「君という光」のタイトルどおりの「君という光」という表現に如実に現れています。「個」に属する「手のひら」にある町並 み(情景)。「君」という「個」=「光」(情景)。情景描写的な表現を得意とする AZUKI七ですが、頻繁に見られる情景と「個」の情景の微妙なつながり。
欧米の自然観においては、人間は自然の上に立ち、君臨するもの、また、もともと日 本と比べ過酷な自然の中で育ってきた文化ですので、自然は征服すべき対象として存在します。これに反して日本の文化においては「八百万の神」に象徴されるように森 羅万象に人格を感じる、逆に見れば人間も自然の一部であると考えます。そう考えれば「海の底のような手のひらの中の街並」や「君という光」という表現もきわめて日本的な自然観にもとづいたものだと理解できます。
こういった自然観は日本人の意識下に深く根付いており、日本人の心というか、ほとんどDNAの一部です。この辺がAZUKI七の詩が我々の心の琴線に直接触れてくるゆえんでしょう。
AZUKI七がどういう生い立ちの人なのか、一切明らかにされていませんが、よほどこういった日本人特有の感覚に敏感なのか、もしくは萩原朔太郎や中原中也など の詩などにはまった、かなりの文学少女(だった)と思われます。なぜならば、読み手、聞き手としてはDNAに任せておけばよいのですが、送り手となるとそうはいかない、意識下のものを意識の上に持ってくる作業がどうしても必要です。その点だけでも非凡な才能なのですが、彼女は得意の擬態語(「ゆらり」など)や間投詞(「ほら」など、個人的にはこの「ほら」が気に入っています)を駆使することによりやや もすれば重くなりがちな死と生のテーマや別離のテーマをさりげなく語りかけることに成功しています。
さて、日本的感覚にこだわる彼女は漢字にもこだわるようです。「生命」と書いて 「ゆめ」と読ませたり、「命」と書いて「まぼろし」と読ませたり、「過去」と書いて「とおいむかし」と読ませたり、三途の川と書いて「かわ」と読ませたり。また一方「鼓動」と書いて「リズム」とよませたりもしています。前者はそれこそ「人生わずか50年、ゆめまぼろし」の人生観、後者は書くならこちらのほうがふさわしいとい う感覚でしょう。ほとんど音の世界というよりは視覚の世界です。これは歌詞として 聞くだけではわからないことで、読まれることも想定した、詩人としてのこだわり、 仕掛けでしょう。
ご存知の方も多いと思いますが、グリムの童話が結構残酷な内容であるのと同様、日本の民謡、特に子守唄とわらべ歌は結構悲しい内容のものが多くあります。民話の世界はそういうものかもしれません。一度AZUKI七に童謡の詩を書いてもらい、 中村由利に歌ってもらいたいものです。それと「島原の子守唄」や「とおりゃんせ」 (子買いの話)、「シャボン玉とんだ」(間引きの話)などを中村由利に歌ってもらいたいものです。それらを集めたアルバムもいいですね。