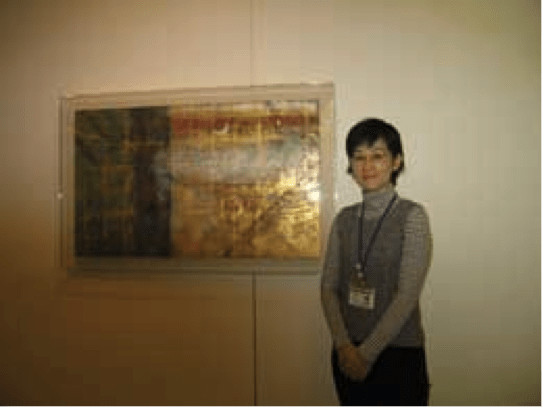『原田俊一』氏はサラリーマンコレクターの草分け的存在である。一貫して新しい日本画に関心を持ち、東京芸大など美大の若手作家との交流を深めてきた。コレクションは河嶋淳司、マコトフジムラ他、いまや中堅実力派として活躍している作家たちの作品ばかりだ。アートNPO立ち上げを最初に相談したアートの世界の友人であり、苦労を共にしてきた同志的存在である。『クリスマス・イン・ピース展』、『コレクターの見る視点展』など提案・実行いただいたアート企画は、いずれもアートNPO活動の歴史に残るものである。
『伊藤厚美』氏は『アスクエア神田ギャラリー』代表であるが、美術業界の現状についても率直に語ることができる新しい時代のギャラリストである。読書家でもあり、名著のこと、経済や社会のことなど話題も豊富で楽しい。日常のなかに生きている美術といったことに関心を持ち、アート市民時代の到来に期待を寄せる。アートNPOにおける理論派でもあり、メディアへの紹介など継続的支援を頂戴した。現在、京都造形大学の環境美術講師として教壇に立つなど活動の幅を広げている。美術同好会『ASの会』役員でもある。
『御子柴大三』氏は大手百貨店の外商の仕事の傍ら、絵画コレクションを続けて30年。若い頃松田正平や野見山暁治の絵に惹かれ、小貫政之助の作品を購入した経験から、無名作家の発掘こそ収集の道との持論を展開するこだわりのコレクターである。アートNPOにおいては『ぼくらの・・展』を提案、森本秀樹など好きな作家のコレクション展を実現させたが、これらの企画はアートNPOの事業の一つに育ち、会の発展にも貢献した。
『立島恵』氏は佐藤美術館の学芸部長である。『(財)佐藤国際文化育英財団』の選考委員、或いは東山魁夷記念日本画大賞推薦委員として若手作家育成など幅広く活躍中である。学芸員として取り組んできた日本画家マコトフジムラや岡村桂三郎研究については高い評価を得ている。アートNPOにおいては常務理事としてご尽力いただいたが、特にマコト・フジムラ氏の『アイアムの会』との共催展覧会『クリスマス・イン・ピース展』を成功裡にやり遂げることができたのは、立島氏の力量と佐藤美術館のご支援によるものである。
『黒田裕一郎』氏は、私が定年間近の時期に経営に携わったベンチャー企業時代以来の若き友人である。アートNPOの理事を快く引き受けていただいた上、各種アート企画の裏方的任務にご尽力いただいた。専門は出版業界の広告・営業であるが、個人的にはTOEICに挑戦し続け、700点を合格した努力家である。弘法大師空海を敬愛し、毎年大晦日に真言密教の道場である京都東寺を訪ねる旅を続けている。
『中谷孝司』氏とは、私が理事をしていた『(社)長寿社会文化協会』時代以来のお付き合いだが、美術と音楽のコラボレーション実現のため理事をお引き受けいただいた。音楽の世界で豊かな人脈を持ち、その後、『国立楽器』の代表取締役に就任、サロン・ド・ノアン主宰や一橋大学兼松講堂での大規模コンサートを推進している。業務多忙のため美術&音楽の企画は実現していないが、役員として変わることのないご支援をいただいた。
『廣川和徳』氏は家業である工務店経営の傍ら、『日本民家再生リサイクル協会』理事や街おこしボランティアなど幾つもの活動に関わっている。アートNPOにおいては『コレクターの見る視点展』に毎回参加、藤倉明子など若手作家を紹介する他、アート街作りの提案や、クリスマス・イン・ピース展のオークション入札箱製作など裏方としても貢献していただいた。古民家や伝統建築の魅力を熱っぽく語る、気さくな人柄の好人物だ。
『太田信之』氏は若い頃からの我が尊敬する先輩である。某大手建材メーカーを定年退職後、早稲田大学の特別研究員&講師の他、環境保護の視点からの木造建築・伝統的工法の重要性を世に問うべくNPO法人『建築市場委員会』を設立、事務局長として活躍中である。アートNPOでは監査役としてご尽力いただいた。三味線・小唄などの趣味人で、蓼流玉和会の幹事でもある。いずれ辰巳芸者の古き街で津軽三味線の流しをやるのだそうだ。
『伊藤厚美』氏は『アスクエア神田ギャラリー』代表であるが、美術業界の現状についても率直に語ることができる新しい時代のギャラリストである。読書家でもあり、名著のこと、経済や社会のことなど話題も豊富で楽しい。日常のなかに生きている美術といったことに関心を持ち、アート市民時代の到来に期待を寄せる。アートNPOにおける理論派でもあり、メディアへの紹介など継続的支援を頂戴した。現在、京都造形大学の環境美術講師として教壇に立つなど活動の幅を広げている。美術同好会『ASの会』役員でもある。
『御子柴大三』氏は大手百貨店の外商の仕事の傍ら、絵画コレクションを続けて30年。若い頃松田正平や野見山暁治の絵に惹かれ、小貫政之助の作品を購入した経験から、無名作家の発掘こそ収集の道との持論を展開するこだわりのコレクターである。アートNPOにおいては『ぼくらの・・展』を提案、森本秀樹など好きな作家のコレクション展を実現させたが、これらの企画はアートNPOの事業の一つに育ち、会の発展にも貢献した。
『立島恵』氏は佐藤美術館の学芸部長である。『(財)佐藤国際文化育英財団』の選考委員、或いは東山魁夷記念日本画大賞推薦委員として若手作家育成など幅広く活躍中である。学芸員として取り組んできた日本画家マコトフジムラや岡村桂三郎研究については高い評価を得ている。アートNPOにおいては常務理事としてご尽力いただいたが、特にマコト・フジムラ氏の『アイアムの会』との共催展覧会『クリスマス・イン・ピース展』を成功裡にやり遂げることができたのは、立島氏の力量と佐藤美術館のご支援によるものである。
『黒田裕一郎』氏は、私が定年間近の時期に経営に携わったベンチャー企業時代以来の若き友人である。アートNPOの理事を快く引き受けていただいた上、各種アート企画の裏方的任務にご尽力いただいた。専門は出版業界の広告・営業であるが、個人的にはTOEICに挑戦し続け、700点を合格した努力家である。弘法大師空海を敬愛し、毎年大晦日に真言密教の道場である京都東寺を訪ねる旅を続けている。
『中谷孝司』氏とは、私が理事をしていた『(社)長寿社会文化協会』時代以来のお付き合いだが、美術と音楽のコラボレーション実現のため理事をお引き受けいただいた。音楽の世界で豊かな人脈を持ち、その後、『国立楽器』の代表取締役に就任、サロン・ド・ノアン主宰や一橋大学兼松講堂での大規模コンサートを推進している。業務多忙のため美術&音楽の企画は実現していないが、役員として変わることのないご支援をいただいた。
『廣川和徳』氏は家業である工務店経営の傍ら、『日本民家再生リサイクル協会』理事や街おこしボランティアなど幾つもの活動に関わっている。アートNPOにおいては『コレクターの見る視点展』に毎回参加、藤倉明子など若手作家を紹介する他、アート街作りの提案や、クリスマス・イン・ピース展のオークション入札箱製作など裏方としても貢献していただいた。古民家や伝統建築の魅力を熱っぽく語る、気さくな人柄の好人物だ。
『太田信之』氏は若い頃からの我が尊敬する先輩である。某大手建材メーカーを定年退職後、早稲田大学の特別研究員&講師の他、環境保護の視点からの木造建築・伝統的工法の重要性を世に問うべくNPO法人『建築市場委員会』を設立、事務局長として活躍中である。アートNPOでは監査役としてご尽力いただいた。三味線・小唄などの趣味人で、蓼流玉和会の幹事でもある。いずれ辰巳芸者の古き街で津軽三味線の流しをやるのだそうだ。