民法などの法律を見てみると、実によく考えられていますね。
そこまで考えたのか、ということが随所にあります。
では、ひとつ取り上げておきましょう。それは、賃貸借において、何が一番大切か、重要か、とみているかです。
普通、賃料だ、少しでも安いお金で借りられる方がいいから、ともいえますが、本当にそうでしょうか。
実は、法律を作るときに最も重要なものとして考えているのは、賃料のことではなく、期間つまり存続期間についてなんです。
まあ、確かにいつまで借りられるのか、また、自分の手許から離して貸しておくのか、ということは互いに重要でしょう。売ったわけでないからですね。
いつかは返さなければならない、でもそんなに早く返すのは十分使えない、一方貸す方としては、100年貸していたら、売ったのと同じ(?)ではないか、などなどいろいろ考えられます。
実質はこのようなものですが、条文でもひとつあげておきましょうね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(保佐人の同意を要する行為等)
第13条1項
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
9号-第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
※(短期賃貸借)
第602条
処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
1号-樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
2号-前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
3号-建物の賃貸借 3年
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このポイントは、被保佐人は、“重要な行為”を単独ではできないとする条文です。
立法者が重要と見ている行為が列挙されているぞ、ということです。
13条9号は、何が重要かというと、賃貸借の場合には、短期賃貸借の期間を超える場合だといっています。
たとえば、自分に建物を持っていて、人に貸す場合、それが被保佐人なら、3年を1秒でも超えれば、重要になって、単独ではできないよ、といってますね。
むーん、そう見ているのか、という感動ものです。
では、また。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
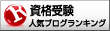
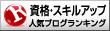
そこまで考えたのか、ということが随所にあります。
では、ひとつ取り上げておきましょう。それは、賃貸借において、何が一番大切か、重要か、とみているかです。
普通、賃料だ、少しでも安いお金で借りられる方がいいから、ともいえますが、本当にそうでしょうか。
実は、法律を作るときに最も重要なものとして考えているのは、賃料のことではなく、期間つまり存続期間についてなんです。
まあ、確かにいつまで借りられるのか、また、自分の手許から離して貸しておくのか、ということは互いに重要でしょう。売ったわけでないからですね。
いつかは返さなければならない、でもそんなに早く返すのは十分使えない、一方貸す方としては、100年貸していたら、売ったのと同じ(?)ではないか、などなどいろいろ考えられます。
実質はこのようなものですが、条文でもひとつあげておきましょうね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(保佐人の同意を要する行為等)
第13条1項
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
9号-第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
※(短期賃貸借)
第602条
処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
1号-樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
2号-前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
3号-建物の賃貸借 3年
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このポイントは、被保佐人は、“重要な行為”を単独ではできないとする条文です。
立法者が重要と見ている行為が列挙されているぞ、ということです。
13条9号は、何が重要かというと、賃貸借の場合には、短期賃貸借の期間を超える場合だといっています。
たとえば、自分に建物を持っていて、人に貸す場合、それが被保佐人なら、3年を1秒でも超えれば、重要になって、単独ではできないよ、といってますね。
むーん、そう見ているのか、という感動ものです。
では、また。























