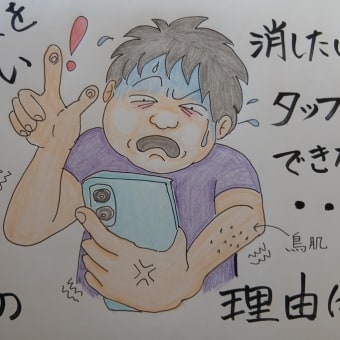番組では、大抵シニアのご夫婦などが営むお店等を紹介している。素敵なカフェやレストラン、パン屋さんだったり、地元の産物を使って起業したりする方等もおり、シニアの奮闘する様子は、年代の近い私にとっては、大変興味深い番組だ。
昨年末の番組では、珍しくシニアでは無く、30代の若い夫婦が出演していた。確か子供が3人いる5人家族で、米づくり農家さんだった。
ご主人の前の職業はIT関係だったそうで、180度の大胆な転職だ。
最近IT関係の企業から、農業や酪農等の第一次産業へ転職する人の紹介を何度かテレビで目にした。そんなに数は多くないのだろうが、珍しい事なので、メディアに取り上げられる機会が多いのだろう。
何故IT企業からの転職を試みたのだろうか。気になるところだが、番組ではそこまでは紹介していなかったが、何となく色々想像されるところではある。
社会全体が人手不足の現在、IT関係も例外ではない。
一人当たりの仕事量が増え、日々仕事に追われる状況となり、キャパシティを超えて仕事を抱えると、人は精神を病んでいく。
本来は生活のために稼ぐはずが、働くことがメインになり、生活がおざなりになる。お金はあるけど時間がないと言った具合だ。
タスクに追われて食事を取る時間も無い生活などを送り、人間らしさからかけ離れていくようにも見える。
転職の背景には少なからずそんな事もあるのでは無いかと、勝手な憶測をしてしまう。
全く未経験の稲作農家への転職は、子供たちもまだ幼いのに、随分思い切った挑戦だと思う。
奥様も、ご主人の転職に加え、知り合いの居ない地域への転居、田舎暮らしと肉体労働等など、よく受け入れられたと思う。
稲作のノウハウについては、その地域の方の田んぼを分けてもらい、年配の農家さんに、一から教わりながら始めたそうだ。
番組の中では見事に実った稲を、家族総出で一緒に刈る作業が見られた。小さな子供も鎌を持って稲を刈り、家族みんな笑顔で幸せそうだった。
夫婦は、人手が欲しいので、子供はあと二人欲しいと言っていた。
それを聞いて、何かとてもホッとするというか、懐かしいというか、そんな気持ちになった。
太古の昔から、稲作の始まった弥生時代から、人はこのようにして生活してきたのだ。
「子供を産むか産まないか」なんて選択する考えも及ばなかった時代。
愛し合って自然に子供が生まれ、農作業に追われる日々を送り、収穫時期には一家総出で作業に取り組む。自然の中で四季の流れと共に生活を送る。
少子化なんて生じなかったおおらかな時代。出生率なんて誰も気にもしなかった時代。
楽しそうに農作業をしている夫婦と子供たちを見て、何だか昔ながらの自然な当たり前の“人の生き方”を見る思いだった。
第一次産業に若者が従事してくれたら、食の自給率の問題や、少子化問題も解決できるのになあ、と安易に考えてしまった。
とはいえ、農作業に苦労は付き物だ。肉体労働だし天候に左右される。やることは次から次と山ほどある。決して平坦な道ではないだろう。
北海道の酪農業も後継者不足で年々減っている。
設備投資に多額の借金を抱え、生き物相手だから休む暇もない。
私達の食卓に欠かせない食料を提供してくれている人たちが、苦労ばかりして割に合わない生活では申し訳ない。
国政がしっかりしていないと埒が明かない。
将来の日本の第一次産業はどうなってしまうのか不安ではあるが、彼らのような若者がいることがかすかな希望だ。
番組を見ながら、そんな事を思った。