読まないと。読みたい。という本が積み上がっています。推薦されたり、人に紹介されて興味を持ったり。現在は、3冊を同時平行して読むことに挑戦中。
その小説、以前勤めていた会社の大先輩にもらったものなのですが。私は「イージス」も「ローレライ」も読んでいません。食わず嫌いで。クランシーやラドラムやフォーサイスが好きですが、日本人作家の作品は如何ばかりか。と思っていました。

せっかくの頂き物。と読み始めたら、これが面白い。主人公の朋希。好きなタイプ。こういうヒーロー。(実際に身近に居たら嫌になると思います)よく、主人公よりサブキャラに嵌って・・と言う人がいますが、私は、真っ当、主人公に惹かれます。作者の意図どおりに読む非常に素直な読者です。文庫、上・中・下の3冊で、まだ2冊目の途中なのですが。すごい密度です。少し前に、読んで、文庫5冊という長さだけでなく、内容的にもすごいボリューム。と思ったのですが、ローズダストは3冊で、模倣犯5冊の重みを軽く超えそうな気がします。どちらが良いというわけじゃないけれど。模倣犯のほうは、もう少し、軽くできたではないか、軽くしたほうが良かったのではないかと。ローズダストを読みながら思ったりしました。模倣犯読了時点では、そうは思わなかったのですが。連続殺人とテロの話を比べても仕方がないのですが。
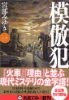
途中なので読み終わったときにどう感じるかはわかりませんが。日本という国がどうなっても良いから、朋希くんにとって救いのある結末であることを祈りながら読んでいる私です。お勉強の本も、ちゃんと読まないと。それより、サボらず仕事しないと。
本日の読書:1/595冊目 志水辰夫著 「つばくろ超え」新潮社
その小説、以前勤めていた会社の大先輩にもらったものなのですが。私は「イージス」も「ローレライ」も読んでいません。食わず嫌いで。クランシーやラドラムやフォーサイスが好きですが、日本人作家の作品は如何ばかりか。と思っていました。

せっかくの頂き物。と読み始めたら、これが面白い。主人公の朋希。好きなタイプ。こういうヒーロー。(実際に身近に居たら嫌になると思います)よく、主人公よりサブキャラに嵌って・・と言う人がいますが、私は、真っ当、主人公に惹かれます。作者の意図どおりに読む非常に素直な読者です。文庫、上・中・下の3冊で、まだ2冊目の途中なのですが。すごい密度です。少し前に、読んで、文庫5冊という長さだけでなく、内容的にもすごいボリューム。と思ったのですが、ローズダストは3冊で、模倣犯5冊の重みを軽く超えそうな気がします。どちらが良いというわけじゃないけれど。模倣犯のほうは、もう少し、軽くできたではないか、軽くしたほうが良かったのではないかと。ローズダストを読みながら思ったりしました。模倣犯読了時点では、そうは思わなかったのですが。連続殺人とテロの話を比べても仕方がないのですが。
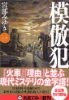
途中なので読み終わったときにどう感じるかはわかりませんが。日本という国がどうなっても良いから、朋希くんにとって救いのある結末であることを祈りながら読んでいる私です。お勉強の本も、ちゃんと読まないと。それより、サボらず仕事しないと。
本日の読書:1/595冊目 志水辰夫著 「つばくろ超え」新潮社













