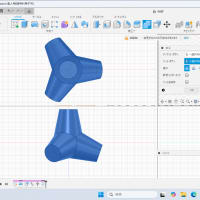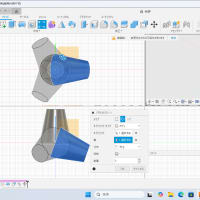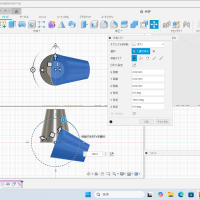私が意識についての話をするとき、多く取り上げるアイヒマン実験であるが。このスタンレー:ミルグラムの著作「服従の心理。」において、第十章「なにゆえの服従か。」のくだりについては、従来の生物学のパラダイムに基づき書かれたものであるため、根本的に間違っていることを明確にしておきたい。
従来の生物学のパラダイムに則った「理論。」の多くは、生存に繋がる話を「目的。」としておきながら、生存に繋がらない話は「進化の袋小路。」などと都合の良いようにこじつけており。論理的一貫性すら担保されていない。
現在の生物というものは、何億年もの淘汰の結果として、非常に高度な生存能力を持っているのは確かだが。こうした生存能力であっても、淘汰の過程において莫大な「犠牲。」を生じているのであり。これらの生存に適さなかった個体の能力の全ても含めれば、決して生物というのは生存することを目的とした行動選択をしているとは言えないのである。
ましてや自発的には行動選択不可能なウイルスなどの進化過程というものであれば、それは遺伝的に不安定性を持つことによる、いうなれば、かなりいい加減な進化(変化)の乱れ撃ち、「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる。」的な構造を持つことによって、様々な環境への適応能力を発揮しているだけなのである。
生物種の進化的な変化のほとんどは生存には適さず、言い換えれば「死ぬために変異を生じていたら、偶発的に生存に適することもあったという、その結果として生存する個体が現れる。」という、偶発性だけを頼りにした結果論であって。そこに目的など、ウイルス自身には存在しない。
単なる生存だけを追求するのであれば、もはや知能もへったくれも要らず、ただひたすら結果的生存だけを目的であると言い張るのであれば、それはゴキブリで充分ということになるのである。数億年単位でほとんど変化を必要としない生物種であるということは、いわば生存に関して究極の種であるということだからである。
ヒトであっても自分の遺伝子は選択不可能であり。遺伝的要因がどのような結果を引き起こしたとしても、そこには意識的な「目的。」行動であることの証明などない。
従って、淘汰によって進化的に組み込まれた情動を発生させる、大脳辺縁系のシーケンスが特定条件下において、どんなに高度な生存能力を発揮したことを枚挙しても。それが人間としての意識的目的行動選択とは無関係なのである。
ヒトの身体は非常に高度な生存能力を持っている。しかし、それ自体は誰も自分自身で意識的に選択したものではないし。かつ、必ずしも生存につながるとも限らないのである。大脳辺縁系自体は、サルでもイヌでも、あるいはワニであっても、さしたる構造の違いなどないのである。それが絶対にヒトという種における目的行動を促すものであることの論理的根拠は全く存在しないのである。
単なる生存という結果だけを論じても、そこには必ずしも本質的知能が存在するわけではない。重大な科学的発見をしても、「コーヒー豆扱い。(*注)」されることは珍しくない。多数の大衆が流される傾向性に準じていたのでは、本当の科学的検証はできないのである。
むしろ、大衆が流され易い傾向性というものを客観的に捉え。それによって生ずる諸問題の原因究明と、それに伴う再発防止策の確立こそが。本当の意味における「社会の要請。」であるはずなのだ。その過程において、大衆からの人気が得られないことに意味などない。
それでも、書いている本人の気分的には楽しいものではない。
意識に関わる話ばかりをすると、アクセスIPが激減するが、本来アクセス数を稼ぐための理論ではないので、無視して書き続ける。
地震に関連する情報はアクセスIPが激増するが。これは事象の重大さに依存する結果的なものであり、むやみに書けば良いというものでもない。古い情報はもはや誤解を招くだけなので削除した。でわまた。
*注:ガリレオ:ガリレイの地動説に下された、当時の社会からの評価のこと。
従来の生物学のパラダイムに則った「理論。」の多くは、生存に繋がる話を「目的。」としておきながら、生存に繋がらない話は「進化の袋小路。」などと都合の良いようにこじつけており。論理的一貫性すら担保されていない。
現在の生物というものは、何億年もの淘汰の結果として、非常に高度な生存能力を持っているのは確かだが。こうした生存能力であっても、淘汰の過程において莫大な「犠牲。」を生じているのであり。これらの生存に適さなかった個体の能力の全ても含めれば、決して生物というのは生存することを目的とした行動選択をしているとは言えないのである。
ましてや自発的には行動選択不可能なウイルスなどの進化過程というものであれば、それは遺伝的に不安定性を持つことによる、いうなれば、かなりいい加減な進化(変化)の乱れ撃ち、「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる。」的な構造を持つことによって、様々な環境への適応能力を発揮しているだけなのである。
生物種の進化的な変化のほとんどは生存には適さず、言い換えれば「死ぬために変異を生じていたら、偶発的に生存に適することもあったという、その結果として生存する個体が現れる。」という、偶発性だけを頼りにした結果論であって。そこに目的など、ウイルス自身には存在しない。
単なる生存だけを追求するのであれば、もはや知能もへったくれも要らず、ただひたすら結果的生存だけを目的であると言い張るのであれば、それはゴキブリで充分ということになるのである。数億年単位でほとんど変化を必要としない生物種であるということは、いわば生存に関して究極の種であるということだからである。
ヒトであっても自分の遺伝子は選択不可能であり。遺伝的要因がどのような結果を引き起こしたとしても、そこには意識的な「目的。」行動であることの証明などない。
従って、淘汰によって進化的に組み込まれた情動を発生させる、大脳辺縁系のシーケンスが特定条件下において、どんなに高度な生存能力を発揮したことを枚挙しても。それが人間としての意識的目的行動選択とは無関係なのである。
ヒトの身体は非常に高度な生存能力を持っている。しかし、それ自体は誰も自分自身で意識的に選択したものではないし。かつ、必ずしも生存につながるとも限らないのである。大脳辺縁系自体は、サルでもイヌでも、あるいはワニであっても、さしたる構造の違いなどないのである。それが絶対にヒトという種における目的行動を促すものであることの論理的根拠は全く存在しないのである。
単なる生存という結果だけを論じても、そこには必ずしも本質的知能が存在するわけではない。重大な科学的発見をしても、「コーヒー豆扱い。(*注)」されることは珍しくない。多数の大衆が流される傾向性に準じていたのでは、本当の科学的検証はできないのである。
むしろ、大衆が流され易い傾向性というものを客観的に捉え。それによって生ずる諸問題の原因究明と、それに伴う再発防止策の確立こそが。本当の意味における「社会の要請。」であるはずなのだ。その過程において、大衆からの人気が得られないことに意味などない。
それでも、書いている本人の気分的には楽しいものではない。
意識に関わる話ばかりをすると、アクセスIPが激減するが、本来アクセス数を稼ぐための理論ではないので、無視して書き続ける。
地震に関連する情報はアクセスIPが激増するが。これは事象の重大さに依存する結果的なものであり、むやみに書けば良いというものでもない。古い情報はもはや誤解を招くだけなので削除した。でわまた。
*注:ガリレオ:ガリレイの地動説に下された、当時の社会からの評価のこと。