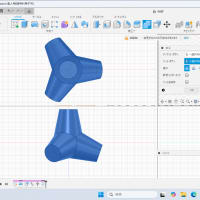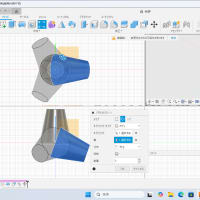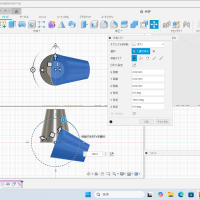一括投稿
○コミュニケーション能力。
動物としての本能的/感情的な「社会性。」であるコミュニケーション能力というものは現状世間においては金銭的価値を求められているであろうが、これは「ヒト。」という種の生物的価値にはなっても人間としての本質的価値とは関係がない。
高いコミュニケーション能力によって世間的に成功しているとしても、社会的持続可能性や安全性という本質的社会性に適していることの論証にはならない。
しかし、多くの文系大衆観念上では気分的に安心することばかりが優先され、本質的な人間としての社会性は多くの場合無視されるのである。
空気を読まず、迎合しない者であっても自律的に社会安全性を優先しないことの論証にはならず。逆に空気を読んで権威に迎合することによってヒトの多くは差別や虐殺に加担する習性が存在することをアイヒマン実験は立証しているのであり、大衆に迎合せず多数のご機嫌をとらないからといって人間としての価値が低いことの証明にはならない。
生物的/本能的すなはち気分的な安心感といったものは意識ではなく機械条件反射的無意識に過ぎない。ヒトの多くはこうした気分感情による行動バイアスこそが意識であると錯覚しがちであるが、人間としての本質的な意識というものは論理的思考による本質的合理性追求であることに対してヒステリックな拒絶反応をするのである。
Ende;
○「事件のカギを握る麻原。」
麻原は事件のカギなど握っていない。
教団の暴走というものは教祖に目的がなかったからこその結果である。暴走族が目的もなく暴走するのも統率自体が本能的な目的だからであって、集団で統一的統率をしていることの気分的安心を追求した結果に過ぎない。
幹部達はただ教祖への忠誠忠実と評価を求めていただけであって、教祖もまた従順に服従する幹部の言うことを盲目的に信用していただけなのである。
ヤクザやゲリラと同様に、統率的に行動することによって気分的安心を追求しているだけであって、彼らのリーダーには何ら目的など一切存在せず。麻原やナチスのヒトラーも同様に何の目的もない。
暴走する集団というものには、そもそも誰にも合理的目的行動選択が行われないからこそ暴走するのであって。命令を下している教祖リーダーであるからといっても目的だの「事件のカギ。」を期待するのは間違いである。
暴力団がなぜ暴力団であるのかを暴力団の構成員に尋ねても答がないのと同様、暴走族がなぜ暴走行為を行うのかを暴走族に尋ねても答がないのと同様、ゲリラがなぜ残虐なのかをゲリラ当人に尋ねても答がないのと同様、カルト宗教の暴走の原因をカルト宗教の教祖や幹部に尋ねても合理的回答が返ってくることは原理的にない。
合理的回答を持っているのであれば最初から暴走になど陥らないのである。
子供のイジメも同様であり、誰にも目的など存在せず、特定の仕切りたがり屋による扇動による多数同調の結果であり。リーダーとなる仕切り屋自身もまた多数からのウケ狙いを求めて扇動しているに過ぎない。子供になぜイジメを行うのかを問うても合理的説明による原因究明は原理的に不可能なのである。
昭和天皇が軍による誘導によって太平洋戦争の責任者であるかのように祭り上げられたのと同様、北朝鮮の金正恩もまた何ら本質的には自発的選択など一切出来ない状況なのである。形式上の統率者だけが全てを取り仕切っているかのような錯覚を抱きがちであるが、実際には体制自体、集団全体の多数迎合性によって暴走性は作り出されるのである。
自律的に目的行動選択を持たない本能的社会形成だけで統率された集団にとって、自律的に目的行動選択を行う者というのは気分が悪い邪魔な存在であるため、徹底的に差別排除され、粛正というヒステリックな最終解決が短絡的に行われることになり。集団は益々暴走の一途を辿ることに陥るのである。
こうした無意識的な社会形成本能による暴走性というものは、司法による当事者への罰では何ら原因究明にも再発防止策もなることはなく。ただ漫然と慣習に従って感情的満足を得ているだけの無駄な行為に過ぎない。
司法が追求する真実というのは、「その。」事案においての断片的真実を暴くことだけしか行われることはなく。ヒトという種の生物自体に由来する本能的暴走性については全く言及されることはない。刑事裁判の目的は再発防止ではなく、あくまで科料の妥当性を吟味することだけであるからだ。
法制度手続きだけに基づいて行われる司法というものは、制度上規定された刑罰科料の妥当性吟味だけが目的であり。こうした手続き自体も、多数の大衆による論理的根拠を持たない観念によって維持保守されるだけである限り根本的解決としての科学的解析や再発防止対策の確立には構造的になっていない。
裁判というものは、これ自体が刑罰を決定するためだけに存在するためのものであって。三権分立という制度自体はあくまで経験則的に構築された結果的制度に過ぎず、必ずしも科学的論理的根拠に基づいて規定されたものではない。
何せ法律こそが具体的だと思い込んでいるようなバカが検察官をやっているような現状において、具体的な事件の原因究明や再発防止策の確立などされるわけがない。司法に携わる者達というのは法手続きに則って機械的に処理することによる評価報酬だけが目的であって、社会全体の安全性も持続可能性も意識の俎上には全くないからである。
警察や検察による事件の捏造も、真実の追求によって安全性や持続可能性を高めることが評価になるようには構造的になっていないからであって、利己的な評価だけを目的としているからこその結果なのである。
最近では評価の方法を変えることによって無意識な役人達の行動を制御する方法論というものが提唱されているが、これは役人個人の主体的自律判断というものを無視した「バカの取り扱い方。」を論じているに過ぎない。警察が取り締まりを最終目的とするよりは社会安全性を目的とするように「誘導。」できた方がいくらかはマシではあろうが、根本的な解決策とするのは大きな間違いである。個人が「バカである。」こと自体を改善しない限りはバカげた結果に至ることは避けられないからだ。
本来であれば制度云々といった環境に依らず自律的に社会全体の安全性や持続可能性を追求するのが「人間。」としての社会性というものであるが。こうした根本的人間性というものが全く無視されたまま学力競争だけを漫然と強要してきた頭の悪さ、意識の低さ浅さ狭窄さというもの放置しておいて、社会が良くなる保証など全くないのである。
ヒトの多くは漫然と慣習に則って同じことを繰り返しておけば安心で満足を得られるであろう。逆に言えば無意味な慣習であっても改革を行うことは恐怖と不安を抱くものでもある。ましてや無意識な多数に対して異議を唱えるとなれば世間からの排除をされることも少なくはない。その恐怖心/強迫観念こそがあらゆる社会集団における暴走性を助長する結果を招くことになるのである。
Ende;
○「勝てると思っているのかしら。」
TBSの「怒り新党。」って番組で、自転車が自動車の間をすり抜けることについてマツコデラックスが形容してたんだけど。
自転車が自動車の隙間をすり抜けするのは、自動車が道路を封鎖しているからすり抜けなければならないのであって、別に「勝ちたい。」からすり抜けているわけではない。と思う。
有吉が言うには「俺ら(自動車)が避けてやっている。」とも言っていたが、すり抜けをしなければならいのは、赤信号で自動車が道路を封鎖しているからであって、多くの自動車は自転車が走れるようには考えていない。
特にタクシーの場合、客を拾うために急な幅寄せをしてくることも多いために自転車からは嫌われている傾向もある。おいらも何回か経験がある。仕事で二輪車を運転をしていればタクシーは敵だと思われているかも知れない。
自動車運転をしている者の多くは、赤信号の交差点に「詰めて。」並ぶためだけにスピードを出している場合が非常に多く、自転車からすると温室効果ガスを撒き散らして進路妨害をしているだけにしか見えない。
そもそも「勝つ。」だのという観念は一体どこから出て来ているであろうか。こうした文系大衆観念というものには合理的根拠というものが全くなく、その場限りの気分から出て来る感情的なものに過ぎない。勝てれば良いというのなら、クレーン車が小学生を踏み殺しても構わないとでも言うのであろうか。
法律上は自転車であっても「車両。」であるから、車道上では同じ扱いをされなければならないものであって、速度が遅いからといって無理矢理追い抜きをしなければならないわけではなく。むしろ速度の速いロードレーサー自転車を先頭に自動車が追従すれば、自ずと「ふんわりアクセル。」になって温室効果ガス削減にもなるし、赤信号で無駄に「詰める。」必要性もなくなる。
幹線道路の多くは法定速度で走ることによって信号が順序よく青に変わるように設定されていることも多く、ロードレーサーの速度の方が無駄なアクセル/ブレーキ操作をせずに走ることも出来ることが多い。それに対して自動車の多くは無駄に加速して赤信号で道路を封鎖し、自転車の走行を妨害している場合が多く、その上路上駐車が重なると自転車としてはすり抜けをすることに「なってしまう。」のであろう。
自転車で車道を走っていると、自動車は自転車の横をギリギリですり抜けてゆくことは日常茶飯事であり。それを無視して自転車の方のすり抜けだけを問題視するのは極めて身勝手な間違いである。
そもそも自動車教習所では自転車が走っていたら何メートルかは離れて追い抜くように習ったはずであり、速度が遅いからといって無理矢理追い抜いて進路を封鎖して良いわけではなく。あくまで同じ「車両。」である以上、速度がどうあれ同じ扱いをしなければならないのである。
「速度が速い方が偉い。」「車体重量が重たい方が勝てる。」などといった文系大衆観念というものは道路交通法上は全く根拠のない自動車の方の身勝手な決めつけに過ぎない。そんなものは道路交通法律上では何ら規定されてなどいないのである。
大型車両が軽自動車よりも優先されないのと同様、自動車は別に自転車よりも優先されているわけではないことを認識すべきである。たとえ荷車であっても法律上は「車両。」であって、何ら邪魔にされるいわれはない。ベンツに載ってりゃ偉いわけでも優遇されるわけでもないのである。
認識が足りないというのは、それが無意識であるからであって、文系大衆観念というものは論理的根拠のない無意識的な「常識。」のことでもある。
法律を無視して、何となく無意識に自転車や荷車を蔑んで見る傾向というものが自動車運転者に限らず大衆観念的にはある。
自動車を運転している者の多くは、何となくゆっくり走ることが「負け。」であるかのような感覚的錯覚を持っており。これによって強迫観念的に加速しなければならないと勝手に思い込んでいる場合が多い。
ふんわりアクセルで法定速度を守って走っていると、時折煽ってくるバカもいるであろう。こうした一部のバカにつられて急加速を強迫観念的に行うのは無意識的な観念であることを認識する必要がある。
ヒトというのは、一部の乱暴な者の扇動につられて強迫観念的に行動をしてしまうことが少なくない。多数の者が文系大衆観念に基づいて行動していれば、文系大衆観念こそが気分的安心や満足になってしまうものである。意識の9割以上が無意識であることを認識していれば、自分の行動が一体何を根拠に選択されているのかに思慮が働くものであるが、それが出来ていないから多くのヒトは「意識が低い。」状態から解脱することが出来ないのである。
東京電力ではたくさんの社員が働いているはずである。その社員のほとんど全員が会社の「空気。」に迎合していたからこそ原発の暴走を招いたのである。
「赤信号、皆で渡れば恐くない。」というのは集団心理傾向ギャグである。「恐い。」だの「勝てる。」だのといった気分感情に基づいた観念で行動選択がされているから無意識なのであって、これは極めて子供じみた発想である。
芸人というのは大衆迎合が商売であるから、文系大衆観念に寄り添って空気を読むことが仕事であろう。だが、自動車の運転というものは原発同様社会的責任を伴うものであることを忘れるべきではない。
疋田智が冗談半分で言っていたが、幹線道路では違法路上駐車車両は破壊されても賠償責任がないことにしてしまえば良いとおいらも思う。
おいらの場合は冗談半分ではなく9割以上本気である。
Ende;
○帰属。
ヒトという種の生物は、その本能的社会形成習性によって個人の意思尊重よりも集団帰属による安心を優先しがちである。
特定集団への帰属による気分的/本能的安心満足というものは、個人の主体的で自律的判断を蔑ろにし、方向性のない集団暴走へと陥る傾向がある。
個人が主体的な自律判断を誰もしない集団が暴走するのは当たり前のことであるが、集団心理が持つ気分的本能的安心満足感によって、あたかも集団の誰かが安全性や持続可能性を担保してくれていると論理的根拠もなく勝手に思い込むのである。
北朝鮮の金正恩が、自発的に目的意識に基づいた政治選択をしているものであると多くの人は思うかも知れないが。実際には形式上の最高指導者として祭り上げられているだけであって、指導者個人が主体的に何かを選択しているのではなく、周囲の幹部による誘導によってしか判断をすることは出来ないのである。
日本政府であっても大臣の多くは役人の言いなりであるのと同様、制度によって限定された閉じた集団の内部だけでヒトの選択はなされてしまいがちなのである。
周囲の幹部の誰か特定の者に目的意識はなく、あくまで集団内部における最高指導者への忠誠忠実さ競争するための功績や評価を得るためだけの選択しかされることはない。
本能的社会形成習性というものは、集団の統率性を作り出すものではあるが。その集団のトップが常に自律的に目的意識を持って選択を下していることはなく。むしろ多くの体制団体というものでは誰にも目的意識もなく、結果的に暴走しか生み出すことはない。
ヤクザ、暴走族、カルト宗教といった反社会集団が持つ暴走性というものは、本能的社会形成習性の純粋発露であり、集団への帰属や忠誠忠実性の競争によって気分的/本能的安心感を得るための強迫観念的行動習性に過ぎない。
こうした暴走性というものは形式上の反社会集団に限ったことではなく、東京電力や大王製紙、オリンパス、西武グループなど、挙げればキリがない程の多くの企業団体においても発生しうるヒトの普遍的行動習性であり。決して他人事ではない。
集団内部における多数の観念というものが社会的に正しいのかどうかを個人が自律的に判断しなければ暴走は簡単に発生し、歯止めは全く働かない。
危険学、ヒューマンエラーというものを論ずるためには、当人に危険意識/論理的危険性判断というものが不可欠であるが。個人が気分的安心と論理的安全性の区別が出来ないことには危険学というものは全く知識や教訓として生かされることはないのである。
安全性を認識するのは個人である。集団体制というものは気分的安心しか満たすことは出来ないことを認識区別できなければ論理的安全性や危険性が何であるかを認識することは出来ない。
ヒトの多くは特定の集団や世間多数への帰属による気分的安心ばかりを追求するばかりで、自律的な社会安全性や持続可能性といったものを目的とした選択を簡単に忘れるものである。
Ende;
○コミュニケーション能力。
動物としての本能的/感情的な「社会性。」であるコミュニケーション能力というものは現状世間においては金銭的価値を求められているであろうが、これは「ヒト。」という種の生物的価値にはなっても人間としての本質的価値とは関係がない。
高いコミュニケーション能力によって世間的に成功しているとしても、社会的持続可能性や安全性という本質的社会性に適していることの論証にはならない。
しかし、多くの文系大衆観念上では気分的に安心することばかりが優先され、本質的な人間としての社会性は多くの場合無視されるのである。
空気を読まず、迎合しない者であっても自律的に社会安全性を優先しないことの論証にはならず。逆に空気を読んで権威に迎合することによってヒトの多くは差別や虐殺に加担する習性が存在することをアイヒマン実験は立証しているのであり、大衆に迎合せず多数のご機嫌をとらないからといって人間としての価値が低いことの証明にはならない。
生物的/本能的すなはち気分的な安心感といったものは意識ではなく機械条件反射的無意識に過ぎない。ヒトの多くはこうした気分感情による行動バイアスこそが意識であると錯覚しがちであるが、人間としての本質的な意識というものは論理的思考による本質的合理性追求であることに対してヒステリックな拒絶反応をするのである。
Ende;
○「事件のカギを握る麻原。」
麻原は事件のカギなど握っていない。
教団の暴走というものは教祖に目的がなかったからこその結果である。暴走族が目的もなく暴走するのも統率自体が本能的な目的だからであって、集団で統一的統率をしていることの気分的安心を追求した結果に過ぎない。
幹部達はただ教祖への忠誠忠実と評価を求めていただけであって、教祖もまた従順に服従する幹部の言うことを盲目的に信用していただけなのである。
ヤクザやゲリラと同様に、統率的に行動することによって気分的安心を追求しているだけであって、彼らのリーダーには何ら目的など一切存在せず。麻原やナチスのヒトラーも同様に何の目的もない。
暴走する集団というものには、そもそも誰にも合理的目的行動選択が行われないからこそ暴走するのであって。命令を下している教祖リーダーであるからといっても目的だの「事件のカギ。」を期待するのは間違いである。
暴力団がなぜ暴力団であるのかを暴力団の構成員に尋ねても答がないのと同様、暴走族がなぜ暴走行為を行うのかを暴走族に尋ねても答がないのと同様、ゲリラがなぜ残虐なのかをゲリラ当人に尋ねても答がないのと同様、カルト宗教の暴走の原因をカルト宗教の教祖や幹部に尋ねても合理的回答が返ってくることは原理的にない。
合理的回答を持っているのであれば最初から暴走になど陥らないのである。
子供のイジメも同様であり、誰にも目的など存在せず、特定の仕切りたがり屋による扇動による多数同調の結果であり。リーダーとなる仕切り屋自身もまた多数からのウケ狙いを求めて扇動しているに過ぎない。子供になぜイジメを行うのかを問うても合理的説明による原因究明は原理的に不可能なのである。
昭和天皇が軍による誘導によって太平洋戦争の責任者であるかのように祭り上げられたのと同様、北朝鮮の金正恩もまた何ら本質的には自発的選択など一切出来ない状況なのである。形式上の統率者だけが全てを取り仕切っているかのような錯覚を抱きがちであるが、実際には体制自体、集団全体の多数迎合性によって暴走性は作り出されるのである。
自律的に目的行動選択を持たない本能的社会形成だけで統率された集団にとって、自律的に目的行動選択を行う者というのは気分が悪い邪魔な存在であるため、徹底的に差別排除され、粛正というヒステリックな最終解決が短絡的に行われることになり。集団は益々暴走の一途を辿ることに陥るのである。
こうした無意識的な社会形成本能による暴走性というものは、司法による当事者への罰では何ら原因究明にも再発防止策もなることはなく。ただ漫然と慣習に従って感情的満足を得ているだけの無駄な行為に過ぎない。
司法が追求する真実というのは、「その。」事案においての断片的真実を暴くことだけしか行われることはなく。ヒトという種の生物自体に由来する本能的暴走性については全く言及されることはない。刑事裁判の目的は再発防止ではなく、あくまで科料の妥当性を吟味することだけであるからだ。
法制度手続きだけに基づいて行われる司法というものは、制度上規定された刑罰科料の妥当性吟味だけが目的であり。こうした手続き自体も、多数の大衆による論理的根拠を持たない観念によって維持保守されるだけである限り根本的解決としての科学的解析や再発防止対策の確立には構造的になっていない。
裁判というものは、これ自体が刑罰を決定するためだけに存在するためのものであって。三権分立という制度自体はあくまで経験則的に構築された結果的制度に過ぎず、必ずしも科学的論理的根拠に基づいて規定されたものではない。
何せ法律こそが具体的だと思い込んでいるようなバカが検察官をやっているような現状において、具体的な事件の原因究明や再発防止策の確立などされるわけがない。司法に携わる者達というのは法手続きに則って機械的に処理することによる評価報酬だけが目的であって、社会全体の安全性も持続可能性も意識の俎上には全くないからである。
警察や検察による事件の捏造も、真実の追求によって安全性や持続可能性を高めることが評価になるようには構造的になっていないからであって、利己的な評価だけを目的としているからこその結果なのである。
最近では評価の方法を変えることによって無意識な役人達の行動を制御する方法論というものが提唱されているが、これは役人個人の主体的自律判断というものを無視した「バカの取り扱い方。」を論じているに過ぎない。警察が取り締まりを最終目的とするよりは社会安全性を目的とするように「誘導。」できた方がいくらかはマシではあろうが、根本的な解決策とするのは大きな間違いである。個人が「バカである。」こと自体を改善しない限りはバカげた結果に至ることは避けられないからだ。
本来であれば制度云々といった環境に依らず自律的に社会全体の安全性や持続可能性を追求するのが「人間。」としての社会性というものであるが。こうした根本的人間性というものが全く無視されたまま学力競争だけを漫然と強要してきた頭の悪さ、意識の低さ浅さ狭窄さというもの放置しておいて、社会が良くなる保証など全くないのである。
ヒトの多くは漫然と慣習に則って同じことを繰り返しておけば安心で満足を得られるであろう。逆に言えば無意味な慣習であっても改革を行うことは恐怖と不安を抱くものでもある。ましてや無意識な多数に対して異議を唱えるとなれば世間からの排除をされることも少なくはない。その恐怖心/強迫観念こそがあらゆる社会集団における暴走性を助長する結果を招くことになるのである。
Ende;
○「勝てると思っているのかしら。」
TBSの「怒り新党。」って番組で、自転車が自動車の間をすり抜けることについてマツコデラックスが形容してたんだけど。
自転車が自動車の隙間をすり抜けするのは、自動車が道路を封鎖しているからすり抜けなければならないのであって、別に「勝ちたい。」からすり抜けているわけではない。と思う。
有吉が言うには「俺ら(自動車)が避けてやっている。」とも言っていたが、すり抜けをしなければならいのは、赤信号で自動車が道路を封鎖しているからであって、多くの自動車は自転車が走れるようには考えていない。
特にタクシーの場合、客を拾うために急な幅寄せをしてくることも多いために自転車からは嫌われている傾向もある。おいらも何回か経験がある。仕事で二輪車を運転をしていればタクシーは敵だと思われているかも知れない。
自動車運転をしている者の多くは、赤信号の交差点に「詰めて。」並ぶためだけにスピードを出している場合が非常に多く、自転車からすると温室効果ガスを撒き散らして進路妨害をしているだけにしか見えない。
そもそも「勝つ。」だのという観念は一体どこから出て来ているであろうか。こうした文系大衆観念というものには合理的根拠というものが全くなく、その場限りの気分から出て来る感情的なものに過ぎない。勝てれば良いというのなら、クレーン車が小学生を踏み殺しても構わないとでも言うのであろうか。
法律上は自転車であっても「車両。」であるから、車道上では同じ扱いをされなければならないものであって、速度が遅いからといって無理矢理追い抜きをしなければならないわけではなく。むしろ速度の速いロードレーサー自転車を先頭に自動車が追従すれば、自ずと「ふんわりアクセル。」になって温室効果ガス削減にもなるし、赤信号で無駄に「詰める。」必要性もなくなる。
幹線道路の多くは法定速度で走ることによって信号が順序よく青に変わるように設定されていることも多く、ロードレーサーの速度の方が無駄なアクセル/ブレーキ操作をせずに走ることも出来ることが多い。それに対して自動車の多くは無駄に加速して赤信号で道路を封鎖し、自転車の走行を妨害している場合が多く、その上路上駐車が重なると自転車としてはすり抜けをすることに「なってしまう。」のであろう。
自転車で車道を走っていると、自動車は自転車の横をギリギリですり抜けてゆくことは日常茶飯事であり。それを無視して自転車の方のすり抜けだけを問題視するのは極めて身勝手な間違いである。
そもそも自動車教習所では自転車が走っていたら何メートルかは離れて追い抜くように習ったはずであり、速度が遅いからといって無理矢理追い抜いて進路を封鎖して良いわけではなく。あくまで同じ「車両。」である以上、速度がどうあれ同じ扱いをしなければならないのである。
「速度が速い方が偉い。」「車体重量が重たい方が勝てる。」などといった文系大衆観念というものは道路交通法上は全く根拠のない自動車の方の身勝手な決めつけに過ぎない。そんなものは道路交通法律上では何ら規定されてなどいないのである。
大型車両が軽自動車よりも優先されないのと同様、自動車は別に自転車よりも優先されているわけではないことを認識すべきである。たとえ荷車であっても法律上は「車両。」であって、何ら邪魔にされるいわれはない。ベンツに載ってりゃ偉いわけでも優遇されるわけでもないのである。
認識が足りないというのは、それが無意識であるからであって、文系大衆観念というものは論理的根拠のない無意識的な「常識。」のことでもある。
法律を無視して、何となく無意識に自転車や荷車を蔑んで見る傾向というものが自動車運転者に限らず大衆観念的にはある。
自動車を運転している者の多くは、何となくゆっくり走ることが「負け。」であるかのような感覚的錯覚を持っており。これによって強迫観念的に加速しなければならないと勝手に思い込んでいる場合が多い。
ふんわりアクセルで法定速度を守って走っていると、時折煽ってくるバカもいるであろう。こうした一部のバカにつられて急加速を強迫観念的に行うのは無意識的な観念であることを認識する必要がある。
ヒトというのは、一部の乱暴な者の扇動につられて強迫観念的に行動をしてしまうことが少なくない。多数の者が文系大衆観念に基づいて行動していれば、文系大衆観念こそが気分的安心や満足になってしまうものである。意識の9割以上が無意識であることを認識していれば、自分の行動が一体何を根拠に選択されているのかに思慮が働くものであるが、それが出来ていないから多くのヒトは「意識が低い。」状態から解脱することが出来ないのである。
東京電力ではたくさんの社員が働いているはずである。その社員のほとんど全員が会社の「空気。」に迎合していたからこそ原発の暴走を招いたのである。
「赤信号、皆で渡れば恐くない。」というのは集団心理傾向ギャグである。「恐い。」だの「勝てる。」だのといった気分感情に基づいた観念で行動選択がされているから無意識なのであって、これは極めて子供じみた発想である。
芸人というのは大衆迎合が商売であるから、文系大衆観念に寄り添って空気を読むことが仕事であろう。だが、自動車の運転というものは原発同様社会的責任を伴うものであることを忘れるべきではない。
疋田智が冗談半分で言っていたが、幹線道路では違法路上駐車車両は破壊されても賠償責任がないことにしてしまえば良いとおいらも思う。
おいらの場合は冗談半分ではなく9割以上本気である。
Ende;
○帰属。
ヒトという種の生物は、その本能的社会形成習性によって個人の意思尊重よりも集団帰属による安心を優先しがちである。
特定集団への帰属による気分的/本能的安心満足というものは、個人の主体的で自律的判断を蔑ろにし、方向性のない集団暴走へと陥る傾向がある。
個人が主体的な自律判断を誰もしない集団が暴走するのは当たり前のことであるが、集団心理が持つ気分的本能的安心満足感によって、あたかも集団の誰かが安全性や持続可能性を担保してくれていると論理的根拠もなく勝手に思い込むのである。
北朝鮮の金正恩が、自発的に目的意識に基づいた政治選択をしているものであると多くの人は思うかも知れないが。実際には形式上の最高指導者として祭り上げられているだけであって、指導者個人が主体的に何かを選択しているのではなく、周囲の幹部による誘導によってしか判断をすることは出来ないのである。
日本政府であっても大臣の多くは役人の言いなりであるのと同様、制度によって限定された閉じた集団の内部だけでヒトの選択はなされてしまいがちなのである。
周囲の幹部の誰か特定の者に目的意識はなく、あくまで集団内部における最高指導者への忠誠忠実さ競争するための功績や評価を得るためだけの選択しかされることはない。
本能的社会形成習性というものは、集団の統率性を作り出すものではあるが。その集団のトップが常に自律的に目的意識を持って選択を下していることはなく。むしろ多くの体制団体というものでは誰にも目的意識もなく、結果的に暴走しか生み出すことはない。
ヤクザ、暴走族、カルト宗教といった反社会集団が持つ暴走性というものは、本能的社会形成習性の純粋発露であり、集団への帰属や忠誠忠実性の競争によって気分的/本能的安心感を得るための強迫観念的行動習性に過ぎない。
こうした暴走性というものは形式上の反社会集団に限ったことではなく、東京電力や大王製紙、オリンパス、西武グループなど、挙げればキリがない程の多くの企業団体においても発生しうるヒトの普遍的行動習性であり。決して他人事ではない。
集団内部における多数の観念というものが社会的に正しいのかどうかを個人が自律的に判断しなければ暴走は簡単に発生し、歯止めは全く働かない。
危険学、ヒューマンエラーというものを論ずるためには、当人に危険意識/論理的危険性判断というものが不可欠であるが。個人が気分的安心と論理的安全性の区別が出来ないことには危険学というものは全く知識や教訓として生かされることはないのである。
安全性を認識するのは個人である。集団体制というものは気分的安心しか満たすことは出来ないことを認識区別できなければ論理的安全性や危険性が何であるかを認識することは出来ない。
ヒトの多くは特定の集団や世間多数への帰属による気分的安心ばかりを追求するばかりで、自律的な社会安全性や持続可能性といったものを目的とした選択を簡単に忘れるものである。
Ende;