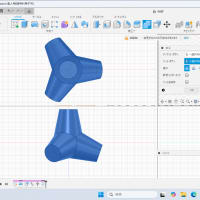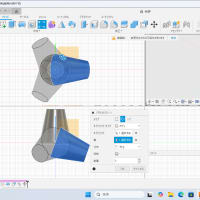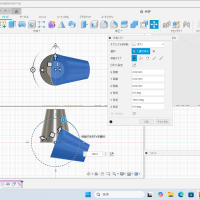○集団組織的手抜き。
簡単にぶちギレるような動物的でヒステリックな者に対して、ヒトの多くは気分的に面倒臭いために観念して服従する習性がある。
ヒトという種の生物というのは、服従する相手を必ずしも論理的に検証して選択する訳ではなく、目先の感情気分に基づき、目先の多数集団に迎合してしまう習性がある。
ヒトの多くは意識的目的として、合理的判断に基づく目的のための統率的協調行動のための服従ではなく。単なる目先の感情気分を満たすだけの結果的統率協調行動に流される傾向習性がある。
イジメを扇動するような相手に対し、多くのヒトは迎合し、結果的に組織的イジメを統率的協調行動「してしまう。」のである。当然「してしまう。」というのは個人の自律的意思は介在しておらず無意識の「結果」でしかない。
こうした無意識こそがあらゆる集団組織腐敗の原因であり、個人の自律的判断を放棄させるのである。
イジメによる自殺や傷害事件という「結果」や、原発の暴走という「結果」に至るまで集団組織の腐敗性を放置してしまうのは、集団組織を構成する一人一人の個人の意識的自律判断が全く働いておらず、無意識的に本能によって促される動物的服従迎合性に流された結果として、暴走破綻に至って「しまう。」のである。
制度や法律といったシステムというものは、あくまで機械的条件反射行動を促すだけであって、個人の自律的な社会的責任判断を促すようなものではない。
ヒトには自律的な社会的責任判断可能性があり、これを阻害するのは本能的な世間への迎合服従性による無意識な判断撹乱、思考停止が働くからである。
目先の多数世間に迎合したり、力を持った相手の命令に盲目的に服従してしまえば、個人が自律的に社会的責任判断を行わなくてはなるのは必然的結果である。
通り魔などの単独犯罪においても、その動機には世間への復讐という現状世間に対する無為無策な迎合性が根源にあり、当然行動自体はには何の合理性もなく、単なる気分的満足のための行動に過ぎない。
現状世間における価値観を鵜呑みにしているからこそ、自己自身の本質的満足が一切出来ず、その不満を全て自分以外になすりつける形で通り魔は実行されるのである。
「他人に認めてもらいたい。」という、他者からの評価報酬を目的にしていることこそが、本質的自発性の欠如、自己自身の価値観を持たない証明である。どんなに外見上「自発的」に見えるとしても、現状世間からの評価を求めることは本質的な自発性ではない。
当然自発性がなければ自律判断も行われることはない。これは定理である。
感情的でヒステリック暴力的な者に対する無為で盲目的服従を多数で共有迎合していれば、暴力こそが世間的価値観として刷り込み学習されてしまうことになる。バスジャックを「カッコイイ」などと思い込むのは、そこに自律的論理検証性が全く働いていないからこその結果である。
「合理性追究」という言葉への観念的拒絶反応によって、論理検証性の重要性を無視するというのは、意識狭窄であり精神的怠慢である。論理的反論が全くないにも関わらず観念的気分的拒絶反応に流されているのも、そこに本質的な自己自身による自律的論理検証性が働いていないからである。
論理的に何が正しいのかを自律的に判断できなければ、何も「考え」が成立しないのは当たり前であり、自律的に論理検証することこそが「考え」なのである。
ところがヒトの多くは自律的論理検証を放棄し、多数他人の意見に論理的根拠が欠落しているとしても看過し、問題の根源がどこにあるのかを自発的には認識せず、気分的に安心して諸問題を放置する傾向習性がある。
特定個人を天才と称して特別扱いしたがるのも、多数の凡庸さを正当化するための免罪符にすりかえようとする言い逃れ/取り繕いに過ぎない。バカであることを多数で共有すればバカであることが正当化されるわけではない。
制度や法律といったものは、いわば抗生物質のような対処療法であり。犯罪や危険性放置というものはウイルスのように次々と進化変化する多様性を持っているために、最終的には効力を失うものである。
脱法麻薬類などはその典型である。
刃物を何に用いるか、その選択こそが通り魔と調理の違いであり、法律手続きによる機械的抑圧によって通り魔を抑制することは原理的に不可能なのである。
機械手続き的な抑圧という、実質的有効性を持たない手段だけしか行わないというのは、単なる手抜き怠慢である。
ヒトの多くは気分的に面倒臭いことを観念的に拒絶し、社会の危険性を放置しがちである。子供のイジメを些細であると程度問題やバランス問題という観念的解釈にすりかえることによって、結果的にあらゆるヒトの問題は放置されることになり。小さな事象を放置した結果として大きな事象が発生するまで放置することになるのである。
原発を暴走にまで放置した東電幹部や社員達の無能さを作り出したのは、ことなかれ主義的で自律的には何も「考え」ることのない者を大量生産した教育機関にも問題の一端は免れない。
ハインリッヒの法則というものを、重大事象に発展する前の予防的対策の必要性として認識していないから、あらゆる危険性は放置されるのである。
どんなに学力が高くても、人間として出来損ないでは意味がない。優先すべきは自律的思考であって、「教えたことを鵜呑みにする。」ことではない。どんなに沢山の知識を詰め込んでも、自律的思考がなければ教えたこと以上の何も気付くことは出来ず、何ら本質的な知能は発揮されることはないのである。間違いを教えても自律的に気付くことができない高学力なエリートが毒ガステロを実行したことを忘れるべきではない。
何が論理根拠のない観念的解釈であるか、何が合理的根拠のある理論的理解であるか。その区別は論理検証による「考え」でしか導き出すことは出来ない。これは決して観念的なバランス問題や程度問題によって区別されるべきものではない。
個人が自律的に論理検証をしないから、あらゆる諸問題や危険性が放置されるのである。
「想定外」などというのは、はじめから想定すること自体を誰も行わないという自発性の欠落の結果であり。何ら言い訳にはならない。
危険性というものを程度問題にすりかえ放置した怠慢の言い逃れとして「想定外」という言葉が用いられることがあまりに多すぎる。想定可能なものを意識から外し無視しただけのことを「想定外」と言い逃れしているに過ぎない。
教育機関が学力を優先するのは、教育機関の組織の利益を優先して社会的責任を放棄しているからである。教育機関における本質的社会的役割とは、自律的に社会的責任判断を行える人材を社会に輩出することであって、単なる学力バカを大量生産することなどではない。
養老孟司のようなキチガイを名誉教授扱いしている東大に合格しても、キチガイをキチガイと認識出来ないバカしか生産されることはない。バカというのはキチガイが誘導する実証不能の観念に迎合し満足する者のことを指すのである。それなら地下鉄に毒ガスを撒いて「人類の救済。」だと勘違いするのも必然である。
他人の迷惑を気遣うのと、多数に服従迎合することの違いは、そこに自発的自律的判断が伴うかどうかである。本質的な自発的「考え」がなければ、それが区別出来ないのは当然である。
Ende;