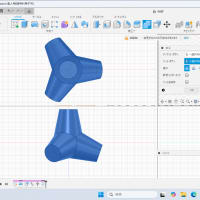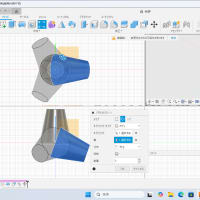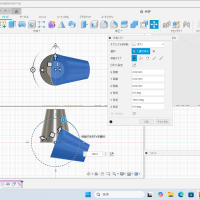アラン:チューリングという数学者が提唱する「チューリングテスト。」という予測があり、これに懸賞金がかかっているという話を、何年か前に東大生物学部が言っていた。
東大がこれを言う前から、私はチューリングテストには意味がないことを言っていたのだが。東大はバカの集団なので、これが理解できないのである。
チューリングテストとは、ヒトをチャットのようなコンソールによって何者かと「会話。」をさせ。その相手がヒトが機械かを判別できなければ、それは人工知能と見なす。という観念である。
「見なし。」を行う人物によって、判定は様々であろう。電話機で会話をしていても、ヒトは振り込め詐欺師なのか警察官なのかすら判定は一定ではない。人工知能に詳しい電子工学者と心理学者でも判定は異なるであろう。
自閉症患者の発言を機械で文字列に変換していたら、相手がヒトだと思う可能性は激減するであろう。
そもそも、チューリングテストによって人工知能であると「見なし。」たとして、それが何かの役に立つかといえば、全く無意味である。
「シーマン。」というビデオゲームが一時期流行したが、これを高性能にすれば多くのヒトは相手をヒトであると錯覚するだろう。それが何の役に立つであろうか。会話ができれば原子炉の運転を任せられるのであろうか。高速バスの運転を任せられるのであろうか。
ヒトであっても会話ができるからといって信用できるとは言えないのである。どんなにたくさんのヒトから信頼され、人気を得たとしても。それが本当に信用するに値する人物である証明にすらならない。
言語というものが意識と同義であるという観念は、一般大衆の観念でしかない。言語をどんなに巧みに操り、巧妙な詐欺を行っても、それが「人間としての社会性。」すなはち、公益倫理的な自律判断を行っていることの証明にはならない。
糸井重里を丸め込んで、一般大衆の人気取りに邁進する養老孟司を。東大生物学部は現在まで一切反論していない。どんなに読者の大脳辺縁系に快楽を与える条件反射行動ができたとしても、それが社会にとって悪影響しか与えない実証不能の観念であることが認識できなくても。大衆の観念の上では、それは「知能。」として扱われる。
かつて、ドイツでは優性学に基づく観念によって大量虐殺が行われたが。その原因については誰一人として言及してこなかった。優性学の「論拠。」となる生物学における「生物の目的は、生存。」という実証不能の観念について、生物学界は一切言及してこなかった。
ヒトの多くは「死ぬことが嫌い。」である。その多数決的な感情を枚挙することによって、あたかも「ヒトの目的は、生存。」であると盲目的に信じ込んでいたいのであろう。それが大衆にとって気分的に「安心。」なのであろう。だからマイケル:サンデルは「生き抜く。」などという大衆迎合を標榜するのである。立花隆も同様に「生き抜くためには。」などと論じていた。立花は既に棺桶に頭を半分突っ込んでいるのでどうでも良いが。単なる生存だけを目的とした生物学の観念に基づけば、詐欺であろうと何だろうと、結果的に生存につながりさえすれば「正当。」であり、「正義。」なのである。
こんなバカげた話を、凡庸な大衆マスコミは鵜呑みにし続ける。「嫌な話は無視する。意識から外す。」といった感情論に則って大衆迎合をしていれば、大衆の大脳辺縁系は「安心。」なのである。
原発を暴走させた人間は、おそらく潤沢な利益を得ているであろうから。放射能に汚染された日本なんぞ放棄して南半球にでも国外逃亡して安穏と暮らせるであろう。
国家最高学府の腐敗を放置しているから、こんなことになるのである。以前にも述べたが、これは公開アイヒマン実験と同じである。権威の命令を鵜呑みにしておいて、その結果がどうなるのかを全く自律的には判断しないことが、どれだけ恐ろしい結末を導くのか。
もう遅いのかも知れないし、遅くないかも知れない。諦めてしまえば簡単である。私の大脳辺縁系は楽になる。何も考えなくて済むからである。
バカになって、大脳辺縁系のおもむくままに生きていられたら、どんなに楽であろうか。時折そんなことも考える。
§ 腹が立つシーケンス
空腹になると、意味もなく苛立つことがある。これは、ドーパミンが作り出す情動行動的な不安を、副腎皮質ホルモンの影響によって促すためにノルアドレナリンによって補う大脳辺縁系のシーケンスによるものである。
苛立つとか、落ち着かないといった感情というのは。要するに気分的に安心できないから促されるのである。
生物学的な社会形成習性における、たとえばイヌのボスに見られる特異行動は、服従対象の喪失による機械手続き的条件反射行動なのである。従って、そこに目的論風味なこじつけを行っても、全く論理的な根拠はない。
イヌに生物としての意識はあるが、行動の全ては極めて機械手続き的であり、条件反射的である。これはイヌには本質的な意識が存在せず、行動のほとんど全てが環境依存的な結果的行動しかしないことの証明である。
躾を間違えた小型犬が飼い主の手を噛む。この行動に一体何の「目的。」をこじつけるのであろうか。また、そのこじつけた目的の果てにどのような結果がこじつけられるのであろうか。イヌは単に服従対象としての「飴とムチ。」によって服従への快楽「甘え。」が得られないことが感情的に不満であるため、暴力性や性衝動を条件反射的に発揮しているだけなのである。
アイヒマン実験においても、やはり被験者は権威に反論する時に感情的に苛立つ。観念的には「権威者というものは、権威でない者に対して命令を下す時には。その行動責任を担保するものである。」という「錯覚。」を覆されることの不安によって、感情的に「腹が立つ。」のである。
「権威。」とは、それ自体は科学的な根拠など存在しない。よく、「科学的権威。」などという言い回しがあるが。それは「科学界における見なし。」であって。権威というもの自体に科学的根拠とか、論理的証明とかが存在するわけではない。
このことはミルグラムも言及していなかったような気がする。サイバネティクスの観点からは権威の必要性を断片的に「説明。」はしていたが、これは「結果。」と「目的。」の区別がついていない生物学の観念に由来するものであるから、無視して構わない。というか自分で気付け。
東大がこれを言う前から、私はチューリングテストには意味がないことを言っていたのだが。東大はバカの集団なので、これが理解できないのである。
チューリングテストとは、ヒトをチャットのようなコンソールによって何者かと「会話。」をさせ。その相手がヒトが機械かを判別できなければ、それは人工知能と見なす。という観念である。
「見なし。」を行う人物によって、判定は様々であろう。電話機で会話をしていても、ヒトは振り込め詐欺師なのか警察官なのかすら判定は一定ではない。人工知能に詳しい電子工学者と心理学者でも判定は異なるであろう。
自閉症患者の発言を機械で文字列に変換していたら、相手がヒトだと思う可能性は激減するであろう。
そもそも、チューリングテストによって人工知能であると「見なし。」たとして、それが何かの役に立つかといえば、全く無意味である。
「シーマン。」というビデオゲームが一時期流行したが、これを高性能にすれば多くのヒトは相手をヒトであると錯覚するだろう。それが何の役に立つであろうか。会話ができれば原子炉の運転を任せられるのであろうか。高速バスの運転を任せられるのであろうか。
ヒトであっても会話ができるからといって信用できるとは言えないのである。どんなにたくさんのヒトから信頼され、人気を得たとしても。それが本当に信用するに値する人物である証明にすらならない。
言語というものが意識と同義であるという観念は、一般大衆の観念でしかない。言語をどんなに巧みに操り、巧妙な詐欺を行っても、それが「人間としての社会性。」すなはち、公益倫理的な自律判断を行っていることの証明にはならない。
糸井重里を丸め込んで、一般大衆の人気取りに邁進する養老孟司を。東大生物学部は現在まで一切反論していない。どんなに読者の大脳辺縁系に快楽を与える条件反射行動ができたとしても、それが社会にとって悪影響しか与えない実証不能の観念であることが認識できなくても。大衆の観念の上では、それは「知能。」として扱われる。
かつて、ドイツでは優性学に基づく観念によって大量虐殺が行われたが。その原因については誰一人として言及してこなかった。優性学の「論拠。」となる生物学における「生物の目的は、生存。」という実証不能の観念について、生物学界は一切言及してこなかった。
ヒトの多くは「死ぬことが嫌い。」である。その多数決的な感情を枚挙することによって、あたかも「ヒトの目的は、生存。」であると盲目的に信じ込んでいたいのであろう。それが大衆にとって気分的に「安心。」なのであろう。だからマイケル:サンデルは「生き抜く。」などという大衆迎合を標榜するのである。立花隆も同様に「生き抜くためには。」などと論じていた。立花は既に棺桶に頭を半分突っ込んでいるのでどうでも良いが。単なる生存だけを目的とした生物学の観念に基づけば、詐欺であろうと何だろうと、結果的に生存につながりさえすれば「正当。」であり、「正義。」なのである。
こんなバカげた話を、凡庸な大衆マスコミは鵜呑みにし続ける。「嫌な話は無視する。意識から外す。」といった感情論に則って大衆迎合をしていれば、大衆の大脳辺縁系は「安心。」なのである。
原発を暴走させた人間は、おそらく潤沢な利益を得ているであろうから。放射能に汚染された日本なんぞ放棄して南半球にでも国外逃亡して安穏と暮らせるであろう。
国家最高学府の腐敗を放置しているから、こんなことになるのである。以前にも述べたが、これは公開アイヒマン実験と同じである。権威の命令を鵜呑みにしておいて、その結果がどうなるのかを全く自律的には判断しないことが、どれだけ恐ろしい結末を導くのか。
もう遅いのかも知れないし、遅くないかも知れない。諦めてしまえば簡単である。私の大脳辺縁系は楽になる。何も考えなくて済むからである。
バカになって、大脳辺縁系のおもむくままに生きていられたら、どんなに楽であろうか。時折そんなことも考える。
§ 腹が立つシーケンス
空腹になると、意味もなく苛立つことがある。これは、ドーパミンが作り出す情動行動的な不安を、副腎皮質ホルモンの影響によって促すためにノルアドレナリンによって補う大脳辺縁系のシーケンスによるものである。
苛立つとか、落ち着かないといった感情というのは。要するに気分的に安心できないから促されるのである。
生物学的な社会形成習性における、たとえばイヌのボスに見られる特異行動は、服従対象の喪失による機械手続き的条件反射行動なのである。従って、そこに目的論風味なこじつけを行っても、全く論理的な根拠はない。
イヌに生物としての意識はあるが、行動の全ては極めて機械手続き的であり、条件反射的である。これはイヌには本質的な意識が存在せず、行動のほとんど全てが環境依存的な結果的行動しかしないことの証明である。
躾を間違えた小型犬が飼い主の手を噛む。この行動に一体何の「目的。」をこじつけるのであろうか。また、そのこじつけた目的の果てにどのような結果がこじつけられるのであろうか。イヌは単に服従対象としての「飴とムチ。」によって服従への快楽「甘え。」が得られないことが感情的に不満であるため、暴力性や性衝動を条件反射的に発揮しているだけなのである。
アイヒマン実験においても、やはり被験者は権威に反論する時に感情的に苛立つ。観念的には「権威者というものは、権威でない者に対して命令を下す時には。その行動責任を担保するものである。」という「錯覚。」を覆されることの不安によって、感情的に「腹が立つ。」のである。
「権威。」とは、それ自体は科学的な根拠など存在しない。よく、「科学的権威。」などという言い回しがあるが。それは「科学界における見なし。」であって。権威というもの自体に科学的根拠とか、論理的証明とかが存在するわけではない。
このことはミルグラムも言及していなかったような気がする。サイバネティクスの観点からは権威の必要性を断片的に「説明。」はしていたが、これは「結果。」と「目的。」の区別がついていない生物学の観念に由来するものであるから、無視して構わない。というか自分で気付け。