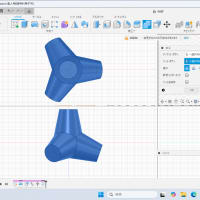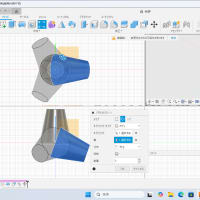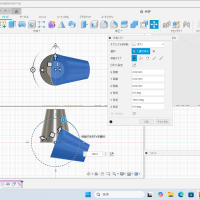○学力競争。
イジメや学級崩壊というものは、教師が生徒の自主性を信じてあげないことが原因なのだそうだ。
被害者だったおいら的には、「教師が信じてくれない。」なんていう環境依存性の結果に流されている無意識な時点で認めたくはないけれど。精神的不安こそが生徒を教室内部での封建性を作り出してしまう原因なのだという。
教室における序列として、教師が生徒を信頼することで、生徒は精神気分的に安心することで教室全体が和やかになるんだそうだ。
まあ、要は「空気」に流されているだけなので、教師が「良い空気」を作り出してしまえば改善はするということらしい。でも当然教師が「良い空気」を作り出さなければ主体的には改善しない時点で、所詮はバカの集団に過ぎないってことなんだろうけれども。小学生であれば致し方ないことなのかも知れない。
子供が勝手に作り出す教室内部の封建性を放置しなければ、イジメや生徒個人の暴力性といったものも醸成しずらいのかも知れない。イジメや暴力性といったものを習慣的に行動「学習」してしまうことによって、情動の激しい生徒は暴力的に育ってしまう可能性は高い。
学校での勉強よりも、生徒の話に耳を傾けてあげることによって。生徒の自主的学習意欲を引き出すことも可能なんだそうだ。
だから、「その学年における学力。」よりも、生徒自身の自発的主体性意欲というものを引き出してあげること、生徒自身に見つけ出せる手助けをしてあげることこそが、教育というものの社会的役割であると言えるんだろうな。
静岡知事が学力テストに異常執着しているけど、こうした数値結果に対する抽象的強迫観念こそが生徒の主体的自信を喪失させる原因なのではないだろうか。
学力というのは、「その学年における結果。」に過ぎないのであって。小柴昌俊のように小学校時代に成績が悪くてもノーベル賞を獲得することだってある。小柴昌俊が特別だと言うのであれば、一体どの子供は特別ではないと断言できるのであろう。その論理的根拠がどこにあるのであろう。どの子供がノーベル賞を受賞するかを教師が予測可能だとでも言えるのだろうか、だとすればノーベル賞受賞者よりも優れていることになるのである。
そんな神みたいな教師はいません。それは当人の勝手な妄想であって、カルト宗教の教祖が「自分は絶対的だ。」と思い込んでいるのと同じで、むしろキチガイの領域です。
だから学力競争「だけ」に異常執着するというのは、生徒の主体性を蔑ろにし、社会を崩壊へと導く破壊行為だと言える。
アインシュタインも含めてノーベル賞受賞者の多くは、子供の主体性を大切にすべきだと論じているにも関わらず、単なる政治家の強迫観念に基づいて社会を崩壊へと導くようなことをしてはいけない。
ただ、学力成績というのも、学級崩壊やイジメが多い学校程低い傾向もあるので、平均成績が極端に低い学校の内情に注目するという点においてだけは間違いではないかも知れない。
極端な話、県知事が校長を「信じて」あげないと、反ってイジメや学級崩壊を隠蔽してしまう可能性は高い。
優先すべきは生徒が安心して学習できる環境を整えてあげることであって、その結果として学力成績の向上を期待すべきであって。学力成績だけを目的にすることは、「高学力な無差別殺人犯」を作り出す可能性も高いのです。
教師が権威や力を振り回して生徒を強制的に服従させてしまえば、短絡的インスタントに学力を上げることも可能かも知れない。それこそが社会を崩壊に招く最大の原因だと、アインシュタインも述べているのです。
-------------------------------------------------------------------
無知で自分勝手な教師が与える屈辱と精神的抑圧は、若者の心に荒廃をもたらす。荒廃はけっして元には戻らず、しばしば後に有害な影響を残す。
私にとって、最悪だと思われるのは学校が主として恐怖、力、人工的な権威という方法を用いることです。そのような扱いは、生徒の健全な情緒、誠実さ、自信を破壊します。それが作り出すのは従順な臣民です。
学校がつねに目標とすべきは、若い(人たち)が調和のとれた人格の持ち主としてそこを出ることです。専門家としてではなく。
(調和のとれた人格に育たなければ)そうした(専門化した知識を持つ)人達は、調和のとれた成長した人間というよりも、よくしつけられた犬のほうにいっそう似るでしょう。
-----アインシュタインは語る 大月書店刊より-----
「従順な臣民」や、「よくしつけられた犬。」というのは、外見上は従順で扱い易いように見えるかも知れませんが。東京電力という環境の中では「組織の利益を優先し、社会安全性を蔑ろにする。」ようなヒトでもあるのです。
子供を従順にしつけることは簡単なことです。それこそシエラレオネでは子供を凶悪なゲリラに育て上げることも簡単だと言えるでしょう。
「学力」という結果だけを取り上げて、これを目的にすり替えることは短絡的思考であり、大変危険なものです。
学力というのは目的ではありません、生徒が社会に出た時の主体的目的のための手段として学力があるのであって、学力という抽象化された数値に踊らされてはいけません。
生徒は大人の数値競争の道具ではないのです。
ヒトという種の生物は、しばしば手段を目的と錯覚しがちです。それは意識の狭窄性によって生ずるものであって、こうした意識狭窄性こそが、ヒトという種の生物が人間として振る舞うことが出来なくなる、「心が失われる。」最大の原因です。
子供時代に学力競争を強いられていたヒト程、生徒に対しても学力競争を強いる傾向があります。これは「虐待の連鎖」と同様な無意識に刷り込み行動「学習」された条件反射に他なりません。
こういった刷り込み行動「学習」というのは、ヒステリックな異常執着を作り出し、「しばしば後に有害な影響を残す。」ことになるのです。
ヒトは自分が強いられて来たことを事後正当化しておかないと満足しない性質があります。自分が強いられてきたことを正当化するために、生徒子供に対しても同じような強制的抑圧をしておきたがる習性が、ヒトの脳にはあります。
本当に大切なものが何なのかを自主的には「考え」ることなく、条件反射的無意識に固定観念をぶちまけておけば安心で満足を得ることが出来るように、ヒトという種の生物の大脳辺縁系は出来ているのです。
これを「意識がない。」と言うのです。
自律的に何が正しいのかを判断出来ないのであれば、どんなに学力成績が高くても、科学的進歩が得られないのは必然的結果です。
東京大学情報学環の佐倉統のように、「大勢を占めていない。」ことを根拠に自律判断を全く行わない学術権威というのは、権威としての社会的役割を全く果たさないデクノボウに過ぎません。
現在の生物学や哲学、経済学というのは、こういった無能なデクノボウしかいないから具体性のある対策というものが全く立たず、目先の大衆的評価しか追求しないのです。
経済学者の多くは、「これさえやっときゃ、金が儲かる。」といった手口手法の開陳にばかり固執しますが。これは「目先の効用の追求」だけを目的とした大衆迎合であり、サブプライム問題などの経済破綻に対する具体的再発防止対策などについて真剣に取り組む経済学者がいないのも、研究者として極めて無責任であると言えるのです。
「目先の効用の追求」ばかりをしていれば、その行き着く先に何が起き得るのかを考えなくても済むので安心かも知れませんが。こうしたその場限りの目先にしか意識が働かないことこそが、意識狭窄性というものです。
ヒトの多くは「経済とは、金儲けである。」と短絡的に思うかも知れませんが、「経済」という言葉はそもそも「経世済民」すなはち、「世を経て民を救済する。」という言葉の略であり、「利己的な金儲け。」を意味するものではないのです。
つまり経済における企業活動とは、社会貢献が目的でなくてはならず、金儲けはその手段に過ぎないことを、多くのヒトは忘れてしまっているのです。
残念ながらこういった話は義務教育でも満足に教えません。なぜなら教師の多くが自分達の成績のために生徒を利用するだけで、教育というものの社会的役割なんぞどうでも良いと思っているからでしょう。
学力成績向上政策によって生徒の学力が上がれば、政治家としての評価を上げることは可能かも知れませんが、それは目先の評価欲しさの大衆迎合に過ぎません。
市民の一人一人も、もっと広い視野に基づいて政治家の政策を鑑みなければいけないのです。主権者である市民がバカならば、「民主主義」が「バカ主義」にしか陥らないのは必然的結果だからです。
現在の司法制度のように、特定の悪者探しをして罪の全てをなすりつけておけば気分的には満足を得ることも可能なのかも知れませんが。それは社会全体の安全性にとって何の利益ももたらさず、単に目先の主観的安心満足にしかならない身勝手なものなのです。
Ende;
イジメや学級崩壊というものは、教師が生徒の自主性を信じてあげないことが原因なのだそうだ。
被害者だったおいら的には、「教師が信じてくれない。」なんていう環境依存性の結果に流されている無意識な時点で認めたくはないけれど。精神的不安こそが生徒を教室内部での封建性を作り出してしまう原因なのだという。
教室における序列として、教師が生徒を信頼することで、生徒は精神気分的に安心することで教室全体が和やかになるんだそうだ。
まあ、要は「空気」に流されているだけなので、教師が「良い空気」を作り出してしまえば改善はするということらしい。でも当然教師が「良い空気」を作り出さなければ主体的には改善しない時点で、所詮はバカの集団に過ぎないってことなんだろうけれども。小学生であれば致し方ないことなのかも知れない。
子供が勝手に作り出す教室内部の封建性を放置しなければ、イジメや生徒個人の暴力性といったものも醸成しずらいのかも知れない。イジメや暴力性といったものを習慣的に行動「学習」してしまうことによって、情動の激しい生徒は暴力的に育ってしまう可能性は高い。
学校での勉強よりも、生徒の話に耳を傾けてあげることによって。生徒の自主的学習意欲を引き出すことも可能なんだそうだ。
だから、「その学年における学力。」よりも、生徒自身の自発的主体性意欲というものを引き出してあげること、生徒自身に見つけ出せる手助けをしてあげることこそが、教育というものの社会的役割であると言えるんだろうな。
静岡知事が学力テストに異常執着しているけど、こうした数値結果に対する抽象的強迫観念こそが生徒の主体的自信を喪失させる原因なのではないだろうか。
学力というのは、「その学年における結果。」に過ぎないのであって。小柴昌俊のように小学校時代に成績が悪くてもノーベル賞を獲得することだってある。小柴昌俊が特別だと言うのであれば、一体どの子供は特別ではないと断言できるのであろう。その論理的根拠がどこにあるのであろう。どの子供がノーベル賞を受賞するかを教師が予測可能だとでも言えるのだろうか、だとすればノーベル賞受賞者よりも優れていることになるのである。
そんな神みたいな教師はいません。それは当人の勝手な妄想であって、カルト宗教の教祖が「自分は絶対的だ。」と思い込んでいるのと同じで、むしろキチガイの領域です。
だから学力競争「だけ」に異常執着するというのは、生徒の主体性を蔑ろにし、社会を崩壊へと導く破壊行為だと言える。
アインシュタインも含めてノーベル賞受賞者の多くは、子供の主体性を大切にすべきだと論じているにも関わらず、単なる政治家の強迫観念に基づいて社会を崩壊へと導くようなことをしてはいけない。
ただ、学力成績というのも、学級崩壊やイジメが多い学校程低い傾向もあるので、平均成績が極端に低い学校の内情に注目するという点においてだけは間違いではないかも知れない。
極端な話、県知事が校長を「信じて」あげないと、反ってイジメや学級崩壊を隠蔽してしまう可能性は高い。
優先すべきは生徒が安心して学習できる環境を整えてあげることであって、その結果として学力成績の向上を期待すべきであって。学力成績だけを目的にすることは、「高学力な無差別殺人犯」を作り出す可能性も高いのです。
教師が権威や力を振り回して生徒を強制的に服従させてしまえば、短絡的インスタントに学力を上げることも可能かも知れない。それこそが社会を崩壊に招く最大の原因だと、アインシュタインも述べているのです。
-------------------------------------------------------------------
無知で自分勝手な教師が与える屈辱と精神的抑圧は、若者の心に荒廃をもたらす。荒廃はけっして元には戻らず、しばしば後に有害な影響を残す。
私にとって、最悪だと思われるのは学校が主として恐怖、力、人工的な権威という方法を用いることです。そのような扱いは、生徒の健全な情緒、誠実さ、自信を破壊します。それが作り出すのは従順な臣民です。
学校がつねに目標とすべきは、若い(人たち)が調和のとれた人格の持ち主としてそこを出ることです。専門家としてではなく。
(調和のとれた人格に育たなければ)そうした(専門化した知識を持つ)人達は、調和のとれた成長した人間というよりも、よくしつけられた犬のほうにいっそう似るでしょう。
-----アインシュタインは語る 大月書店刊より-----
「従順な臣民」や、「よくしつけられた犬。」というのは、外見上は従順で扱い易いように見えるかも知れませんが。東京電力という環境の中では「組織の利益を優先し、社会安全性を蔑ろにする。」ようなヒトでもあるのです。
子供を従順にしつけることは簡単なことです。それこそシエラレオネでは子供を凶悪なゲリラに育て上げることも簡単だと言えるでしょう。
「学力」という結果だけを取り上げて、これを目的にすり替えることは短絡的思考であり、大変危険なものです。
学力というのは目的ではありません、生徒が社会に出た時の主体的目的のための手段として学力があるのであって、学力という抽象化された数値に踊らされてはいけません。
生徒は大人の数値競争の道具ではないのです。
ヒトという種の生物は、しばしば手段を目的と錯覚しがちです。それは意識の狭窄性によって生ずるものであって、こうした意識狭窄性こそが、ヒトという種の生物が人間として振る舞うことが出来なくなる、「心が失われる。」最大の原因です。
子供時代に学力競争を強いられていたヒト程、生徒に対しても学力競争を強いる傾向があります。これは「虐待の連鎖」と同様な無意識に刷り込み行動「学習」された条件反射に他なりません。
こういった刷り込み行動「学習」というのは、ヒステリックな異常執着を作り出し、「しばしば後に有害な影響を残す。」ことになるのです。
ヒトは自分が強いられて来たことを事後正当化しておかないと満足しない性質があります。自分が強いられてきたことを正当化するために、生徒子供に対しても同じような強制的抑圧をしておきたがる習性が、ヒトの脳にはあります。
本当に大切なものが何なのかを自主的には「考え」ることなく、条件反射的無意識に固定観念をぶちまけておけば安心で満足を得ることが出来るように、ヒトという種の生物の大脳辺縁系は出来ているのです。
これを「意識がない。」と言うのです。
自律的に何が正しいのかを判断出来ないのであれば、どんなに学力成績が高くても、科学的進歩が得られないのは必然的結果です。
東京大学情報学環の佐倉統のように、「大勢を占めていない。」ことを根拠に自律判断を全く行わない学術権威というのは、権威としての社会的役割を全く果たさないデクノボウに過ぎません。
現在の生物学や哲学、経済学というのは、こういった無能なデクノボウしかいないから具体性のある対策というものが全く立たず、目先の大衆的評価しか追求しないのです。
経済学者の多くは、「これさえやっときゃ、金が儲かる。」といった手口手法の開陳にばかり固執しますが。これは「目先の効用の追求」だけを目的とした大衆迎合であり、サブプライム問題などの経済破綻に対する具体的再発防止対策などについて真剣に取り組む経済学者がいないのも、研究者として極めて無責任であると言えるのです。
「目先の効用の追求」ばかりをしていれば、その行き着く先に何が起き得るのかを考えなくても済むので安心かも知れませんが。こうしたその場限りの目先にしか意識が働かないことこそが、意識狭窄性というものです。
ヒトの多くは「経済とは、金儲けである。」と短絡的に思うかも知れませんが、「経済」という言葉はそもそも「経世済民」すなはち、「世を経て民を救済する。」という言葉の略であり、「利己的な金儲け。」を意味するものではないのです。
つまり経済における企業活動とは、社会貢献が目的でなくてはならず、金儲けはその手段に過ぎないことを、多くのヒトは忘れてしまっているのです。
残念ながらこういった話は義務教育でも満足に教えません。なぜなら教師の多くが自分達の成績のために生徒を利用するだけで、教育というものの社会的役割なんぞどうでも良いと思っているからでしょう。
学力成績向上政策によって生徒の学力が上がれば、政治家としての評価を上げることは可能かも知れませんが、それは目先の評価欲しさの大衆迎合に過ぎません。
市民の一人一人も、もっと広い視野に基づいて政治家の政策を鑑みなければいけないのです。主権者である市民がバカならば、「民主主義」が「バカ主義」にしか陥らないのは必然的結果だからです。
現在の司法制度のように、特定の悪者探しをして罪の全てをなすりつけておけば気分的には満足を得ることも可能なのかも知れませんが。それは社会全体の安全性にとって何の利益ももたらさず、単に目先の主観的安心満足にしかならない身勝手なものなのです。
Ende;