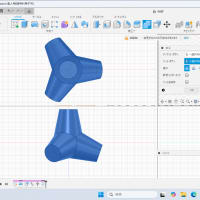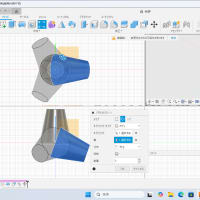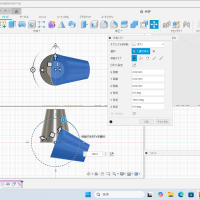○逸脱と同調。
ヒトが本来逸脱的であるのか、それとも調和的であるのか。この議論には構造的問題がある。
シエラレオネのゲリラ集団の内部で育った少年にとって、ゲリラの価値観に迎合することはゲリラ内部においては逸脱的とは言えない。
東京電力内部において、原発の危険性を放置することは東電内部においては同調的、調和的であると言える。
逆に言えば、ナチス政権下においてナチズムに反対することは第二次世界大戦下のドイツ社会にとっては逸脱的であると言える。
ガリレオ:ガリレイによる地動説であっても、当時の社会においては逸脱だったのである。
単なる逸脱性や同調性だけを論じても、自律的な社会的責任判断とは無関係である。
逸脱とか同調というのは多数派を基準にしているだけであって、少数派は常に逸脱として扱われることになるため、多数派と少数派のどちらが人間としての本質的社会性に値するのかの議論が欠落しており、多数派だけが常に正しいという勝手にな前提に基づいた議論にしかならない。
ヒトの多くは多数派同調が促す気分的安心を論理的安全性と取り違え、錯覚することで不毛な議論に陥り真理を見失うことに陥るのである。
ヒトの多くは体育会系集団のように気分感情を用いた強制的意識誘導による規律意識を刷り込み学習させておけば気分的に安心であるため、刑務所のような規律意識を強制的に刷り込み学習させておきさえすれば再犯をしなくなるものであると勝手に錯覚しているため、漫然と刑法の厳罰化さえしておけば気分的に安心なのである。
Ende;