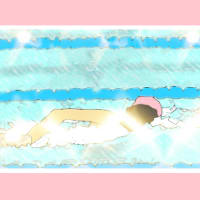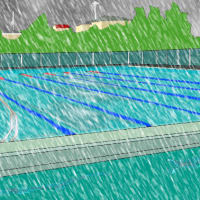心配そうなハルカは、心なしか先ほどよりもハラルドの近くにいる。ハラルドは無意識に右手の拳を作ろうとしていた。だがこの状況では、何があってもハルカに手を上げることは許されない。
「話をつづけるぞ。いいな?」
「は、はい……」
「私は、例のダティ間での取り決めもあったので、ハルカを人質にすることにした」
激しい衝撃を受けたようなハルカ。たしかに、保護されたような自分が形だけであっても人質に転換されたとすれば、言葉も失う。たたでさえ、人質という言葉には凄惨さがつまっている。記憶にもない自分の当時の姿を必死にたどってみればなおのことだろう。
「だがな、ハルカ。人質といってもそれは形だけのものだった。敵対する外界の者が迫ってきたことはなく、ハルカを縦にして窮地を脱したということもない。保障のようなものだった。外界の者が降伏し、ダティの主権が再び確立されるまで、その形態をつづけただけのことだ」
「その間、ずっとですか?」
「信じられないかもしれないがそうだった」
「手を出そうとはしなかったのですか?」
「手を出す? 誰に?」
「わたしに、です」
上目づかいで慎重に聞いてくるハルカ。なぜかそれは、しべがあり、一定の間にだけ咲き誇る植物のようにも見えていた。暗い部屋の中でも艶やかに目立つ。ハラルドは気をしっかり持たねばならなかった。
「なぜそんなことをする必要がある? お前はまるで眠っているようだったのだぞ? 貴重な人質だ。殺して何になる」
「そうですよね。人質ですもんね。すみません、変なこと聞いちゃって」
ハルカは安心したようにほほ笑んでいる。その安堵の意味することをハラルドにはすぐ理解できなかった。そんなことよりも、話を少しでも早く終わる方向に進めていかねばと思った。ここに長くいてはいけない。そんな不穏な空気を察知していたからなのかもしれない。
「とにかく、だ。結局ハルカの身柄は、我々が外界の者たちを労役者として扱うことを決定してから、外界の者たちへ引き渡した。それが、ハルカのここでの最初の記憶とつながっているのだろう。無責任なことを言うようだが、その後ハルカが息を引き取ろうがどなろうが、知ったことではなかった」
ハラルドはそこまでまくしたてると、もう何度目になるかという、頭上を仰ぎ見る行為に逃げていった。ハルカの顔を直視できない。先ほどのような不思議な感覚に陥る危惧がそうさせていた。これ以上ひどい面相をさらすことは絶えられなかった。
ハラルドは立ち上がり、壁際に積まれた古い木箱に手をかけていた。そのままハルカを背後にして口を開く。
「気を悪くしないでくれ。すべて私には必要なことだった」
「わかっています。少なくとも、わたしはここでこうして生きています。あなたが見捨てていたら、気づきもしなければ、わたしは今、ここにいなかったかもしれません」
ハルカの優しくささやくような言葉が、ハラルドの心にかかる。手を止めそうになった。
なぜ感謝されなければならないのか。なぜ外界の地の者どもは、これほどにも礼を尽くすのか。いずれ死が待っているというのに。心がかき乱されていく。まるで積悪の報いを受けつづけているようだった。
ハラルドは吐き捨てるように言った。
「助けたわけではない」
「はい」
ハルカの返答をかき消すように、木箱を荒っぽく下ろしていく。とどめだ。とどめを刺す必要がある。ハラルドは喉の奥で叫んだ。だが、それが誰に対してのとどめなのかはわからなかった。
埃が舞う中、目星をつけておいた上から三個目にあたる木箱を灯りの直下に移動させる。中身を改めるのは久しぶりであったが、記憶が確かであるならば、この中に目的のものがあるはずだ。
ふたを開けてそれを他の木箱の上に置く。途端に、湿っぽいかびの臭気が部屋内に充満していった。ハルカはたまらずに咳をしている。ハラルドは木箱の中から用途不明の戦利品をとりだしていた。今となっては用途不明、とはいえないそれを。
古びてぼろぼろになったかたまりをハルカの目の前にゆっくりと置いた。暗がりの中の灯りに照らされてみれば、そのどれもの色合いが地面の土色と大差がないように映る。だがハルカは目を見開き、その全てをたぐりよせていた。
炎の中心にある色合いの褪せた衣は、あらゆる個所で糸がほつれ、中身の綿が飛びだしている。
内側の白い布は、斑紋のようなしみが無数にできていて穴も開いていた。
紅色の細い紐状のものは、末端が散り散りに分かれている。
花弁のような闇色の布は、切れ目の部位から裂けるように分離し、ハルカの膝の上で広がっていた。
もとの色彩や型がどうであったかは、もはや知るよしもない。だが、これらをまとっていたのは、まぎれもなくハルカであった。
これらを見てハルカは何と言うのだろう。火をつけてしまえば一瞬にして無になる、価値のないようなこれらを見て。ハラルドはただ黙っておくしかできなかった。
ああ、あああ。
ハルカは吐息とも声とも言えぬ音を発し、崩れ落ちた。
握りしめられた布の中に顔をうずめて。
息を何度も何度ものどにつまらせて、しゃくりあげていた。
しばらくすると面を上げ、思い立ったように黄色の衣をまさぐる。
紙片のようなものを見つけ、時を止めたようになった。
肩口の布がずれ、胸の谷間が露(あら)わになっていたのを気にも留めない。
はらはらと落ちる長い髪は、うかがい知れないその表情を隠していく。
こんなにも間近で外界の者が涙するのを見たことがなかった。
ハラルドは、かける言葉を探さなかった。
≪つづく≫
「話をつづけるぞ。いいな?」
「は、はい……」
「私は、例のダティ間での取り決めもあったので、ハルカを人質にすることにした」
激しい衝撃を受けたようなハルカ。たしかに、保護されたような自分が形だけであっても人質に転換されたとすれば、言葉も失う。たたでさえ、人質という言葉には凄惨さがつまっている。記憶にもない自分の当時の姿を必死にたどってみればなおのことだろう。
「だがな、ハルカ。人質といってもそれは形だけのものだった。敵対する外界の者が迫ってきたことはなく、ハルカを縦にして窮地を脱したということもない。保障のようなものだった。外界の者が降伏し、ダティの主権が再び確立されるまで、その形態をつづけただけのことだ」
「その間、ずっとですか?」
「信じられないかもしれないがそうだった」
「手を出そうとはしなかったのですか?」
「手を出す? 誰に?」
「わたしに、です」
上目づかいで慎重に聞いてくるハルカ。なぜかそれは、しべがあり、一定の間にだけ咲き誇る植物のようにも見えていた。暗い部屋の中でも艶やかに目立つ。ハラルドは気をしっかり持たねばならなかった。
「なぜそんなことをする必要がある? お前はまるで眠っているようだったのだぞ? 貴重な人質だ。殺して何になる」
「そうですよね。人質ですもんね。すみません、変なこと聞いちゃって」
ハルカは安心したようにほほ笑んでいる。その安堵の意味することをハラルドにはすぐ理解できなかった。そんなことよりも、話を少しでも早く終わる方向に進めていかねばと思った。ここに長くいてはいけない。そんな不穏な空気を察知していたからなのかもしれない。
「とにかく、だ。結局ハルカの身柄は、我々が外界の者たちを労役者として扱うことを決定してから、外界の者たちへ引き渡した。それが、ハルカのここでの最初の記憶とつながっているのだろう。無責任なことを言うようだが、その後ハルカが息を引き取ろうがどなろうが、知ったことではなかった」
ハラルドはそこまでまくしたてると、もう何度目になるかという、頭上を仰ぎ見る行為に逃げていった。ハルカの顔を直視できない。先ほどのような不思議な感覚に陥る危惧がそうさせていた。これ以上ひどい面相をさらすことは絶えられなかった。
ハラルドは立ち上がり、壁際に積まれた古い木箱に手をかけていた。そのままハルカを背後にして口を開く。
「気を悪くしないでくれ。すべて私には必要なことだった」
「わかっています。少なくとも、わたしはここでこうして生きています。あなたが見捨てていたら、気づきもしなければ、わたしは今、ここにいなかったかもしれません」
ハルカの優しくささやくような言葉が、ハラルドの心にかかる。手を止めそうになった。
なぜ感謝されなければならないのか。なぜ外界の地の者どもは、これほどにも礼を尽くすのか。いずれ死が待っているというのに。心がかき乱されていく。まるで積悪の報いを受けつづけているようだった。
ハラルドは吐き捨てるように言った。
「助けたわけではない」
「はい」
ハルカの返答をかき消すように、木箱を荒っぽく下ろしていく。とどめだ。とどめを刺す必要がある。ハラルドは喉の奥で叫んだ。だが、それが誰に対してのとどめなのかはわからなかった。
埃が舞う中、目星をつけておいた上から三個目にあたる木箱を灯りの直下に移動させる。中身を改めるのは久しぶりであったが、記憶が確かであるならば、この中に目的のものがあるはずだ。
ふたを開けてそれを他の木箱の上に置く。途端に、湿っぽいかびの臭気が部屋内に充満していった。ハルカはたまらずに咳をしている。ハラルドは木箱の中から用途不明の戦利品をとりだしていた。今となっては用途不明、とはいえないそれを。
古びてぼろぼろになったかたまりをハルカの目の前にゆっくりと置いた。暗がりの中の灯りに照らされてみれば、そのどれもの色合いが地面の土色と大差がないように映る。だがハルカは目を見開き、その全てをたぐりよせていた。
炎の中心にある色合いの褪せた衣は、あらゆる個所で糸がほつれ、中身の綿が飛びだしている。
内側の白い布は、斑紋のようなしみが無数にできていて穴も開いていた。
紅色の細い紐状のものは、末端が散り散りに分かれている。
花弁のような闇色の布は、切れ目の部位から裂けるように分離し、ハルカの膝の上で広がっていた。
もとの色彩や型がどうであったかは、もはや知るよしもない。だが、これらをまとっていたのは、まぎれもなくハルカであった。
これらを見てハルカは何と言うのだろう。火をつけてしまえば一瞬にして無になる、価値のないようなこれらを見て。ハラルドはただ黙っておくしかできなかった。
ああ、あああ。
ハルカは吐息とも声とも言えぬ音を発し、崩れ落ちた。
握りしめられた布の中に顔をうずめて。
息を何度も何度ものどにつまらせて、しゃくりあげていた。
しばらくすると面を上げ、思い立ったように黄色の衣をまさぐる。
紙片のようなものを見つけ、時を止めたようになった。
肩口の布がずれ、胸の谷間が露(あら)わになっていたのを気にも留めない。
はらはらと落ちる長い髪は、うかがい知れないその表情を隠していく。
こんなにも間近で外界の者が涙するのを見たことがなかった。
ハラルドは、かける言葉を探さなかった。
≪つづく≫