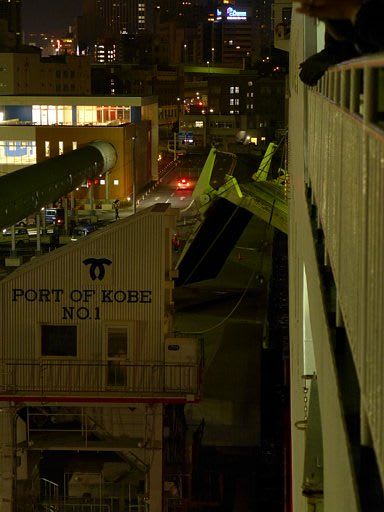鹿児島の続き。
鹿児島市内に泊まった翌日は温泉めぐりへ。
その前に、岩元邸の向かいにある玉江橋を見ていこう。

鹿児島市街地を流れる甲突川には、玉江橋、新上橋、西田橋、高麗橋、武之橋 という5つの石橋が架かっていたが、
1993(平成5)年の集中豪雨で新上橋と武之橋が流失してしまった。それを受け、残る3つの石橋を確実に
保存するため、石橋記念公園に移築保存された。

ここには前にも来たことがあり、圧倒されるような巨大な石橋の構造を間近で見られるのはうれしいのだが、
実際の川でなく申し訳程度に流した水たまりに架けられているのがちょっと残念・・・と思っていたら、
この玉江橋は実際の川に架かっているじゃないの。

前回は、西田橋と高麗橋、2つしか見ていなかったのだった(汗)

おや、近くで見たら4連アーチだったのか!

散歩の人や通り抜ける人などがちょこちょこ通るので、写真を撮ろうと待ち構えていてもなかなか撮れない。
普通にちゃんと橋としての役割を担っているのはうれしいことだなぁ!


さて、温泉めぐりへ。まずやってきたのは鹿児島市内からほど近い大黒温泉。やってるのかよく分からない感じ
だが、坂道を下りた川側が入口。もちろん元気に営業中だ。

朝っぱらからいきなりお風呂(笑)。つるつるしたお湯はアルカリ性PH8.2!気持ちいい~

ここでも八十八湯めぐりのスタンプゲット!

少し走ると船津温泉に。連続になってしまうが道順なんだから仕方ないな。。。(苦笑)
ここは立派な施設で、つるつるアルカリ系ほんのりモール臭。味はおいしく結構飲んでしまった。

さてお昼ごはんをどうしようかと検索して、蒲生(かもう)にある心地庵というカフェにやって来た。

この蒲生郷というところも麓という武家集落だった場所で、武家門や石垣が残る。
心地庵は120年前の古民家を改装したお店で、ピザが名物らしい。

ちょっと変わっているのは、ここは何でもセルフで、自分で食べるピザも庭の窯で自分で焼くのだ。


ご主人に教えてもらいながら、薄い生地のピザを窯の中へ入れてくるくると回し、2~3分でカリッと焼けた。
こんなにすぐ焼けるもんなんだな。自分で焼いたピザはとってもおいしかった!

ちょっと贅沢にデザートまでプラスして、しばしほっこりとした時間を過ごした。

さぁここから霧島山に向けて走ろう。
途中で山田の凱旋門という案内板が見えたのでストーップ!これも登録有形文化財のリストにあったな。

日露戦争で従軍した村人の帰還を祝して1906(明治39)年に建てられた。凝灰岩が使われたアーチは
石橋の技術を応用したものだとか。

ちょうど道すがらにあって見れたのでよかった!
続く。
鹿児島市内に泊まった翌日は温泉めぐりへ。
その前に、岩元邸の向かいにある玉江橋を見ていこう。

鹿児島市街地を流れる甲突川には、玉江橋、新上橋、西田橋、高麗橋、武之橋 という5つの石橋が架かっていたが、
1993(平成5)年の集中豪雨で新上橋と武之橋が流失してしまった。それを受け、残る3つの石橋を確実に
保存するため、石橋記念公園に移築保存された。

ここには前にも来たことがあり、圧倒されるような巨大な石橋の構造を間近で見られるのはうれしいのだが、
実際の川でなく申し訳程度に流した水たまりに架けられているのがちょっと残念・・・と思っていたら、
この玉江橋は実際の川に架かっているじゃないの。

前回は、西田橋と高麗橋、2つしか見ていなかったのだった(汗)

おや、近くで見たら4連アーチだったのか!

散歩の人や通り抜ける人などがちょこちょこ通るので、写真を撮ろうと待ち構えていてもなかなか撮れない。
普通にちゃんと橋としての役割を担っているのはうれしいことだなぁ!


さて、温泉めぐりへ。まずやってきたのは鹿児島市内からほど近い大黒温泉。やってるのかよく分からない感じ
だが、坂道を下りた川側が入口。もちろん元気に営業中だ。

朝っぱらからいきなりお風呂(笑)。つるつるしたお湯はアルカリ性PH8.2!気持ちいい~

ここでも八十八湯めぐりのスタンプゲット!

少し走ると船津温泉に。連続になってしまうが道順なんだから仕方ないな。。。(苦笑)
ここは立派な施設で、つるつるアルカリ系ほんのりモール臭。味はおいしく結構飲んでしまった。

さてお昼ごはんをどうしようかと検索して、蒲生(かもう)にある心地庵というカフェにやって来た。

この蒲生郷というところも麓という武家集落だった場所で、武家門や石垣が残る。
心地庵は120年前の古民家を改装したお店で、ピザが名物らしい。

ちょっと変わっているのは、ここは何でもセルフで、自分で食べるピザも庭の窯で自分で焼くのだ。


ご主人に教えてもらいながら、薄い生地のピザを窯の中へ入れてくるくると回し、2~3分でカリッと焼けた。
こんなにすぐ焼けるもんなんだな。自分で焼いたピザはとってもおいしかった!

ちょっと贅沢にデザートまでプラスして、しばしほっこりとした時間を過ごした。

さぁここから霧島山に向けて走ろう。
途中で山田の凱旋門という案内板が見えたのでストーップ!これも登録有形文化財のリストにあったな。

日露戦争で従軍した村人の帰還を祝して1906(明治39)年に建てられた。凝灰岩が使われたアーチは
石橋の技術を応用したものだとか。

ちょうど道すがらにあって見れたのでよかった!
続く。