
![]()

標高2,100mに位置する山上の温泉が人気の小屋で、この温泉に宿泊するのだけを目的に登って帰る人もいるそうです。
山小屋の料金など詳細は公式ホームページでご確認ください。
宿泊した'10年7月中旬は、猿倉からこの小屋に至るまでの道は巨大な雪渓が残っていたので、急斜面の雪上歩きに自信のない方にはおすすめできません。でも雪道初体験の方も多数登っていたので、それほど難易度は高くないと思います。
道中 数箇所、雪解け直後のもろい地盤が多数の落石を発生させており、人が歩く目の前で岩が落ちてくることもありました。雪のない場所でも崩落や滑落の危険が高いザレたトラバースもあるので、注意が必要です。
※今回も素泊まりだったので、食堂風景や食事の様子は取材していません。

かけ流しの温泉なので登山道の山小屋直下付近には、湯気の立つ温泉の川が流れていました。岩は硫黄成分で緑色になっています。雰囲気出ますなぁ
初夏のこの日は残雪量も多く、巨大な雪渓を直登してたどり着いたので、温泉の硫黄の香りを嗅いだ時はいつも以上に山小屋到着がうれしくなりました。

山小屋のすぐ手前にある棚状のテント場。
真上にテン場専用トイレ舎がありました。
(写真なし。多分男女共用)
テント場の目の前には足湯。

山小屋がガヤガヤにぎやかなのが苦手な人は、こちらの方が少し喧騒から離れてゆったりできるかもしれません。

山小屋の入り口付近は屋根つきの休憩場所になっています。
この日は平日にも関わらず混んでいて…
ベンチに座りきれない人々が通路とか階段に座り込んで通行の阻害をしていたり、
人・人・人って感じが
しょっぱなから超うんざりでした。
こんなんだったら空いてて温泉がない方がよかった。
(そうです人ごみ嫌い1号なんです)
土日祝日はもっとすごいんでしょうね…
ひー 絶対無理
下駄箱はありますが、靴は受付時に貸し出された硬質ビニール袋に入れて各自寝所にて保管します。
入り口付近の休憩場所(テラス)兼 乾燥室 兼 自炊場。屋根付なので雨の日は助かると思います。
眼下にある露天風呂が丸見えにならないように目隠しのすだれが立っていて、眺めがないのでここはあまり好きになれませんでした。向かい合って座り合うシステムなんかも電車みたいで窮屈に感じます。広がりがない。

この狭苦しい空間を出て外で自炊したくても、小屋周辺にはテーブルなどなし。斜面に建つ小屋なので登山道以外で休めそうな場所が見つけられませんでした。雪渓がたっぷり残っていたせいもあります。
思い当たる場所といえばテント場の空間です。
テントの人がいっぱいいる所でぽつーんと自炊…どうなんだろう。意外とありか?
休憩場所は建物の長辺に沿って横長に続いていて、奥の方だけ目隠しが外されてたけど、乾燥室を兼ねているため大勢の人の衣類が干され、結局景色が見え難い状態でした。
 ←翌日の早朝の様子
←翌日の早朝の様子上の写真と比べても干された衣類が倍増。
夕ご飯の自炊は結局、この中で済ましました。みんなが小屋で夕食の配膳を受けている隙を狙ってさっきまで酔っ払いが陣取っていた隅っこを確保し、衣類を少しどかして、暮れゆく山の風景を眺めながらまったり静かなひと時。
寝所は1号館~3号館まであるようですが、この日は1号と2号のみ開放されてました。
一段の天井が高い二段棚で一区画が広くなってます。もちろん男女相部屋式です。
1号館は混んでいたため何人収容かちゃんと確認できませんでしたが
空いていた2号館の方は、大きい区画は8人くらいの容量だと思います。(布団の数から)
写真を見比べるとどちらも同じ収容みたいですね。奥行きもそんなになく、1つの建物に9区画(大8・小1)。

上の写真はカーテン付に見えるかもしれませんが、ここは山小屋のスタッフ専用みたいでした。
客用はみんなカーテンなし。(カーテン好きのプカプカはこれがとっても苦痛だった)
それぞれの館には少人数用(2人)の小さい区画も各1つ(多分)ありました。
平面の男女混合の大部屋よりは、壁があるだけ相当マシなんだけど…
やっぱり目隠しがないと、寝場所の前を男性がどかどか通るのは落ち着きません。
いつも女性専用部屋などの配慮をしてもらえる小屋ばかりなので、すっかり贅沢者になっとります

布団の清潔度はまずまずでした。そんなに匂いが気になることもありません。
しかし、枕 (合成ビニール皮で四角く包まれたタイプ) は異常に臭い!!!!
頭皮の脂とかがこってりコーティングされてます。
そっと指先で触れて匂いを確かめただけで うぇっぷとなりました。もちろん使うもんかいっ
鑓温泉小屋の水場 詳細は最後部にまとめて記載
鑓温泉小屋のトイレ(男女共用)ペーパーあり。トイレ前に手洗い用水道(飲用可)・石鹸あり。
やっぱ、男女共用なんですね。これも滅多にない体験です。
日常で男女共同トイレなんて、自宅以外でありませんから、こういう環境は少し戸惑います。
家族以外の男の人と同じ便器を使うのは、正直気持ちいいもんじゃないんです。
さて、では最後にお風呂について。申し訳ありませんが女性用の内風呂以外取材してません。
男性用露天風呂は多くの方が写真を公開してますので、情報はあまるほどあると思います。
ここはひとつプカプカ視点で…
女性用内風呂 脱衣所
狭い脱衣所です。写真はありませんが、浴場の方にトイレ前にあったのと同じ小さな水道があります。
鏡なし。そう、この鑓温泉小屋には鏡がどこにもありませんでした。
内湯は壁に囲まれていますが、半屋根なので空が見えます。
かけ湯は緑の敷物の場所で据え置きの湯桶を使用して湯船の湯を使います。

掛け流しの湯ノ花のにごり湯、最高でーす。ぬるめなのが実にいい。
長湯できるし、あつ湯より疲れを癒してくれる。
露天風呂が女性専用の時刻になるのは夜20時過ぎ… 寝てるっつーの。次の日2時起きだっつーの。
内湯だけで済ませました。露天は一応女性時間外も混浴可なので、入湯してきた女の人に様子を聞いたところ
「 汚 か っ た 」そうです… (いろいろなカスが浮いてて超気持ち悪かったって) やっぱりね…
男の人の入った後のお風呂のお湯ってなんでいつも汚いんですか。ちゃんとかけ湯してんのか?湯の中でアカこすりでもしてんのか?
消灯:21時。 深夜にトイレを使用しなかったので、夜のトイレ舎までの様子は調査不足です。
更衣室:なし。 女性の着替えは女性用内湯の脱衣所を使用していいそうです。
山小屋受付脇の水道から給水。洗面などもここで行います。飲用可能な沢水ですが、
当日は黒い粒粒したゴミ(腐葉土かな?)が少し目立ちました。
お腹の弱いプカプカですが、生水をたらふく飲んでもお腹をこわすことはありませんでした。
トイレ前と内風呂内にも小さい水道台あり、ここの水も飲用可能。
外来・宿泊者共に無料。
【日の出を見るためのマメ情報】
稜線までは相当遠いです。道も多少複雑です。登山道は低木や草木の豊富な道ですが、時々は頸城山塊など東側の山々が見渡せるすばらしい展望が望めるので、薄暗い内に出発して道の途中から日の出を見るのはアリだと思います。
ただ、小さな滝を横切ったり、足場の細い崖(クサリあり)を渡る上に雪渓越えもいくつかあるので、夜歩行に慣れた人や相当の技術経験のある方でないと危険度が増すと思います。
山小屋前からも存分に日の出の空と山並みを眺めることができます。
テント場の辺りとか、未確認ですが よさそう。
小屋前の休憩場所は先述の通り干された衣類が邪魔だし、すだれも立てかけてあるの視界不良ですが、隙間とかすだれの裏とか、思い思いの場所を探せばそれなりにいい感じで空を眺められます。

休憩場所最奥部のベンチに座りながら眺めた日の出の空が左の写真です。
朝ごはんを作って食べながら日の出を満喫できました。
一番開放感があるのはなんてったって露天風呂でしょう。
丸出して朝日。これでもかと。
最高でしょうな~
ちっ うらやましい限りだぜ。 プカプカも男になりたいぜ。
白馬鑓ヶ岳に向かう登山道より見下ろす白馬鑓温泉小屋と雪渓
この時の従業員は音楽好きな若いメンズが多かったようで、
日の出前の早朝や夕方などは、宿泊棟の隣に続くキッチンから常に音楽が聞こえてきたり
(ジャンルは何だったかな…和製ヒップホップだったかな?男子が好きそうなやつ)
消灯間際まで、楽しそうに会話しながら働く様子が伝わってきました。
ここで働いた夏はきっと彼らにとって楽しい思い出になりそうです。(うるさかったけど)
白馬鑓温泉小屋は営業期間が7月中旬から9月下旬と ものすごく短いそうですが、
その積雪量の深さから冬季は解体して、また夏になったら再建するそうです。
その行程にあたるみなさまのご尽力を思うととってもありがたくなります。
(その割には不満点は正直に挙げるプカプカ。だからって感謝してないわけじゃないんです)
白馬三山レポはこちらから→
![]()
久しぶりにコメントの受付を再開しています。
申し訳ありませんが、今はコメントへのお返事をしていませんです…
↓詳しいことはこちらに書きました(クリックすると開きます)↓
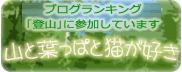
←お気に召したらクリックしながら一言
「あ ぽちっとな」




















白馬岳方面からの縦走の最終日でしたが、とっても空いてて最高でした。
テントから見た朝焼けと、小屋のチョイ下のクルマユリの群生は、忘れられない光景でした!