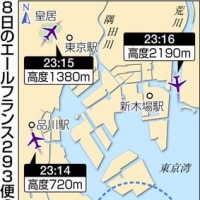<小型機墜落 「事故の瞬間初めて見た」八尾空港近くの住民>
毎日新聞2016年3月26日 22時09分(最終更新 3月26日 22時17分)




ふらついた小型機が滑走路に墜落し、黒煙が立ち上った。大阪府八尾市の八尾空港で26日夕に起きた墜落事故。大破した小型機がある滑走路には消防車や救急車、ドクターヘリが駆けつけ、サイレンの音が鳴り響く現場は騒然となった。救急隊員が機内に向かって「大丈夫か」と大声で叫び、空港周辺の住民らが不安そうに見守っていた。
事故を目撃した近くの主婦(71)によると、小型機は失速した状態でほぼ真下に墜落し、特に操縦席が大破したという。その20〜30秒後に炎と黒煙が上がった。「空港の近くに45年間住んでいるが、墜落の瞬間を見たのは初めて。スローモーションのように見えた。今でも足が震えている」と興奮した様子。「最近、飛行機が住宅街に墜落する事故も相次いでいるので本当に怖い。もし民家に落ちていたら大惨事になっていただろう」と不安も漏らした。
近所の男性(70)は事故を起こしたとみられる小型機について、「いつも見るのと違う飛行ルートを飛んでいるのでおかしいと思った。その3〜4分後、空港の方から地響きのような鈍い音が聞こえた」と話した。事故の直前には小型機から「キュ、キュ」という異様な音が聞こえたという。
空港周辺には衝撃音が響き渡った。近くで建設業を営む桜井正人さん(46)は、「突然『ボーン』と大きな音が聞こえた。滑走路を見ると、飛行機の胴体が真ん中で折れ、火が噴き出していた。燃料も漏れ、小型機の周囲が一気に火に包まれた」と事故直後の様子を語った。
現場に向かった消防隊員によると、機内は激しく燃えており、亡くなった男性らは座席に座った状態だった。事故直後から空港職員数人が小型機に駆け寄り、消防車や救急車、パトカーが次々に駆けつけた。現場に居合わせた新聞販売店員の男性は「救急隊員が『大丈夫か』と呼びかけていた。数十メートル離れていても聞こえるほどの大声だった」と驚いた様子だった。
操縦の妨げ、考えにくい
事故が起きた午後4時前後の八尾空港は、弱い西の風が吹いていたが、風向も一定しており、操縦の妨げになったとは考えにくい。視界も10キロ以上あり、有視界飛行の小型機にとって特に操縦に支障のある気象条件ではなかった。
事故機の「M20C」は米国の小型機メーカー、ムーニー社製の単発機。原型機は1950年代に開発された。引き込み式の車輪を装備し、セスナ社など競合メーカーの同クラスの機種を意識し、スピードを重視した設計が特徴だ。
国土交通省などによると、事故機は墜落の直前、管制塔に着陸のやり直し(ゴー・アラウンド)を要求していた。その後、正常に上昇できず、A滑走路の中央付近に墜落した。
一般的に、パイロットが着陸やり直しを決断するのは、降下率が大きくなりすぎた▽強い横風などで、機体の姿勢が乱れた▽滑走路上に障害物を発見した−−などが原因。速やかに機首を上げ、エンジンの出力をフルパワーにし、失速を避けるため規定の上昇速度を維持するという操作手順が定められている。特に速度の維持は重要なポイントで、操縦訓練でも速度計のチェックを怠らないよう厳しく指導される。今回の事故では、着陸やり直しの操作の前後に何があったかが、調査のポイントになる。
日本航空の元機長で航空評論家の小林宏之さんは、操縦者の操作ミスか、エンジンなど機材の故障か、どちらかの可能性が高いとみる。「ミスだとすると、機首を上げすぎ、十分な速度が得られず失速したことなどが考えられる。小型機の事故はここ数年目立ち、経験や安全意識の不足といったヒューマンエラーが原因の場合が多い。国交省も問題視して対策に力を入れていたところだったので、残念だ」と話す。【山田泰正、安高晋】
国内の主な小型機などの事故◇
1998年9月 大阪府の八尾空港から離陸した小型機が、高槻市の山中に墜落。搭乗の5人が死亡
2001年5月 三重県桑名市で小型機とヘリが空中衝突。墜落して民家2棟が全焼。搭乗の6人が死亡
03年9月 長崎県の対馬空港で小型機が着陸に失敗。滑走路手前の斜面に突っ込み、搭乗の3人が死亡
04年1月 甲府市の病院近くの駐車場に小型機が墜落。搭乗の3人が死亡
07年10月 八尾空港を離陸したヘリが、約10分後に堺市の南海高野線の線路上に墜落。搭乗の2人が死亡
08年8月 八尾空港に着陸しようとした小型機が、近くの国道に不時着。搭乗の2人が軽傷。機体が周辺建物の看板や車に接触
15年7月 東京都の調布飛行場を離陸直後の5人乗り小型機が、民家に墜落。民家の女性を含む3人が死亡、5人が負傷