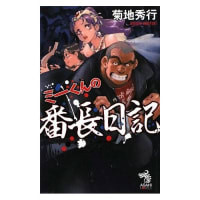ドアチャイムが鳴った。
家を購入して以来、最初にそれを鳴らしたのは他ならぬ彼の父だった。
「久しぶりだな、俊」
「父さん。連絡をくれれば駅まで迎えに行ったのに」
家主――石原俊はにっこりと破顔し、父――石原誠一郎を招き入れた。
「散らかってるけど気にしないで」
「いい。いきなり押し掛けたこっちが悪い」
言いつつ誠一郎は舌を巻いた。散らかってるどころの話ではない。何もないのである。男の一人暮らしと聞いていたが、本当にここで暮らしているのだろうか。
通された客間はちゃぶ台以外何もない。埃ひとつ落ちていない畳がかえって誠一郎の気にかかった。
「父さん、昼食はまだでしょう?丁度作っているところだったんで、少し待ってて下さい」
そう言うと、俊は部屋を出て行った。
誠一郎はゆっくりと部屋を見回した。掃除の行き届いた清潔感ある部屋である。鬼姑が見ても満点を出すだろう。
料理人になると言って俊が家を飛び出したのが十二年前。なかば勘当同然だったが、去年の夏に自分の店を持ったという手紙が届いた。ほとぼりも冷めていたし、バツが悪いなりにようやく足を運ぶこととなったのである。
感動の再会にならないだろうことは予想していたが、会わなかった年月を感じさせない俊の態度に誠一郎は違和感を拭えないでいた。
ただ座っているのも落ち着かないので部屋をウロウロする。
一本の糸が落ちていた。そんなことに息子の人間味を感じ拾い上げると、それは糸ではなく髪の毛であった。俊の髪は料理人なだけに短く刈られていた。これは十五センチはある。とすると――。
誠一郎の顔がほころぶ。
あいつもいい年だ。ひょっとすると孫の顔が拝めるかもしれん。
想像をかきたてながら隅にあるゴミ箱に捨てた。
「お待たせしました。どうしたんです?何か嬉しいことでも?」
俊が昼食を持って入ってきた。
「あ、いや、なんでもない」
慌てて正座をする父を見て、俊はクスリと笑った。
並べられた料理は一般家庭にあるようなものであったが、そこかしこに食べる人間への気遣いが感じられた。
「いただきます」
「いただきます」
息子と向かい合って食事を取れることがこんなに嬉しいとは。
自然と箸が進む。
見た目こそ質素だが味は段違いである。
自分の店を持つだけあって、その腕は確かなようであった。
「料理人、しっかりやってるようだな」
「それはまあ。修行しましたから」
「店のほうはどうなんだ。うまくいってるのか?」
「まあ、ぼちぼちってとこですね」
「その喋り方はなんとかならんか。堅苦しい」
「すみません。癖になってまして」
なんとか会話を弾ませようとしてみたが、どうしてもぶっきらぼうになってしまう。誠一郎は素直になれない自分が歯がゆかった。
沈黙が流れる。聞こえるのは箸が食器に触れる音くらいだ。
意を決して言ってみた。
「ところで、お前彼女とかいないのか?」
それまで落ち着き払っていた俊が、思いがけない質問にむせた。
この父から彼女などという単語が出てきたことが予想外だったのである。
「げほっ、げほっ。いきなりなに?」
「お前もいい年だ。気になる女の一人や二人いるんだろう?」
「そりゃボクだって男ですから」
「いつ一緒になるんだ」
「やだなあ、気が早いですよ」
言いつつも俊の顔は笑みを隠せずにいた。
これはひょっとするとひょっとするかもしれない。
「まあ、気が向いたら帰ってこい。その人も連れてな。母さんも会いたがってる」
「母さん……」
俊の箸が止まった。
家を出る直前まで母は俊の味方だった。
俊に料理を教えたのも母だったし、家を出るときこっそり金を工面したのも母だった。
「母さん、どうしてる?」
「元気にやってる。最近はガーデニングに凝りだした。食い物だけだがな」
「食べ物だけ?」
「ああ。お前に調理してもらうと言っていた。母さんも驚いてたぞ。連絡ひとつ寄越さなかったバカ息子が、自分の家と店を持つようになったなんてな。これで彼女もいると知ったら卒倒しかねん」
「そうですね」
誠一郎の口がへの字に曲がる。そのときの様子が見えているのだろう。
「あ、そうだ。ちょっと食べて頂きたいものがあるんですが」
「なんだ」
「うなぎですよ。店の新メニューを考えてましてね。モニターになってもらえればと」
「ほう、うなぎか。母さんの好物じゃないか」
「じゃあ、これから作ってきます。少し時間はかかりますが」
「ああ、ゆっくり待たせてもらおう」
俊は空いた皿を手に台所へ戻っていった。
まだおかずは何品か残っている。
それぞれ完成度が高くよい出来だ。
その才能を潰そうとしていたのかと思うと、誠一郎はやるせない気持ちになった。
「父親失格だな」
大きく息を吐く。
白米と一緒に食べるおかずは、やはり美味かった。
家を購入して以来、最初にそれを鳴らしたのは他ならぬ彼の父だった。
「久しぶりだな、俊」
「父さん。連絡をくれれば駅まで迎えに行ったのに」
家主――石原俊はにっこりと破顔し、父――石原誠一郎を招き入れた。
「散らかってるけど気にしないで」
「いい。いきなり押し掛けたこっちが悪い」
言いつつ誠一郎は舌を巻いた。散らかってるどころの話ではない。何もないのである。男の一人暮らしと聞いていたが、本当にここで暮らしているのだろうか。
通された客間はちゃぶ台以外何もない。埃ひとつ落ちていない畳がかえって誠一郎の気にかかった。
「父さん、昼食はまだでしょう?丁度作っているところだったんで、少し待ってて下さい」
そう言うと、俊は部屋を出て行った。
誠一郎はゆっくりと部屋を見回した。掃除の行き届いた清潔感ある部屋である。鬼姑が見ても満点を出すだろう。
料理人になると言って俊が家を飛び出したのが十二年前。なかば勘当同然だったが、去年の夏に自分の店を持ったという手紙が届いた。ほとぼりも冷めていたし、バツが悪いなりにようやく足を運ぶこととなったのである。
感動の再会にならないだろうことは予想していたが、会わなかった年月を感じさせない俊の態度に誠一郎は違和感を拭えないでいた。
ただ座っているのも落ち着かないので部屋をウロウロする。
一本の糸が落ちていた。そんなことに息子の人間味を感じ拾い上げると、それは糸ではなく髪の毛であった。俊の髪は料理人なだけに短く刈られていた。これは十五センチはある。とすると――。
誠一郎の顔がほころぶ。
あいつもいい年だ。ひょっとすると孫の顔が拝めるかもしれん。
想像をかきたてながら隅にあるゴミ箱に捨てた。
「お待たせしました。どうしたんです?何か嬉しいことでも?」
俊が昼食を持って入ってきた。
「あ、いや、なんでもない」
慌てて正座をする父を見て、俊はクスリと笑った。
並べられた料理は一般家庭にあるようなものであったが、そこかしこに食べる人間への気遣いが感じられた。
「いただきます」
「いただきます」
息子と向かい合って食事を取れることがこんなに嬉しいとは。
自然と箸が進む。
見た目こそ質素だが味は段違いである。
自分の店を持つだけあって、その腕は確かなようであった。
「料理人、しっかりやってるようだな」
「それはまあ。修行しましたから」
「店のほうはどうなんだ。うまくいってるのか?」
「まあ、ぼちぼちってとこですね」
「その喋り方はなんとかならんか。堅苦しい」
「すみません。癖になってまして」
なんとか会話を弾ませようとしてみたが、どうしてもぶっきらぼうになってしまう。誠一郎は素直になれない自分が歯がゆかった。
沈黙が流れる。聞こえるのは箸が食器に触れる音くらいだ。
意を決して言ってみた。
「ところで、お前彼女とかいないのか?」
それまで落ち着き払っていた俊が、思いがけない質問にむせた。
この父から彼女などという単語が出てきたことが予想外だったのである。
「げほっ、げほっ。いきなりなに?」
「お前もいい年だ。気になる女の一人や二人いるんだろう?」
「そりゃボクだって男ですから」
「いつ一緒になるんだ」
「やだなあ、気が早いですよ」
言いつつも俊の顔は笑みを隠せずにいた。
これはひょっとするとひょっとするかもしれない。
「まあ、気が向いたら帰ってこい。その人も連れてな。母さんも会いたがってる」
「母さん……」
俊の箸が止まった。
家を出る直前まで母は俊の味方だった。
俊に料理を教えたのも母だったし、家を出るときこっそり金を工面したのも母だった。
「母さん、どうしてる?」
「元気にやってる。最近はガーデニングに凝りだした。食い物だけだがな」
「食べ物だけ?」
「ああ。お前に調理してもらうと言っていた。母さんも驚いてたぞ。連絡ひとつ寄越さなかったバカ息子が、自分の家と店を持つようになったなんてな。これで彼女もいると知ったら卒倒しかねん」
「そうですね」
誠一郎の口がへの字に曲がる。そのときの様子が見えているのだろう。
「あ、そうだ。ちょっと食べて頂きたいものがあるんですが」
「なんだ」
「うなぎですよ。店の新メニューを考えてましてね。モニターになってもらえればと」
「ほう、うなぎか。母さんの好物じゃないか」
「じゃあ、これから作ってきます。少し時間はかかりますが」
「ああ、ゆっくり待たせてもらおう」
俊は空いた皿を手に台所へ戻っていった。
まだおかずは何品か残っている。
それぞれ完成度が高くよい出来だ。
その才能を潰そうとしていたのかと思うと、誠一郎はやるせない気持ちになった。
「父親失格だな」
大きく息を吐く。
白米と一緒に食べるおかずは、やはり美味かった。