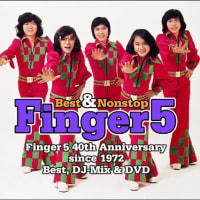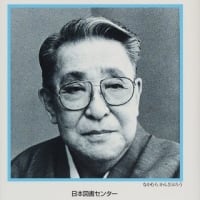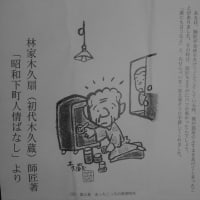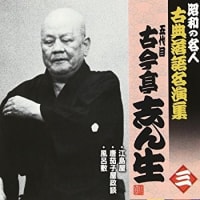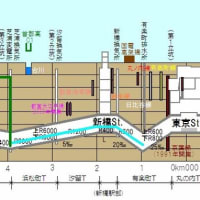牛丼と正午の「ドン」 
冒頭の写真は・・正午のドン
牛丼好きには、吉野家のファンが多いらしい。理由は知らないが・・。

牛丼ファンは、当たり前のことだが、牛丼がとても好きらしい。それも「吉野家」の牛丼でないと駄目だという吉野家ファンがいる。どれを食べても似たり寄ったりだと思うのだが・・・確かに通常の理解を超えており、常軌を逸しているとも言える偏執ブリだ。
どこの牛丼が旨いかマズイかは、取り敢えず擱くとして…
牛丼の「正式な喰い方」を“牛丼オタク”の方に伺った。ご存知だろうか? 牛丼の一番旨い喰い方だそうだ。それによれば・・・・・
「生卵も注文し、牛丼が目の前に出てきたら、丼の中央頂きに穴を掘って生卵をトッピングする。紅ショウガを具が見えなくなるくらい牛丼一杯にかけ、さらに唐辛子を思いっきりたくさんぶっかける」 のだそうだ。
これが“牛丼を喰らう正式な作法”らしい。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ところで…
牛丼ではないが、昔は【正午の「ドン」】というのがあった。漱石の小説にもよく出てくる。
1871年(明治4)の9月9日,皇居の旧本丸で正午の合図として空砲を1発打つ午砲が開始された。
陸軍省の管轄で,大砲を打つのは近衛砲兵。その音から「ドン」と呼ばれ,東京市民(当時)に親しまれたそうだ。その後東京以外にも広がり,仙台や大阪,名古屋,熊本などの師団司令部でも実施されたそうだ。
狛江市役所ホームページに「昔の時計」
 という面白い記事が出ている。 ダイジェスト(抄)にして、ご紹介してみる。
という面白い記事が出ている。 ダイジェスト(抄)にして、ご紹介してみる。
昔の時計
「おいらの子どもの時分には、時計のないうちが普通だった」と、猪方の小川芳三さん(明治二十四年生)は話す。ニワトリは「時をふく」ので時間を知る目安になっていた。昔は、たいていの家でニワトリを飼っていて、トリの巣といって、土間の手の届く高さのところに、止まり木だとか籠が吊してあり、多くて十羽くらいのニワトリを飼っていたものだった。「一番トリが鳴いたから、もう少しだけ寝るべえや」などと言った。
「ハチが鳴く」のを食事にする目安にもしたという話を、和泉の白井秀さん(明治二十六年生)から聞いた。ブンブン、ハチが鳴くと、朝のご飯だよとか、昼になったからハチが鳴いたよなどといわれたものだった。
遠くから聞こえてくる寺の鐘が朝夕の時を告げ、“正午のドン”を合図に午前中の仕事を切り上げたりした。
「ドンが鳴ったから、お昼だい」とか、深大寺の鐘は十一時半に鳴るので「早いけど昼にすべえ」などと言ったものである。皇居前で鳴らす空砲のドンの係だったという、駒井出身の近衛の兵隊もいた。(以上)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
やや古めかしい話でしたが、いかがでしたか?