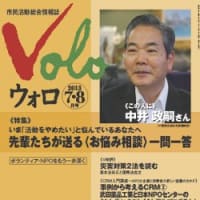観る人と被写体をつなぐ橋渡し役。
映画の創り手としての私の使命です。
記録映画作家
東 志津さん
32歳の記録映画作家の初監督作は、80余年を生き抜いた女性の物語だった。
60年以上も前の日本と「満州」の記憶、そして自分は知るよしもない大戦の記憶…。テレビや本の中でしか見聞きすることのなかったそれらを、みずから継いでいこうとカメラを回し続けた東志津さん。彼女を突き動かしたもの。それは栗原貞子さんという、一人の中国残留婦人との出会いである。
■『花の夢 ある中国残留婦人』、何ともいえない柔らかな映像に引き込まれ、気がついたら1時間37分が終わっていました。撮影も全編ご自分で手がけられたんですね。
あの映像を出せたのは奇跡です。私自身も信じられないくらいで。「孫」の世代にもあたる私ですが、同じ女性として栗原さんの優しさと強さを秘めた生き方に共感し、かつ敬意を込めて撮り続けていました。
3年間通って撮った60分テープが7、80本。これをどれだけ使うかということよりも、カメラを回すことで、栗原さんの心の中により近づけるのではないかと思ったんですね。撮影は栗原さんを疲れさせないように、かなり断続的に行いました。お住まいの都営住宅に幾度となく寄せていただいて。観客の方などから、相当長い時間家にお邪魔して撮影したんですね、と言われることもあるんですが、実際は30分から1時間くらいです。長くても2時間を超えないようにしました。回を重ねるごとに撮影のためにという意識がだんだんなくなり、遊びに行ったらカメラがある。お話のついでに撮影もしましょうか、みたいになっていきました。
■映画の冒頭、洗濯機の回るシーンが延々と長巻きで映し出されますね。次いで台所にあるペットボトルのジュース、風を送る扇風機など、ともすればカットされるようなシーンをひとつひとつ残されているのが印象的でした。
お住まいの部屋にあるいろいろな生活の小道具は、栗原さんの「今」とともに存在するんですね。「今、栗原さんが生きている場所」というのを、私自身がていねいに見つめ直してみたかったんだと思います。でも撮影をしているあいだは、他に撮るものがないしとりあえず撮っとこうかな、みたいな感じでした。「これを撮らなければ」とかは全然考えてなかったんですよ。それが最終的に編集をする段階になって、それらの持つ重要な意味に気づかされました。
それぞれのカットが映し出された瞬間だけではなく、エンドロール(映画の終幕に流されるスタッフなどの一覧)になったときに、今まで映し出されていたシーンが全部つながって、わあっ、こんなことなんだ、と感じてくれるような作品になればいいな、と、ずっと考えていたんです。だから部屋の中のものを大事に撮っておいたことはよかったですね、今になって思えば。
私は日本へ帰ってからの栗原さんしか知りません。だから中国の映像などは一切ないし、あえて使わないようにしたんです。たとえ今、中国の映像を撮ったとしても、それは栗原さんが住んでいたころの中国ではないんですよね。「ここに住んでました」とナレーション入れて、栗原さんがその前で語ったとしても、それはあくまで「過去」になっちゃうんです。
『野や山にそのまんま、死んで棄てられた子ども。川で流された子ども。何も食べるものもなくて飢え死にした子。あの、野原にこう、死んでるのか、生きてるのか、寝てるのかっていうような。寝てるんじゃない。もう、死んでるんだけど、かわいそうでね…』
こんな壮絶な話も、現在のお住まいで語るなら永遠に「過去」にならない。むしろ観る人の想像の世界では「現実」っていうか、終わってない物語になっていくんじゃないかと。「過去を振り返ればこういうことがありました」という映画にはしたくなかったんです。
■非常に重たいテーマを、あの部屋にあるいろいろなものが中和してくれているような…。
栗原さんの言葉が生きるためには、どういう舞台を揃えれば一番いいのかを考えたんです。さまざまな小道具のシーンをつなぎ合わせながら、「今」の生活に流れる淡々とした「日常」を映せば、それが活かされてくるのではないかと。あんまり深く考えてなかったんですけどね。いわば凡人のなげやりといいますか(笑)。
洗濯物が風になびく窓。外からは子どもたちの声が聞こえる。そんな空間のなかで語られる言語を絶する体験。でもそこは私たちが普段生活している場とさほど変わらない。この距離の近さが、観る人一人ひとりと非常につながりやすいものになってたと思うんです。自分の家の隣に住んでる人が、もしかしたらそんな体験をしてきた人かも知れない、と自分の身に引き寄せて考えてみる、想像してみる。それは決して難しいことではなく、私たちの日常とも密接に結びついているんだということを伝えたかったんですね。
■栗原さんとはどうやってお知り合いになられたのですか。
大学卒業後、フリーのディレクターとしてたまたま関わったケーブルテレビの番組制作がきっかけです。中国残留孤児や残留婦人、あるいはその二世・三世が多く住んでおられる地域での取材だったので、あちこちで中国語を耳にしました。当初、「残留婦人」の存在はおろか、その言葉自体もまったく知らなかった私は、日本の名字なのに、あの人たちはなぜ中国語を話しているのだろうかと不思議に思っていました。その後いろんな歴史的背景を知るにつれ、残留孤児のお子さんやお孫さん、残留孤児ご本人、そして残留婦人へと、取材の対象が変わっていきました。
そんな時期、ある支援団体の方から新年会にお誘いいただき、会場で栗原さんに出会ったんです。ご本人から初めて中国での体験談を聞いたあと、「こんなことがあっていいのか」と憤り、今まで「知らなかった」自分に腹立たしさも覚えました。小学校や中学校のとき、担任の先生が年配だったこともあり、戦争体験はよく聞かされ、私自身もわりと興味を持ってたほうでした。でも広島、長崎はもとより、東京大空襲の話にしても、主に日本がどれだけ被害を受けたかに終始するんです。何でそうなったのかまでの説明はないし、「満州」のことなんか教科書では2、3行で終わっちゃうんですね。まあそれを語ろうとすると「日本が何をしたか」というふうになってくるので、大人もあまり話したがらないんですが。
だから、この映画をつくるきっかけは「もっと聞かせてほしい」「もっと知りたい」という、私自身の思いからスタートしています。
■映画の中で語られるエピソードは想像を絶する悲惨な話ばかりです。栗原さんご自身、語るのが辛いと思われてはいませんでしたか。
始めは話を聞く私の方にためらいがありました。戦争を知らない時代に生まれた、半世紀近く年代の違う私と、戦禍をくぐり抜け、何十年も苦労を重ねながら異郷の地で6人のお子さんを育て上げてきた栗原さんの境遇はかなり違います。そんな耐え難いほどの辛い記憶を、ご本人の人生の奥深いところまで入り込んで、私なんかが聞いていいのだろうかと。でも後でビデオテープを観ると確かに辛そうな場面もあるんですが、「知りたい」私に対して、一生懸命答えてくれる栗原さんがいる。ということは、この話は外に向かって開かれていくべきものなのでは、と思えるようになりました。私自身の見方が変わってきたんです。
どんな話をするときも栗原さんの語り口は優しく柔和で、決して誰かを告発したり恨んだりという感じがないんですね。そういうお人柄にひかれ、次々とインタビューを続けていけるようになりました。
映画が完成したとき先輩から言われて嬉しかった言葉があります。「東は映画を創っていたというより、(映画制作を通して)東自身が栗原さんに包まれていたんだね」。
■「日常の目線」で感じた問題意識がふくらんで、大きな実が結べたということですね。後に続く若い世代がドキュメントを撮るときのアドバイスなどがあればお聞かせください。
そうですね、逆に私がアドバイスしてほしいくらいなんですが。まあ、独りよがりにならないということでしょうか。編集、つまり仕上げの段階になると、人に観てもらう、ということが大前提なので、音楽、ナレーションにしても、自分が観客であれば次のカットに何を観たいか、ということを始終考えています。
常に頭をよぎるのは、作品のなかから「いかに自分を消すか」ということですね。完成したら、もう私という存在は完全に消えてなくなってる、そんな映画を創りたいなと思います。もう少しあなたの主張が出てもいいんじゃない、って言われることもあります。でも映画を創ること自体がもう主張なので、私の場合、どうやってもそういうふうに主張を出した作品にはならないと思うんです。それが私の個性なんですから。あとは観客の方の見方、感じ方にすべてを委ねていけたらと思いますね。
私のような仕事を一般的には「監督」と呼びますが、自分としてはあまり意識してないんですよ。私は観る人と被写体をつなぐ橋渡しのような存在にすぎないし、それが映画の創り手としての私の使命かなと思っています。
インタビュー・執筆
編集委員 村岡 正司
●プロフィール●1975年大阪生まれ。生後まもなく東京へ移る。大学卒業後、映像の世界へ。PR映画、CMなどの制作をへて、03年よりドキュメンタリー映画の制作を始める。04年、『花の夢』の前身となる『あなたの話を聞かせて下さい~中国残留婦人栗原貞子さんの日々~』(30分作品)で、「2004年地方の時代映像祭(市民自治体部門)」奨励賞受賞。
■中国残留婦人とは
1945(昭和20)年8月、日本が敗戦を迎えると、在満州開拓民たちは難民となった。ソ連(当時)の侵攻や中国人らの報復を受けながら、決死の思いで引き揚げた人もいたが、その3分の1にあたる約8万人が、避難途中の襲撃や、飢え・寒さのため命を落とした。難民の大半は女性と子どもで、それが犠牲者を増やした原因のひとつになった。日本の戦況悪化に伴い、男性は根こそぎ召集を受けていたのだ。
中国に取り残された日本女性たちが生き延びる手段のひとつは、現地の中国人との結婚だった。子どもを生かしたい一心で、中国人のもとに身を寄せた母親も少なくなかった。
近い未来、状況が落ち着けば帰国できると信じていた彼女たちであったが、1958(昭和33)年、長崎で起こった中国国旗侮辱事件を契機に、引き揚げ船事業が打ち切られるなど「日中国交全面断絶」といわれる事態になった。これら3千人以上にのぼる「中国残留婦人」は、以後20年以上にわたり異郷の地での生活を強いられたが、その間日本政府からの連絡は一切なかった。現在も約200人が中国で暮らす。
厚生労働省は、「中国残留孤児」を終戦時12歳以下、「中国残留婦人」を13歳以上と区別し、補償にも一線を画している。13歳以上であれば正常な判断ができる大人だとみなし、中国へ残ったのもみずからの意思、つまり“自己責任”だというのが、現在までの政府見解である。
映画の創り手としての私の使命です。
記録映画作家
東 志津さん
32歳の記録映画作家の初監督作は、80余年を生き抜いた女性の物語だった。
60年以上も前の日本と「満州」の記憶、そして自分は知るよしもない大戦の記憶…。テレビや本の中でしか見聞きすることのなかったそれらを、みずから継いでいこうとカメラを回し続けた東志津さん。彼女を突き動かしたもの。それは栗原貞子さんという、一人の中国残留婦人との出会いである。
■『花の夢 ある中国残留婦人』、何ともいえない柔らかな映像に引き込まれ、気がついたら1時間37分が終わっていました。撮影も全編ご自分で手がけられたんですね。
あの映像を出せたのは奇跡です。私自身も信じられないくらいで。「孫」の世代にもあたる私ですが、同じ女性として栗原さんの優しさと強さを秘めた生き方に共感し、かつ敬意を込めて撮り続けていました。
3年間通って撮った60分テープが7、80本。これをどれだけ使うかということよりも、カメラを回すことで、栗原さんの心の中により近づけるのではないかと思ったんですね。撮影は栗原さんを疲れさせないように、かなり断続的に行いました。お住まいの都営住宅に幾度となく寄せていただいて。観客の方などから、相当長い時間家にお邪魔して撮影したんですね、と言われることもあるんですが、実際は30分から1時間くらいです。長くても2時間を超えないようにしました。回を重ねるごとに撮影のためにという意識がだんだんなくなり、遊びに行ったらカメラがある。お話のついでに撮影もしましょうか、みたいになっていきました。
■映画の冒頭、洗濯機の回るシーンが延々と長巻きで映し出されますね。次いで台所にあるペットボトルのジュース、風を送る扇風機など、ともすればカットされるようなシーンをひとつひとつ残されているのが印象的でした。
お住まいの部屋にあるいろいろな生活の小道具は、栗原さんの「今」とともに存在するんですね。「今、栗原さんが生きている場所」というのを、私自身がていねいに見つめ直してみたかったんだと思います。でも撮影をしているあいだは、他に撮るものがないしとりあえず撮っとこうかな、みたいな感じでした。「これを撮らなければ」とかは全然考えてなかったんですよ。それが最終的に編集をする段階になって、それらの持つ重要な意味に気づかされました。
それぞれのカットが映し出された瞬間だけではなく、エンドロール(映画の終幕に流されるスタッフなどの一覧)になったときに、今まで映し出されていたシーンが全部つながって、わあっ、こんなことなんだ、と感じてくれるような作品になればいいな、と、ずっと考えていたんです。だから部屋の中のものを大事に撮っておいたことはよかったですね、今になって思えば。
私は日本へ帰ってからの栗原さんしか知りません。だから中国の映像などは一切ないし、あえて使わないようにしたんです。たとえ今、中国の映像を撮ったとしても、それは栗原さんが住んでいたころの中国ではないんですよね。「ここに住んでました」とナレーション入れて、栗原さんがその前で語ったとしても、それはあくまで「過去」になっちゃうんです。
『野や山にそのまんま、死んで棄てられた子ども。川で流された子ども。何も食べるものもなくて飢え死にした子。あの、野原にこう、死んでるのか、生きてるのか、寝てるのかっていうような。寝てるんじゃない。もう、死んでるんだけど、かわいそうでね…』
こんな壮絶な話も、現在のお住まいで語るなら永遠に「過去」にならない。むしろ観る人の想像の世界では「現実」っていうか、終わってない物語になっていくんじゃないかと。「過去を振り返ればこういうことがありました」という映画にはしたくなかったんです。
■非常に重たいテーマを、あの部屋にあるいろいろなものが中和してくれているような…。
栗原さんの言葉が生きるためには、どういう舞台を揃えれば一番いいのかを考えたんです。さまざまな小道具のシーンをつなぎ合わせながら、「今」の生活に流れる淡々とした「日常」を映せば、それが活かされてくるのではないかと。あんまり深く考えてなかったんですけどね。いわば凡人のなげやりといいますか(笑)。
洗濯物が風になびく窓。外からは子どもたちの声が聞こえる。そんな空間のなかで語られる言語を絶する体験。でもそこは私たちが普段生活している場とさほど変わらない。この距離の近さが、観る人一人ひとりと非常につながりやすいものになってたと思うんです。自分の家の隣に住んでる人が、もしかしたらそんな体験をしてきた人かも知れない、と自分の身に引き寄せて考えてみる、想像してみる。それは決して難しいことではなく、私たちの日常とも密接に結びついているんだということを伝えたかったんですね。
■栗原さんとはどうやってお知り合いになられたのですか。
大学卒業後、フリーのディレクターとしてたまたま関わったケーブルテレビの番組制作がきっかけです。中国残留孤児や残留婦人、あるいはその二世・三世が多く住んでおられる地域での取材だったので、あちこちで中国語を耳にしました。当初、「残留婦人」の存在はおろか、その言葉自体もまったく知らなかった私は、日本の名字なのに、あの人たちはなぜ中国語を話しているのだろうかと不思議に思っていました。その後いろんな歴史的背景を知るにつれ、残留孤児のお子さんやお孫さん、残留孤児ご本人、そして残留婦人へと、取材の対象が変わっていきました。
そんな時期、ある支援団体の方から新年会にお誘いいただき、会場で栗原さんに出会ったんです。ご本人から初めて中国での体験談を聞いたあと、「こんなことがあっていいのか」と憤り、今まで「知らなかった」自分に腹立たしさも覚えました。小学校や中学校のとき、担任の先生が年配だったこともあり、戦争体験はよく聞かされ、私自身もわりと興味を持ってたほうでした。でも広島、長崎はもとより、東京大空襲の話にしても、主に日本がどれだけ被害を受けたかに終始するんです。何でそうなったのかまでの説明はないし、「満州」のことなんか教科書では2、3行で終わっちゃうんですね。まあそれを語ろうとすると「日本が何をしたか」というふうになってくるので、大人もあまり話したがらないんですが。
だから、この映画をつくるきっかけは「もっと聞かせてほしい」「もっと知りたい」という、私自身の思いからスタートしています。
■映画の中で語られるエピソードは想像を絶する悲惨な話ばかりです。栗原さんご自身、語るのが辛いと思われてはいませんでしたか。
始めは話を聞く私の方にためらいがありました。戦争を知らない時代に生まれた、半世紀近く年代の違う私と、戦禍をくぐり抜け、何十年も苦労を重ねながら異郷の地で6人のお子さんを育て上げてきた栗原さんの境遇はかなり違います。そんな耐え難いほどの辛い記憶を、ご本人の人生の奥深いところまで入り込んで、私なんかが聞いていいのだろうかと。でも後でビデオテープを観ると確かに辛そうな場面もあるんですが、「知りたい」私に対して、一生懸命答えてくれる栗原さんがいる。ということは、この話は外に向かって開かれていくべきものなのでは、と思えるようになりました。私自身の見方が変わってきたんです。
どんな話をするときも栗原さんの語り口は優しく柔和で、決して誰かを告発したり恨んだりという感じがないんですね。そういうお人柄にひかれ、次々とインタビューを続けていけるようになりました。
映画が完成したとき先輩から言われて嬉しかった言葉があります。「東は映画を創っていたというより、(映画制作を通して)東自身が栗原さんに包まれていたんだね」。
■「日常の目線」で感じた問題意識がふくらんで、大きな実が結べたということですね。後に続く若い世代がドキュメントを撮るときのアドバイスなどがあればお聞かせください。
そうですね、逆に私がアドバイスしてほしいくらいなんですが。まあ、独りよがりにならないということでしょうか。編集、つまり仕上げの段階になると、人に観てもらう、ということが大前提なので、音楽、ナレーションにしても、自分が観客であれば次のカットに何を観たいか、ということを始終考えています。
常に頭をよぎるのは、作品のなかから「いかに自分を消すか」ということですね。完成したら、もう私という存在は完全に消えてなくなってる、そんな映画を創りたいなと思います。もう少しあなたの主張が出てもいいんじゃない、って言われることもあります。でも映画を創ること自体がもう主張なので、私の場合、どうやってもそういうふうに主張を出した作品にはならないと思うんです。それが私の個性なんですから。あとは観客の方の見方、感じ方にすべてを委ねていけたらと思いますね。
私のような仕事を一般的には「監督」と呼びますが、自分としてはあまり意識してないんですよ。私は観る人と被写体をつなぐ橋渡しのような存在にすぎないし、それが映画の創り手としての私の使命かなと思っています。
インタビュー・執筆
編集委員 村岡 正司
●プロフィール●1975年大阪生まれ。生後まもなく東京へ移る。大学卒業後、映像の世界へ。PR映画、CMなどの制作をへて、03年よりドキュメンタリー映画の制作を始める。04年、『花の夢』の前身となる『あなたの話を聞かせて下さい~中国残留婦人栗原貞子さんの日々~』(30分作品)で、「2004年地方の時代映像祭(市民自治体部門)」奨励賞受賞。
■中国残留婦人とは
1945(昭和20)年8月、日本が敗戦を迎えると、在満州開拓民たちは難民となった。ソ連(当時)の侵攻や中国人らの報復を受けながら、決死の思いで引き揚げた人もいたが、その3分の1にあたる約8万人が、避難途中の襲撃や、飢え・寒さのため命を落とした。難民の大半は女性と子どもで、それが犠牲者を増やした原因のひとつになった。日本の戦況悪化に伴い、男性は根こそぎ召集を受けていたのだ。
中国に取り残された日本女性たちが生き延びる手段のひとつは、現地の中国人との結婚だった。子どもを生かしたい一心で、中国人のもとに身を寄せた母親も少なくなかった。
近い未来、状況が落ち着けば帰国できると信じていた彼女たちであったが、1958(昭和33)年、長崎で起こった中国国旗侮辱事件を契機に、引き揚げ船事業が打ち切られるなど「日中国交全面断絶」といわれる事態になった。これら3千人以上にのぼる「中国残留婦人」は、以後20年以上にわたり異郷の地での生活を強いられたが、その間日本政府からの連絡は一切なかった。現在も約200人が中国で暮らす。
厚生労働省は、「中国残留孤児」を終戦時12歳以下、「中国残留婦人」を13歳以上と区別し、補償にも一線を画している。13歳以上であれば正常な判断ができる大人だとみなし、中国へ残ったのもみずからの意思、つまり“自己責任”だというのが、現在までの政府見解である。