マイクを向けて一瞬で、素人のみなさんから返ってくる
コトバのほうが、数100倍面白い。
立原啓裕さん(放送タレント)
●プロフィール●
1954年生まれ。大阪生まれ、奈良育ち。中学生の時、映画『メリーポピンズ』に出会い、ミュージカルの世界を目指す事を決意! 大阪芸術大学を卒業後、「劇団四季」に入団。その後、「ハイヤング京都」でラジオDJ としてデビュー、放送タレントの第一歩を歩みだす。85年、劇団「売名行為」を主宰。1公演に8千人という記録的な観客動員数を誇り、一大ムーブメントを巻き起こす。89年、『探偵!ナイトスクープ』に、探偵として出演(17年間、探偵を務め、06年からは顧問)。92年には、テレビ・ラジオのレギュラー番組数週16本という日本記録を樹立。日本医学ジャーナリスト協会会員で、04年には、自らの体験をもとに『立原啓裕の自律神経安定法(CD付)』を出版、3万部に迫るベストセラーとなる。07年、大阪芸術大学グループ・客員教授に就任し、後進の指導に力を入れている。「心の健康」や「情緒力を培うコミュニケーション」等、全国的に講演活動を精力的に行っている。
■一瞬に発するコトバ、それを生み出す感性。
もう3年前に卒業しましたが、『探偵!ナイトスクープ』(※1)という番組に出演していました。今日、お集まりのみなさん、わたしの顔、「見たことあるなあ」という方、お手を挙げていただくと・・・おお、こんなにぎょうさん、ありがとうございます。
ナイトスクープという番組には台本ないんですが、その手前の状態、シノプスっていいますが、放送作家が考えた質問を渡されるときもある。ぼくら、一応、受け取ります。確かに面白い質問なんかが書いてある。ところが、一生懸命、放送作家が頭を使って考えたギャグよりも、マイクを向けて一瞬で、素人のみなさんから返ってくるコトバのほうが、数100倍面白いこと、いっぱいあるんです。とくに関西ね。そういう意味では、一瞬に発するコトバ、それを生み出す感性、これが大事なんです。
ひとつのロケ、番組を作るのには、インタビューにも、映像の編集にも、頭を使います。つまり知性ですね。でも、マインドがないとできません。感性が大事なんです。依頼者の気持ちが分かるから、共感できるから、やれるんですよね。まあ、ロケは大変でしたけど、いろんな出会いありましたし、そんな中からも、感性を磨く大切さを教えてもらいました。
■こころの感性の磨き方。
われわれタレントの感性の磨き方ですが、アンテナをいつも張り巡らしています。これは意識して張っています。
子どもは、意識せずに張れてますね。ウォルト・ディズニーは、こんな言葉を残しています。「大人の5分間と子どもの5分間を比べてみよう。子どもの5分間のなんと素晴らしいことか」。子どもの5分って、おっ!虫がおる、あっ! 花が咲いている、わっ!お日さんが眩しい… 発見の連続でしょう。これ感性のかたまりですね。
大人になるとそうもいかない。だから意識して張ります。新幹線で移動なんかのときでも、われわれは寝たりなんかしません。車両の中に、面白い人はいないか、窓の外の景色に何か発見はないか、絶えずアンテナを張っています。
今日も、こっちに来るのにJRの在来線を利用してきたんですが、同じ車両の、斜めむこうにお客さんが乗ってきはった。ビニール袋を持っている。何するのかな、と見てたら、ビニール袋からですよ、いきなりゆでた蟹を取り出して、食べ始めたんですよ。たとえば、そんなこと一つとっても、普段しゃべるネタを探している。
次に、感じた後に、なぜそれを、私はユニークだと感じたのか。それを分析し、考えることです。そして、ここが一番大事なんですが、必ず自分なりのコトバで、それをまとめといてください。ここで大事なのは、「自分なりの」です。Aさんなりのコトバ、Bさんなりのコトバ、同じものごとを感じてても、違うコトバになるはずです。そこが面白い。
感じることは感性です。そこから考えて、自分のコトバを持つこと、これは知性のはたらきです。両方あわせて、思考ですね。そうして自分のコトバにする、それは他ならない自分の意見なのです。そしてコトバがまとまったら、それを必ず、誰かに伝えてください。そのコトバがCさんの中に入っていくと、相手も何らかのコトバを返してくれるでしょう。これでコミュニケーションが完成するのです。
■それ面白いから、ひとつ僕らにくれや。
関西にはお笑い文化がありますね。実は、お笑いも、この感性、知性、コトバのコミュニケーションとよく似た関係をもっています。なんばグランド花月(※2)の楽屋に行きますと、真ん中に、芸人さんが、うだ話(※3)をするロビーがある。吉本はケチや言いますが、先代の故・林会長(※4)が、「絶対このロビーだけはええもん作れ」と。そこ行くとね、いろんな芸人さん達が、みんなでうだ話をしている。ぼくなんか、ずっと個人事務所ですから、このロビーがあることが、本当にうらやましい。でね、例えば、さっきの話、「今日、J Rで蟹、食べ
とった客がおってなあ」なんて、Aという芸人さんが話をするとする。それ聞いていたBという芸人さんが、こんなこと言うかもしれんわけです。「おお、それ面白いから、ひとつ僕にくれや」ってね。「くれや」…その話を使わせてという意味ですが、で、「どうぞ、使ってください」と。
Bという芸人さんはね、きっとその話のどこが面白かったか、一生懸命考える。それで自分のコトバにして、Bさんのネタができあがる。それをお客さんに伝えると、「笑い」という返しがある。お笑い文化もコミュニケーションのひとつなんですね。
■動けば、出会える。聞けば、深まる。話せば、深まる。
コミュニケーションで感性が磨かれますと、わたしたちの「文化度」が高まります。さらに何より、これがポイントですが、「情緒力」も身についてくる。情緒の力…最近、ずいぶんと薄れてきましたね。いま世の中、殺伐としてきて、昔は人同士がええつきあいしてましたけどなあ…。
Aさんの感性に、心の襞にどっか一部分でも引っかかったら、ぜひそれをコトバにして、Bさんに、それをCさんに、Dさんに伝えてください。そのつながりの中で、文化度、民度が上がっていきます。人と出会えば、視野が広まります。また、その体験を別の人に語れば深まります。動けば、出会える。聞けば、深まる。話せば、深まる。そう思います。人とのふれあいは、生きたコトバを交わすこと、心をまじえること、それで人間は成長していく。原点は、一人ひとりが、堂々と自分の意見を人に伝えていくことだと思います。
09年10月27日に開催された福島区人権講演会より(主催は、福島区人権啓発推進協議会)
まとめ 編集委員 影浦 弘司
(※1)『探偵!ナイトスクープ』
朝日放送( A B C ) 制作の視聴者参加型テレビバラエティ番組。スタジオをひとつの探偵事務所と想定し、視聴者から寄せられた依頼を、探偵局員(レギュラー芸人たち)が依頼者と共に調査し、その過程のVTRを流す。1988年より関西ローカルでスタートし、現在は全国35局で放送。最高視聴率32.2%。20年間の平均視聴率20.1%。
(※2)なんばグランド花月
大阪市中央区にあるお笑い・喜劇専門の劇場。略称NGK(エヌジーケー)。
(※3)うだ話
副詞の「うだうだ」は、とるに足りないことをいつまでも言ったりするさま、を意味する。
(※4)林会長
林正之助(しょうのすけ)。1899 年~ 1991 年。吉本興業元会長・社長。
コトバのほうが、数100倍面白い。
立原啓裕さん(放送タレント)
●プロフィール●
1954年生まれ。大阪生まれ、奈良育ち。中学生の時、映画『メリーポピンズ』に出会い、ミュージカルの世界を目指す事を決意! 大阪芸術大学を卒業後、「劇団四季」に入団。その後、「ハイヤング京都」でラジオDJ としてデビュー、放送タレントの第一歩を歩みだす。85年、劇団「売名行為」を主宰。1公演に8千人という記録的な観客動員数を誇り、一大ムーブメントを巻き起こす。89年、『探偵!ナイトスクープ』に、探偵として出演(17年間、探偵を務め、06年からは顧問)。92年には、テレビ・ラジオのレギュラー番組数週16本という日本記録を樹立。日本医学ジャーナリスト協会会員で、04年には、自らの体験をもとに『立原啓裕の自律神経安定法(CD付)』を出版、3万部に迫るベストセラーとなる。07年、大阪芸術大学グループ・客員教授に就任し、後進の指導に力を入れている。「心の健康」や「情緒力を培うコミュニケーション」等、全国的に講演活動を精力的に行っている。
■一瞬に発するコトバ、それを生み出す感性。
もう3年前に卒業しましたが、『探偵!ナイトスクープ』(※1)という番組に出演していました。今日、お集まりのみなさん、わたしの顔、「見たことあるなあ」という方、お手を挙げていただくと・・・おお、こんなにぎょうさん、ありがとうございます。
ナイトスクープという番組には台本ないんですが、その手前の状態、シノプスっていいますが、放送作家が考えた質問を渡されるときもある。ぼくら、一応、受け取ります。確かに面白い質問なんかが書いてある。ところが、一生懸命、放送作家が頭を使って考えたギャグよりも、マイクを向けて一瞬で、素人のみなさんから返ってくるコトバのほうが、数100倍面白いこと、いっぱいあるんです。とくに関西ね。そういう意味では、一瞬に発するコトバ、それを生み出す感性、これが大事なんです。
ひとつのロケ、番組を作るのには、インタビューにも、映像の編集にも、頭を使います。つまり知性ですね。でも、マインドがないとできません。感性が大事なんです。依頼者の気持ちが分かるから、共感できるから、やれるんですよね。まあ、ロケは大変でしたけど、いろんな出会いありましたし、そんな中からも、感性を磨く大切さを教えてもらいました。
■こころの感性の磨き方。
われわれタレントの感性の磨き方ですが、アンテナをいつも張り巡らしています。これは意識して張っています。
子どもは、意識せずに張れてますね。ウォルト・ディズニーは、こんな言葉を残しています。「大人の5分間と子どもの5分間を比べてみよう。子どもの5分間のなんと素晴らしいことか」。子どもの5分って、おっ!虫がおる、あっ! 花が咲いている、わっ!お日さんが眩しい… 発見の連続でしょう。これ感性のかたまりですね。
大人になるとそうもいかない。だから意識して張ります。新幹線で移動なんかのときでも、われわれは寝たりなんかしません。車両の中に、面白い人はいないか、窓の外の景色に何か発見はないか、絶えずアンテナを張っています。
今日も、こっちに来るのにJRの在来線を利用してきたんですが、同じ車両の、斜めむこうにお客さんが乗ってきはった。ビニール袋を持っている。何するのかな、と見てたら、ビニール袋からですよ、いきなりゆでた蟹を取り出して、食べ始めたんですよ。たとえば、そんなこと一つとっても、普段しゃべるネタを探している。
次に、感じた後に、なぜそれを、私はユニークだと感じたのか。それを分析し、考えることです。そして、ここが一番大事なんですが、必ず自分なりのコトバで、それをまとめといてください。ここで大事なのは、「自分なりの」です。Aさんなりのコトバ、Bさんなりのコトバ、同じものごとを感じてても、違うコトバになるはずです。そこが面白い。
感じることは感性です。そこから考えて、自分のコトバを持つこと、これは知性のはたらきです。両方あわせて、思考ですね。そうして自分のコトバにする、それは他ならない自分の意見なのです。そしてコトバがまとまったら、それを必ず、誰かに伝えてください。そのコトバがCさんの中に入っていくと、相手も何らかのコトバを返してくれるでしょう。これでコミュニケーションが完成するのです。
■それ面白いから、ひとつ僕らにくれや。
関西にはお笑い文化がありますね。実は、お笑いも、この感性、知性、コトバのコミュニケーションとよく似た関係をもっています。なんばグランド花月(※2)の楽屋に行きますと、真ん中に、芸人さんが、うだ話(※3)をするロビーがある。吉本はケチや言いますが、先代の故・林会長(※4)が、「絶対このロビーだけはええもん作れ」と。そこ行くとね、いろんな芸人さん達が、みんなでうだ話をしている。ぼくなんか、ずっと個人事務所ですから、このロビーがあることが、本当にうらやましい。でね、例えば、さっきの話、「今日、J Rで蟹、食べ
とった客がおってなあ」なんて、Aという芸人さんが話をするとする。それ聞いていたBという芸人さんが、こんなこと言うかもしれんわけです。「おお、それ面白いから、ひとつ僕にくれや」ってね。「くれや」…その話を使わせてという意味ですが、で、「どうぞ、使ってください」と。
Bという芸人さんはね、きっとその話のどこが面白かったか、一生懸命考える。それで自分のコトバにして、Bさんのネタができあがる。それをお客さんに伝えると、「笑い」という返しがある。お笑い文化もコミュニケーションのひとつなんですね。
■動けば、出会える。聞けば、深まる。話せば、深まる。
コミュニケーションで感性が磨かれますと、わたしたちの「文化度」が高まります。さらに何より、これがポイントですが、「情緒力」も身についてくる。情緒の力…最近、ずいぶんと薄れてきましたね。いま世の中、殺伐としてきて、昔は人同士がええつきあいしてましたけどなあ…。
Aさんの感性に、心の襞にどっか一部分でも引っかかったら、ぜひそれをコトバにして、Bさんに、それをCさんに、Dさんに伝えてください。そのつながりの中で、文化度、民度が上がっていきます。人と出会えば、視野が広まります。また、その体験を別の人に語れば深まります。動けば、出会える。聞けば、深まる。話せば、深まる。そう思います。人とのふれあいは、生きたコトバを交わすこと、心をまじえること、それで人間は成長していく。原点は、一人ひとりが、堂々と自分の意見を人に伝えていくことだと思います。
09年10月27日に開催された福島区人権講演会より(主催は、福島区人権啓発推進協議会)
まとめ 編集委員 影浦 弘司
(※1)『探偵!ナイトスクープ』
朝日放送( A B C ) 制作の視聴者参加型テレビバラエティ番組。スタジオをひとつの探偵事務所と想定し、視聴者から寄せられた依頼を、探偵局員(レギュラー芸人たち)が依頼者と共に調査し、その過程のVTRを流す。1988年より関西ローカルでスタートし、現在は全国35局で放送。最高視聴率32.2%。20年間の平均視聴率20.1%。
(※2)なんばグランド花月
大阪市中央区にあるお笑い・喜劇専門の劇場。略称NGK(エヌジーケー)。
(※3)うだ話
副詞の「うだうだ」は、とるに足りないことをいつまでも言ったりするさま、を意味する。
(※4)林会長
林正之助(しょうのすけ)。1899 年~ 1991 年。吉本興業元会長・社長。










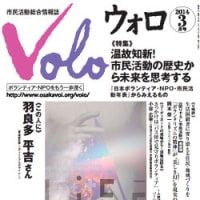
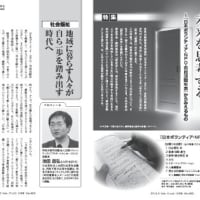
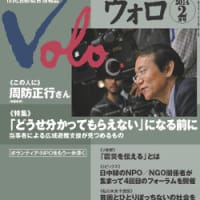
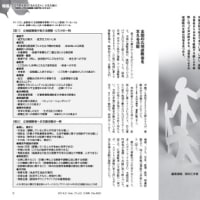
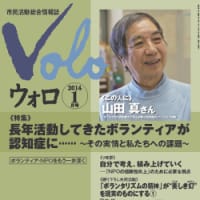
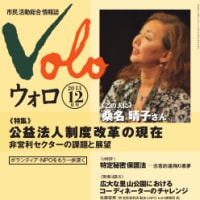
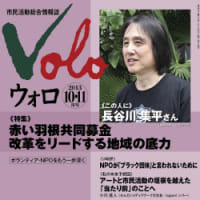
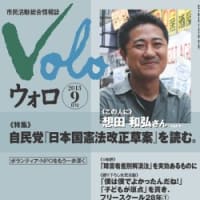
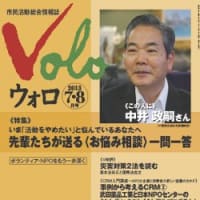
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます