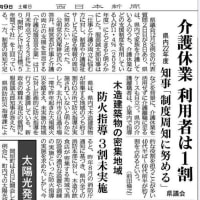代表質問続き
⑤人口減少・少子化対策について
日本の人口減少、少子化の流れが止まりません。2021年は、新型コロナの影響もあり、婚姻数が戦後最小の50万1千件余り、出生数も戦後最小の81万1千人余で、前年より2万9千人も少ない数でした。女性が一生涯に産む子供の数を表す合計特殊出生率は1・30となり、前年より一気に0・03ポイント下がりました。
出産適齢の女性の数も減少し続けています。
この深刻な事態をもたらしている要因の一つに、日本のジェンダーギャップを挙げる識者がいます。すなわち、日本は世界経済フォーラムが算出するジェンダーギャップ指数で146カ国中116位と先進国では最下位。先進国に限ってはジェンダーギャップ指数と出生率がリンクしていることがOECDの分析で分かっているというものです。相模女子大学大学院の白河桃子(しらかわ・とうこ)特任教授は、女性の生き方を限定しないこと、女性が最低賃金ではなく高い賃金で働ける職場を増やすこと、男性が育児をすること、男尊女卑の風土を廃していくこと。
これこそが少子化対策の第一歩であると強調しています。
そこで、まずジェンダーギャップ解消へ向けた本県の取り組みについて説明を願います。
少子化対策としてのジェンダーギャップ解消に必要なのは、まずは女性の収入アップや就業の継続です。そこで、本県において賃金が低い非正規雇用の男女別の割合はどれくらいか、また、結婚前後と第一子出産前後の女性の就業継続率はどれくらいか、それぞれお示しください。その上で、一般的に女性の賃金が男性の賃金より低いことについて、知事はその原因をどのように分析されているのか、
また、その解消へどのような施策に取り組まれるのかお答えください。
次に、女性に子どもを産んでも大丈夫という安心感がないのは、「孤独な育児」「ワンオペ育児」にプレッシャーがあるからとの指摘があります。そこで、本県の男性従業員の育児休業取得率についてお示しください。今年度からの育児介護休業法改正で「産後パパ育休」すなわち「出産育児休業」という新設制度ができました。
この「産後パパ育休」の取得を進めるため、どのような施策に取り組まれているのかお尋ねします。
また、県庁自身も率先すべきだと思いますが、県庁職員の育児休業取得率はどうなっているのか。「産後パパ育休」の取得促進の取り組みと併せてお答えください。
少子化は各地域において進み方がまちまちです。
県内においても少子化や人口減少が極めて深刻な地域がある一方で、流入人口があるため実感が伴わない都市部もあります。その意味で、福岡県全体での一体感のある意識の在り方や取り組みが必要であり、知事のリーダーシップが求められます。
少子化、人口減少の問題に知事として今後どのような決意で取り組まれるのか、ご所見をお伺いします。
⑥0~2歳の支援について
次に、0~2歳児の支援についてお尋ねします。
少子化や人口減少は我が国が直面する最重要課題であり、7年早く少子化が進んでいます。「安心して子どもを産み育てられる社会」の構築が急務であります。国もようやく子ども家庭庁設置に踏み切り、真剣に取り組もうとしています。こども基本法には、「時代の社会を担うすべての子どもが、生涯にわたる人格形成の基盤を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、子どもの心身の状況、おかれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な人生を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進する」とあります。
まず、国の子ども家庭庁設置に伴って、本県における子ども施策の組織体制をどのように考えておられているか、お尋ねいたします。
核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、孤立感や不安感を抱く妊婦・子育て家庭も少なくないです。すべての妊婦・子育て世代が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題です。
12月2日に国の補正予算が採決され、公明党が提案した0~2歳の支援が本格的に始まります。厚生労働省では新規に、出産・子育て応援交付金が創設されます。当交付金は、市町村の創意工夫により、妊娠から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援に繋ぐ伴走型の相談支援と、経済的支援を一体として実施する事業を支援するとされています。
そこで質問です。今回、国が創設する交付金により、妊娠から出産・子育てに係る支援はどのように充実されるのか。また、当交付金による事業において、市町村の取組に格差が生じないよう、県は市町村に対して、どのように関わっていくのか、お尋ねします。
本県で生まれる子どもたちは、明日の本県を担う大事な宝です。
知事の誠意ある答弁を求めます。
⑦特定妊婦の支援(1207)
次に、特定妊婦の支援について伺います。
核家族化や地域とのつながりの希薄により孤立、不安感をいだく妊産婦が少なくない中で、全ての妊産婦が出産子育てできる環境を整えることが喫緊の課題となっています。
特に孤立や貧困、予期せぬ妊娠などで出産前後に支援を必要とする「特定妊婦」が増えています。虐待死した子どものうち、実母が加害者だった事例が多い中、国は、2009年改正児童福祉法で特定妊婦を支援対象に位置付けました。
2020年4月時点で、全国で特定妊婦は8327人に上り、制度開始の2009年から約8倍に増加。生後間もない乳児が遺棄される事件などが相次いだことを受け、官民で手を差し伸べる動きが本格化してきたところであり、特定妊婦の支援は母親だけでなく、虐待を受ける子どもを救うことにもつながります。
特定妊婦の中には、パートナーからのDVや、虐待のリスクのある方、予期せぬ妊娠や経済的な事情で親に相談できない等、将来への不安や多くの悩みを抱えており、相談ができる環境で産前産後を安心して過ごせる居場所が必要となります。
母親と子どもが一緒に暮らせる母子生活支援施設がありますが、母子生活支援施設では女性は出産前から利用できない制度となっています。
Q1. そこで質問です。特定妊婦は、産前からの支援が必要であることから、他県では産前の支援から産後、自立まで一貫して支援する施設ができ、孤立を防ぐ取り組みが始まっています。本県ではどのように取り組まれているのか。知事の見解を求めます。
Q2.特定妊婦と認定されていない妊婦でも支援の必要な女性は多く、相談窓口を知らなかったり、経済的な事情で妊婦健診を受診しない等、把握できずに支援につながらない妊婦が多いと聞きますが、こうした妊婦が支援から零れ落ちないように、市町村において福祉分野と母子保健分野の連携を取ることや、相談窓口の情報発信に注力すべきですが、県ではどのように取り組まれているのか、知事の見解を求めます。
⑧強度行動障がいの支援(1207)
強度行動障がいの支援についてお尋ねします。
強度行動障がいとは、自閉症や重度の知的障がいの方が起こす自傷他害行為や物を壊すなど周囲の人や暮らしに影響を及ぼす行動が高い頻度で起こるため、特別な支援が必要とされる障がいで、家庭での通常の子育ては困難な状況が続きます。
障がい者施設でも自傷他害行為によって社会に適用することができない強行の程度が重い人の場合、支援員が複数で対応せざるを得ず、民間事業者では経営面の難しさから、受け入れに消極的にならざるを得ず、受け入れ施設が極めて少ないのが現状です。
強度行動障がいの症状が起こると、家庭への暴力を繰り返し、親は落ち着くまで明け方までドライブを続けるなど、家族は疲弊し、過酷な日常から本人御家族の苦しみは限界を超え、生きづらさを抱えているケースが少なくなく、第3者による支援が必要となっています。
Q1. まず、県では強度行動障がいのある方とその家族の実態について、どのように認識されているのか、知事の見解を求めます。
先般、私は北九州市のある社会福祉法人を視察しました。同法人は家族でケアができない重い強行の方を受け入れたのをきっかけに、社会福祉士や臨床心理士など専門家によるチームで支援し向き合っています。同法人では日中一時支援の他、グループホームでも受け入れていますが、強行の方が落ち着けるように、他の利用者が他害の被害に遭わないよう、強行の方の個室への玄関や水回りを別個に設置することで、一人で過ごす時間を選択できるようにしました。その後他害行為がなくなり、現在もその状態が続いています。理事長は、強行の方の行動はつらいことへの防衛的行動であり、人的支援、物理的環境を整え、本人が安全安心と思える環境を作ることで他害行為がなくなる、同法人では、強行の方全員が腕まくりをして、新型コロナのワクチン接種を終えることができたと言われていました。
また、福岡市のある社会福祉法人では、フロアに利用者が行き来できる半個室のブースを設置し、壁は外からの視界が遮られ、立てば外が見える140㎝の高さで、強行の行動が出た方を閉じ込めるのではなく、きついと思った時点で自ら半個室に入って落ち着くことができます。そうした環境を整えてからは、強行の行動の一つである大声をあげることが大幅に減少しており、理事長は選択肢があることが大事であると言われていました。
Q2. そこで質問です。強度行動障がいのある方の支援は、その特性を理解した人材による専門的な支援だけでなく、施設や設備などの物理的な環境調整の工夫が状態の安定・改善に有効です。
強度行動障がいの特性から、受け入れを拒む施設がある中で、一人でも多く受け入れができるよう、こうした体制の整備が進む必要があると考えますが、県では、現在、障がい福祉サービス事業所等の人材育成や強度行動障がいのある方を入居対象とするグループホームの施設整備について、どのような支援を行っているのか、知事の見解を伺います。
Q3. 強度行動障がいのある方の受け入れに消極的な事業所があるのは、強度行動障がいがどのような状態か正しく理解されておらず、また専門的な支援、環境調整を行って受け入れ、状態の安定・改善につなげている事業所があることがあまり認知されていないためと考えます。
市町村が親からの相談に乗りやすくなり、また受け入れに消極的だった事業所で受け入れの検討が進むよう、県が、支援体制を確立し受け入れている法人等から、実践的な支援方法、施設整備の構造等、改善事例の情報を収集し、市町村や事業所に周知してはどうかと考えますが、知事の見解を求めます。
⑨学校図書館における学校司書の役割について(1207)
次に、学校図書館における学校司書の役割について教育長にお尋ねします。
先日新聞のコラムに、4年生の教室での、物語「一つの花」(今西祐行・作)の授業の様子が書かれていました。作中の、父親がコスモスを渡した時の心理描写について、登場人物の立場に立ち、状況や背景を踏まえれば、行間から父親の気持ちを想像できますが、一部生徒は読み解く力がなく、父親の悪意や欲望を描いた作品だと受け取ってしまうという衝撃的な記事でした。しばしばこの物語の誤読問題が取り上げられており、特例ではないと思われます。
読解力の低下については、OECDのPISA(生徒の学習到達度調査)に参加した当初、PISAショックと呼ばれ、大きな衝撃を与えたが、直近の2018年の調査でも数学が6位、化学が5位に対して、読解力は15位と読解力が長らく低迷しています。
ある校長は、学校現場で見られる子どもの思考力の欠如や珍妙な解釈を、「読解力の低下」という問題だけにとどめてはならず、読解力以前の基礎的能力の低下を危惧されています。
発達心理学の今井むつみ教授は子どもが言葉を育めるようになるかどうかの分岐点について、「誰もが生まれ持って分析力、推論力、学習力を兼ね備えているが、それを発揮させられるかどうかは家庭環境が大きな役割を担っている、親が子に対して話かける言葉の量と質が大きな影響を与える」と指摘しています。
家庭の中で培われる言語能力の低下が言われる中、公立の学校に期待される役割が大きくなっています。現行の学習指導要領の解説では、「言語能力は全ての教科等における資質・能力の育成や学習の基盤となる」と位置付け、各学校において充実が求められる学習活動とされています。子どもたちの言語能力を高めるためには、単に言語を使わせる機会を増やすだけではなく、言葉を使って伝えたいという気持ちや言葉にできる豊かな感情や経験が必要と考えます。
読書は、多くの語彙や多様な表現を通じて様々な世界に触れ、疑似的な体験、知識の習得、新たな考え方に出会うことを可能にするものであり、言語能力を向上させる重要な活動の一つです。ソサエティ5.0時代に、福岡県でも児童生徒に一人1台タブレットが配布されました。ICT化と両輪で紙媒体の本に触れることが重要であり、学校図書館は言語能力だけでなく情報活用能力を育む上でその役割は大きくなっています。課題は子どもたちと本を結ぶ橋渡し役として、学校図書館を支える学校司書が配置され、機能し、役割を果たせるようにすることです。
そこで教育長に伺います。
Q1子どもたちの読書を促すためには、学校図書館の充実が欠かせません。学校図書館を充実させるために必要な専門的・技術的職務に従事するのが学校司書です。学校司書の果たす役割についてどのように認識しているのか、教育長の見解を求めます。
Q2本県の公立小中学校の中には、学校司書が常駐する学校、複数の学校を兼務し、本来の役割が果たせていない学校、配置していない学校もあると聞いています。宇美町では「図書館を使った調べる学習コンクール」を独自に実施し、子どもたちの図書館利用を推進しつつ、町内の5小学校、3中学校に1人ずつ司書を置き、毎月、調べ学習に役立つ本などについて情報交換するなど先進的に取り組む市町もあります。県教委では司書の配置が進むようどのように取り組んでいるのか、教育長の見解を求めます。
⑩フィッシング対策について
次に、フィッシング対策についてお尋ねします。
一昨年6月の定例県議会のわが会派の代表質問で、新型コロナに関連した詐欺対策について質したところ、警察本部長から、「県内では、実在する宅配事業者や携帯電話事業者、金融機関等を装って電子メール等を送り、受信者を偽のウェブサイトに誘導し、ID、パスワード、クレジットカード番号等を読み取る、いわゆるフィッシング詐欺に関連する相談が増加傾向」にあるとの認識を示し、「県警察のホームページ内に、フィッシング詐欺に関する情報提供専用フォームを開設し、一般の方から提供を受けた情報を分析した上で、偽サイトに対するより迅速、効果的な捜査活動はもとより、被害の未然防止を目的とした犯行手口のタイムリーな情報発信などの取組を実施しているところ」であるとの答弁がありました。
いまだに偽メールが横行しており、後を絶ちません。コロナ禍にあって、クレジットカードの利用は増加傾向にあるようです。経済産業省は、キャッシュレス決済比率を2025年までに4割程度、将来的には世界最高水準の80%まで上昇させることを目指し、キャッシュレス決済の推進に取り組んでいますが、昨年のキャッシュレス決済比率は32.5%となり年々増加しています。また、その内訳は、クレジットカードが27.7%と大部分を占め、今後、こうした状況に伴う詐欺被害の拡大が心配されます。クレジットカードの不正利用等の詐欺被害を未然に防ぐためには、その入口となるフィッシング対策の強化が求められます。
そこで、警察本部長にお聞きします。
まず、本県に寄せられているフィッシングに関する相談の状況はどのようになっているのでしょか?具体的な相談件数の推移と相談内容等の傾向についてご教示願います。
次に、今後も、社会情勢に応じた様々な手口によりフィッシング行為の増加が懸念されるとともに、キャッシュレス決済を推進するにあたり、フィッシングを入口としたクレジットカードの不正利用等の詐欺を未然に防ぐため、フィッシング対策の強化は重要であると考えますが、本県の現状を踏まえた今後の対策をどのように進めていくのか、警察本部長のご所見をお尋ねします。
答弁骨子
二-①
問 ジェンダーギャップ解消へ向けた本県の取組について
○ 県では、令和3年3月に策定した第5次男女共同参画計画に基づき、
・働く場や地域・家庭・社会活動において男女がともに活躍できる社会の実現
・女性等に対する暴力の根絶など誰もが安全・安心に暮らせる社会の実現
・男女共同参画社会の実現に向けた意識改革・教育の推進
の3つの柱のもと、施策を推進している。
○ 計画においては、女性の就業率や性別役割分担に賛成しない人の割合など、23の成果指標を設定し、
・働く場における女性の活躍推進や仕事と生活の両立のための働き方改革の推進
・自治会等地域コミュニティの運営における男女共同参画の推進
・DVなどの暴力被害や貧困などの生活上の困難に直面している方々への支援
・性別役割分担意識の解消や性の多様性に関する理解の促進
などに取り組んでいるところである。
二-②
問 男女間の賃金格差についての原因分析とその解消に向けた施策について
○ 本県の雇用者に占める非正規雇用の割合は、平成29年度調査で、男性が約2割であるのに対し、女性は5割を超えている。
女性の就業継続率は、平成27年から令和元年の間で結婚または出産した女性を対象とする全国調査では、結婚前後で約8割、第一子出産前後で約7割となっている。
○ 男女間の賃金格差は、男性に比べて女性は、①非正規雇用に占める割合が高いこと、②平均勤続年数が短いこと、③管理職比率が低いことが原因とされており、これらの解消が課題と考える。
○ このため、「正規雇用促進企業支援センター」において、県内企業への正社員採用の働きかけや企業内での非正規から正規雇用への転換に向けたアドバイスを行うとともに、「子育て女性就職支援センター」において、正規雇用を希望する方に対するきめ細かな就職支援などを行っているところである。
○ また、女性が長く働き続けることができるよう、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための取組を宣言・実行する「子育て応援宣言企業」や、自社の働き方の見直しを宣言・実行する「よかばい・かえるばい企業」の登録推進に取り組んでいる。
○ さらに、女性の管理職への登用を促進するため、企業等の幹部候補者を対象とする「トップリーダー育成研修」や、課長・係長・若手といった職務経験に応じた階層別の研修を実施し、女性人材の育成を図っている。
○ 今後も、こうした取組を通じて、結婚や出産などのライフステージが変化しても、女性がキャリアを中断することなく、やりがいをもって働き続けることができるよう就業環境の整備を推進してまいる。
二-③
問 「産後パパ育休」の取得促進のための取組について
○ 令和3年度の子育て応援宣言企業の男性従業員の育児休業取得率は、
21.4%と、前年度から5.2ポイント増加し、年々着実に増加している。
しかしながら、毎年90%台後半で推移している女性の取得率と比べると、低水準に留まっている。
◯ こうした状況を踏まえ、県では、「産後パパ育休」が施行された今年10月から2か月間にわたり、男性の育児休業取得を促進するための動画 「育休のススメ!パパ育フォーラム2022」をYouTubeで配信し、約500名の方に参加いただいた。
その中で、私もサイボウズ株式会社の青野社長と対談を行い、事業主や県民の皆様に対し、男性の育児休業の取得促進を呼びかけた。
◯ また、福岡労働局との共催で、企業の代表者や人事・労務担当者を対象に、今回の育児・介護休業法の改正内容や、育児休業等を取得しようとする男性に対する職場における嫌がらせ、いわゆるパタニティハラスメントの防止についての研修会をWeb上で開催し、135名の方に参加いただいた。
◯ このほか、子育て応援宣言企業のホームページやメルマガを活用し、今回の法改正の内容や、育児休業取得を促進する事業主への助成金について周知を図っているところである。
二-④
問 県庁男性職員の育児休業取得率と「産後パパ育休」の取得促進について
○ 県庁男性職員の育児休業取得率は、令和3年度で36.2%となっており、特定事業主行動計画の目標値である30%を上回った。
○ 男性の育児休業については、更なる取得の促進を図るため、今年8月から、職員への1か月以上の休暇・休業の取得パターンの紹介など、新たな取組を進めている。
これと併せ、今年10月から始まった新たな「産後パパ育休」についても制度の活用を促すため、職員に向けて積極的に周知を図ってきたところである。
○ 具体的には、
・ 男性職員に1か月以上の育児休暇・休業の取得を呼びかけるポスターの中に、「産後パパ育休」の概要を記載し、全所属に掲示するとともに、
・ 「産後パパ育休」も含めた育児休業等の制度改正の概要を分かりやすくまとめたリーフレットを作成し、職員に配付、
・ さらには、出産・育児の際に取得できる休暇等を取りまとめた「仕事と子育ての両立支援ハンドブック」を改訂し、庁内ネットワークを活用して周知を行った。
○ 今後とも、育児休業等の制度周知と取得しやすい環境づくりに努めてまいる。
二-⑤
問 少子化、人口減少に対する決意について
○ 人口動態統計速報によると、今年1月から9月までの全国の出生数は、昨年と比較してマイナス4.9%で、調査開始以来、最も少なかった昨年を下回るペースとなり、松野官房長官は、先月の会見で「危機的状況である」との認識を示された。
県においても、同時期の出生数は、昨年と比較してマイナス3.6%と非常に厳しい状況にあり、少子化に歯止めをかけることは喫緊の課題であると考えている。
○ そのため、先ほど申し上げた、仕事と生活の両立のための働き方改革の推進などジェンダーギャップの解消に向けた取組や、出会い・結婚、出産、育児などそれぞれのライフステージに合わせた施策を、今後ともきめ細かく総合的に行ってまいる。
○ 併せて、人口減少を食い止めるためには、少子化のみならず、就職などによる若者の流出といった社会的な減少にも対処しなければならない。
そのため、中小企業への支援、農林水産業の振興、企業誘致などにより、魅力ある雇用の場をつくるとともに、医療・福祉サービスの充実、地域公共交通の維持・確保、ICTの積極的な活用による教育の充実などに取り組むことが重要である。
○ こうした取組により、住み慣れたところで働く、長く元気に暮らす、子どもを安心して産み育てることができる地域社会づくりを、しっかり進めてまいる。
三-①
問 こども家庭庁設置に伴うこども施策の組織体制について
○ 来年4月施行の「こども基本法」では、こども施策について、新生児期、乳幼児期、学童期、思春期を経ておとなになるまで、心身発達の過程を通じて切れ目なく、こどもの健やかな成長に対する支援を行うことなどが定められている。
このため、こども施策に関わっている保健医療介護部、福祉労働部、人づくり・県民生活部に教育委員会を含め対応を検討してきた。
○ その結果、こども施策を一元的に策定実施する「こども家庭庁」、及び、「こども家庭センター」を設置して住民の皆様に総合的・一体的にこども施策を
提供する市町村のカウンターパートとして、新たな課を福祉労働部に新設し、県内どの地域にあっても、健やかな成長に対する切れ目ない支援が受けられ、こどもの意見が尊重されることを推進することによって、「こどもまんなか社会」を目指したいと考えている。
○ 同課において、福祉労働部内をはじめ数多くの地域の社会資源とのつながりを生かし、医療、保健、福祉、教育、療育等の多分野にわたる「県こども計画」の策定の総合調整や、こどもの貧困問題、家庭・学校以外のこどもの居場所づくりなど、近年のこどもを取り巻く新たな部局横断的な課題にも機動的に対応してまいる。
三-②
問 出産・子育て応援交付金について
○ 本交付金は、市町村が、妊娠届出時と出生届出時にそれぞれ5万円相当の支給を行う「経済的支援」と、妊婦や低年齢期の子育て家庭に、出産・育児等の見通しを立てるための面談や情報提供を行う「伴走型相談支援」を一体として実施する事業に補助するものである。
○ 本交付金に基づく事業により、産後ケア等のサービスを受ける際の経済的負担が軽減されるとともに、支援が必要な妊産婦が、市町村等の相談窓口につながりやすくなり、妊娠期から出産・子育て期まで、面談等による支援を継続的に受けることで、孤立感や不安感が軽減されると考えている。
○ 県としては、市町村に対し、妊娠届出から乳児家庭に全戸訪問するまでの面談実施のイメージや、事業開始前に出産した方等への対応、今後のスケジュール等を分かりやすく示し、事業を速やかに開始できるよう支援してまいる。
四-①
問 特定妊婦の孤立を防ぐ取組について
○ 県では、昨年度から、予期せぬ妊娠に悩む方や経済的困窮等により出産後の養育不安を抱える方などを対象に、相談支援や出産・育児のサポート、一時的な住まいの提供、就労支援等、産前から産後まで継続した支援を行う「特定妊婦等母子支援事業」に取り組んでいる。
○ 具体的には、社会福祉法人が運営する母子生活支援施設に委託して実施しており、施設に配置したコーディネーターが相談対応や必要な支援の検討、児童相談所や市町村などの関係機関との調整等を行うとともに、施設の看護師が出産や子育てを援助し、出産後も母子が安定した生活を送れるよう支援している。
また、在宅での支援が必要な方については、コーディネーターや看護師がご自宅まで伺う、アウトリーチでの支援を行っているほか、住まいの提供が必要な場合は出産前であっても施設への入所が可能となっている。
○ 今年度からは、実施箇所を1か所から2か所に増やしており、事業の拡充を図っているところである。
四-②
問 支援を必要とする妊婦の方への取組について
○ 市町村では、母子保健担当部署が把握した特定妊婦について、要保護児童対策地域協議会で協議、進捗管理を行いながら、それぞれの妊婦の状況に応じて、家庭訪問による相談支援や家事・育児の援助など、必要な支援に取り組んでいる。
県では、こうした市町村の取組が適切に行われるよう、児童相談所が実施する市町村担当職員向け研修において、母子保健と児童福祉の連携について助言を行っているところである。
○ また、健診未受診など市町村や医療機関等に繋がっていない方に、先ほどご答弁申し上げた「特定妊婦等母子支援事業」の相談窓口や、妊娠に悩む方の相談窓口「にんしんSOS」の情報を知っていただくことが重要である。
このため、こうした情報を県のホームページや、LINE、インスタグラムといったSNSを活用して、広く県民へお知らせするほか、ミニカードをコンビニや商業施設の女性用トイレに設置し、きめ細かな周知に努めているところである。
四-③
問 強度行動障がいのある方とその家族の実態について
○ 強度行動障がいのある方とは、自らを傷つける、他者に暴力をふるう、物を壊すなどの行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別な配慮や支援が必要であると考えている。
〇 現在、強度行動障がいのある方の人数を把握するための確立された方法がないことから、国において、強度行動障がいのある方の支援に関する検討会を立ち上げ、全国的に把握するためのルールに関する検討が始まっているところである。
〇 ご家族は、常日頃から見守りを行うとともに、そのような行動が起きた場合には、ご本人や周囲の安全を確保しつつ、行動がおさまるようご本人を落ち着かせる必要があり、大変なご負担がかかっていると認識している。
四-④
問 事業所に対する人材育成やグループホームの整備への支援について
〇 県では、事業所の従業者を対象に、平成27年度から、支援者養成研修に取り組み、強度行動障がいのある方に適切な支援を行う人材の育成を図っている。これまでに、約5,800人の方が、この研修を修了した。
〇 グループホームについては、国の整備方針に基づき、県では、強度行動障がいを含む重度障がいのある方を入居対象とするものを、優先的に整備することとしており、その費用の一部を補助している。
四-⑤
問 強度行動障がいの状態が改善した事例の周知について
〇 強度行動障がいのある方への支援には、支援者の高い専門性と、落ち着ける空間の確保などの環境面での配慮が必要である。
〇 御紹介いただいたように、個室に玄関や水回りを設置し、一人で過ごす時間を選択できるようにすることや、半個室をフロアに設置し自ら入って落ち着くことができるようにすることで、他害行為などの危険を伴う行動の回数が減少するなどの事例がある。
〇 今後、専門的な支援に取り組んでいる事業所から対応事例を収集し、支援者養成研修の教材に追加するとともに、市町村担当課長会議や事業所に対する集団指導において周知してまいる。
五-①
問 学校司書の役割について(教育長答弁)
○ 学校図書館は、子どもたちが本に親しむ最も身近な場所であり、読書を通して、情報を得たり、学習を深めたりする機能を有している。
学校司書は、司書教諭等と共に、児童生徒が進んで学校図書館を訪れたくなるような環境づくりや、児童生徒や教員の学習情報ニーズへの対応、授業に役立つ資料の整備などを通して、こうした学校図書館の機能を向上させる役割を担っているものと認識している。
五-②
問 学校司書の配置の促進について(教育長答弁)
○ 国において策定された、第6次「学校図書館図書整備等5か年計画」には、学校図書館法において学校司書の配置が努力義務とされていることを踏まえ、学校司書の配置の推進を図ることが示されている。
これに基づき、市町村に対しては地方財政措置が講じられており、県教育委員会においても毎年これを周知しているところである。
また、県教育センターの研修において、学校司書との連携による充実した図書館活動の事例を紹介しており、これらの取組を通して、学校司書の配置促進に努めてまいる。
六-①
問 フィッシングに関する相談件数の推移及び相談内容等の傾向について(警察本部長答弁)
○ フィッシングの相談件数については、令和2年は1,153件、令和3年は2,011件、令和4年10月末現在では、前年同期比プラス297件の1,695件と増加傾向にある。
○ 県民から寄せられるフィッシングの相談内容等については、通信事業者、通信販売事業者やクレジットカード会社などを装った手口に関するものが多く、また、最近では、国税庁などを装う新たなものも見られるところである。
六-②
問 本県の現状を踏まえた今後の対策について(警察本部長答弁)
○ 県警察においては、県民から寄せられた相談や独自に開発したシステム等を活用して、フィッシングや偽サイトに関する情報について分析を行い、県警察のホームページやツイッターなどを活用して、タイムリーに注意喚起を行っているところである。
○ 把握した偽サイトの情報については、警察庁を通じてウィルス対策ソフト事業者に提供しており、同事業者を通じ、その偽サイトを閲覧しようとする利用者に警告を表示して注意を促している。
○ また、県内の学術機関とフィッシングに関する調査・研究を実施するなど、産学機関と連携した取組を行っているところである。
○ 県警察としては、引き続き、社会情勢と共に変化する手口を的確に把握した上で、各種対策を推進してまいる。
⑤人口減少・少子化対策について
日本の人口減少、少子化の流れが止まりません。2021年は、新型コロナの影響もあり、婚姻数が戦後最小の50万1千件余り、出生数も戦後最小の81万1千人余で、前年より2万9千人も少ない数でした。女性が一生涯に産む子供の数を表す合計特殊出生率は1・30となり、前年より一気に0・03ポイント下がりました。
出産適齢の女性の数も減少し続けています。
この深刻な事態をもたらしている要因の一つに、日本のジェンダーギャップを挙げる識者がいます。すなわち、日本は世界経済フォーラムが算出するジェンダーギャップ指数で146カ国中116位と先進国では最下位。先進国に限ってはジェンダーギャップ指数と出生率がリンクしていることがOECDの分析で分かっているというものです。相模女子大学大学院の白河桃子(しらかわ・とうこ)特任教授は、女性の生き方を限定しないこと、女性が最低賃金ではなく高い賃金で働ける職場を増やすこと、男性が育児をすること、男尊女卑の風土を廃していくこと。
これこそが少子化対策の第一歩であると強調しています。
そこで、まずジェンダーギャップ解消へ向けた本県の取り組みについて説明を願います。
少子化対策としてのジェンダーギャップ解消に必要なのは、まずは女性の収入アップや就業の継続です。そこで、本県において賃金が低い非正規雇用の男女別の割合はどれくらいか、また、結婚前後と第一子出産前後の女性の就業継続率はどれくらいか、それぞれお示しください。その上で、一般的に女性の賃金が男性の賃金より低いことについて、知事はその原因をどのように分析されているのか、
また、その解消へどのような施策に取り組まれるのかお答えください。
次に、女性に子どもを産んでも大丈夫という安心感がないのは、「孤独な育児」「ワンオペ育児」にプレッシャーがあるからとの指摘があります。そこで、本県の男性従業員の育児休業取得率についてお示しください。今年度からの育児介護休業法改正で「産後パパ育休」すなわち「出産育児休業」という新設制度ができました。
この「産後パパ育休」の取得を進めるため、どのような施策に取り組まれているのかお尋ねします。
また、県庁自身も率先すべきだと思いますが、県庁職員の育児休業取得率はどうなっているのか。「産後パパ育休」の取得促進の取り組みと併せてお答えください。
少子化は各地域において進み方がまちまちです。
県内においても少子化や人口減少が極めて深刻な地域がある一方で、流入人口があるため実感が伴わない都市部もあります。その意味で、福岡県全体での一体感のある意識の在り方や取り組みが必要であり、知事のリーダーシップが求められます。
少子化、人口減少の問題に知事として今後どのような決意で取り組まれるのか、ご所見をお伺いします。
⑥0~2歳の支援について
次に、0~2歳児の支援についてお尋ねします。
少子化や人口減少は我が国が直面する最重要課題であり、7年早く少子化が進んでいます。「安心して子どもを産み育てられる社会」の構築が急務であります。国もようやく子ども家庭庁設置に踏み切り、真剣に取り組もうとしています。こども基本法には、「時代の社会を担うすべての子どもが、生涯にわたる人格形成の基盤を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、子どもの心身の状況、おかれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な人生を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進する」とあります。
まず、国の子ども家庭庁設置に伴って、本県における子ども施策の組織体制をどのように考えておられているか、お尋ねいたします。
核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、孤立感や不安感を抱く妊婦・子育て家庭も少なくないです。すべての妊婦・子育て世代が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題です。
12月2日に国の補正予算が採決され、公明党が提案した0~2歳の支援が本格的に始まります。厚生労働省では新規に、出産・子育て応援交付金が創設されます。当交付金は、市町村の創意工夫により、妊娠から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援に繋ぐ伴走型の相談支援と、経済的支援を一体として実施する事業を支援するとされています。
そこで質問です。今回、国が創設する交付金により、妊娠から出産・子育てに係る支援はどのように充実されるのか。また、当交付金による事業において、市町村の取組に格差が生じないよう、県は市町村に対して、どのように関わっていくのか、お尋ねします。
本県で生まれる子どもたちは、明日の本県を担う大事な宝です。
知事の誠意ある答弁を求めます。
⑦特定妊婦の支援(1207)
次に、特定妊婦の支援について伺います。
核家族化や地域とのつながりの希薄により孤立、不安感をいだく妊産婦が少なくない中で、全ての妊産婦が出産子育てできる環境を整えることが喫緊の課題となっています。
特に孤立や貧困、予期せぬ妊娠などで出産前後に支援を必要とする「特定妊婦」が増えています。虐待死した子どものうち、実母が加害者だった事例が多い中、国は、2009年改正児童福祉法で特定妊婦を支援対象に位置付けました。
2020年4月時点で、全国で特定妊婦は8327人に上り、制度開始の2009年から約8倍に増加。生後間もない乳児が遺棄される事件などが相次いだことを受け、官民で手を差し伸べる動きが本格化してきたところであり、特定妊婦の支援は母親だけでなく、虐待を受ける子どもを救うことにもつながります。
特定妊婦の中には、パートナーからのDVや、虐待のリスクのある方、予期せぬ妊娠や経済的な事情で親に相談できない等、将来への不安や多くの悩みを抱えており、相談ができる環境で産前産後を安心して過ごせる居場所が必要となります。
母親と子どもが一緒に暮らせる母子生活支援施設がありますが、母子生活支援施設では女性は出産前から利用できない制度となっています。
Q1. そこで質問です。特定妊婦は、産前からの支援が必要であることから、他県では産前の支援から産後、自立まで一貫して支援する施設ができ、孤立を防ぐ取り組みが始まっています。本県ではどのように取り組まれているのか。知事の見解を求めます。
Q2.特定妊婦と認定されていない妊婦でも支援の必要な女性は多く、相談窓口を知らなかったり、経済的な事情で妊婦健診を受診しない等、把握できずに支援につながらない妊婦が多いと聞きますが、こうした妊婦が支援から零れ落ちないように、市町村において福祉分野と母子保健分野の連携を取ることや、相談窓口の情報発信に注力すべきですが、県ではどのように取り組まれているのか、知事の見解を求めます。
⑧強度行動障がいの支援(1207)
強度行動障がいの支援についてお尋ねします。
強度行動障がいとは、自閉症や重度の知的障がいの方が起こす自傷他害行為や物を壊すなど周囲の人や暮らしに影響を及ぼす行動が高い頻度で起こるため、特別な支援が必要とされる障がいで、家庭での通常の子育ては困難な状況が続きます。
障がい者施設でも自傷他害行為によって社会に適用することができない強行の程度が重い人の場合、支援員が複数で対応せざるを得ず、民間事業者では経営面の難しさから、受け入れに消極的にならざるを得ず、受け入れ施設が極めて少ないのが現状です。
強度行動障がいの症状が起こると、家庭への暴力を繰り返し、親は落ち着くまで明け方までドライブを続けるなど、家族は疲弊し、過酷な日常から本人御家族の苦しみは限界を超え、生きづらさを抱えているケースが少なくなく、第3者による支援が必要となっています。
Q1. まず、県では強度行動障がいのある方とその家族の実態について、どのように認識されているのか、知事の見解を求めます。
先般、私は北九州市のある社会福祉法人を視察しました。同法人は家族でケアができない重い強行の方を受け入れたのをきっかけに、社会福祉士や臨床心理士など専門家によるチームで支援し向き合っています。同法人では日中一時支援の他、グループホームでも受け入れていますが、強行の方が落ち着けるように、他の利用者が他害の被害に遭わないよう、強行の方の個室への玄関や水回りを別個に設置することで、一人で過ごす時間を選択できるようにしました。その後他害行為がなくなり、現在もその状態が続いています。理事長は、強行の方の行動はつらいことへの防衛的行動であり、人的支援、物理的環境を整え、本人が安全安心と思える環境を作ることで他害行為がなくなる、同法人では、強行の方全員が腕まくりをして、新型コロナのワクチン接種を終えることができたと言われていました。
また、福岡市のある社会福祉法人では、フロアに利用者が行き来できる半個室のブースを設置し、壁は外からの視界が遮られ、立てば外が見える140㎝の高さで、強行の行動が出た方を閉じ込めるのではなく、きついと思った時点で自ら半個室に入って落ち着くことができます。そうした環境を整えてからは、強行の行動の一つである大声をあげることが大幅に減少しており、理事長は選択肢があることが大事であると言われていました。
Q2. そこで質問です。強度行動障がいのある方の支援は、その特性を理解した人材による専門的な支援だけでなく、施設や設備などの物理的な環境調整の工夫が状態の安定・改善に有効です。
強度行動障がいの特性から、受け入れを拒む施設がある中で、一人でも多く受け入れができるよう、こうした体制の整備が進む必要があると考えますが、県では、現在、障がい福祉サービス事業所等の人材育成や強度行動障がいのある方を入居対象とするグループホームの施設整備について、どのような支援を行っているのか、知事の見解を伺います。
Q3. 強度行動障がいのある方の受け入れに消極的な事業所があるのは、強度行動障がいがどのような状態か正しく理解されておらず、また専門的な支援、環境調整を行って受け入れ、状態の安定・改善につなげている事業所があることがあまり認知されていないためと考えます。
市町村が親からの相談に乗りやすくなり、また受け入れに消極的だった事業所で受け入れの検討が進むよう、県が、支援体制を確立し受け入れている法人等から、実践的な支援方法、施設整備の構造等、改善事例の情報を収集し、市町村や事業所に周知してはどうかと考えますが、知事の見解を求めます。
⑨学校図書館における学校司書の役割について(1207)
次に、学校図書館における学校司書の役割について教育長にお尋ねします。
先日新聞のコラムに、4年生の教室での、物語「一つの花」(今西祐行・作)の授業の様子が書かれていました。作中の、父親がコスモスを渡した時の心理描写について、登場人物の立場に立ち、状況や背景を踏まえれば、行間から父親の気持ちを想像できますが、一部生徒は読み解く力がなく、父親の悪意や欲望を描いた作品だと受け取ってしまうという衝撃的な記事でした。しばしばこの物語の誤読問題が取り上げられており、特例ではないと思われます。
読解力の低下については、OECDのPISA(生徒の学習到達度調査)に参加した当初、PISAショックと呼ばれ、大きな衝撃を与えたが、直近の2018年の調査でも数学が6位、化学が5位に対して、読解力は15位と読解力が長らく低迷しています。
ある校長は、学校現場で見られる子どもの思考力の欠如や珍妙な解釈を、「読解力の低下」という問題だけにとどめてはならず、読解力以前の基礎的能力の低下を危惧されています。
発達心理学の今井むつみ教授は子どもが言葉を育めるようになるかどうかの分岐点について、「誰もが生まれ持って分析力、推論力、学習力を兼ね備えているが、それを発揮させられるかどうかは家庭環境が大きな役割を担っている、親が子に対して話かける言葉の量と質が大きな影響を与える」と指摘しています。
家庭の中で培われる言語能力の低下が言われる中、公立の学校に期待される役割が大きくなっています。現行の学習指導要領の解説では、「言語能力は全ての教科等における資質・能力の育成や学習の基盤となる」と位置付け、各学校において充実が求められる学習活動とされています。子どもたちの言語能力を高めるためには、単に言語を使わせる機会を増やすだけではなく、言葉を使って伝えたいという気持ちや言葉にできる豊かな感情や経験が必要と考えます。
読書は、多くの語彙や多様な表現を通じて様々な世界に触れ、疑似的な体験、知識の習得、新たな考え方に出会うことを可能にするものであり、言語能力を向上させる重要な活動の一つです。ソサエティ5.0時代に、福岡県でも児童生徒に一人1台タブレットが配布されました。ICT化と両輪で紙媒体の本に触れることが重要であり、学校図書館は言語能力だけでなく情報活用能力を育む上でその役割は大きくなっています。課題は子どもたちと本を結ぶ橋渡し役として、学校図書館を支える学校司書が配置され、機能し、役割を果たせるようにすることです。
そこで教育長に伺います。
Q1子どもたちの読書を促すためには、学校図書館の充実が欠かせません。学校図書館を充実させるために必要な専門的・技術的職務に従事するのが学校司書です。学校司書の果たす役割についてどのように認識しているのか、教育長の見解を求めます。
Q2本県の公立小中学校の中には、学校司書が常駐する学校、複数の学校を兼務し、本来の役割が果たせていない学校、配置していない学校もあると聞いています。宇美町では「図書館を使った調べる学習コンクール」を独自に実施し、子どもたちの図書館利用を推進しつつ、町内の5小学校、3中学校に1人ずつ司書を置き、毎月、調べ学習に役立つ本などについて情報交換するなど先進的に取り組む市町もあります。県教委では司書の配置が進むようどのように取り組んでいるのか、教育長の見解を求めます。
⑩フィッシング対策について
次に、フィッシング対策についてお尋ねします。
一昨年6月の定例県議会のわが会派の代表質問で、新型コロナに関連した詐欺対策について質したところ、警察本部長から、「県内では、実在する宅配事業者や携帯電話事業者、金融機関等を装って電子メール等を送り、受信者を偽のウェブサイトに誘導し、ID、パスワード、クレジットカード番号等を読み取る、いわゆるフィッシング詐欺に関連する相談が増加傾向」にあるとの認識を示し、「県警察のホームページ内に、フィッシング詐欺に関する情報提供専用フォームを開設し、一般の方から提供を受けた情報を分析した上で、偽サイトに対するより迅速、効果的な捜査活動はもとより、被害の未然防止を目的とした犯行手口のタイムリーな情報発信などの取組を実施しているところ」であるとの答弁がありました。
いまだに偽メールが横行しており、後を絶ちません。コロナ禍にあって、クレジットカードの利用は増加傾向にあるようです。経済産業省は、キャッシュレス決済比率を2025年までに4割程度、将来的には世界最高水準の80%まで上昇させることを目指し、キャッシュレス決済の推進に取り組んでいますが、昨年のキャッシュレス決済比率は32.5%となり年々増加しています。また、その内訳は、クレジットカードが27.7%と大部分を占め、今後、こうした状況に伴う詐欺被害の拡大が心配されます。クレジットカードの不正利用等の詐欺被害を未然に防ぐためには、その入口となるフィッシング対策の強化が求められます。
そこで、警察本部長にお聞きします。
まず、本県に寄せられているフィッシングに関する相談の状況はどのようになっているのでしょか?具体的な相談件数の推移と相談内容等の傾向についてご教示願います。
次に、今後も、社会情勢に応じた様々な手口によりフィッシング行為の増加が懸念されるとともに、キャッシュレス決済を推進するにあたり、フィッシングを入口としたクレジットカードの不正利用等の詐欺を未然に防ぐため、フィッシング対策の強化は重要であると考えますが、本県の現状を踏まえた今後の対策をどのように進めていくのか、警察本部長のご所見をお尋ねします。
答弁骨子
二-①
問 ジェンダーギャップ解消へ向けた本県の取組について
○ 県では、令和3年3月に策定した第5次男女共同参画計画に基づき、
・働く場や地域・家庭・社会活動において男女がともに活躍できる社会の実現
・女性等に対する暴力の根絶など誰もが安全・安心に暮らせる社会の実現
・男女共同参画社会の実現に向けた意識改革・教育の推進
の3つの柱のもと、施策を推進している。
○ 計画においては、女性の就業率や性別役割分担に賛成しない人の割合など、23の成果指標を設定し、
・働く場における女性の活躍推進や仕事と生活の両立のための働き方改革の推進
・自治会等地域コミュニティの運営における男女共同参画の推進
・DVなどの暴力被害や貧困などの生活上の困難に直面している方々への支援
・性別役割分担意識の解消や性の多様性に関する理解の促進
などに取り組んでいるところである。
二-②
問 男女間の賃金格差についての原因分析とその解消に向けた施策について
○ 本県の雇用者に占める非正規雇用の割合は、平成29年度調査で、男性が約2割であるのに対し、女性は5割を超えている。
女性の就業継続率は、平成27年から令和元年の間で結婚または出産した女性を対象とする全国調査では、結婚前後で約8割、第一子出産前後で約7割となっている。
○ 男女間の賃金格差は、男性に比べて女性は、①非正規雇用に占める割合が高いこと、②平均勤続年数が短いこと、③管理職比率が低いことが原因とされており、これらの解消が課題と考える。
○ このため、「正規雇用促進企業支援センター」において、県内企業への正社員採用の働きかけや企業内での非正規から正規雇用への転換に向けたアドバイスを行うとともに、「子育て女性就職支援センター」において、正規雇用を希望する方に対するきめ細かな就職支援などを行っているところである。
○ また、女性が長く働き続けることができるよう、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための取組を宣言・実行する「子育て応援宣言企業」や、自社の働き方の見直しを宣言・実行する「よかばい・かえるばい企業」の登録推進に取り組んでいる。
○ さらに、女性の管理職への登用を促進するため、企業等の幹部候補者を対象とする「トップリーダー育成研修」や、課長・係長・若手といった職務経験に応じた階層別の研修を実施し、女性人材の育成を図っている。
○ 今後も、こうした取組を通じて、結婚や出産などのライフステージが変化しても、女性がキャリアを中断することなく、やりがいをもって働き続けることができるよう就業環境の整備を推進してまいる。
二-③
問 「産後パパ育休」の取得促進のための取組について
○ 令和3年度の子育て応援宣言企業の男性従業員の育児休業取得率は、
21.4%と、前年度から5.2ポイント増加し、年々着実に増加している。
しかしながら、毎年90%台後半で推移している女性の取得率と比べると、低水準に留まっている。
◯ こうした状況を踏まえ、県では、「産後パパ育休」が施行された今年10月から2か月間にわたり、男性の育児休業取得を促進するための動画 「育休のススメ!パパ育フォーラム2022」をYouTubeで配信し、約500名の方に参加いただいた。
その中で、私もサイボウズ株式会社の青野社長と対談を行い、事業主や県民の皆様に対し、男性の育児休業の取得促進を呼びかけた。
◯ また、福岡労働局との共催で、企業の代表者や人事・労務担当者を対象に、今回の育児・介護休業法の改正内容や、育児休業等を取得しようとする男性に対する職場における嫌がらせ、いわゆるパタニティハラスメントの防止についての研修会をWeb上で開催し、135名の方に参加いただいた。
◯ このほか、子育て応援宣言企業のホームページやメルマガを活用し、今回の法改正の内容や、育児休業取得を促進する事業主への助成金について周知を図っているところである。
二-④
問 県庁男性職員の育児休業取得率と「産後パパ育休」の取得促進について
○ 県庁男性職員の育児休業取得率は、令和3年度で36.2%となっており、特定事業主行動計画の目標値である30%を上回った。
○ 男性の育児休業については、更なる取得の促進を図るため、今年8月から、職員への1か月以上の休暇・休業の取得パターンの紹介など、新たな取組を進めている。
これと併せ、今年10月から始まった新たな「産後パパ育休」についても制度の活用を促すため、職員に向けて積極的に周知を図ってきたところである。
○ 具体的には、
・ 男性職員に1か月以上の育児休暇・休業の取得を呼びかけるポスターの中に、「産後パパ育休」の概要を記載し、全所属に掲示するとともに、
・ 「産後パパ育休」も含めた育児休業等の制度改正の概要を分かりやすくまとめたリーフレットを作成し、職員に配付、
・ さらには、出産・育児の際に取得できる休暇等を取りまとめた「仕事と子育ての両立支援ハンドブック」を改訂し、庁内ネットワークを活用して周知を行った。
○ 今後とも、育児休業等の制度周知と取得しやすい環境づくりに努めてまいる。
二-⑤
問 少子化、人口減少に対する決意について
○ 人口動態統計速報によると、今年1月から9月までの全国の出生数は、昨年と比較してマイナス4.9%で、調査開始以来、最も少なかった昨年を下回るペースとなり、松野官房長官は、先月の会見で「危機的状況である」との認識を示された。
県においても、同時期の出生数は、昨年と比較してマイナス3.6%と非常に厳しい状況にあり、少子化に歯止めをかけることは喫緊の課題であると考えている。
○ そのため、先ほど申し上げた、仕事と生活の両立のための働き方改革の推進などジェンダーギャップの解消に向けた取組や、出会い・結婚、出産、育児などそれぞれのライフステージに合わせた施策を、今後ともきめ細かく総合的に行ってまいる。
○ 併せて、人口減少を食い止めるためには、少子化のみならず、就職などによる若者の流出といった社会的な減少にも対処しなければならない。
そのため、中小企業への支援、農林水産業の振興、企業誘致などにより、魅力ある雇用の場をつくるとともに、医療・福祉サービスの充実、地域公共交通の維持・確保、ICTの積極的な活用による教育の充実などに取り組むことが重要である。
○ こうした取組により、住み慣れたところで働く、長く元気に暮らす、子どもを安心して産み育てることができる地域社会づくりを、しっかり進めてまいる。
三-①
問 こども家庭庁設置に伴うこども施策の組織体制について
○ 来年4月施行の「こども基本法」では、こども施策について、新生児期、乳幼児期、学童期、思春期を経ておとなになるまで、心身発達の過程を通じて切れ目なく、こどもの健やかな成長に対する支援を行うことなどが定められている。
このため、こども施策に関わっている保健医療介護部、福祉労働部、人づくり・県民生活部に教育委員会を含め対応を検討してきた。
○ その結果、こども施策を一元的に策定実施する「こども家庭庁」、及び、「こども家庭センター」を設置して住民の皆様に総合的・一体的にこども施策を
提供する市町村のカウンターパートとして、新たな課を福祉労働部に新設し、県内どの地域にあっても、健やかな成長に対する切れ目ない支援が受けられ、こどもの意見が尊重されることを推進することによって、「こどもまんなか社会」を目指したいと考えている。
○ 同課において、福祉労働部内をはじめ数多くの地域の社会資源とのつながりを生かし、医療、保健、福祉、教育、療育等の多分野にわたる「県こども計画」の策定の総合調整や、こどもの貧困問題、家庭・学校以外のこどもの居場所づくりなど、近年のこどもを取り巻く新たな部局横断的な課題にも機動的に対応してまいる。
三-②
問 出産・子育て応援交付金について
○ 本交付金は、市町村が、妊娠届出時と出生届出時にそれぞれ5万円相当の支給を行う「経済的支援」と、妊婦や低年齢期の子育て家庭に、出産・育児等の見通しを立てるための面談や情報提供を行う「伴走型相談支援」を一体として実施する事業に補助するものである。
○ 本交付金に基づく事業により、産後ケア等のサービスを受ける際の経済的負担が軽減されるとともに、支援が必要な妊産婦が、市町村等の相談窓口につながりやすくなり、妊娠期から出産・子育て期まで、面談等による支援を継続的に受けることで、孤立感や不安感が軽減されると考えている。
○ 県としては、市町村に対し、妊娠届出から乳児家庭に全戸訪問するまでの面談実施のイメージや、事業開始前に出産した方等への対応、今後のスケジュール等を分かりやすく示し、事業を速やかに開始できるよう支援してまいる。
四-①
問 特定妊婦の孤立を防ぐ取組について
○ 県では、昨年度から、予期せぬ妊娠に悩む方や経済的困窮等により出産後の養育不安を抱える方などを対象に、相談支援や出産・育児のサポート、一時的な住まいの提供、就労支援等、産前から産後まで継続した支援を行う「特定妊婦等母子支援事業」に取り組んでいる。
○ 具体的には、社会福祉法人が運営する母子生活支援施設に委託して実施しており、施設に配置したコーディネーターが相談対応や必要な支援の検討、児童相談所や市町村などの関係機関との調整等を行うとともに、施設の看護師が出産や子育てを援助し、出産後も母子が安定した生活を送れるよう支援している。
また、在宅での支援が必要な方については、コーディネーターや看護師がご自宅まで伺う、アウトリーチでの支援を行っているほか、住まいの提供が必要な場合は出産前であっても施設への入所が可能となっている。
○ 今年度からは、実施箇所を1か所から2か所に増やしており、事業の拡充を図っているところである。
四-②
問 支援を必要とする妊婦の方への取組について
○ 市町村では、母子保健担当部署が把握した特定妊婦について、要保護児童対策地域協議会で協議、進捗管理を行いながら、それぞれの妊婦の状況に応じて、家庭訪問による相談支援や家事・育児の援助など、必要な支援に取り組んでいる。
県では、こうした市町村の取組が適切に行われるよう、児童相談所が実施する市町村担当職員向け研修において、母子保健と児童福祉の連携について助言を行っているところである。
○ また、健診未受診など市町村や医療機関等に繋がっていない方に、先ほどご答弁申し上げた「特定妊婦等母子支援事業」の相談窓口や、妊娠に悩む方の相談窓口「にんしんSOS」の情報を知っていただくことが重要である。
このため、こうした情報を県のホームページや、LINE、インスタグラムといったSNSを活用して、広く県民へお知らせするほか、ミニカードをコンビニや商業施設の女性用トイレに設置し、きめ細かな周知に努めているところである。
四-③
問 強度行動障がいのある方とその家族の実態について
○ 強度行動障がいのある方とは、自らを傷つける、他者に暴力をふるう、物を壊すなどの行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別な配慮や支援が必要であると考えている。
〇 現在、強度行動障がいのある方の人数を把握するための確立された方法がないことから、国において、強度行動障がいのある方の支援に関する検討会を立ち上げ、全国的に把握するためのルールに関する検討が始まっているところである。
〇 ご家族は、常日頃から見守りを行うとともに、そのような行動が起きた場合には、ご本人や周囲の安全を確保しつつ、行動がおさまるようご本人を落ち着かせる必要があり、大変なご負担がかかっていると認識している。
四-④
問 事業所に対する人材育成やグループホームの整備への支援について
〇 県では、事業所の従業者を対象に、平成27年度から、支援者養成研修に取り組み、強度行動障がいのある方に適切な支援を行う人材の育成を図っている。これまでに、約5,800人の方が、この研修を修了した。
〇 グループホームについては、国の整備方針に基づき、県では、強度行動障がいを含む重度障がいのある方を入居対象とするものを、優先的に整備することとしており、その費用の一部を補助している。
四-⑤
問 強度行動障がいの状態が改善した事例の周知について
〇 強度行動障がいのある方への支援には、支援者の高い専門性と、落ち着ける空間の確保などの環境面での配慮が必要である。
〇 御紹介いただいたように、個室に玄関や水回りを設置し、一人で過ごす時間を選択できるようにすることや、半個室をフロアに設置し自ら入って落ち着くことができるようにすることで、他害行為などの危険を伴う行動の回数が減少するなどの事例がある。
〇 今後、専門的な支援に取り組んでいる事業所から対応事例を収集し、支援者養成研修の教材に追加するとともに、市町村担当課長会議や事業所に対する集団指導において周知してまいる。
五-①
問 学校司書の役割について(教育長答弁)
○ 学校図書館は、子どもたちが本に親しむ最も身近な場所であり、読書を通して、情報を得たり、学習を深めたりする機能を有している。
学校司書は、司書教諭等と共に、児童生徒が進んで学校図書館を訪れたくなるような環境づくりや、児童生徒や教員の学習情報ニーズへの対応、授業に役立つ資料の整備などを通して、こうした学校図書館の機能を向上させる役割を担っているものと認識している。
五-②
問 学校司書の配置の促進について(教育長答弁)
○ 国において策定された、第6次「学校図書館図書整備等5か年計画」には、学校図書館法において学校司書の配置が努力義務とされていることを踏まえ、学校司書の配置の推進を図ることが示されている。
これに基づき、市町村に対しては地方財政措置が講じられており、県教育委員会においても毎年これを周知しているところである。
また、県教育センターの研修において、学校司書との連携による充実した図書館活動の事例を紹介しており、これらの取組を通して、学校司書の配置促進に努めてまいる。
六-①
問 フィッシングに関する相談件数の推移及び相談内容等の傾向について(警察本部長答弁)
○ フィッシングの相談件数については、令和2年は1,153件、令和3年は2,011件、令和4年10月末現在では、前年同期比プラス297件の1,695件と増加傾向にある。
○ 県民から寄せられるフィッシングの相談内容等については、通信事業者、通信販売事業者やクレジットカード会社などを装った手口に関するものが多く、また、最近では、国税庁などを装う新たなものも見られるところである。
六-②
問 本県の現状を踏まえた今後の対策について(警察本部長答弁)
○ 県警察においては、県民から寄せられた相談や独自に開発したシステム等を活用して、フィッシングや偽サイトに関する情報について分析を行い、県警察のホームページやツイッターなどを活用して、タイムリーに注意喚起を行っているところである。
○ 把握した偽サイトの情報については、警察庁を通じてウィルス対策ソフト事業者に提供しており、同事業者を通じ、その偽サイトを閲覧しようとする利用者に警告を表示して注意を促している。
○ また、県内の学術機関とフィッシングに関する調査・研究を実施するなど、産学機関と連携した取組を行っているところである。
○ 県警察としては、引き続き、社会情勢と共に変化する手口を的確に把握した上で、各種対策を推進してまいる。