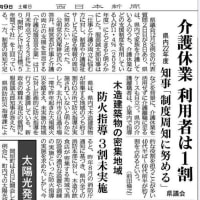新型コロナを機にオンライン授業に取り組む中で、今まで様々な障害があり取り組めなかったことが実現した中学校を視察、オンライン学習を活用した不登校児童生徒への学習支援について質問しました。県教委からは、不登校児童生徒に対してオンライン学習を行うことは、プリント等による家庭学習と比べ、学習内容に封する理解の深まりや、授業ならではの臨場感による学習意欲の高まりが期待できる。県教育委員会としては、学校教育のICT化を推進する中で、不登校児童生徒等に対する新たな学習支援策としてのICT活用についても研究していくとの答弁がありました。
オンライン等を活用した不登校児童生徒への学習支援について(令和2年10月6日)
公明党 大塚勝利 ※義務教委課長、施設課長、副教育長の答弁は要旨です。
(大塚委員)
新型コロナにより臨時休業が長期に及び、教育課程の再編成や、感染予防しながらの学習活動の実施など学校現場では新たな対応に取り組まれているところです。一方、新型コロナを機にオンライン授業に取り組む中で、今まで様々な障害があり取り組めなかったことが実現した学校があります。
まず、本県の小学校、中学校で、基礎疾患を抱えている等で新型コロナを理由に登校していない児童生徒数、及び不登校の児童生徒数をお聞きします。
(義務教育課長)
県域の公立小中学校において、新型コロナウイルス感染症への不安や家族に病弱な者が居るなどの理由で30日以上登校していない児童生徒数は、 7月末現在では、中学生8名である。なお、小学生では該当がない。また、県域の公立小中学校における不登校児童生徒数は、平成31年3月末時点において、公立小中学校で7,215人である。
(大塚委員)
極めて深刻な状況です。
さて、学校になじめない不登校の子どもたちへの新たな学習支援策として取り組みを始めた学校を紹介します。福岡市東区の福岡市立青葉中学校では、学校再開後の6月初めオンライン授業の開始をきっかけに、今まで学校までは登校できるもののそれぞれの理由で教室に入ることができない校内適応指導教室で学ぶ生徒9名にオンライン授業を始めました。その結果、「学習を受けることで生活のリズムができた。」「一緒に授業を受けている感覚で、先生が声をかけてくれてうれしい。」「教室で受けてみようと思った。」との感想が寄せられたそうです。現在、同校では不登校の生徒、家庭にも意向調査を実施しオンライン授業を行う方針です。相良校長は「生徒ごとに得意、不得意な学習環境は異なる。学び方の選択肢を増やし、生徒の主体的な学びにつなげていきたい。誰一人取り残さない。」と話されていました。
福岡市は当初オンライン授業を、新型コロナを理由に欠席した児童生徒に限定して行っていましたが、青葉中が不登校生徒へ運用を開始したことで、福岡市では不登校生徒にも運用を認めたと聞いています。
福岡市では9/1の時点で新型コロナを理由に登校していない児童生徒 321人中、希望者全員の93人、不登校などその他の理由で登校していない児童生徒3754人のうち、45人がオンライン授業を受けたと聞いています。
そこで質問です。新型コロナを理由に登校できない児童生徒や、不登校の児童生徒にオンライン授業を活用することは学びの保障の可能性を広げます。本県ではそのような事例はあるのか。新たな学習支援策として県教委はどのようにお考えか、伺います。
(義務教育課長)
県域の市町村において新型コロナウイルス感染症への不安等を理由に登校できない、または不登校の児童生徒に対して、様々な工夫がなされていると考えるがヽ具体的なオンライン学習の具体的な実践については現時点では把握していない。
しかしながら、それらの児童生徒や、病気等の何らかの理由で学校に来られない児童生徒に対してオンライン学習を行うことは、プリント等による家庭学習と比べ、学習内容に封する理解の深まりや、授業ならではの臨場感による学習意欲の高まりが期待できると考える。県教育委員会としては、学校教育のICT化を推進する中で、不登校児童生徒等に対する新たな学習支援策としてのICT活用についても研究してまいる。
(大塚委員)
先進事例を調査するとともに、是非、進めていただきたい。青葉中学校で話を伺う中で、家から出られない、登校できるが教室に入れない不登校の児童生徒に対応する教育相談コーディネーターすなわち不登校対応専属の教員の役割が大変に重要であると痛感したところです。本県の配置状況とその役割をお聞きします。
(義務教育課長)県域の公立小中学校においては、不登校封応専属の教員配置は行っていないが、各学校においては性t指導担当教員や養護教諭等を教育担当者として位置付けている。
担当者は、個々の児童生徒が不登校になったきっかけや児童生徒と信頼関係のある教員などを整理し、支援方法等の立案や、教員の役害J分担、スクールカウンセラー等の専門スタッフと連携した教育相談の実施等、学校が組織的。計画的に対応するための総合調整を行っている。
(大塚委員)
福岡市では69名全中学校ブロックに専属の教員が配置されています。本県では職務を分掌して対応されているとのことですが、先ほど不登校の児童生徒数の報告がありましたが、対応状況の検証をすすめていただくよう要望しておきます。
学校現場で話を聞いて、不登校児童生徒の中には、学校への復帰を望んでいるにもかかわらず、不登校であることによる学習の遅れなどが、学校への復帰の妨げになっている児童生徒や、独学で懸命に努力を続けている児童生徒もいるようです。
不登校の理由はそれぞれですが、学ぶ意欲のある不登校の児童生徒を最大限にバックアップすべきです。オンラインの状況が整備されていない学校においては新型コロナを理由に登校しない児童生徒、不登校の児童生徒に現在、どのような学習支援を行っているのか、伺います。
(義務教育課長)
各学校においては、学級担任や児童生徒と信頼関係のある教員が、定期的な家庭訪問を通して、授業で使用した教材や家庭学習課題を届けて必要に応じて丁寧に説明や点検を行いながら学習支援を行っている。
(大塚委員)
家庭訪問で児童生徒に直接会うことは重要と考えます。
さて、一昨年の決算特別委員会で私は小児がん等長期入院する高校生に学習支援について質問したところ、生徒のニーズに応じて多様な学習機会を提供できるよう、ICTを活用した学習など、より適切な支援のあり方について研究をしていくとの答弁がありました。昨年度から県立高校ではクラッシーなどの教材の活用が開始され、実際に長期入院の生徒が学習していると聞いています。新型コロナを理由に登校していない児童生徒、不登校の児童生徒に対しても教材の活用を検討されては如何でしょうか。
(義務教育課長)
新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休業中の家庭学習においては、その時点においては環境整備が不十分だったこともあり、学習ソフトやアプリケーションを活用した学校は極めて少ない状況だった。
今後、GIGAスクール構想による環境整備により、個別最適化された学習の充実等、授業の高度化が期待されることから、県教育委員会としては、児童生徒の学習の習熟度に応じたドリル教材の活用について研究を行うこととしている。その成果を市町村教育委員会に周知するとともに、不登校の児童生徒への活用についても研究してまいる。
(大塚委員)
是非進めていただきたい
教室での授業に加え、オンライン授業の活用は学習の機会を広げます。今後、不登校のみならず、長期入院の児童生徒、新型コロナで陽性または家族が感染し登校できない児童生徒、自然災害により登校ができない児童生徒の学びを止めないために、学習支援の新たな選択肢としてオンラインを活用できるよう、必要最低限のICT環境整備を急ぐべきだが県教委の方針をお聞きします。
(施設課長)
市町村小中学校の1人1台端末については、今年度中にすべての市町村において整備される見通しとなっている。これとあわせて、各市町村においては、再び臨時休業となった場合のオンライン学習に備える為、通信環境が整っていない家庭に貸与するためのモバイルルータ等の整備や検討が進められている状況である。県教育委員会としては、今後とも機会あるごとに、必要な環境が整備されるよう、市町村教育委員会に促してまいる。
(大塚委員)
ご答弁の通り、本県の小中学校において不登校は深刻な状況が続いています。こうした中で、不登校児童生徒に対する新たな学習支援策としてICTの活用について研究する、学習の習熟度に応じたドリル教材の活用について、また不登校児童生徒への活用についても研究してまいると答弁がありました。
ご紹介した通り、福岡市では不登校の児童生徒にオンライン授業を開始し田学校があります。県内で市町村によって隔てなく、県内全ての小中学校で、不登校児童生徒に新たな学習支援策としてオンライン授業が実施できるように速やかに取り組むことについて、副教育長の決意をお願いします。
(副教育長)
オンライン等を活用した不登校児童生徒への学習支援につきましては、不登校児童生徒の学習等に対する意欲を高め、一人ひとりの学習保障のために有効な方法に一つと考えます。
県と致しましては、学校教育のICT化推進の中で、児童生徒の個別最適化された学習の充実を図るとともに、不登校児童瀬戸などに対する学びの保障としての活用について研究を行ってまいりたいと考えております。
(大塚委員)
実際に中学校で取り組みをお聞きし、ICT化の推進と言っても、不登校児童生徒の対応については、Wifi環境とカメラ付きPCに、Zoomを設定するだけで決して難しいものではなく、通信環境が整っていない家庭に貸与する機器の問題だけです。先ほど検討が進められているとの答弁でした。
資料など作成する必要もなく、授業を映すだけです。あとは不登校児童生徒が希望するか否かの判断だけです。
あとは学校長のやる気、熱意です。
速やかに遠隔授業のモデルケースを提示し、小中学校が取り組みを開始できるよう重ねて要望し質問を終わります。
オンライン等を活用した不登校児童生徒への学習支援について(令和2年10月6日)
公明党 大塚勝利 ※義務教委課長、施設課長、副教育長の答弁は要旨です。
(大塚委員)
新型コロナにより臨時休業が長期に及び、教育課程の再編成や、感染予防しながらの学習活動の実施など学校現場では新たな対応に取り組まれているところです。一方、新型コロナを機にオンライン授業に取り組む中で、今まで様々な障害があり取り組めなかったことが実現した学校があります。
まず、本県の小学校、中学校で、基礎疾患を抱えている等で新型コロナを理由に登校していない児童生徒数、及び不登校の児童生徒数をお聞きします。
(義務教育課長)
県域の公立小中学校において、新型コロナウイルス感染症への不安や家族に病弱な者が居るなどの理由で30日以上登校していない児童生徒数は、 7月末現在では、中学生8名である。なお、小学生では該当がない。また、県域の公立小中学校における不登校児童生徒数は、平成31年3月末時点において、公立小中学校で7,215人である。
(大塚委員)
極めて深刻な状況です。
さて、学校になじめない不登校の子どもたちへの新たな学習支援策として取り組みを始めた学校を紹介します。福岡市東区の福岡市立青葉中学校では、学校再開後の6月初めオンライン授業の開始をきっかけに、今まで学校までは登校できるもののそれぞれの理由で教室に入ることができない校内適応指導教室で学ぶ生徒9名にオンライン授業を始めました。その結果、「学習を受けることで生活のリズムができた。」「一緒に授業を受けている感覚で、先生が声をかけてくれてうれしい。」「教室で受けてみようと思った。」との感想が寄せられたそうです。現在、同校では不登校の生徒、家庭にも意向調査を実施しオンライン授業を行う方針です。相良校長は「生徒ごとに得意、不得意な学習環境は異なる。学び方の選択肢を増やし、生徒の主体的な学びにつなげていきたい。誰一人取り残さない。」と話されていました。
福岡市は当初オンライン授業を、新型コロナを理由に欠席した児童生徒に限定して行っていましたが、青葉中が不登校生徒へ運用を開始したことで、福岡市では不登校生徒にも運用を認めたと聞いています。
福岡市では9/1の時点で新型コロナを理由に登校していない児童生徒 321人中、希望者全員の93人、不登校などその他の理由で登校していない児童生徒3754人のうち、45人がオンライン授業を受けたと聞いています。
そこで質問です。新型コロナを理由に登校できない児童生徒や、不登校の児童生徒にオンライン授業を活用することは学びの保障の可能性を広げます。本県ではそのような事例はあるのか。新たな学習支援策として県教委はどのようにお考えか、伺います。
(義務教育課長)
県域の市町村において新型コロナウイルス感染症への不安等を理由に登校できない、または不登校の児童生徒に対して、様々な工夫がなされていると考えるがヽ具体的なオンライン学習の具体的な実践については現時点では把握していない。
しかしながら、それらの児童生徒や、病気等の何らかの理由で学校に来られない児童生徒に対してオンライン学習を行うことは、プリント等による家庭学習と比べ、学習内容に封する理解の深まりや、授業ならではの臨場感による学習意欲の高まりが期待できると考える。県教育委員会としては、学校教育のICT化を推進する中で、不登校児童生徒等に対する新たな学習支援策としてのICT活用についても研究してまいる。
(大塚委員)
先進事例を調査するとともに、是非、進めていただきたい。青葉中学校で話を伺う中で、家から出られない、登校できるが教室に入れない不登校の児童生徒に対応する教育相談コーディネーターすなわち不登校対応専属の教員の役割が大変に重要であると痛感したところです。本県の配置状況とその役割をお聞きします。
(義務教育課長)県域の公立小中学校においては、不登校封応専属の教員配置は行っていないが、各学校においては性t指導担当教員や養護教諭等を教育担当者として位置付けている。
担当者は、個々の児童生徒が不登校になったきっかけや児童生徒と信頼関係のある教員などを整理し、支援方法等の立案や、教員の役害J分担、スクールカウンセラー等の専門スタッフと連携した教育相談の実施等、学校が組織的。計画的に対応するための総合調整を行っている。
(大塚委員)
福岡市では69名全中学校ブロックに専属の教員が配置されています。本県では職務を分掌して対応されているとのことですが、先ほど不登校の児童生徒数の報告がありましたが、対応状況の検証をすすめていただくよう要望しておきます。
学校現場で話を聞いて、不登校児童生徒の中には、学校への復帰を望んでいるにもかかわらず、不登校であることによる学習の遅れなどが、学校への復帰の妨げになっている児童生徒や、独学で懸命に努力を続けている児童生徒もいるようです。
不登校の理由はそれぞれですが、学ぶ意欲のある不登校の児童生徒を最大限にバックアップすべきです。オンラインの状況が整備されていない学校においては新型コロナを理由に登校しない児童生徒、不登校の児童生徒に現在、どのような学習支援を行っているのか、伺います。
(義務教育課長)
各学校においては、学級担任や児童生徒と信頼関係のある教員が、定期的な家庭訪問を通して、授業で使用した教材や家庭学習課題を届けて必要に応じて丁寧に説明や点検を行いながら学習支援を行っている。
(大塚委員)
家庭訪問で児童生徒に直接会うことは重要と考えます。
さて、一昨年の決算特別委員会で私は小児がん等長期入院する高校生に学習支援について質問したところ、生徒のニーズに応じて多様な学習機会を提供できるよう、ICTを活用した学習など、より適切な支援のあり方について研究をしていくとの答弁がありました。昨年度から県立高校ではクラッシーなどの教材の活用が開始され、実際に長期入院の生徒が学習していると聞いています。新型コロナを理由に登校していない児童生徒、不登校の児童生徒に対しても教材の活用を検討されては如何でしょうか。
(義務教育課長)
新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休業中の家庭学習においては、その時点においては環境整備が不十分だったこともあり、学習ソフトやアプリケーションを活用した学校は極めて少ない状況だった。
今後、GIGAスクール構想による環境整備により、個別最適化された学習の充実等、授業の高度化が期待されることから、県教育委員会としては、児童生徒の学習の習熟度に応じたドリル教材の活用について研究を行うこととしている。その成果を市町村教育委員会に周知するとともに、不登校の児童生徒への活用についても研究してまいる。
(大塚委員)
是非進めていただきたい
教室での授業に加え、オンライン授業の活用は学習の機会を広げます。今後、不登校のみならず、長期入院の児童生徒、新型コロナで陽性または家族が感染し登校できない児童生徒、自然災害により登校ができない児童生徒の学びを止めないために、学習支援の新たな選択肢としてオンラインを活用できるよう、必要最低限のICT環境整備を急ぐべきだが県教委の方針をお聞きします。
(施設課長)
市町村小中学校の1人1台端末については、今年度中にすべての市町村において整備される見通しとなっている。これとあわせて、各市町村においては、再び臨時休業となった場合のオンライン学習に備える為、通信環境が整っていない家庭に貸与するためのモバイルルータ等の整備や検討が進められている状況である。県教育委員会としては、今後とも機会あるごとに、必要な環境が整備されるよう、市町村教育委員会に促してまいる。
(大塚委員)
ご答弁の通り、本県の小中学校において不登校は深刻な状況が続いています。こうした中で、不登校児童生徒に対する新たな学習支援策としてICTの活用について研究する、学習の習熟度に応じたドリル教材の活用について、また不登校児童生徒への活用についても研究してまいると答弁がありました。
ご紹介した通り、福岡市では不登校の児童生徒にオンライン授業を開始し田学校があります。県内で市町村によって隔てなく、県内全ての小中学校で、不登校児童生徒に新たな学習支援策としてオンライン授業が実施できるように速やかに取り組むことについて、副教育長の決意をお願いします。
(副教育長)
オンライン等を活用した不登校児童生徒への学習支援につきましては、不登校児童生徒の学習等に対する意欲を高め、一人ひとりの学習保障のために有効な方法に一つと考えます。
県と致しましては、学校教育のICT化推進の中で、児童生徒の個別最適化された学習の充実を図るとともに、不登校児童瀬戸などに対する学びの保障としての活用について研究を行ってまいりたいと考えております。
(大塚委員)
実際に中学校で取り組みをお聞きし、ICT化の推進と言っても、不登校児童生徒の対応については、Wifi環境とカメラ付きPCに、Zoomを設定するだけで決して難しいものではなく、通信環境が整っていない家庭に貸与する機器の問題だけです。先ほど検討が進められているとの答弁でした。
資料など作成する必要もなく、授業を映すだけです。あとは不登校児童生徒が希望するか否かの判断だけです。
あとは学校長のやる気、熱意です。
速やかに遠隔授業のモデルケースを提示し、小中学校が取り組みを開始できるよう重ねて要望し質問を終わります。