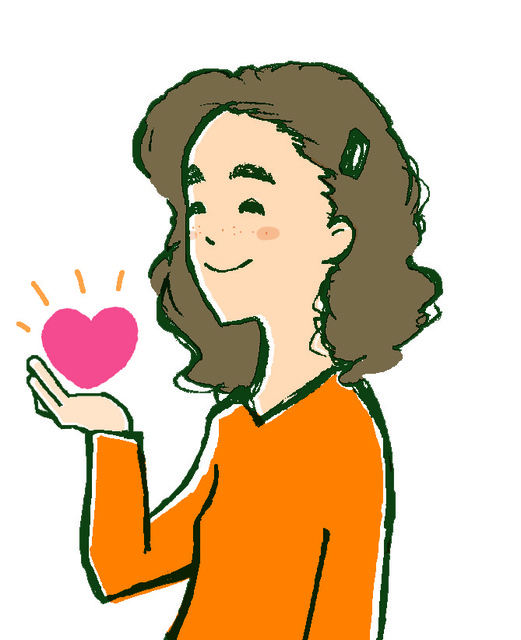ハマリングの目的概念に反対する人が、
「目的に反する自然の出来事もいっぱいあるじゃないか」と、
有象無象の例を山盛り集めて、
あらゆる場面で自然が示す「目的に叶う世界」に
当てはまらないものもあるじゃないか
と、反論をするのも、同じように愚かしい。
※
短い段落ですが。
自然に目的なんてないよ、と言いたくて、
自然がある一定の法則を持って成り立っていること
それ自体を否定する人もおろかだ、と。 . . . 本文を読む
ハマリングの言葉が続きます。
「人の体の一節(関節ひとつ、爪ひとつ)を決めるのは、
関節や爪についての宙に浮いた考えではなく、
もっと大きな全体である体との関わりだ。
関節や爪は、まさに体にあって決められている」。
「同じように、草木、動物、人も含め、
ありとあらゆる自然物の形を決めるのは、
ものについての宙に浮いた考えではなく、
もっと大きな目的を持つ宇宙全体、自然全体との関わりで
決められ . . . 本文を読む
考えは、人によってのみ、目的にふさわしく実現される。
だから、(神の)理念が人類の歴史によって実現していく、
と言うような言い方はふさわしくない。
歴史を捉えるのに
「自由に向かう人間の進化だ」とか、
「倫理的な秩序が実現していく過程だ」などという言い方も、
一元論の観点からは、認められない。
「(歴史や神の)目的」という考えを指示する人たちは、
「目的」という考えを捨てたら、
「世の秩序や . . . 本文を読む
一元論は、人の行動だけに目的を認める。
一元論は、自然の法則は探るけど、自然の目的は探らない。
「自然の目的」という考えは、人に見えない力と同じように、
人間が勝手に思い設けたものだ。
しかし、一元論の観点では、人が生きる目的も、
本人が設定したものでなければ認められない。
なぜなら、自分が何かをかなえるために行動するなら、
その何かを設定するのは自分しかできない。
モノにたとえると分かりやす . . . 本文を読む
覚えられるものだけを現実だと認める素朴実在論者の意識は、
繰り返して言うように、考えでしかとらえられないところを
覚えに仕立てようとする。
覚えられることについて、覚えられる関わりを求める。
と言っても、考えで覚えと覚えをつなぐのではなくて、
その関わりを夢の世界にかぶせ、勝手にストーリー立てる。
自分の行動の原因には目的というものがある、という考えが、
こんなふうに、人間以外のものにも目的 . . . 本文を読む
原因と結果に分かれる課程のうちに、
覚えと考えが区別される。
原因の覚えは、結果の覚えに先立つ。
原因と結果は、私たちがふさわしく考えて、
原因と結果を結ぶ因果関係を結びつけることをしない限り、
並列してバラバラにあるだけだ。
結果の覚えは、原因の覚えの後に起こる。
その反対、
結果が先にあって、それが原因に働きかけるとしたら、
それは、考えがその二つを媒介しているからだ。
そもそも、結果 . . . 本文を読む
人間の精神生活にさまざまな流れがある中、
ひとつ、この流れを追ってみよう。
言うならば、
「目的という考えが似合わない域がある」
ということについてだ。
目的に合うことは、
連続する現象(雨が降る→ぬかるむ→乾く→地面が固まる)
(おなかがすく→冷蔵庫を開ける→何かつまむ→満たされる)
の中の、ある特定の続き方のことだ。
目的に合うことが真実であるのは、
因果の関わりの中で、
因が果を決める( . . . 本文を読む
11章のタイトルは
「世の目的と生きる目的~人たるの定め」。
この章では、
世に目的はあるのか。
自然物や人に生きる目的はあるのか。
人である定めとはどういうものなのか、
を見ていきます。
生きる目的。
それは…いろいろありますが、
私なりに1本筋を通すなら、
「自分を生かし、周囲とともに幸せになること」
とは思っています。
年齢によって変わってきましたが、
ここ数年は、そんな感じです。
多く . . . 本文を読む
一元論では、次のことを自覚している。
物理なり道徳なりの強制によって行動するのは、
本当のその人の行動ではあり得ない、ということを。
一元論は、
自然のもよおしや本能に従っての行動(ex:おなかすいた)や、
きまりに従ったり、人の言うことを聞いての行動
(ex:誰か答えを教えて)を、
その人(あるいは人類)の成長の、初期段階だと見てとる。
そして、それをやがて、自由な精神が越えていくことも見抜く . . . 本文を読む
一元論は、知っている。
自然は、人を自由な精神に仕上げて
完成形にしてから、手放すのではなく、
一定の次元にまで導いた段階で、手放す。
そこから人は、
まだまだ、不自由な者として成長を続けながら、
だんだん「自分自身とはこれだ!」と
自分を見いだすところに至る。
※
自然は、
人が幼い頃には、親をあてがって世話をさせ、
大きくなってからも20歳くらいまでは、
人の成長を見守るようにしてくれる。 . . . 本文を読む
一元論は、つまり、
「人が行動する」ということにおいて、
本当に「自由の哲学」だ。
一元論は、現実的な哲学だから、
自由な精神を縛る、
形而上実在論の「高い存在」とかいう
現実には思い設けることでしかわからない存在を認めず
また、素朴実在論の人を縛る
「物理的な制約」という存在も認めない。
しかし、成長していく上での、
素朴で現実的な制約があることは認める。
一元論は、「人は今あるままの状態で . . . 本文を読む
そもそも考えの世は、
学校や会社、地域や社会などというグループの中に
固定されてあるのではなく、
人ひとりひとりの中に出てきて、生き生きと生まれ育つ。
グループが向かう方向は、
まずは、人それぞれ、一人ひとりが
欲して行動する結果として出てくる。
でも、現実は、少数のエリートたちの決めた結果なんだけど。
なぜそうなるかというと、
他の人たちが、自分で考えることをせずに、
権威に従いたいと思うか . . . 本文を読む
単なる想像や推論で成り立っている形而上論が、
高い世界(神とか)から生まれた結果だと見なす「人が動くきまり」。
一元論者にとって「人が動くきまり」は、人の考えから生まれる。
人が動くきまりの秩序は、自然の秩序の単なるコピーでもなく、
人をのけ者にした世界の秩序のコピーでもなくて、
あくまで、人が創っているのだ。
人は、他の誰か・何かの欲するままに動いているのではなく、
自分の欲するままに動 . . . 本文を読む
一元論のとらえるところ、
人のすることには、
「自由なする」と「不自由なする」の両方がある。
人は覚えの世では、自分を不自由な者となるし、
自分の内では、現実に自分が、自由な精神の者となることができる。
※
ここ、短い段落だけど、すごく真理だな~。
物質界に関わってる間は、いつまでも不自由なんだ。
そうそう。他人は思い通りにならないし、
欲しいものが全部買えるわけじゃないし。
だから、精神界 . . . 本文を読む
一元論(自由の哲学はこの立場)も、
部分的には素朴実在論を認める。
つまり、覚えの世の正しさも認めるからだ。
自分の行為の動機を自分の直観で悟れない人は、
それを外から受け取るしかない。
人が自分の行為の原理を外から受け取るなんて、
ホントに不自由だ。
一元論は「考え」にも「覚え」と同じように
現実性を認める。
考えは(集団ではなくて)個人の中に現れうる。
自分の内側から沸きだした考えに沿う . . . 本文を読む