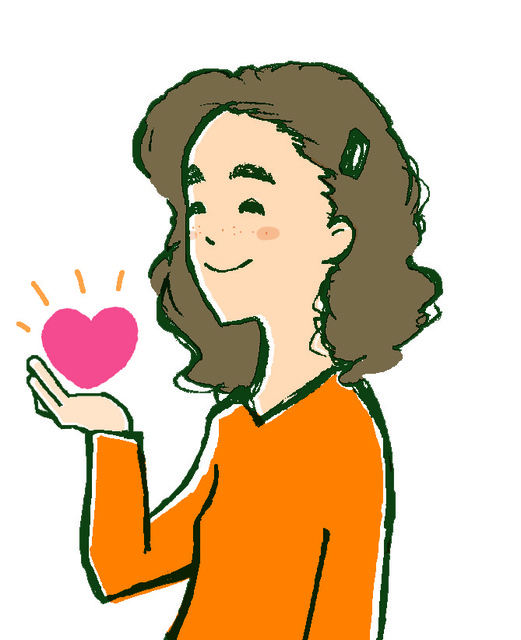素朴実在論者も形而上実在論者も、
「人を必然の原理の実施者か執行者としか見ない」
という、同じ根拠で、自由を否定する。
素朴実在論が自由を否定するのは、
覚えられるものや、そこから派生するものに縛られ、
物質的なものに踊らされているからだ。
その姿勢は最終的には、
あいまいで、何かわからない「良心」という
内面の声の命令に従うことで、自由を否定する。
形而上実在論者は、人間以外の絶対者の存在 . . . 本文を読む
「理性を備えつつ、自ら意識的に動く一人ひとりの側から、
行動の秩序が清く正しく立てられて、はじめて、
世は世の求める“あるべき世”へのゴールに向かえる」
「この現実世界は神が受肉したものだ。
世の移り変わりは、
受肉して現実存在となった神の苦痛の歩みであり、
かつ、生身で十字架にかかった神の救いへの道だ。
そして人の行いは、この神の苦痛と救いとの道のりを、
ともに縮めることになる」
以上2文 . . . 本文を読む
また、たとえば、
神のような絶対的な存在を、現象の後ろに見る人もいます。
そう人ならば、行動への原動力も人ではなくて
何かそういう精神的な絶対的なものの中に求めるでしょう。
そして、
探せば自分の理性の中に見いだせるはずの行動への原動力も、
人に対して特別な働きかけをする
精神ものそのものから生まれたものだ、とするだろう。
そういう二元論者には、人の行動原理が
絶対者(精神・神など)から命じら . . . 本文を読む
自分の外に答えを求める方法はいろいろあります。
それが、素朴実在論で言う、
自分を動かす「覚え」が「覚え」だけで考えを欠き、
ただ、機械的な法則に従って動くものなら、
~たとえば
唯物論(物質こそすべて)の言うブツみたいなものなら~、
たった一人の自分ですら、
それに関わるアレコレと同じように、
単に機械的な法則で動いているに過ぎない。
そこに「自由」の意識は幻想でしかあり得ない。
自分で自 . . . 本文を読む
自分の内なる良心に従う人は、
すでに素朴実在論の次元を越えている。
肉体やその他の何ものからも離れて、
倫理だ毛で成立する次元へと踏み込んでいる。
それはもはや、
倫理が何の担い手も持たずに、
倫理が倫理だけで倫理として成立する
形而上の次元になり変わっている。
その倫理は、
私の体(損得とか欲とか)や、
心(ウキウキや申し訳なさなどの喜怒哀楽)を越えた、
「形而上実在論」における「見えないけ . . . 本文を読む
■自由の哲学10章02段落
素朴実在論者が、
自分の行動の拠り所として至るもっとも高い次元は、
行動原理の拠り所を、外の人や神から切り離して、
自分の内側に絶対の力がある、と思い設ける次元だ。
1段落目で言った「外から聞いた、感官で覚えられる神の声」を
今度は、自分の中に聞き、
それを、良心と同じように捉える。
※
これ、めちゃくちゃわかる。
私は、今コレによく陥ります。
自分がサラッと考 . . . 本文を読む
10章です。タイトルは「自由の哲学と一元論」。
1段落目は、わりとわかりやすい。
目で見えるもの、手でつかめるものだけが現実だとする
素朴実在論者は、
自分が生きて行動する際にも
目で見えるもの、手でつかめるものなどの
「感官で捉えられること」を拠り所にしたがる。
それを感官で捉えられるように立てくれる何者かを求める。
素朴実在論者は、
自分より賢い人、力のある人、自分の上に立つ人などから、 . . . 本文を読む
今年に入ってから、
「続けるかどうか考えさせてください」
と、先生に言われていた、自由の哲学の講座。
この5年間、ずっと身近に感じ、
この本と取り組むことで自分が成長するのを感じながら、
自分一人ではチンプンカンプンで意味不明な本だった。
今、全体の4分の3あたりの真っ最中。
9章になって、やっと「自由とは」という言葉が出てきて、
この章は、特に、読んでいるだけで前向きになれる。
その講座 . . . 本文を読む
神戸シュタイナーハウス、大人クラスでは、
「自由の哲学」の14章~15章を読んだ。
自覚的であろうとすればするほど、
人は孤独になっていく。
自分を意識しないで流されていればいるほど、
人は孤独を感じなくて済む。
…というようなことが自由の哲学の14章に書いてあった。
私は「人よりも孤独を感じやすいタイプ」
だと、自覚はしていたが、
それは、自分が
ウニャウニャと本質を気にする性分なので、
人 . . . 本文を読む
13章、前半後半については、
前回に書きました。
続いて、次の2文
道徳的であるために、自分の本性の欲求を捨て去る必要はない。
道徳性は正しいと認めた目標への努力の中にある。
善と呼ばれるものは、真の人間本性にとって、
為すべき事柄なのではなく、為そうと欲する事柄なのだ。
我慢したり、自分を抑えたりせず、
自分のやりたいことを、きっちりやっていくこと。
それでいい、と。それがい . . . 本文を読む
神戸シュタイナーハウスでの今月の勉強会は、
「自由の哲学」13章でした。
前半は快と不快について。
後半は人生の価値について。
前半。
こういうのは快感で、こういうのは不快、
こうやって快感は計れるよ、
などという例がこれでもかというほど出てくる。
あまりにも懇切丁寧に、畳みかけるように書いてあるので、
「人生の目的は快感だけじゃないんだけどなぁ」と
思わずにはいられなかった。
「じゃあ、人 . . . 本文を読む
この本の書かれた時代背景として(今もわりとそーだけど)、
「自然科学は不動のものである」という前提がある。
水は0度で氷、100度で沸騰する、これは、変わらない。
1+1=2 これも、変わらない。
…という前提がある。
これが、変わらないとしたら、
生きていく中で、周囲のあれこれとの関わり方は
次の二通りしかない。
①いかに
②なぜ、
①の「いかに」という視点で関わることで、
技術をどんど . . . 本文を読む
5章に入り、ますます冴える感覚人。
「あ、いいダジャレ思いついた。“思考は至高だ”どう?」
おお。おやじギャグ系だが、真実だ。
それはさておき。
連綿と続いている精神的なものを、
自然科学がブチブチ切り捨てていることに、
強い違和感を抱いているところが随所に見られる。
「単純な人間は、ただ生きることに没頭して
経験の中で示される通りの事物を真実と考えている」
っていうのは、自分にも思い当た . . . 本文を読む
4章は、いろんな哲学者が登場して、とにかくややこしい。
メンバーの一人が、ちょっと辟易して言った。
「私は自由をこう考えます、って
シンプルに書いてくれたら、それだけでいいのに、
私の考えは、誰とどう違うとかいう細かい批判に、
いちいちつきあうのはしんどい」って。
ごもっとも。
私も、前に読んだ時、ややこしい書き方の論をやっと理解して、
「あ、そっか!私もそうしてる時あるよ」と納得した次の行 . . . 本文を読む
すんごい感覚的な人が、今回の大人クラスの担当。
哲学者の名前がいっぱい出てくるこの章を
その豊かな感覚を駆使して、どんな風に読むのか、
ワクワクでした(^^)。
期待通り、4章を通して読んでどうだったか、の第1声が
「シュタイナーがずっとケンカ売ってて笑えました」だって(^^;)。
続いて、あちこちの文章に触れながら、
「この人のこと、嫌いなのかな」とか、
「ここはイキイキ書いてて楽しそう」と . . . 本文を読む