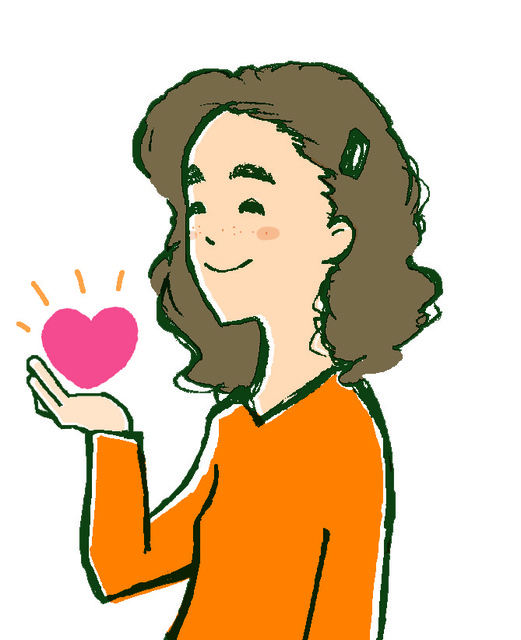自分で悟りを得て見て考えて動くことで、
私たちは私たちの中身を作り出す
(前段階のA→後段階のB)。
生み出した中身を倫理学者が云々するのは、
自然科学者には虫類が与えられるのと同じく、
後段階(=B)として、だ。
は虫類(=B)は原羊膜類(=A)から出てきた。
しかし、自然科学者はAからBを引き出せない。
新しい道徳の考え(後段階B)は前段階Aから出てくる。
ややこしくなってしまうのは、私 . . . 本文を読む
ここで請け合う見解(=倫理の個人主義。
新しいルールは私が作る。人だけはそういう進化をする)は、
普通の進化論(=個ではなく類として進化する)と
食い違うように見えるが、
実際は矛盾しない。矛盾するように見えるだけだ。
「進化」とは、自然法則の道筋で、
前の未熟なものから後のより完成したものが出てくることだ。
進化論者なら次のことを思えるはずだ。
大昔にタイムスリップして早送りで進化を見たとし . . . 本文を読む
道徳をどこかから持ってきたい人は、
道徳を栄養学みたいな意味で捉えている。
栄養学は、食べ物を分析したり人の内臓の動きを観察して
人類共通の法則を引き出し、一人ひとりの体に働きかけようとする。
(パウルゼン:倫理学体系)
でも、私たちが生きて行為するのは、
誰の内臓の動きもだいたい同じ、というのとは比べられない。
内臓の法則は、別に意識しなくても動いているけど、
道徳の法則は、私たちがまず作り出 . . . 本文を読む
5
道徳的に何かをするためには、
そのジャンルに関する知識が欠かせない。
そういう意味で、私たちの行動は、知識に支えられている。
その知識の中でも、自然の法則が大切だ。
自然の科学の知識が必要であって、倫理学が必要なのではない。
6
道徳のファンタジーと道徳の考えの力とは
自由な人から生みなした後で、知識となりえる。
それは、もはや自分の生き方を縛ることはない。
自分が生んだのだから、自分が手 . . . 本文を読む
道徳を元に行為しようとすれば、
道徳の考えの力、道徳のファンタジーに並んで、
この現実の世の自然法則に従って作り替える力も必要となる。
その力が「道徳のテクニック」だ。
それは、勉強が勉強できるのと同じ意味で、勉強できる。
つまり、多くの人は、これまでにない未来の行為を
ファンタジーから生み出して作り出すよりも、
今ある世に沿った考えを見いだす方が得意だ。
だから、道徳のファンタジーを作り出す . . . 本文を読む
道徳のファンタジーは、単に想像力を磨けばいいというものではない。
道徳のファンタジーを実現するためのテクニックとして、
「覚えの領域」が不可欠で、
覚えの領域とがっぷり四つに組み合うことが求められる。
人の行いは覚えをゼロから生み出すのではなく、
すでにある覚えをより良くしていく。
つまり、すでにある覚えに、新しい面を与えるのだ。
世にあるひとつのもの、または集合体を捉え、
それを、自分なりの . . . 本文を読む
人は、ある決まった想いを
自分の考えの世界のまるごとから、
まず、ファンタジーによって生み出す。
よって、自由な精神が自分の考えを現実にし、
自分を立てるのに必要なものは、
道徳のファンタジーだ。
道徳のファンタジーは、自由な精神の行動の源だ。
だから、自分の道徳的な行動を生み出せるのは、
道徳のファンタジーを作り出す人、と言える。
道徳を諭すだけ、倫理を説くばっかりで、
それを自分で厚く濃 . . . 本文を読む
私の行動への動機が、一般的な考えの形
(たとえば、他人に良くする、自分が幸せになるように生きる)
である場合でも、
ひとつずつの行動に、まず、具体的な絵姿
(一般的な考えと、それぞれの覚えとの重なり)が、
まず見いだされなければならない。
すなわち、前例や罰への恐れで動くのではない自由な精神には、
一般的な考えを具体的なそれぞれの想いに描くことが欠かせない。
※
一般的な考えの形というのは、 . . . 本文を読む
決まりは、前向きな行動をうながすよりも、
特定の行動を禁止するのが得意だ。
ふつう、決まりが普遍的な考えとして現れるのは、
「~するな」という場合であって、
「~しなさい」という場合ではない。
「~しなさい」という規則が不自由な精神に命令される場合は、
具体的な形を取る。
「門の前を掃除しなさい」「税金を○○円払いなさい」など。
一方、「~するな」という規則の場合、
「盗むな」「姦淫するな」 . . . 本文を読む
考えと結果の間をつなぐのは、想いだ。
不自由な精神には、覚えも想いも前もって予想されている。
何をするにしても、前例とか、命じられたままに、
前もって予想されている通り、決まった通りに行動する。
だから権威は、過去の例を出すことで、もっと有効に働きかける。
ひとつの前例を取り上げて「ここではこうなっているんです」と
不自由な精神に伝えることで、権威は力を発揮する。
キリスト教徒が、
教義を読 . . . 本文を読む
自由な精神は、自分の志に沿って行動する。
自分が考えている世のまるごと全体の中から、
自分で考えて取り出した悟りに沿って行動する。
不自由な精神は、自分が考えている世の中から、
ある一部の悟りを取り出して、行動の理由にする時、
現実の世ですでに与えられた前例や他人の意見を基にする。
不自由な人は、行動の理由として、
誰かが「こうしたらよかったよ」とか、
神が「こうしなさい」と命じたアレコレを想 . . . 本文を読む
12章に入ります。
その前に。なんでしょ、このタイトル??
鈴木一博さん訳では
「道徳のファンタジー」(ダーウィニズムと倫理)
高橋巌さん訳では
「道徳的想像力」(ダーウィン主義と道徳)
本間英世さん訳では
「倫理的想像力」(ダーウィン主義と倫理)
う~ん、3人3様です。
ここで、「道徳」とか「倫理」とか訳されているのは、
一体、何のことなんでしょうか。
諏訪先生によると、もとの単語は「モラ . . . 本文を読む
二元論は、歴史や世の中、自然の目的を論じます。
周囲を見るにつけ、法則に則った因果関係が出てくるたびに、
二元論者は仮に思うのです。
「私たちは、神(絶対者)が敷いたレールの上を必然的に歩いている」と。
一元論者には、神(絶対者)や、歴史や世の中、自然の目的を、
仮に思い設ける必要がない。
※そうこうするうちに11章が終わりました。
結構短い章だったけど、いいなぁ。
二元論者は、人は必然で . . . 本文を読む
然のモノが外から決まる(宙に浮いた考えだろうが、造物主の中にある理念だろうが)ことを打ち消す者なら、
きっと、自然のものは目的相応ではなく
内からの法則相応に決まると。
私が機械を目的に合わせて作るのは、
私が、そのままではバラバラな各パーツを、
目的にあわせて組み合わせるからだ。
機械が目的に合っているのは、
私が考えた機械の動きを、機械に与えるからだ。
機械は、それで、目的どおりの動きをす . . . 本文を読む
目的に合う、という考えは、何を指すか。
バラバラの覚え(ex:山にあるそれぞれの草木花土動物光水…)が
ひとつにまとまる(ex:六甲山系)ことを、だ。
しかし、覚えという覚えには、
普段は隠されているけれど、
私たちが考えることによって見いだされる「法則」がある。
だから、山の各草木花が計画的にまとまる、というのは、
六甲山系、という考えに見いだされるそれぞれが、
考えとしてまとまっているから . . . 本文を読む