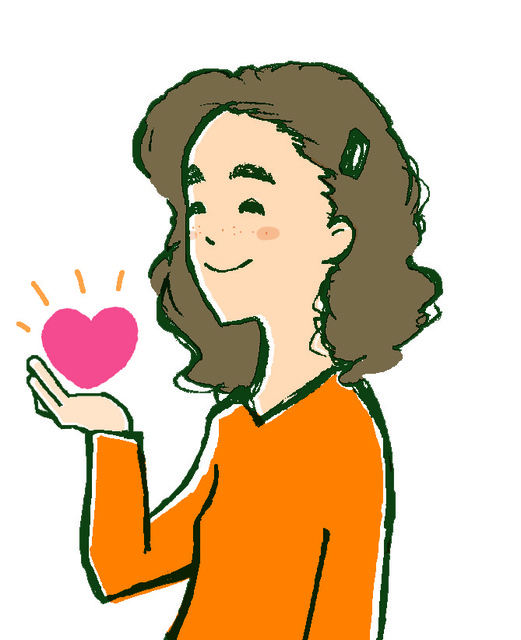■自由の哲学13章40段落
私たちは、何でもいいから快に向かって努力するのではない。
ある特定の欲(おなかがすいた、本が読みたい、など)に向かって、
快を満たそうとする。
だから、他の快がヨコにあっても、
そんなものでは満足できない。
おなかがすいているのに散歩ができるとか、
本が読みたいのに映画に行けるとかでは、満足できない。
快であれば何でもいいなら、それで満足できるはずなのに、
特定の . . . 本文を読む
■自由の哲学13章39段落
私たちの欲は、その都度変わる。
これまで見て来たように、
欲の大きさを分母にして、快の量を分子にし、
分子が大きければ大きいほど、快の値は大きくなるし、
欲の大きさが大きければ、
ガマンできる不快の量も大きくなる。
私たちは、
不快の量を快の量と比べるのではなくて、
欲の大きさと快の量を比べているのだ。
食べるのがとても好きな人なら、
後でおいしいものをよりおい . . . 本文を読む
▼37段落
さて、悲観論者は言うだろう。
おなかがすいているというのは、
「食べたい(欲)に応じて食べられたら
その分快の値が大きくなり、足りなければ不快だ」
というようなレベルの話ではなく、
ひもじさ、苦しさという、もっと切実なものだ、と。
そこには、食べ物のために捨てるプライドや、屈辱、
冬になると食べるものがなくなって飢える獣の苦しみ
などが、例としてあげられるかもしれない。
とにか . . . 本文を読む
快の量が一番嬉しいのは、
欲しかったのと同じだけのものが来た時だ。
小さければ、足りなくて値は小さくなるし、
大きければ、欲しくもない分が余る。
余りも嬉しい、という時は、欲も大きくなっている時だ。
欲がどんどん大きくなるに伴って
快もどんどん大きくなっていくうちはいいが、
バランスが崩れると快が不快になる。
欲しかったはずのものが溢れて、苦しくなる。
快が私たちに何かの値を出すのは、
欲が基 . . . 本文を読む
いくら「欲が大事だ」と言っても、
いつでも求めるだけ得られるわけじゃないから、
欲のせいで喜びが減る時もある。
でも、トータルで楽しみが全部満たされた訳じゃなくても、
欲がちょっとでも満たされた時には、
リアルタイムで見ると、喜びの値は、ちょっとはある。
(たしかに、ある。ゼロではない)。
私たちの欲が大きければ大きいほど、
喜びの値は、小さくなる。
※
いくら全部が満たされなくても、欲があ . . . 本文を読む
■自由の哲学13章34段落_2
前半の論を例示して解説しています。
たとえば、楽しみ(エサ)の量が同じなら、
一匹(一人)の求める量が多ければ多いほど
生きる「快の値」は減る。
これは、すべての生き物に当てはまるだろう。
世界中のあらゆる食べ物を集めて
全ての生物におなかいっぱい食べさせる試みをするとしたら、
生物の数が増えれば増えるほど(みんなで分ければ分けるほど)
おなかいっぱいにはなれ . . . 本文を読む
現代の自然科学の見解では、
餌は少ないのに命はいっぱい生まれるので、
自然は、すべての命を生かすことはできません。
生存競争で負けておなかがすいた生き物は、
苦しみのうちに命を閉じます。
生きている者にしても、飢えている人がいっぱい。
でも、ある時は、飢えておなかがすいていたとしても、
食べられた時の喜びは、小さくならない。
それで、生きる楽しみが邪魔されたりしない。
欲が満たされる時、それ . . . 本文を読む
おなかがすいた、と感じるのは、
体が飢えてちゃんと動けなくなるときだ。
おなかがすいたら、まずおなかを満たそうとするだろう。
満足できるほどたくさん食べたら、
おなかがすいた、というのも満たされるだろう。
おなかを満たす楽しみは、まず、
空きっ腹の苦しみをのぞくことにある。
単純におながかすいたことが満たされると、
次には、おいしいものを食べようとする。
さらには、おなかがすいていても、
も . . . 本文を読む
ここまでは、すべて、
快・不快が生きるの値を決めるという前提だ。
生きることは、生きるに必要なもよおしを合わせて現れる。
生きることが快・不快の値の大きさで決まるなら、
快より不快の方が多いなら生きないだろう。
では、もよおしと快とをもう一度よく見てみよう。
はたして、もよおしが快ではかれるかどうか。
生きることを
「精神の貴族主義」の立場で考えないために
「獣としての生き物」の必要性
= . . . 本文を読む
悲観論者は言う。
人は快を求めても得られないんだから、
存在することに耐えられず、
存在しないことによって救われるというのが、
理性的な答えになるだろう。
加えて、世がこんなにめちゃくちゃなのは、
神が苦しんでいるからだ、という見解に従うなら、
人は神に救いをもたらすのが課題になる。
存在しないこと=自殺が救いだという悲観論者はしかし、
人が自殺してしまっては、
神に救いをもたらすことができな . . . 本文を読む
悲観論を認め、エゴを捨て、
神に仕えることを望むその倫理感は、
本当にわがままを乗り越えるだろうか。
その倫理感に沿って見ると、
人が神に仕えるために自分のエゴをセーブする理由は、
「欲なんて満たされないものだからね」と見抜くからだ。
おいしそうなブドウ(快)を欲しがり、
手が届かない時「すっぱいブドウだ」と見なす。
そして、確かめもせずすっぱいからね、と考えて、
ブドウを欲しがるのをやめ . . . 本文を読む
■自由の哲学13章27~28段落
独自の方法でハルトマンは
不快が快を上回るから人生は宇¥生きる値打ちがない
と言っている。
なのに同時に、生きなければならない、とも。
なぜ、生きなければならないのかというと、
神の重荷を人が肩代わりするために、だ。
人が自分の欲に従っていると、
神の目的に叶う動きはしない。
やがて、経験を重ねるうちに、
自分の欲に従っても快はそれほど大きくない
と、心底 . . . 本文を読む
だが、自殺者の数は
「絶対人生は不快の方が多い」という割には少ない。
また、生きることって不快が多いから、
生きるかどうかを考えるわ、という人も少ない。
多くはたくましく生き続けている。
これはどういうことか。
結論づけられるのは、次の2つ。
1、「不快は快よりも大きい」というのが間違い。
2、生き続ける理由は快・不快と全く関係ない。
※
そうなのよ。
不快なことがあったって、
「今がん . . . 本文を読む
ここに至って、私たちは快不快のどちらが多いかを
理性だけでは決められないことがわかった。
快不快の多寡は、日常生活の中で、
実際に覚える(=見たり感じたりする)ことと
考えることとの重なりの中でわかることだ。
商人が商売をやめるかどうかは、
帳簿が損失を示すからじゃなくて、
実際にお金が回らなくなるからだ。
お金が回ってるなら、帳簿を見直そう。
人が生きる事を商売に例えても同じ事が言える。 . . . 本文を読む
23段落
経常利益が運用資産に合わないなら、
商人は計算間違いをしていることになる。
ならばまた、ひねり出した快・不快が
気持ちのリアリティと合ってないなら、
哲学者は間違った計算をしていることになる。
24段落
理性に添って世を捕らえようとする
悲観論者の会計方法を
私は今、調べ直すつもりはない。
しかし、
生きるという商売をこれからも続けるべきかどうか
決めるはめになった人ならば、
快と不 . . . 本文を読む