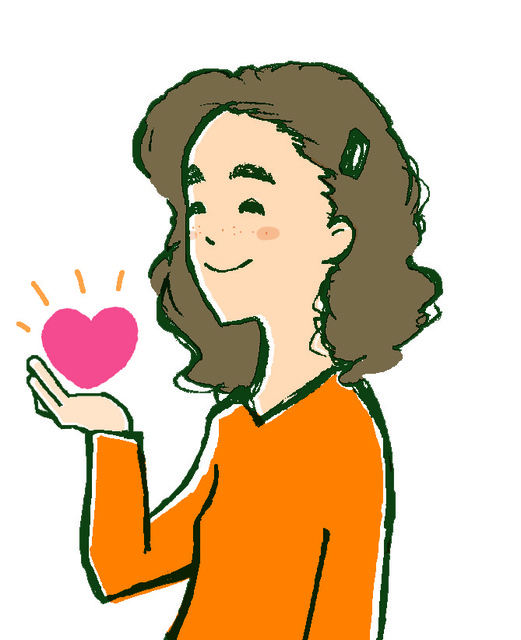「観察(見る)+思考(考える)=認識(知る)」
という法則が述べられています。
哲学者は哲学者なので、
「世界を全部知ることはできるのか」とか、
必要以上にややこしいことを考えます。
でも、ふつーの庶民の私だって、
「見たことに考えを重ねていくことで、世界を知っていくことはできる」、
というシンプルな法則が成り立ちます。
「え、何それ?」と思った時に、
聞いたり見たり考えたりして、ピン!と . . . 本文を読む
「知りたいという衝動は、二元論に由来している」
というのがおもしろい。
自然VS人間、アナタVSワタシ、仏教VSキリスト教、など、
対立概念として捕らえてしまう。
かつてこれらが
「私たち」としてすべて包括できる概念だった時代が
ホントにあったんでしょか??
今、生きている価値観からは信じがたいけど、
そんな時代があったなら、
自分だけエラくなろうとか、
少しでもソンしないようにとか、
エゴ . . . 本文を読む
哲学者の名前がいっぱい出て来るけれど、
すべてを理解しようとするのは早々にあきらめて、
骨子をつかむことに専念~(^^;)。
死ぬほどシンプルに言うと
「考えることは自由へのパスポート」
ということでしょうか。
ただ、シンプルに言えば言うほど
言葉がサラリと流れていくのがはがゆいです。
この言葉の受け止め方や理解の深さ、
ひいては人生の中での生かし方は、
一人ひとりに応じて違った形になる . . . 本文を読む
いつも、頭で理解しようとしてあがく私と違い、
感覚的な発言満載で、堅い本を身近にしてくれるAさん。
今回もフシギ発言の魅力炸裂でした。
1〜3章を読んで、
ここがわからない、ここは大事、ここが好きだった、
などなど、一人ずつ、本に線を引いてきて、
それについて、あーだこーだと
自分の考えや経験を話し合ってた時のこと。
「Aさんはどうですか」とうながされ、
「私、ここにハートマーク . . . 本文を読む
大人の勉強会�(自由の哲学�回目)(神戸シュタイナー)
勉強会の前に、宿題である自由の哲学1〜3段落を読んで、
あれこれ思い出し、ひっかかり、
「こんなにいっぺんに進めるかな」と思いつつ、
勉強会に参加しました。
前回のおさらいで、自由の哲学が書かれた時代までの、
哲学的な流れとして
「観念論」「虚無主義」「唯物論」…と、
怒濤のように「〜 . . . 本文を読む
神戸シュタイナーハウス、今月の大人の講座では、1~3章を読みました。
でも、前回の序章で書き残して「ココだけは!」ってことがあるので、
今日はそこについて書きたいと思います。
鈴木一博さん訳
およそ、知識は
人となりのあるの向きを高める向きが欠けると
なまくらな好奇心を満たすまでだろう。
知識がまことの値を備えるは、
知識により人の向きが際立てばこそだ。
参加者の一人が、この箇所に対して . . . 本文を読む
おととい書いた通り、
大人の講座で、「自由の哲学」の序を担当したのですが、
自分でまとめたり考えたりしたことの内容を、
満足に伝えることはできませんでした。
そのかわり、先生が語る、
この本が成立した時代の哲学的な背景や、
他の参加者の方の思いがけない発言など、
違う方向では、い~っぱい広げてもらえました。
一番おもしろかったのが、冒頭の部分で
「合理的なものと非合理的なものとどう折り合いを . . . 本文を読む
「自由の哲学をやろう」と言い出して、
「じゃあ、アナタが第1回目のチューター役ね」と言われ、
必要に迫られて、何度も何度も「序」を読んでみた。
段落ごとに、要点をまとめ、
ここは私の暮らしの中ではこれのことだな、
と、ひとつずつ理解しながら読んでいった。
そのノートは、序章だけで16ページ分にもなった。
けどね。けどね。
私、人前でしゃべると、舞い上がって、
自分でも何を言ってるかわからなく . . . 本文を読む
自由の哲学の序を読みながら
「自由って何?」
みたいな抽象的なことを考えていた。
選択肢が広がることでもないし、
人に迷惑かけなきゃいいってもんでもないし、
ましてや、好き放題するってことでもないし、
悶々モンモン悶々モンモン…。
寝て起きたら
「自分で考えていいと思った通りに動けること」
って、スッキリわかった。
カミサマ、ありがとう~!!
誰か、何かに強制されることではなく、
考えない . . . 本文を読む
さて、次は「想い」という考えをきちんと規定していこう。
想いについて、これまで述べたのは、
「想いという考え」ではなく、
「想いを覚える」までの道筋だ。
「想いという考え」を明らかにしてみたら、
想いと対象との関わりについても明らかにできるだろう。
さらに、人の主としての自分と、外側の世界との関わりは、
ただ、考えとして知るだけではなくて、
実際に、暮らしのいちいちの中で「どう生きるか」、
とい . . . 本文を読む
客としてやってくる「覚え」とは何か。
これを漠然と問うと何もわからない。
覚えは、いつも限定された具体的なものとして現れる。
その内容は、実際に迎えられて、そこまでで区切りがついている。
実際に、具体的に迎えられる所について問うとしたら、
それは「覚えの他=考えにとって、覚えとは何なのか」だ。
覚えが何なのか、というのは、それに応じて考えて
「コレだ!」と悟った時にわかる。
この観点からする . . . 本文を読む
たとえば、梅干が意識に上るとして。
その梅干をよ~く見ると、ほかの手触りや温もりとつながる。
そのつながりを、「感覚の世の対象」と言おう。
その場に、何が見いだされるか。
そう問うてみて、実験室で見えるものを見ると、
そこでは自分の感覚とかけ離れた実験結果の数値が
現れてくることだろう(赤いとか酸っぱい、じゃない形で)。
またさらに、それを脳波やら電気信号やらで
その結果を科学的に裏打ちされる . . . 本文を読む
「考える」と「覚える」を無くしてしまったら、
私たちは、世の何事も、直に迎えられるものがなくなってしまう。
では、直に迎えるのが「考える」と「覚える」だけだとして、
「考える」は「覚える」についてどんな影響を及ぼすだろう?
「覚えは主(私)による」=「世は想いである」という
批判想念論が成り立たないことを、わたしたちは知った。
だが、批判想念論が成り立たないことイコール
「覚えは主(私)による . . . 本文を読む
何かの物事を解き明かすには、何かの物事を理解するには、
その物事を互いの関係の中で見ることが必要だ。
その物事を周囲の関係から引き離して、単独で見ていたのは、
先述した通り、わたしたちのなりたちのせいだ。
(なりたち→5_15 外を覚える+内を考える=わかる)
どんなことも、世の全体から切り離されて存在しない。
切り離して見えるのは、
私が私として、外の世界とは別の存在だと思っているからだ。
. . . 本文を読む
まさに、その内容(具体的な考えの内容=
なんでライオンはカタツムリより身のなりたちが高いのか、とか)
を、人は、考えることによって
見えない世界(考えの世=精神の世界)から
覚え(見たり聞いたりさわったり)にもたらす。
覚えの内容は外(感官でとらえられる領域)から来る。
考えの内容は内(感官でとらえられない領域)にきざす。
そのきざす矢先の形を「悟り」と言おう。
「考える」と「悟る」の関係は、 . . . 本文を読む