前述の「日本詩人選 『紀貫之』」の中での大岡信の言葉を借りるが、
「明治浪漫的自然主義の渇望」したものは、
「ディレクトネス(直接性)」と
「ストレートネス(虚飾なき単純率直さ)」であり、
これを最も早くあらわしたのは、
子規の『歌よみに与ふる書』であるのではなかろうか、と。
子規は、これの第二回において、こう述べている。
貫之は下手な歌よみにて古今集はくだらぬ集に有之候。
其貫之や古今集を崇拝するは誠に気の知れぬことなどと申すものの、
実は斯く申す生も数年前迄は古今集崇拝の一人にて候ひしかば
今日世人が古今集を崇拝する気味合は能く存申候。
<後略>
文学一般が、その近代化を目指していた時代とはいえ、
この言葉が『古今集』を崇拝し、まだその影響力を多分に受けていた
明治三十年代の詩歌界に、波紋を投げかけないはずがあろうか。
和歌が公的地位や役割を持っていたという点では、
当時も『古今集』の時代と共通性を持っており、
従って私的叙情よりも、むしろ花鳥風月を雅宴に詠ずることや
「文明開化のもたらした『開花新題』を題詠スタイルで詠むこと」を
良しとしていたはずである。
それに対して子規は、貫之や古今集の歌に私的叙情が乏しいことを
指摘することによって、「往々知識に訴えん」とした理屈めいた歌を批判し、
直接感情に訴えんとすることの大切さを説いたのである。
これは、『小説神髄』で坪内逍遙の説いた
「人間の性情そのものを美術(芸術)の独立的価値の自覚のもとに
人情を描きつくさん」
とする論以上に、近代文学及び短歌革新運動に大きな影響を
与えていったのではないだろうか。
さらに子規は『芭蕉雑談』においてこう述べている。
美術文学中最も高尚なる種類に属して、しかも日本文学中最も之を欠く者は
雄渾豪壮といふ一要素なりとす。
和歌にては万葉集以前多少の雄壮なる者なきにあらねど、
古今集以後(実朝一人を除きては)毫も之を見る事を得ず。
(中略)
而して松尾芭蕉は独り此間だに在て豪壮の気を蔵め雄渾の筆を揮ひ、
天地の大観を賦し山水の勝概を叙し、以て一世を驚かしたり。
ここで引用した『芭蕉雑談』の一節は、
前述の「日本詩人選『紀貫之』より、孫引きしたものである。
(つづく)
「明治浪漫的自然主義の渇望」したものは、
「ディレクトネス(直接性)」と
「ストレートネス(虚飾なき単純率直さ)」であり、
これを最も早くあらわしたのは、
子規の『歌よみに与ふる書』であるのではなかろうか、と。
子規は、これの第二回において、こう述べている。
貫之は下手な歌よみにて古今集はくだらぬ集に有之候。
其貫之や古今集を崇拝するは誠に気の知れぬことなどと申すものの、
実は斯く申す生も数年前迄は古今集崇拝の一人にて候ひしかば
今日世人が古今集を崇拝する気味合は能く存申候。
<後略>
文学一般が、その近代化を目指していた時代とはいえ、
この言葉が『古今集』を崇拝し、まだその影響力を多分に受けていた
明治三十年代の詩歌界に、波紋を投げかけないはずがあろうか。
和歌が公的地位や役割を持っていたという点では、
当時も『古今集』の時代と共通性を持っており、
従って私的叙情よりも、むしろ花鳥風月を雅宴に詠ずることや
「文明開化のもたらした『開花新題』を題詠スタイルで詠むこと」を
良しとしていたはずである。
それに対して子規は、貫之や古今集の歌に私的叙情が乏しいことを
指摘することによって、「往々知識に訴えん」とした理屈めいた歌を批判し、
直接感情に訴えんとすることの大切さを説いたのである。
これは、『小説神髄』で坪内逍遙の説いた
「人間の性情そのものを美術(芸術)の独立的価値の自覚のもとに
人情を描きつくさん」
とする論以上に、近代文学及び短歌革新運動に大きな影響を
与えていったのではないだろうか。
さらに子規は『芭蕉雑談』においてこう述べている。
美術文学中最も高尚なる種類に属して、しかも日本文学中最も之を欠く者は
雄渾豪壮といふ一要素なりとす。
和歌にては万葉集以前多少の雄壮なる者なきにあらねど、
古今集以後(実朝一人を除きては)毫も之を見る事を得ず。
(中略)
而して松尾芭蕉は独り此間だに在て豪壮の気を蔵め雄渾の筆を揮ひ、
天地の大観を賦し山水の勝概を叙し、以て一世を驚かしたり。
ここで引用した『芭蕉雑談』の一節は、
前述の「日本詩人選『紀貫之』より、孫引きしたものである。
(つづく)


















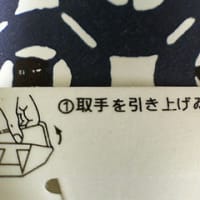


歌の引用のほう、どうぞしてやってください。私も感想をぜひ伺いたいので・・・。
土器土器
ほにゃらかの好きな歌。
(著作権は(・×・)さんにあります。無断転載禁止)
1月
節分の 豆放る手は 幼くて それでもひとつ 豆は増えたり
走り去る 吹きさむ吹雪に 目を閉じ 其れでもいまだ 心は枯れず
2月
黙り込み齧り食みたる巻き寿司の願うのは来年もここにて
3月
まだ寒い明け方の部屋私だけ当然のように指先凍る
4月
涙さえやさしくなでる春風に身を許しすぎ風邪をひきたる
君がもう居なくなってもまた飾り吹き流される天の鯉かな
5月
芽吹き出て空を吸い込み朝顔のいつぞ開くはその色の花
6月
光にて白む公園眩しさの中で響くは幼いノイズ
7月
重たげに実りて落ちる赤茄子に会えずに閉じた君を偲ばん
8月
いらだちを積み重ねても太陽を頂く天に触られぬ夏
9月
忘れずに生きることは幸せと呼べるだろうか鱗雲に問う
こういう感じの歌が、とても好きなほにゃらかです。
(・×・)さんの作品から伝わる「気持ち」があります。
これからも、良い歌を作り続けてくださいね。
楽しみにしております。
感謝、感謝です。
5,7,5,7,7の31文字だけじゃないか、なんて人がいますが、お気に入りの一首をひねり出すには膨大なエネルギーが要りますね。
気分が乗っているときでも10首が限界の私なのでした。
私は、もう何年も詠めませんです。
私の中の歌う必然がなくなったからだと思うのですが…。