明後日からもう3月。日だまりの中、オオイヌノフグリ、ハコベ、ヒメオドリコソウややホトケノザなどがポツポツと花をつけ始めています。

これらの他に、オオイヌノフグリによく似た形態のフラサバソウも園内にはあちこちで蔓延っていますが、このフラサバソウはあまりみかけない珍しい草です。 フラサバソウって聞いたことがないけれど、どんなの?と思われることでしょう。
フラサバソウ Veronica hederaefolia はヨーロッパ原産、オオイヌノフグリ Veronica persica と同じ仲間で、同じように茎は倒れて拡がりますが、全体に柔毛があり、花は青色の4~5mm程の、ほとんど目立たない草です。よく見ると花の形はイヌノフグリやオイヌノフグリと同じなので、クワガタソウ属と分かります。
これらはゴマノハグサ科でしたが、2009年に『被子植物分類表』が公表され、このAPG分類体系では、従来の分類と根本的に異なった分類法のため、現在ではオオバコ科とされています。
従来は、“目に見える外部形態に基づいた類似形態的分類体系”でしたが、新しい分類では、“目に見えない遺伝子情報に基づいた系統発生的分類体系”なので、植物に関わる者としては頭の中は大混乱しています。上記のクワガタソウ(写真)を知っていれば、似た形のイヌノフグ,オオイヌノフグリは同じ仲間だと見当づけられましたが、遺伝子云々では,どうも分かり難いのです。 しかし今後植物園でも新しい分類法の表記に移っていくのだうと思うと、覚えるしかないのか・・・と嘆息しています。
20年ほど前、小石川植物園で、オオイヌノフグリに似ているのに花色の白い、明らかに別種と思えるものを初めて目にしました。調べると本に載っているフラサバソウに形態はそっくりだったので、フラサバソウの白花だと思い込んで、大発見したような気になっていました。ところが、その後勤めた東邦大学の薬用植物園では、形態の似ている青花のものが至ることに生えていました。それこそが本に載っていたフラサバソウだったのです。そのうえ、“白花のフラサバソウ”と思い込んでいたものもあったのです。

それではあの白花は、一体何なのかしら・・・と気になりだしたのですが、当時の本では,見つけることができず、不明のままでした。ところが2010年発行の『日本帰化植物写真図鑑 第二巻』に記載されいて、「コゴメイヌノフグリ」という名前を持っていると漸く分かり、めでたしめでたし。
日本では、1960年から小石川植物園で栽培され、10年程で園内に拡がり、これが逸出して東京都内に野生化したそうですが、まだあまり広がっていいないのか、街中では見かけません。
園には、このように珍しいフラサバソウやコゴメイヌノフグリが、何故か生えているのです。 「これは薬用ではないから、雑草よネ」と一口に片付けないで、ちょっと立ち止まって眺めてみて下さい
植物って、いざ探そうと思っても、なかなか出遭えないものですから。
20年ほど前、小石川植物園で、オオイヌノフグリに

















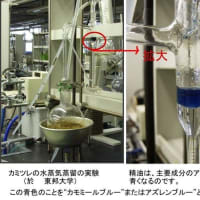

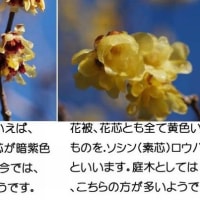
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます