日の入りの時間が、19日には17:00だったのに、20日の今日は16:59分だそうです。毎日1~2分ずつ短くなっています。
陽が傾き始め、見上げると陽のあったっている先端だけが明るい木に、秋だなぁと感じ入っていると、其処に何か生っているのに気付きました。

“アレッ、センダン?”と一瞬センダンと見紛い傍のセンダンと比べると、センダンの果実は未だ緑。目を凝らしてみると、どうも違うようです。樹下に寄ってよく見ると、陽の当たっているところでは朱赤に、日陰では鉄黒(てつぐろ)色に見えます。遠目ではわからないので、下枝を引き寄せようと柄の長い物であれこれで試みても届きません。
 Sさんから「あれはコガキだよ」と教わったのですが、始めて聞く名前でした。「マメガキは知っているけれど、コガキは初めて聞く名前・・・」と云うと 「マメガキって云うかもしれない」との由。早速検索、検索・・・・・。
Sさんから「あれはコガキだよ」と教わったのですが、始めて聞く名前でした。「マメガキは知っているけれど、コガキは初めて聞く名前・・・」と云うと 「マメガキって云うかもしれない」との由。早速検索、検索・・・・・。
結果はマメガキの別称がコガキと分かりました。 しかし私の知っているマメガキは盆栽でしか見た事がなかったので、こんなに大きく育つ木も、小さい盆栽に出来るんだ!!と、驚きでした。
考えてみれば、ブナやケヤキ等の高木も盆栽に創られているのですから、マメガキが大きくても不思議はないはずなのに、何故か驚きました。 自然の風景を切り取って鉢の中で再現しようとするのが盆栽ですが、創るのには、気の遠くなるような時間と労力が要るんだ!!と、改めて思い知ったからでしょうか。

マメガキは10m以上にもなる落葉高木で、耐寒性が強いので長野県以北で、柿渋を採るため栽培されているそうです。柿渋を採るには、未だ青い果実を採りヘタを取り除いて、水を加えて突き砕き、それを布袋で絞って作るそうです。柿渋は布や紙に塗って防水・防腐効果に使われます。
実用ばかりでなく、その柿渋盃1杯に大根おろしを混ぜて、空腹時に飲用すると血圧降下が期待出来るとされたり、しゃっくり止め、しもやけの凍傷やかぶれに塗布したりして民間薬として使われています。 呼び名も、マメガキ、シナノガキ、コガキ、ブドウガキ、千生柿(せんなりがき)、ビンボガキ、サルガキ、スズガキ等々地域によって色んな名前があるようです。
ならば、当地にも野生マメガキがあったのかと疑問に思い調べてみると、千葉県では、聖武天皇の勅で建立された上総国分尼寺遺跡から、マメガキの種子が出土していると知りました。(「上総国分尼寺遺跡の井戸内堆積物から産した植物化石群」http://hisbot.jp/journalfiles/0401/0401_025-034.pdf )
だからといって当地でも野生のマメガキがあったとするには、もう少し詳しく調べなくてはならないでしょう。
その後、勤続20数年のKさんから、マメガキのある場所には、以前は職員住宅があって、盆栽マニアの男性が居住していたと聞きました。考えられるのは、彼が立ち退くとき、盆栽のマメガキを植えて行ったのではないかという事です。Kさんの話を聞く前だったら、野生かもしれないと考えますが、納得出来るのは“当時の居住者の置き土産”の方です。
調べてみると、「マメガキ」と載っている本ばかりではないのです。 『図説牧野和漢薬草大事典』(北隆館)ではシナノガキDiospyros Lotusとして載っていす。
しかし、『薬草カラー大事典」』(主婦の友社)ではマメガキDiospyros Lotusとして記載、類似植物としてシナノガキ(別名リュウキュウマメガキ)とあります。其処には《シナノガキは関東以西から沖縄の山地に自生し、マメガキよりは渋みが少ない》と解説してあります。 また『日本の樹木』(山と社)には、リュウキュウマメガキ、マメガキがそれぞれ載り、それぞれには別名をシナノガキとあります。
こうなるとマメガキとシナノガキは同じ植物なのか別の近縁種なのかと分からなくなりました。
学名だけを見れば同じなのは判然としていますが、解説を読むと (?_?)です。
樹木については苦手意識が強く、どんなに勧められても勉強しなかったので、今になって悔やまれます。
If you have any information, please help me・・・・・
園には甘柿、渋柿、百目柿、山柿などが数本あります。渋柿でも完熟すれば甘く美味しく食べられます。
これらをひっくるめて「カキ」でいいのかしら・・・・・
そうそう、山梨県では甲府弁でマメガキを「あまんど」と呼び、‘干し柿’で売られているそうです。取り寄せてみようと検索してみてもヒットしないので、園のマメガキが熟して黒くなったら、是非食べてみたいと心待ちしています。

















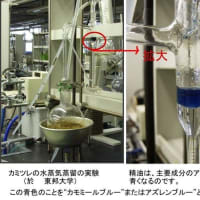

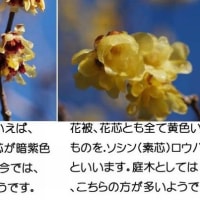
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます