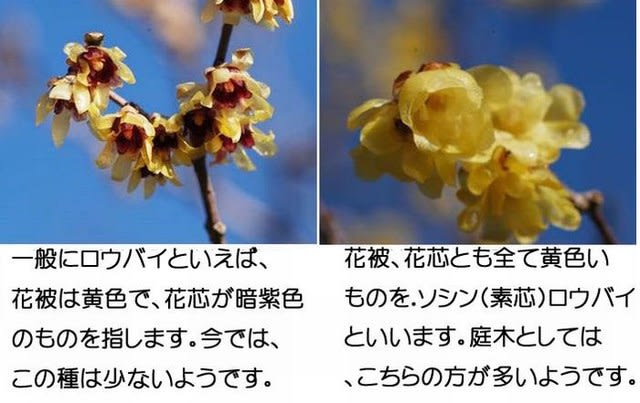ハカマ取りと言っても、 着物姿の殿方のハカマを剥ぐという事ではありませんよ。
昨年、居住区の一カ所だけにツクシが沢山生えているのを見つけていました。啓蟄になればツクシも出るのではないかと、期待してその場所に行ってみると案の定今年も・・・・・。このところの暖かさで一斉に出たのでしょうが、誰も見向きしません。毎朝の散歩の時摘み2,3日分採りためておき、卵とじや、佃煮風にして、春の味を堪能しています。
もっと沢山のツクシを採りたいと、近くの田の畔を歩き回ってみましたが、見つかりません。スギナは至る所に沢山生えていたので、スギナの多い、日向の斜面という条件に該当する場所なら、ツクシはさぞかし大収穫!! と期待して行ったのですが。目当てのツクシは1本もありません。
どうもスギナの多いところにツクシが多く生えるということではなさそうです。
ツクシは採って、洗って直ぐ調理できるのと思い込んでいた私は、よく洗ってそのまま使ったことがありました。
20数年前、初めてツクシの料理に挑んだときのことでした。何も知らずに作った 煮浸しのお味は、よかったのですが、口の中でがさがさして、とても食べられたものではなかったのです。
地方出身の友人に訊くと、「はかまを取らなくちゃ、とても食べられないわよ」と云われました。。
その時初めて,“ツクシのハカマは取り除かなくてならない" ことを知ったのです。

ツクシのハカマとは、上図の茎に段段についている部分をハカマと云います。
<ツクシの煮浸し>作り方は、ハカマを取除いたつくしを洗い、よく水を切って小鍋に入れ胡麻油で炒めます。しんなりしてきたら、お好みの味付けをします。鍋には胞子の緑色の汁が残りますが、心配ご無用です。その胞子の色と、苦味が嫌で、頭を取り除いて茎だけを調理するとも聞きましたが、私はほろ苦さは春の味と思うので、そのまま調理します。
ツクシが手に入ったら、是非一度お試し下さい。検索すれば、作り方はいろいろありますよ。
庭一面に出てきたアズマネザサには、閉口しています。あまりの蔓延り方に半ば諦め、寒い間は手も入れないでいましたが、先日漸く退治するつもりになり、久々に庭に降りました。
憎っくき憎っくきアズマネザサを取り除いていて、シュンランの花の香りに心は和みました。今年は一株から40本あまりの花がついていて、辺りはいかにも和の芳香が漂っていました。例年は花茎を梅酢漬けにし、焼き魚に添えています。今年は塩漬けにして蘭茶にして喫してみるつもりです。

同じようにシュンランにもハカマはあるのです。茎についている薄い皮のような部分です。シュンランも、この部分を取り除かなくては,食べにくいのです。よく洗って,水気を切ったら,梅酢に漬け、一晩おけば、焼魚の付け合わせに使えます。
丁度ハジカミのように使います。シャキッとした食感は、春ならではの楽しみです。
私は梅酢を使いましたが、勿論白い梅酢でも,お好みの甘さの甘酢でもいいのです。
花は愛でるだけではなく、食べれば口福です。
ツクシやシュンランが手に入れば是非お試しになれば・・・・