草案の原文はこちら。
前回のブログでは、今後はもっと軽い内容も織り交ぜながら・・・ということを書いていたのですが、そんなことは言っていられないニュースが飛び込んできました。なので、モードをいつもどおりに戻します。
自民党は立党50年プロジェクトと銘打って新憲法案を策定を進めており、それが昨日発表されました。内容的には天皇制や国会の二院制などは維持、環境権などの新しい権利に配慮したものになっていますが、何よりも大きな変更点は第九条の「戦争放棄」条項が「安全保障」条項に変わり、自衛隊を自衛軍として憲法に明記したところでしょう。これによって現行憲法の解釈を捻じ曲げて存在してきた自衛隊が、憲法上も正式なものとして認められるようになります。まあ、自衛隊は昔から存在しているのだし、最近ではイラク派遣に代表されるような国際貢献の実績もあるので、それが憲法で認められた存在になるということは当然の流れかなと思っています。
と、さらりと流しておこうと思っていたのですが、気になる点があります。それは自衛「軍」と明記している点です。世界に例を見ない自衛「隊」でなく、世界中に存在する自衛のための「軍隊」と明記しています。ということは、可能性としては徴兵制もあり得るということでしょうか?
これまでの自衛隊は、憲法上の「軍隊」ではないため、当然ながら憲法上は徴兵などはありえないはずであり、事実現在に至るまで志願兵(正確には志願隊員とでも言うのでしょうか?)のみで構成されています。しかし、改正案では自衛のための「軍隊」と明記され、「軍隊」であるならば日本の戦前の経緯や世界的な基準に照らし合わせても徴兵制の導入は当然あり得ると考えるのが普通だろうと思います。
もちろん現代の先進国で徴兵制をとっている国はそれほど多くないようです。軍事技術がすさまじく発展してしまったので徴兵制によって集められた素人はさほどの戦力にならず、徴兵制はもはや意味を成さないという意見もあります。しかしそれは今必要ないから徴兵をしていないだけで、必要があれば軍隊を持つすべての国で必要に応じて徴兵制が復活する可能性があるのです。(参考: Wikipedia 徴兵制度)
徴兵制については、賛成論者も反対論者も感情的な議論が多くなる傾向になると思います。賛成論者の意見は「国の危機に国民が国を守るのはあたりまえだ。だから徴兵も必要だ。」、反対論者の意見は「戦争で人を殺したり自分が死んだりするのはいやだ。だから徴兵制は反対だ。」といったものが代表的なものだと思います。
私は、個人的には徴兵制は反対です。理由の一つは前述の感情的な意見とほとんど同じなので議論をするようなものでもないのですが、もう一つの理由として、特に私たち日本人は「状況が破綻した時、人海戦術に活路を見出そうとする」傾向が強いように思える点を指摘しておきたいと思います。
いきなり話が飛んで申し訳ないのですが、私は仕事柄ソフトウェアの開発に携わることが多く、時にプロジェクトマネージメントが不十分で破綻した状況を見聞きすることがあります。ソフト開発の世界ではそのような状況を「デスマーチ(死の行進)」と表現することがあります。このような状況に陥った時、本来であればデスマーチに至った根本原因を追究し一から体制を立て直すというプロセスが必要なのですが、一見遠回りに見えることや原因を引き起こした人の責任が追及されることなどから、安易に人を追加して状況を打開しようとする傾向があります。しかし、本当は計画の不備、進捗確認の不備、品質確認の不備、リスクマネージメントの不備などすべてマネジメントの不備が原因であることがほとんどであり、従って人を追加しただけでは解消しない場合がほとんどです。
安全保障もソフト開発に似たところがあるのかなと思います。安全保障も有事になる前の情報収集、関係国との協力体制強化、兵士の訓練計画・達成度確認、想定される攻撃に対する対応計画、攻撃を受けたときの作戦の計画とその進捗の確認など、十分なマネジメント体制がない状況で成果を挙げることはできません。志願兵で構成されれば、有限のリソースの中で成果を上げなければなりませんから、指揮官にはこれらのマネージメントを十分実施することが求められます。しかし強制的な徴兵制の下で大量のリソースが供給される状況を作ってしまうとこうしたマネージメントがおざなりになり、太平洋戦争末期のような人を弾のように使う作戦などが横行してしまい、結局成果を上げられず大量の戦死者を出すだけになってしまう可能性があります。
従って、私は自衛軍は認めても徴兵制は反対です。改正憲法案に「自衛軍」と書くのであれば「志願者によって構成される」と記載すべきと考えます。
では、徴兵は認めないなどの歯止めは憲法改正案に記載されているのでしょうか。新第九条全文を抜き出して、確認してみましょう。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、または国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
最後の「第九条の二 4項」で自衛軍の組織に関する事項は法律で定めるとあります。つまり、憲法の改正を経なくても徴兵制を認める法案を通してしまえば徴兵制に移行することができてしまいます。せめて4項に「なお、自衛軍は志願者によって構成されるものとし、強制的な徴兵はこれを行わない。」と記載して欲しいと思います。
憲法で歯止めをかけておき、もし世論が「徴兵」を望むのであれば国民投票で憲法を改正すればよいと思います。実際のところは国民の大多数が徴兵を望むような状況になるのであれば、憲法改正を実施しなくても志願兵が増えるような気がしますし、そのような志願兵を教育した方が統率のあるマネージメントしやすい組織となり、安全保障の実現という目的を達成しやすくなるのではないかと考えます。
この憲法草案作成にあたった中曽根元首相や宮沢元首相は、「今すぐの改正ではなく、少なくとも5年~10年くらいは必要であろう」と述べていることから、まだまだ考える時間は十分あります。そのうち民主党なども対案を出すでしょう。国民みんなで議論を深めてゆきましょう。
余談ですが、インターネットそしてブログの登場によってこのような重要な課題について、本当の意味で国民の間で議論を深めてゆくことができるようになったことに感謝しています。










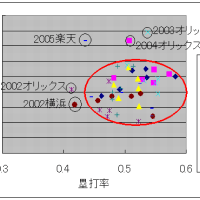
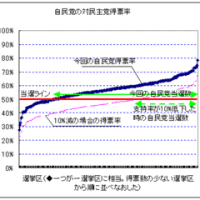
今後の軍隊の方向性の一つとして高度に情報化された組織という側面があり、その運用についてはかなり高度で専門的な知識が求められると考えられている以上、徴兵制により集められた素人集団(意欲の面でも?)は現在の軍隊に対してほとんど要をなさないと考えています。まぁ、現在の政治家やマスコミの軍事音痴ぶりがなくなれば、比較的容易にこのような結論に達すると思われるのですが、現在の状況では難しいと思われますし、その点において私は危惧しています。
ですので、憲法に「志願兵による」自衛軍、と明記するだけでより民意に近くなると思うのですが、徴兵という選択肢を自民党が捨てきれなかった理由は何なのでしょうか?