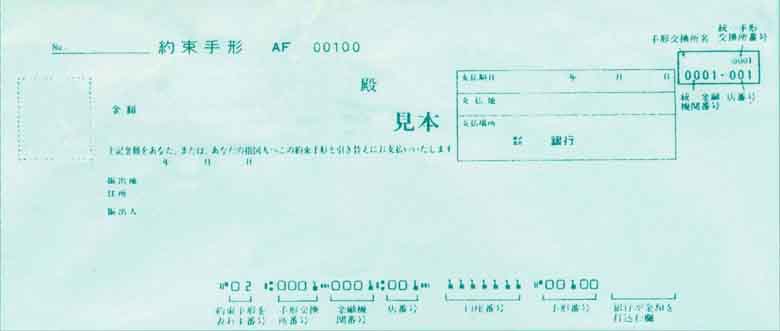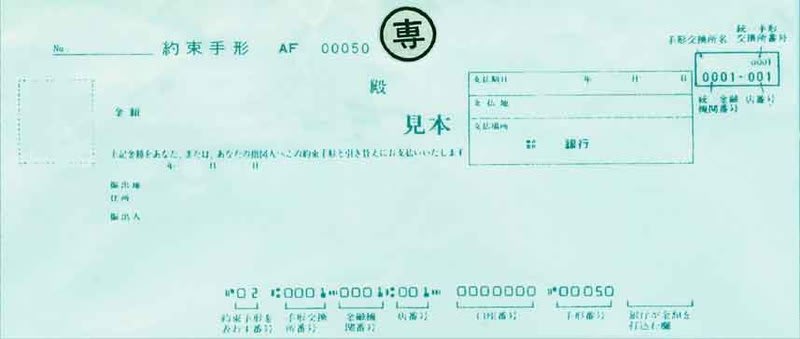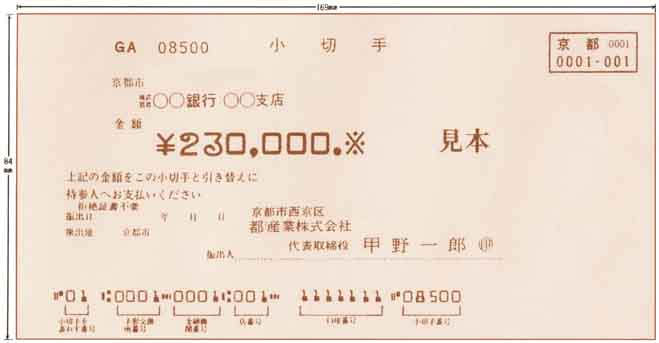もうすぐ4年目を迎えるサラリーマン3年生は、箕面方面への慰安旅行に参加していた。1966(S41).3.5~6のこと。
淡路島から貸切バスで明石へ渡り、西宮へ。そこからチョビットだけ名神高速道路を走る。なにしろ、高速道路というもの、出来てから2年しか経っておらず、まだまだ珍しい。高速道路をバスで通る企画もみんなの希望であった。
貸切バスは女性のガイドが乗務しており、こんなクイズが出ていた。「むかし、この近くで坊さんと尼さんが駈けっこをしたところがあるのだと。それで、どちらが先に着いたと思いますか?」だと。みんなは、考え込んでいた。バスが高速を少し走ったところで、この辺りが「尼がさき」というところなんだ。だから、駈けっこは尼さんが先に着いたのだと。みんな、どっと笑い、あっという間に尼崎を通過、豊中ICを抜けて、箕面に向かっていた。
この尼崎というところ、わたしがもうじき赴任するところでもあった。

↑ 高速降りて着いたところがここ、「箕面スパーガーデン」
なぜか、この旅行では全員写真が無い。撮ってなかったのかな。
淡路島から貸切バスで明石へ渡り、西宮へ。そこからチョビットだけ名神高速道路を走る。なにしろ、高速道路というもの、出来てから2年しか経っておらず、まだまだ珍しい。高速道路をバスで通る企画もみんなの希望であった。
貸切バスは女性のガイドが乗務しており、こんなクイズが出ていた。「むかし、この近くで坊さんと尼さんが駈けっこをしたところがあるのだと。それで、どちらが先に着いたと思いますか?」だと。みんなは、考え込んでいた。バスが高速を少し走ったところで、この辺りが「尼がさき」というところなんだ。だから、駈けっこは尼さんが先に着いたのだと。みんな、どっと笑い、あっという間に尼崎を通過、豊中ICを抜けて、箕面に向かっていた。
この尼崎というところ、わたしがもうじき赴任するところでもあった。

↑ 高速降りて着いたところがここ、「箕面スパーガーデン」
なぜか、この旅行では全員写真が無い。撮ってなかったのかな。