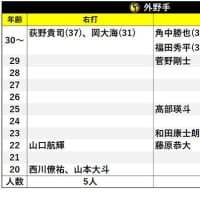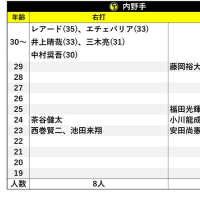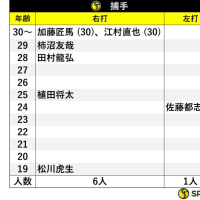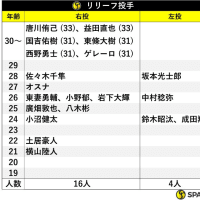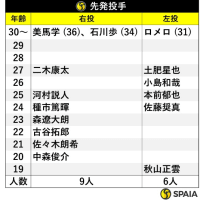あいつがいたから俺がいた ロッテの鈴木と藤岡、東洋大コンビが仲良くお立ち台に

まさに読み勝ちの一打だった。ロッテの鈴木は10日の楽天戦で同点の五回2死二、三塁のチャンスにライト前へ勝ち越しの2点タイムリー。「1、2球目は外角。そろそろ内角へ来ると予想していた」と胸を張った。
一回の第1打席はセカンドフライ。三回の第2打席は一塁ゴロに倒れていた。「同じような凡打。中途半端なバッティングで倒れていたので、今度は振り切った。思い切り詰まったが、いいところへ落ちてくれた」と会心の笑みを見せた。
これを喜んだのは、一塁ベンチ前で肩慣らしをしていたロッテの先発左腕、藤岡だ。「大地(鈴木)を信じていた。ポテンヒットだったが、よく打ってくれたと思う」。藤岡は7回を1失点と好投し、今季2勝目をマークした。
鈴木と藤岡はともに東洋大出身。主将とエースという立場でチームを牽引(けんいん)し、2011年には大学野球選手権で日本一に輝く原動力になった。同年秋のドラフトでは藤岡が1位、鈴木が3位指名を受けて仲良くロッテへ入団した。
鈴木は新人だった12年、開幕1軍入りは果たせなかった。一方、藤岡はいきなりローテーション入り。4月30日のソフトバンク戦では藤岡が先発して勝ち投手となり、ドラフト同期で2位指名の中後(なかうしろ)、4位指名の益田がホールドを挙げ、3人がそろってお立ち台へ上がる光景がテレビに映し出された。
1人蚊帳の外だった鈴木は「あのファームでの2カ月を経験したからこそ今の自分があると思っているが、本音は悔しかった」と振り返る。以来、藤岡と2人でお立ち台へ立つことが鈴木の夢となった。「大学で同じ4年間を過ごし、プロでも同じチームでプレーできるのは幸せですからね。やはり藤岡のことは特別意識します」。ようやく実現したツーショットにご機嫌だった。
今季の鈴木は一時期打撃不振に苦しみ、打率が2割を切った4月下旬には3試合スタメンを外された。そこで佐藤内野守備・走塁コーチにかけてもらったひと言が立ち直りのきっかけとなった。「『ここで頑張るか、しゅんと腐ってしまうかでこの先、全然変わってくるぞ』と。おかげで初心に戻れました」
技術的には、内野のレギュラーを獲得した昨シーズンの好調時の打撃フォームの映像を分析。「下半身の使い方がおろそかになっていた。下半身へ意識を向けることでいい形で打席に入り、四球も選べるようになった」と手応えを語る。
鈴木と藤岡。3年目の若手2人が投打の中心として活躍すれば、ロッテに上昇機運がみなぎってくるはずだ。(三浦馨)
(産経)
交流戦開幕。セがパに勝ち越すための打開策はあるか?
5月20日からプロ野球セ・パ交流戦が開幕する。2005年の導入から今年で10年目を迎えるが、年度別の対戦成績を見るとパ・リーグが9年間で8度勝ち越しており、セ・リーグが勝ち越したのは2009年の一度だけしかない(通算成績はパ・リーグ733勝、セ・リーグは660勝、引き分け47)。同じく優勝チームの変遷を見ても、ソフトバンクの4回を最多とし、パ・リーグのチームが9年間で8度優勝するなど、セ・リーグを圧倒している。

2005年 千葉ロッテマリーンズ
2006年 千葉ロッテマリーンズ
2007年 北海道日本ハムファイターズ
2008年 福岡ソフトバンクホークス
2009年 福岡ソフトバンクホークス
2010年 オリックスバファローズ
2011年 福岡ソフトバンクホークス
2012年 読売ジャイアンツ
2013年 福岡ソフトバンクホークス
昭和の頃から耳にしていた「実力のパ」という言葉通りの結果である。しかし、2009年までの交流戦の上位3チームの見てほしい。
2005年 1位 ロッテ 2位 ソフトバンク 3位 阪神
2006年 1位 ロッテ 2位 ヤクルト 3位 阪神
2007年 1位 日本ハム 2位 巨人 3位 横浜(現DeNA)
2008年 1位 ソフトバンク 2位 阪神 3位 日本ハム
2009年 1位 ソフトバンク 2位 ヤクルト 3位 広島
優勝こそパ・リーグのチームだが、2006年から2009年は2位にセ・リーグのチームが入るなど、実力的に大きな差があるとは思えなかった。実際、この5年間の対戦成績はパ・リーグ427勝、セ・リーグ418勝(引き分け19)と、ほぼ互角の戦いを繰り広げていた。
状況が大きく変わってしまったのは2010年からで、この年の交流戦はパ・リーグのチームが1位から6位を独占し、セ・リーグは7位の巨人が勝率5割を維持するのがやっとだった。2011年も1位から3位までをパ・リーグのチームが独占。2012年こそ巨人がセ・リーグのチームとして初の優勝を飾り、対戦成績もパ・リーグ67勝、セ・リーグ66勝(引き分け11)と接戦と演じたが、2013年はパ・リーグ80勝、セ・リーグ60勝(引き分け4)と再びパ・リーグの圧勝に終わった。
解説者の山崎武司氏はかつてこう語っていた。
「パ・リーグにはダルビッシュ有(現レンジャーズ)や岩隈久志(現マリナーズ)、杉内俊哉(現巨人)をはじめ、球界を代表する投手が揃っていました。彼らとの対戦を重ねることで、打者のレベルが上がっていったというのはあると思います。特にここ数年は、パ・リーグの方が力強さを持った選手が多いのかなという印象を受けますね」
ここでパ・リーグがセ・リーグを圧倒しはじめた2010年以降の個人成績を見てみたい。
2010年
打率
1位 多村仁志(ソフトバンク).415
2位 坂口智隆(オリックス).389
3位 今江敏晃(ロッテ).385
3位 相川亮二(ヤクルト).385
5位 田中賢介(日本ハム).371
防御率
1位 前田健太(広島)1.05
2位 ダルビッシュ有(日本ハム)1.24
3位 マーフィー(ロッテ)1.33
4位 ケッペル(日本ハム)1.62
5位 山本省吾(オリックス)1.82
2011年
打率
1位 坂口智隆(オリックス).412
2位 田口壮(オリックス).363
3位 糸井嘉男(日本ハム).351
4位 マートン(阪神).340
5位 炭谷銀仁朗(西武).329
防御率
1位 ダルビッシュ有(日本ハム)0.21
2位 館山昌平(ヤクルト)0.44
3位 田中将大(楽天)0.68
4位 中山慎也(オリックス)0.73
5位 武田勝(日本ハム)1.03
2012年
打率
1位 角中勝也(ロッテ).349
2位 田中賢介(日本ハム).344
3位 中村剛也(西武).342
4位 荒木雅博(中日).340
5位 糸井嘉男(日本ハム).326
防御率
1位 グライシンガー(ロッテ)0.83
2位 ウルフ(日本ハム)0.91
3位 前田健太(広島)0.92
4位 釜田佳直(楽天)1.14
5位 大隣憲司(ソフトバンク)1.22
2013年
打率
1位 長谷川勇也(ソフトバンク).418
2位 内川聖一(ソフトバンク).385
3位 松田宣浩(ソフトバンク).360
4位 秋山翔吾(西武).351
5位 今江敏晃(ロッテ).350
防御率
1位 ディクソン(オリックス)0.74
2位 岸孝之(西武) 1.21
3位 田中将大(楽天)1.31
4位 木佐貫洋(日本ハム)1.38
5位 戸村健次(楽天)1.40
昨年は投打ともにパ・リーグの選手が上位を独占。山崎氏が指摘するように、セ・パの選手に実力格差が生じていることを感じずにはいられない。こうした個々のレベルの差が、勝敗に大きく影響しているのだろうか。解説者の与田剛氏は次のように語る。
「交流戦は2連戦の変則日程ですので、いい投手の揃うチームが有利になります。成績を見てもわかるように、いい投手が多いパ・リーグの方が優位に戦えているというのはあると思います。ただ昨年の交流戦を見る限り、セ・リーグとパ・リーグの選手個々のレベルの差というものは、以前ほど感じませんでした。結果的にパ・リーグ80勝、セ・リーグ60勝に終わりましたが、数字ほどの差はなかったと思います」
ではどうして、こうした差が生まれたのか。与田氏が続ける。
「昨年の交流戦は11位のヤクルトが借金9、12位のDeNAが借金10とセ・リーグの2チームが大きく負け越してしまいました。でも、他のセ・リーグのチームを見ると、巨人と阪神が勝ち越し、広島と中日も負け越したとはいえ互角の戦いをしていました。だから、パ・リーグにまったく歯が立たなかったというわけではありません。大きく負け越したチームが2つもあったことがこれらの原因だと思います」
とはいえ、今年もヤクルトとDeNAはセ界で苦戦を強いられており、再びパ・リーグの餌食になる可能性はある。そんな状況で、セ・リーグがパ・リーグに勝ち越すにはどうすればいいのだろうか。野球解説者の金村義明氏に「打開策はあるか?」と尋ねると、次のような答えが返ってきた。
「これまでの交流戦の優勝チームを見ると、やはりどのチームも打ち勝っている印象が強いです。谷間登板がない交流戦は、いい投手が揃っているチームが有利と言われていますが、逆に考えれば、それらの投手を打ち崩さないことには勝てません。つまり、打線の強いチームが有利だと思うんです。そういった意味で、今のヤクルトはよく打ちますし、DeNAにしてももうすぐケガで離脱していたブランコが戻ってきます。それに今年は広島が投打ともに充実しています。とにかく、打撃を全面に押し出して戦うべきだと思います。セ・リーグのチームはそこに活路を見い出すしかないでしょうね」
昨年、60本塁打の日本記録を樹立したヤクルトのバレンティンは今季もここまで(5月17日現在)両リーグトップの15本塁打をマークしており、DeNAには長年キューバ代表の中軸を担っていたグリエルが加入する。外国人頼みは寂しいが、今までパ・リーグに大きく負け越していた2チームが持ち前の攻撃力を発揮すれば、セ・リーグにも勝ち越しの目が出てくる。
また、与田氏の見解はこうだ。
「今年の交流戦のカギを握るのは、西武と楽天のパ・リーグ下位2チームだと思います。ここまでの戦いを見ると、投打ともに元気がないのが気になります。この今ひとつ調子の上がらない2チームに、セ・リーグのチームがどこまで貯金を作ることができるのかが重要になってくると思います。セ・リーグは広島の前田健太や巨人の菅野智之を筆頭に、パ・リーグの打者相手にも真っ向勝負できるピッチャーが増えています。彼らが投げる試合を確実に取ることができれば、十分に勝ち越せると思います」
昨年、24連勝という驚異的な記録を達成した楽天の田中将大がヤンキースに移籍し、パ・リーグからスーパーエースがまたひとり去った。それだけでもセ・リーグにとっては大きなアドバンテージになるはずだ。さらに広島の大躍進や、現在5位とはいえヤクルトが圧倒的な攻撃力で順調に白星を重ねている。はたして、パ・リーグ相手にどんな戦いを見せるのか。セ・リーグの意地に期待したい。
(Number)

まさに読み勝ちの一打だった。ロッテの鈴木は10日の楽天戦で同点の五回2死二、三塁のチャンスにライト前へ勝ち越しの2点タイムリー。「1、2球目は外角。そろそろ内角へ来ると予想していた」と胸を張った。
一回の第1打席はセカンドフライ。三回の第2打席は一塁ゴロに倒れていた。「同じような凡打。中途半端なバッティングで倒れていたので、今度は振り切った。思い切り詰まったが、いいところへ落ちてくれた」と会心の笑みを見せた。
これを喜んだのは、一塁ベンチ前で肩慣らしをしていたロッテの先発左腕、藤岡だ。「大地(鈴木)を信じていた。ポテンヒットだったが、よく打ってくれたと思う」。藤岡は7回を1失点と好投し、今季2勝目をマークした。
鈴木と藤岡はともに東洋大出身。主将とエースという立場でチームを牽引(けんいん)し、2011年には大学野球選手権で日本一に輝く原動力になった。同年秋のドラフトでは藤岡が1位、鈴木が3位指名を受けて仲良くロッテへ入団した。
鈴木は新人だった12年、開幕1軍入りは果たせなかった。一方、藤岡はいきなりローテーション入り。4月30日のソフトバンク戦では藤岡が先発して勝ち投手となり、ドラフト同期で2位指名の中後(なかうしろ)、4位指名の益田がホールドを挙げ、3人がそろってお立ち台へ上がる光景がテレビに映し出された。
1人蚊帳の外だった鈴木は「あのファームでの2カ月を経験したからこそ今の自分があると思っているが、本音は悔しかった」と振り返る。以来、藤岡と2人でお立ち台へ立つことが鈴木の夢となった。「大学で同じ4年間を過ごし、プロでも同じチームでプレーできるのは幸せですからね。やはり藤岡のことは特別意識します」。ようやく実現したツーショットにご機嫌だった。
今季の鈴木は一時期打撃不振に苦しみ、打率が2割を切った4月下旬には3試合スタメンを外された。そこで佐藤内野守備・走塁コーチにかけてもらったひと言が立ち直りのきっかけとなった。「『ここで頑張るか、しゅんと腐ってしまうかでこの先、全然変わってくるぞ』と。おかげで初心に戻れました」
技術的には、内野のレギュラーを獲得した昨シーズンの好調時の打撃フォームの映像を分析。「下半身の使い方がおろそかになっていた。下半身へ意識を向けることでいい形で打席に入り、四球も選べるようになった」と手応えを語る。
鈴木と藤岡。3年目の若手2人が投打の中心として活躍すれば、ロッテに上昇機運がみなぎってくるはずだ。(三浦馨)
(産経)
交流戦開幕。セがパに勝ち越すための打開策はあるか?
5月20日からプロ野球セ・パ交流戦が開幕する。2005年の導入から今年で10年目を迎えるが、年度別の対戦成績を見るとパ・リーグが9年間で8度勝ち越しており、セ・リーグが勝ち越したのは2009年の一度だけしかない(通算成績はパ・リーグ733勝、セ・リーグは660勝、引き分け47)。同じく優勝チームの変遷を見ても、ソフトバンクの4回を最多とし、パ・リーグのチームが9年間で8度優勝するなど、セ・リーグを圧倒している。

2005年 千葉ロッテマリーンズ
2006年 千葉ロッテマリーンズ
2007年 北海道日本ハムファイターズ
2008年 福岡ソフトバンクホークス
2009年 福岡ソフトバンクホークス
2010年 オリックスバファローズ
2011年 福岡ソフトバンクホークス
2012年 読売ジャイアンツ
2013年 福岡ソフトバンクホークス
昭和の頃から耳にしていた「実力のパ」という言葉通りの結果である。しかし、2009年までの交流戦の上位3チームの見てほしい。
2005年 1位 ロッテ 2位 ソフトバンク 3位 阪神
2006年 1位 ロッテ 2位 ヤクルト 3位 阪神
2007年 1位 日本ハム 2位 巨人 3位 横浜(現DeNA)
2008年 1位 ソフトバンク 2位 阪神 3位 日本ハム
2009年 1位 ソフトバンク 2位 ヤクルト 3位 広島
優勝こそパ・リーグのチームだが、2006年から2009年は2位にセ・リーグのチームが入るなど、実力的に大きな差があるとは思えなかった。実際、この5年間の対戦成績はパ・リーグ427勝、セ・リーグ418勝(引き分け19)と、ほぼ互角の戦いを繰り広げていた。
状況が大きく変わってしまったのは2010年からで、この年の交流戦はパ・リーグのチームが1位から6位を独占し、セ・リーグは7位の巨人が勝率5割を維持するのがやっとだった。2011年も1位から3位までをパ・リーグのチームが独占。2012年こそ巨人がセ・リーグのチームとして初の優勝を飾り、対戦成績もパ・リーグ67勝、セ・リーグ66勝(引き分け11)と接戦と演じたが、2013年はパ・リーグ80勝、セ・リーグ60勝(引き分け4)と再びパ・リーグの圧勝に終わった。
解説者の山崎武司氏はかつてこう語っていた。
「パ・リーグにはダルビッシュ有(現レンジャーズ)や岩隈久志(現マリナーズ)、杉内俊哉(現巨人)をはじめ、球界を代表する投手が揃っていました。彼らとの対戦を重ねることで、打者のレベルが上がっていったというのはあると思います。特にここ数年は、パ・リーグの方が力強さを持った選手が多いのかなという印象を受けますね」
ここでパ・リーグがセ・リーグを圧倒しはじめた2010年以降の個人成績を見てみたい。
2010年
打率
1位 多村仁志(ソフトバンク).415
2位 坂口智隆(オリックス).389
3位 今江敏晃(ロッテ).385
3位 相川亮二(ヤクルト).385
5位 田中賢介(日本ハム).371
防御率
1位 前田健太(広島)1.05
2位 ダルビッシュ有(日本ハム)1.24
3位 マーフィー(ロッテ)1.33
4位 ケッペル(日本ハム)1.62
5位 山本省吾(オリックス)1.82
2011年
打率
1位 坂口智隆(オリックス).412
2位 田口壮(オリックス).363
3位 糸井嘉男(日本ハム).351
4位 マートン(阪神).340
5位 炭谷銀仁朗(西武).329
防御率
1位 ダルビッシュ有(日本ハム)0.21
2位 館山昌平(ヤクルト)0.44
3位 田中将大(楽天)0.68
4位 中山慎也(オリックス)0.73
5位 武田勝(日本ハム)1.03
2012年
打率
1位 角中勝也(ロッテ).349
2位 田中賢介(日本ハム).344
3位 中村剛也(西武).342
4位 荒木雅博(中日).340
5位 糸井嘉男(日本ハム).326
防御率
1位 グライシンガー(ロッテ)0.83
2位 ウルフ(日本ハム)0.91
3位 前田健太(広島)0.92
4位 釜田佳直(楽天)1.14
5位 大隣憲司(ソフトバンク)1.22
2013年
打率
1位 長谷川勇也(ソフトバンク).418
2位 内川聖一(ソフトバンク).385
3位 松田宣浩(ソフトバンク).360
4位 秋山翔吾(西武).351
5位 今江敏晃(ロッテ).350
防御率
1位 ディクソン(オリックス)0.74
2位 岸孝之(西武) 1.21
3位 田中将大(楽天)1.31
4位 木佐貫洋(日本ハム)1.38
5位 戸村健次(楽天)1.40
昨年は投打ともにパ・リーグの選手が上位を独占。山崎氏が指摘するように、セ・パの選手に実力格差が生じていることを感じずにはいられない。こうした個々のレベルの差が、勝敗に大きく影響しているのだろうか。解説者の与田剛氏は次のように語る。
「交流戦は2連戦の変則日程ですので、いい投手の揃うチームが有利になります。成績を見てもわかるように、いい投手が多いパ・リーグの方が優位に戦えているというのはあると思います。ただ昨年の交流戦を見る限り、セ・リーグとパ・リーグの選手個々のレベルの差というものは、以前ほど感じませんでした。結果的にパ・リーグ80勝、セ・リーグ60勝に終わりましたが、数字ほどの差はなかったと思います」
ではどうして、こうした差が生まれたのか。与田氏が続ける。
「昨年の交流戦は11位のヤクルトが借金9、12位のDeNAが借金10とセ・リーグの2チームが大きく負け越してしまいました。でも、他のセ・リーグのチームを見ると、巨人と阪神が勝ち越し、広島と中日も負け越したとはいえ互角の戦いをしていました。だから、パ・リーグにまったく歯が立たなかったというわけではありません。大きく負け越したチームが2つもあったことがこれらの原因だと思います」
とはいえ、今年もヤクルトとDeNAはセ界で苦戦を強いられており、再びパ・リーグの餌食になる可能性はある。そんな状況で、セ・リーグがパ・リーグに勝ち越すにはどうすればいいのだろうか。野球解説者の金村義明氏に「打開策はあるか?」と尋ねると、次のような答えが返ってきた。
「これまでの交流戦の優勝チームを見ると、やはりどのチームも打ち勝っている印象が強いです。谷間登板がない交流戦は、いい投手が揃っているチームが有利と言われていますが、逆に考えれば、それらの投手を打ち崩さないことには勝てません。つまり、打線の強いチームが有利だと思うんです。そういった意味で、今のヤクルトはよく打ちますし、DeNAにしてももうすぐケガで離脱していたブランコが戻ってきます。それに今年は広島が投打ともに充実しています。とにかく、打撃を全面に押し出して戦うべきだと思います。セ・リーグのチームはそこに活路を見い出すしかないでしょうね」
昨年、60本塁打の日本記録を樹立したヤクルトのバレンティンは今季もここまで(5月17日現在)両リーグトップの15本塁打をマークしており、DeNAには長年キューバ代表の中軸を担っていたグリエルが加入する。外国人頼みは寂しいが、今までパ・リーグに大きく負け越していた2チームが持ち前の攻撃力を発揮すれば、セ・リーグにも勝ち越しの目が出てくる。
また、与田氏の見解はこうだ。
「今年の交流戦のカギを握るのは、西武と楽天のパ・リーグ下位2チームだと思います。ここまでの戦いを見ると、投打ともに元気がないのが気になります。この今ひとつ調子の上がらない2チームに、セ・リーグのチームがどこまで貯金を作ることができるのかが重要になってくると思います。セ・リーグは広島の前田健太や巨人の菅野智之を筆頭に、パ・リーグの打者相手にも真っ向勝負できるピッチャーが増えています。彼らが投げる試合を確実に取ることができれば、十分に勝ち越せると思います」
昨年、24連勝という驚異的な記録を達成した楽天の田中将大がヤンキースに移籍し、パ・リーグからスーパーエースがまたひとり去った。それだけでもセ・リーグにとっては大きなアドバンテージになるはずだ。さらに広島の大躍進や、現在5位とはいえヤクルトが圧倒的な攻撃力で順調に白星を重ねている。はたして、パ・リーグ相手にどんな戦いを見せるのか。セ・リーグの意地に期待したい。
(Number)