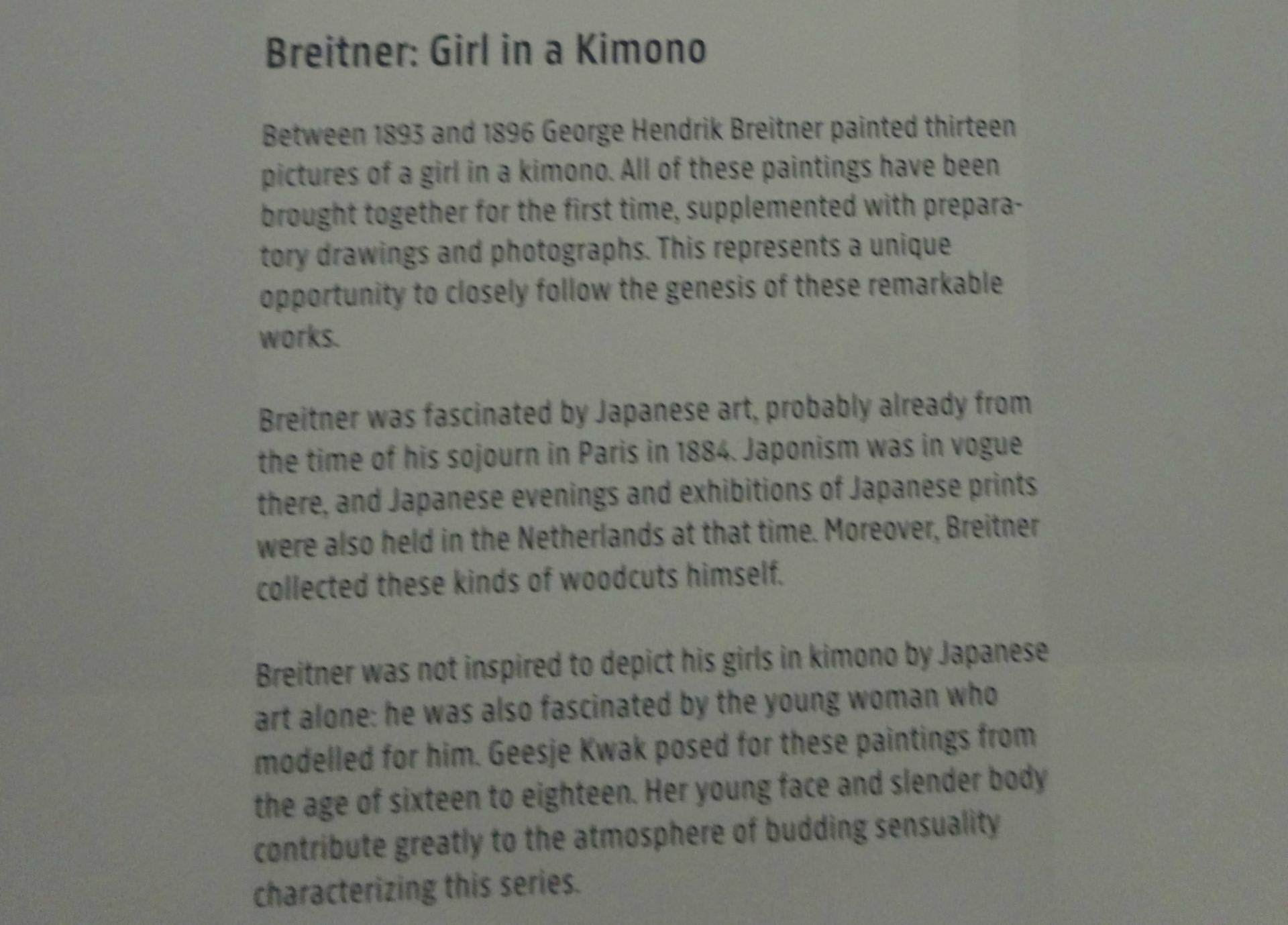少し前までは、完全な形で残ってる最古お法典といわれていた。
現在では、ウル・ナンム法典の方が300年ほど古いといわれていいるが、最初に解読された古代メソポタミアの
法典である。法治国家の始まりといってもよいのではないか。
この石碑はバビロンのマルドック神の神殿にあったといわれてる。上部にハムラビ王と太陽神の像がある。
この石碑は、あまり人気がなく、観客も少なく、ひっそりと佇んでいた。3000年を超えた時間が、
感じられ身の締まるる思いがした。



少し前までは、完全な形で残ってる最古お法典といわれていた。
現在では、ウル・ナンム法典の方が300年ほど古いといわれていいるが、最初に解読された古代メソポタミアの
法典である。法治国家の始まりといってもよいのではないか。
この石碑はバビロンのマルドック神の神殿にあったといわれてる。上部にハムラビ王と太陽神の像がある。
この石碑は、あまり人気がなく、観客も少なく、ひっそりと佇んでいた。3000年を超えた時間が、
感じられ身の締まるる思いがした。



ロゼッタ・ストーンには複雑な歴史がある。
ナポレオンがエジプト遠征で発見したものを、結局、英国が手に入れたという歴史である。
また、エジプトの聖文字の解読には大きなドラマがある。
世界の需要文献に選んだ理由は、考古学上の最大の勝利とヨーロッパの覇権をめぐるツワモノの夢の
残渣であるからである。
2005年に見た時は、あたりに人は全くいず、寂しい限りであった。
その後、何度か訪れるうちに、見る人が増え、昨年は待たないとみられなくなていた。
これは、中近東やヨーロパ以外の人の訪問が増えたためで、世の移り変わりを実感できる。

世界史上需要な文書といえば、取り上げる人により異なるのは当然である。
ここでは、宗教関係の文書を除いて3つ選んでみる。
* ハムラビ法典
世界最古の法典ではないが、ほぼ最古の法治国家の始まりを示すもの。
* ロゼッタ・ストーン
古代の文字が読めるようになり、古代文明の解明に大きく貢献した。
* マグナカルタ
王権を制限し、国家が契約から成り立っていることを示した。
ここではこの3つを取り上げてみる。
マグナカルタは原本は残っていないが、コピーが世界に10枚ほど残されている。アメリカやオーストラリアの
国立文書館に保管されている。
ここに示すものはイングランドのソールスベリーの大聖堂に保管されているものである。
この近くには、アーサー王で有名なウィンチェスター大聖堂もある。少し足を延ばすと
ストーンヘンジがある。

フェルメールとレンブラント展は、いまからみるとがっかりしたものになる。

オランダの絵画の黄金期、プロテスタントのカソリックへの勝利(ルーベンスとベラスケスを指す)
バロックの最高峰を期待していたが失望であった。
ちょうどこの特別展の前に、アムステルダムの国立美術館でフェルメールとレンブラントのすごさに圧倒されて
感動したのちの日本での特別展だったためかもしれない。
オランダのフェルメールは以下が特によかった。


また、レンブラントの以下の作品にも感動した。


これ等に比べるとこの特別展では、公式カタログにある2つに絵が目玉であり、
非常の寂しかった。
カルヴァンジオは、レオナルド・ダヴィンチとルーベンスの間の時期に活躍した画家である。
クラーナハよりは少し時代が後になるが、ほぼ同時代の画家である。

この時代の絵画様式の変化はめまぐるしく、盛期ルネッサンス様式、ヴェネチア派ルネッサンス様式、マニエリスム、
バロックと興味の尽きないところである。
これを概観すると、まず、1470年代のダビンチの受胎告知を取り上げる。

正確な遠近法(画面の中央上部に消失点がある)、空気遠近法(遠くの山が青く薄い)、正確な人体描写などが判る。
しかし、人物(?)-天使と聖母ーのポーズは静的である。しかし。それ以前のゴシック様式とは明らかに異なり、
自然な空間に人物がいる描写である。
ツティアーノやエル・グリコのヴェネチア派やマニエリスムを省略して、カラヴァンジオの女占い師を見てみよう。

これは、上のダビンチから約100年たった時代の作である。
盛期ルネッサンス以後の作品でり、宗教から自由になり、人間的を描いていることが特色である。
タッチはダビンチの延長で、柔らかい光が全体にあたり、人物もポーズをしている。
しかし、ほんの数十年あとのシモーネ・ヴェーユを見ると、この作品も展示されているが、

劇的である。劇的とは、美貌の占い師に見とれている男性の財布を老婆が抜き取ろうとしている瞬間である。
人物のポーズに動きがある。さらに大きな特色は、光が左からあたっていることである。
劇的で、光と闇、もう少しでバロック様式になる。
では、カラヴァンジョのナルキッソスは、人間の内面を光と表情で表している。

光と闇、自分に惚れる劇的瞬間、この強調された、且、人生でも数少ない経験、
これを表そうとする芸術家の衝動がここにある。
すなわち、バロック様式へとつながる道である。
カラヴァンジョはダビンチと、ルーベンスーレンブラントーフェルメールーベラスケスをつなぐ画家である。
クラーナハは、15世紀のドイツの画家である。
イタリアのルネッサンスに呼応した北方ルネッサンスの画家であるが、フランドル地方で活躍した
初期北方ルネッサンスの画家と比べると、少し地味であった。

彼の作品は、キャンバスではなく絵板に書かれている。一部にテンペラ/油彩の絵(ルクレティア)がるので、
テンペラの方が油彩より長持ちするというので比べてみた。


左の正義の寓話の女神の顔にはひび割れが多いが、ルクレティアの顔は比較的きれいである。
服や顔の写実感や質感に関しては、私はフランドールの画家の方が好きであるが、クラーナハの最大の貢献は
裸婦像を定着させたことだと思っている。



左から、ルクレティア、ビーナス、正義の寓話の女神である。どの裸婦も本当に透明なヴェールを羽織っている。
この3枚の絵を比べてみると、手足の長さの誇張、微妙に前後にひねったポーズ、目の力など、マニエリスム的な
印象を受ける。
オランダの画家 ジョージ・H・ブライトナーもジャポニズムの影響を受けた画家である。
着物姿の少女の絵が13点、特別展(2016年2~3月)として展示された。
展示は絵だけでなく、モデルが着た実際の着物も展示されている。
建物には大きくブライトナーの看板が張り出されている。