
微妙な雲行きでしたが、京都に行ってきました。
「国立博物館は嫌やけど、そこ以外やったら京都に行きたい!」
ということで、とりあえず東寺に行ってみようということに。
東寺+妙心寺、東寺+仁和寺、東寺+石清水八幡宮、どれにするかは行ったとこ勝負。
近鉄電車に乗って京都の一つ手前の駅が「東寺」です。
駅を出て西に向かって歩く事数分で東寺の南大門が見えてきます。
東大寺の南大門と違って、奥行きのある門で、仁王像はありません。

南大門を入るとそこには金堂があるのですが、まず左へ曲がってみます。
八幡宮があって、その手前には大きな弘法大師の像が。

「南無大師遍上金剛」・・・
そこから右に曲がって北にむかって歩きます。
右側に金堂、講堂が見てきますが、柵に囲まれています。
暫く進むと「食堂」があります。
この「食堂」は昭和5年に火災で焼失し、再建されたようです。
その内部には火災にあって、炭化した四天王が収められていました。
元々の本尊の千手観音は修復されて、「宝物館」に収められているとのこと。
現在「宝物館」が特別公開されているということで、観にゆかねばなりませんね。
現在の食堂には明珍恒男作の十一面観音像が本尊として安置されていました。
「食堂」の中を通り抜けて東へと進み、そこで拝観券を購入。
五重塔・金堂・講堂の拝観料が800円、宝物館・観智院がそれぞれ500円。
全ての共通券が1300円。
当然共通券ですよね!
ダメモトで障害手帳を見せると割引してくれました。ラッキー!

一番北にあるのが「講堂」です。
最初は弘法大師によって着工されたのですが、
室町時代の土一揆によって消失し、同時代に再建されたそうです。
中は「立体曼荼羅」といわれ、大日如来を中心とした五智如来、五菩薩、五大明王、
四天王、梵天、帝釈天の二十一の仏像が安置されています。
そのうち十五躯が国宝、五躯が重要文化財です。
先日紹介したカレンダーの菩薩もこの中の一躯です。
トップの画像の「梵天」もこの講堂に収められています。


講堂の南側に立っているのが「金堂」。
金堂は796年に創建されたらしいのですが、室町時代に消失、
豊臣秀頼が発願し、江戸時代に完成したそうです。
大きなお堂ですけれども、内部に安置されている仏像は目に入ってくるのは僅か三躯。
本尊の「薬師如来」、「日光菩薩」、「月光菩薩」です。
薬師寺の金堂と同じですね。
しかし、よく見ると中央の薬師如来の台座の下にも仏像があります。
「十二神将」のようです。
「十二神将」といえば、一番有名なのは奈良市の新薬師寺の塑像のものですね。
そちらの十二神将は本尊の周りをぐるりと円形に配置されています。
他には奈良県では興福寺、東大寺、法隆寺にもありますし、
そうそう、やじの故郷の市にある(最近合併して、村から市に格上げになりました)栄山寺にも有るそうです。
この「金堂」の仏像は全て国宝ということです。




金堂・講堂の東側には庭園があって、一休みにもってこいです。


庭園内をうろうろして、庭園の南にある「五重塔」へ。
普段は内部に入ることはできないのですが、今は特別期間なので初層の内部に入ることができます。
内部は極彩色で彩られており、心柱を大日如来として、
その周りを四尊の如来(阿閦如来、宝生如来、阿弥陀如来、不空成就如来)
そして八尊の菩薩が囲んでいます。
内部の柱や壁には八大竜王の、そして真言八祖の絵が描かれていました。
この五重塔も何度かの焼失の後、五代目。徳川家光によって建造されたものらしいです。
四度も焼失しているのに、地震で倒壊したことはないとのこと。


塔を出た後、再び庭園内を北に歩いて、北大門を出たところにある「観智院」へ。
観智院は東寺の勧学院(今で言うと大学院のようなもの)で、所蔵する密教聖教の量と質では日本最高と言われています。
ここには五大虚空菩薩像や愛染明王像が収められています。


「客殿(国宝)」の前に広がる「五大の庭」は弘法大師が唐の長安で密教の全てを受法され、
数々の法具と経典を携えて帰国の途、海上で災難に遭い、守護の海神に護られて無事帰還なされた姿、
そして五大虚空菩薩像の姿とを現しているとされています。


右の写真の右側の島が唐、左奥が日本。
右の写真の手前が龍神、その向こうが鯱、そしてその奥が神亀。
左の写真の左側が弘法大師がお乗りになった遣唐船だった・・・かな。
龍神の顔と、海上に浮かぶ独鈷杵。


様々な襖絵、書を拝見することができました。
そして次に「宝物館」へ。
この中には元々食堂にあった「千手観音」が。
唐招提寺の千手観音に比べると手の数は少ないし、手に仏具を持っていないのですが、
その大きさには圧倒されます。
その他、「大師堂」の北にある鐘楼に掛けられていた鐘も展示されいました。
この鐘は足利尊氏が寄進した鐘で、貞和4年10月に完成して現在に及んだのですが、
鋳造以来650余年が経ち傷みが酷くここに保管され、現在鐘楼に掛けられているのはレプリカらしいです。
では、その大師堂に行かねば・・・
ところで、やじはずっと不思議に思っていた事。
東寺って、京都の南西にあるんですが、なぜ東寺?
この宝物館の出口に、現在の京都市の地図と、昔の平安京の地図を重ねたものがあったのですが、
昔の平安京は今の京都市街よりも西に位置していたようです。
今の京都御所なんて、昔の平安京の東端。
そうだったんだ~。
勉強になりました。
で、「大師堂」」へ。
ちょうど着いたころに堂の中から太鼓と鐘、そしてジャラジャラという音が。
どなたかが御祈祷をお願いされたようです。
その雰囲気を味わうために正座して拝見させてもらいました。
「おんぼうじしつたぼだはだやみ」「おんさんまやさとばん」
中・高時代に覚えたお経が聞こえてきます。


お寺の中にあった、亀の上に乗った石碑。
この亀の周りを亀の頭手足を撫でながら周り、最後に自分の調子の悪いところを撫でると病が治るらしいです。
一生懸命頭をなぜましたよ~。

境内のアツアツの鳩を見つけて、きたが、「あたしたちと一緒やね~ 」。
」。
そうですか?














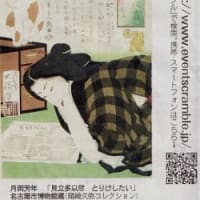
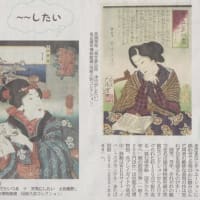





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます