
GW中、大坂城の櫓の内部公開に行ってきました。1620年代の徳川による再建で造営され現存する千貫櫓・乾櫓・多門櫓です。改めて大坂城の石垣や堀の壮大さを実感しました。また、奈良の纒向遺跡の周辺を歩きました。卑弥呼の時代の遺跡と墳墓を歩くと邪馬台国が浮かんでくるような…。加えて、素麺も食べましたが、やはり三輪素麺はいいですねえ。ともにお天気もよく新緑もきれいでした。そんなこんなでGWも終わりました。これからは夏に向かってまっしぐらです。
ということで、今回はヘンデルのオラトリオ『サムソン』であります。これは1741年に『メサイア』とほぼ同時期に作曲されました。1743年2月18日にコヴェント・ガーデンで初演されました。サムソンは、古代イスラエルの士師の1人で、怪力の持ち主として有名です。サン=サーンスもサムソンの歌劇『サムソンとデリラ』を書いていることも周知の通りです。ここでヘンデルは、ハミルトンによる『闘士サムソン』を台本として用いています。
そして、このお話はサムソンの活躍を描くのではなく、捕えられ、両目をくりぬかれてガザで奴隷として鎖につながれているところから、そこでのいろいろな人との交流、そしてペリシテ人が多数集まった建物をその怪力で引き倒し、自分ごとペリシテ人たちを潰し死ぬところまでが描かれています。まあ、それほど興味深い内容でもないですし、内省的とも言えるようなやり取りが多いかなあ、と思ったりしますねえ。
それでこの演奏ですが、カール・リヒターとミュンヘン•バッハ管による演奏が残されています。1968年10,11月にミュンヘンでの録音。アレクサンダー・ヤング(サムソンT)、マルティナ・アーロヨ(デリラS)、
ノーマ・プロクター(ミカA)、トーマス・スチュアート(マノアB)、エツィオ・フラジェルロ(ハノファB)などが主な配役です。リヒターのヘンデルの演奏には、合奏協奏曲や、『メサイア』、『ジュリア・チェーザレ』などがありますが、他にもあるのかも知れませんね。
しかし、このサムソンは、ああやはりリヒターの演奏やなあ、と実感できるものですねえ。特に、第3幕のサムソンが死ぬ前後の演奏については、リヒターのマタイ受難曲でのイエスの処刑の前後の演奏を彷彿とさせるのであります。もちろんマタイのような深さはないのですが、お話がイエスとサムソンの「英雄」の死という共通するところでのオケや合唱の語り口や、そこから感じられる静謐な情景など、このサムソンを聴きながら、マタイの演奏が浮かんできたのでありました。やはり、リヒターの演奏、限りなく深い表情で、実に真摯に、英雄の死を描く。そこには、英雄への限りない共感と憧憬、追憶を感じるのです。そこにはマタイほどの悲痛な哀しみはありませんが、死ということを描くときの静謐な気持ちはとても深いのであります。
そして、ヘンデルらしい、聴きやすく親しみやすい音楽が満載。その中で、まずミカを歌うノーマ・プロクターのアリアがいいです。第二幕の「おお万軍の主よ」と第三幕の「イスラエルの子らよ、今こそ嘆きの声を上げよ」は、とてもいい。暖かみのあるコントラルトで、サムソンへの限りない共感を感じられます。前者は、全曲中で最も繰り返し聴きたくなるアリア。後者は感情がとても深いです。また、サムソンの父のマノアのトマス・スチュアートもいい。最初リヒターとの共演は珍しいな、と思い、フィッシャー=ディースカウだったらどうだったかな、と思ったりしましたが、サムソンの父の愛情が伝わる名唱になっています。第一幕の「お前の輝かしい偉業よ」と第三幕の「この父の愛が」は、暖かみのある男声が深く歌われていますねえ。こんな暖かさが感じられるとは、さすがであります。またイスラエル人の女のヘレン・ドナートは、リヒターとの共演も多いですが、安定した美声で花を添えています。加えて、ミュンヘン・バッハ合唱団、このオラトリオでも活躍しているのですが、とても真摯でリヒターの気持ちを代弁しているようです。これまでのリヒターとの共演者が少ないなあ、と最初は思いましたが、それはそれで新鮮でありました。このリヒター盤はCD三枚ですが、長さを感じない名演でありました。
GWの外出で、かなり日焼けしました。やはり帽子が必要ですねえ。一方、4月29日から1勝9敗のマリーンズです。打てないにもほどがある。実に悲惨な状況であります。これでは最下位も夢でははない!。
(ARCHIV UCCA-3203/5 2007年)
ということで、今回はヘンデルのオラトリオ『サムソン』であります。これは1741年に『メサイア』とほぼ同時期に作曲されました。1743年2月18日にコヴェント・ガーデンで初演されました。サムソンは、古代イスラエルの士師の1人で、怪力の持ち主として有名です。サン=サーンスもサムソンの歌劇『サムソンとデリラ』を書いていることも周知の通りです。ここでヘンデルは、ハミルトンによる『闘士サムソン』を台本として用いています。
そして、このお話はサムソンの活躍を描くのではなく、捕えられ、両目をくりぬかれてガザで奴隷として鎖につながれているところから、そこでのいろいろな人との交流、そしてペリシテ人が多数集まった建物をその怪力で引き倒し、自分ごとペリシテ人たちを潰し死ぬところまでが描かれています。まあ、それほど興味深い内容でもないですし、内省的とも言えるようなやり取りが多いかなあ、と思ったりしますねえ。
それでこの演奏ですが、カール・リヒターとミュンヘン•バッハ管による演奏が残されています。1968年10,11月にミュンヘンでの録音。アレクサンダー・ヤング(サムソンT)、マルティナ・アーロヨ(デリラS)、
ノーマ・プロクター(ミカA)、トーマス・スチュアート(マノアB)、エツィオ・フラジェルロ(ハノファB)などが主な配役です。リヒターのヘンデルの演奏には、合奏協奏曲や、『メサイア』、『ジュリア・チェーザレ』などがありますが、他にもあるのかも知れませんね。
しかし、このサムソンは、ああやはりリヒターの演奏やなあ、と実感できるものですねえ。特に、第3幕のサムソンが死ぬ前後の演奏については、リヒターのマタイ受難曲でのイエスの処刑の前後の演奏を彷彿とさせるのであります。もちろんマタイのような深さはないのですが、お話がイエスとサムソンの「英雄」の死という共通するところでのオケや合唱の語り口や、そこから感じられる静謐な情景など、このサムソンを聴きながら、マタイの演奏が浮かんできたのでありました。やはり、リヒターの演奏、限りなく深い表情で、実に真摯に、英雄の死を描く。そこには、英雄への限りない共感と憧憬、追憶を感じるのです。そこにはマタイほどの悲痛な哀しみはありませんが、死ということを描くときの静謐な気持ちはとても深いのであります。
そして、ヘンデルらしい、聴きやすく親しみやすい音楽が満載。その中で、まずミカを歌うノーマ・プロクターのアリアがいいです。第二幕の「おお万軍の主よ」と第三幕の「イスラエルの子らよ、今こそ嘆きの声を上げよ」は、とてもいい。暖かみのあるコントラルトで、サムソンへの限りない共感を感じられます。前者は、全曲中で最も繰り返し聴きたくなるアリア。後者は感情がとても深いです。また、サムソンの父のマノアのトマス・スチュアートもいい。最初リヒターとの共演は珍しいな、と思い、フィッシャー=ディースカウだったらどうだったかな、と思ったりしましたが、サムソンの父の愛情が伝わる名唱になっています。第一幕の「お前の輝かしい偉業よ」と第三幕の「この父の愛が」は、暖かみのある男声が深く歌われていますねえ。こんな暖かさが感じられるとは、さすがであります。またイスラエル人の女のヘレン・ドナートは、リヒターとの共演も多いですが、安定した美声で花を添えています。加えて、ミュンヘン・バッハ合唱団、このオラトリオでも活躍しているのですが、とても真摯でリヒターの気持ちを代弁しているようです。これまでのリヒターとの共演者が少ないなあ、と最初は思いましたが、それはそれで新鮮でありました。このリヒター盤はCD三枚ですが、長さを感じない名演でありました。
GWの外出で、かなり日焼けしました。やはり帽子が必要ですねえ。一方、4月29日から1勝9敗のマリーンズです。打てないにもほどがある。実に悲惨な状況であります。これでは最下位も夢でははない!。
(ARCHIV UCCA-3203/5 2007年)














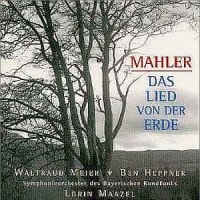
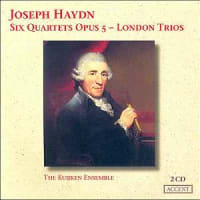
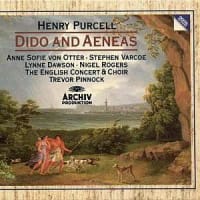








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます