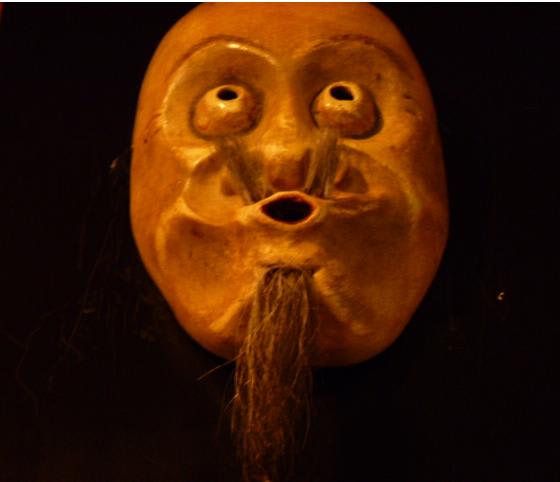文月二十一日 かとよ・・・

野分(台風)吹き しめやかならぬ宵
ひとり つれづれ暮らしたるに・・・

北隣の少将殿 参りて
手づから 瓢(ひさご)携へ
「かやうなる おどろおどろしき夜は いざ 物語せむ!」
など 言ひて・・・

断はりはなくて 上がりぬ・・・
けしうはあらず・・・我 物語のたづき(取りつく手がかり)に

「近頃は 軒に 薄き花の さまざま咲けるが・・・いかむ?」
など 問へば

少将殿「薄き花 葎(むぐら)の門(かど)に 閉ぢられたらむこそ 珍しく覚えめ・・・まして
さやうなる人の らうたげならむ様 いかで はた かかりけむ!
と 怪しく 心とまる わざ なり」など 言ふ

我 「女の これはしも と 難つくまじきは かたくもあるかな・・・」など 返す

少将殿「かたち をかしく 若やかなる程こそは なほ めでたけれ(^^)」など そそめく

我 「しかれども そ は うはべばかりの情(なさけ)なり・・・

・・・品高く 大人しき様したる人の 思ひのほかに らうたげならむ人(^^)・・・
そこ ここ の 門には 落ちておはさむや?」など 言ひて 笑ふ
少将殿「いと むずかしげなり・・・(ーー)」など 返す

我 「ならば しどけなく見奉らむが・・・なでしこの・・・など いかが?」とぞ 尋ぬるに・・・

少将殿「時世の覚え やむごとなきあたりにこそ ひとり ふたり いとゆかしき人もあらん・・・」など 答ふ

我 「まことか! さらば かやうなる うちあひてすぐれたらむ人や いかに?」
少将殿「必ずしも わが思ふにかなはねど・・・いと ゆかしきことも なしや・・・(^^;)」など 言ふ

我 「心もとなくとも 昼顔のごとき やはらかならむ人を とかく引きつくろひては などか見ざらむ」

少将殿「くまなきもの言ひも 頼もしげなきこと・・・なほ 苦しからむ」

夜 更ければなり・・・

風の音 しとどにみだれ飛びて そこここの軒を揺らすに

物語 いぶせきままに・・・

少将殿「我らは・・・絶えて定めかねて 生涯を 子子(ボウフラ)のごとく
あやうきため池に 心づきなき身を浮かべむがよろしき身 ならむ!!!」など うち嘆く
我は 「疾く(とく)帰りたまえば・・・」など 消えも入りぬべく 覚ゆ(ー~;)
♪・・・なでしこの 生ひたつ国の 乙女らの かごとにおぢて うち出でかねつ・・・♪(拙歌)