息子が受けている「駿台模試」(難易度は高く、難しい)。以下の考察をした。
1.出題範囲
2.私が考える対策勉強内容
3.出題内容の詳細と私の出題分析
4.模試の特徴と受ける意味
【駿台模試】内容と対策:関連ページ
・高1:第1回H25.6.9
・高1:第3回H26.2.2
・高2:第1回H26.6.8
◆駿台全国模試:高1(第2回)10月27日(日)実施
1.出題範囲
【英語】
【数学】 小問集合、場合の数と確率、2次関数
※2次不等式、※図形と計量、※図形の性質は選択問題。
【国語】現代文2題、古文1題、漢文1題
2.私が考える対策勉強内容
本来ならば、事前に計画を立て、十分な時間をとって対策をとることが望ましいのだが、
各人の事情により、持ち時間が異なると思われることから、以下のとおり、私なりの対策を考えてみた。
(1)模試の前日にやれること
【英語】
・システム英単語第2章までの1200語の一夜漬け
・ネクステ(Next Stage)Part1文法、Part2語法までの一夜漬け
(英文和訳、英作文、リスニングは諦める)
【数学】
・公式チェックのみ
【現代文】
・必修漢字800選の一夜漬け
【古文】
・文法問題集の一夜漬け
【漢文】
・書き下し文、句形の一夜漬け
(2)模試の1週間前にやれること
【英語】
・システム英単語第2章までの1200語の記憶
・ネクステ(Next Stage)Part1文法、Part2語法までの記憶
(英文和訳、英作文、リスニングは諦める)
【数学】
・公式チェック
・教科書の例題、章末問題のチェック
【現代文】
・必修漢字800選の記憶
・田村のやさしく語る現代文、現代文トレーニング入門編(堀木)の要点を見る。
【古文】
・文法問題集のチェック
【漢文】
・書き下し文、句形を覚える。
(3)模試の1ヵ月前ならできそうなこと
【英語】
・システム英単語第2章までの1200語の3周
・ネクステ(Next Stage)Part1文法、Part2語法までの3周
・英文和訳:英文解釈や英文和訳の問題集の1周
・リスニング 英検準2級、2級のリスニング問題を耳慣らしで聴くのみ
【数学】
・中学分野:平面・立体図形と証明問題の復習
・公式チェック
・教科書の例題、章末問題の3周
・1対1対応の演習 数学Ⅰ、Aの、「数と式」、「2次関数」、「場合の数・確率」、「図形と計量」、「図形の性質」の例題を、読みのみ3周
【現代文】
・必修漢字800選の記憶
・田村のやさしく語る現代文、現代文トレーニング入門編(堀木)の解法を覚える。
【古文】
・文法問題集の3周
(・余裕があったら古文の読解問題集を1周)
【漢文】
・書き下し文、句形の問題集を3周
(4)模試の2ヵ月~数ヵ月前ならできそうなこと
【英語】
・システム英単語第2章までの1200語の3周
・ネクステ(Next Stage)Part1文法、Part2語法、Part3イディオム第20章頻出基本イディオム70までの3周
・英文和訳:英文解釈や英文和訳の問題集の3周
・リスニング 英検準2級、2級のリスニング問題を耳慣らしで聴くのみ
【数学】
・中学分野:平面・立体図形と証明問題の復習
・公式チェック
・教科書の例題、章末問題の3周
・1対1対応の演習 数学Ⅰ、Aの「数と式」、「2次関数」、「場合の数・確率」、「図形と計量」、「図形の性質」の例題の3周
【現代文】
・必修漢字800選の記憶
・田村のやさしく語る現代文、現代文トレーニング入門編(堀木)の解法を覚え、問題を解く。
【古文】
・文法問題集の3周
・古文の読解問題集を3周
【漢文】
・書き下し文、句形の問題集を3周
・漢文の読解問題集を3周
3.出題内容の詳細と私の出題分析
【英語】
・単語は、全問題中を調べてみたところ、システム英単語で言うと、基本レベル(第1章)が41語、センター試験レベル(第2章)が13語、2次試験レベル(第3章)が7個、難語(第4章)2語だった。
システム英単語Basicの第1章とシステム英単語の第1章、第2章までの1200語までをやれば十分だと思われる。
・英文法は、学校で参考書とされてはいるが目を通さず埃がかぶっている「総合英語Forest」も一読しておく。
・総合問題
英文和訳
文章構造がどうなっているか混乱する問題が4題中、1題あった。
その文には、分詞、関係代名詞that、how節が一文に盛り込まれていた。
今使っている「英語リーディング教本」では直接該当する問題はなかったものの、当面は同書を繰り返し、精進する。
参考書・問題集例:ビジュアル英文解釈PART1、英語リーディング教本、英文和訳演習
内容説明
文章読解力は、結局、現代文などと合わせて培っていくしかない。英語独自で鍛錬するには、総合問題集が適当だと思われる。
問題集例:やっておきたい英語長文300、英語長文Rise読解演習1.基礎編、英語総合問題演習
・英作文
引き続き、基本文法事項は確実にすることは当然だが、そこからさらにレベルアップをどう図っていかかが課題であり、変わらず難しいところだ。
使用問題集はペンディングとしたい。
・リスニング
英検のリスニングのスクリプトと比較したところ、会話問題は準2級から2級の間位、長文問題は準1級相当のもので、特に長文問題の方はスクリプトを見る限り、全文を聴きとるのは、かなり聴きこんでいないと難しいように思う。英文音読発音や速読完成の後に、日々の地道な取り組みが必要となってくる。
問題集例:英検準2級、2級リスニング問題、速読英単語(入門編)、速読英単語(必修編)
【数学】
まずは出題内容と手持ちの問題集(数学Ⅰ・A基礎問題精講、青チャート、1対1対応演習)との対応分析について
対応・類題 あり○、一部関連△、なし×:( )は該当しているか分からないもの
〔小問〕
・式の値
数学Ⅰ・A基礎問題精講△、青チャート△、1対1対応演習△(例題)
・2次関数の決定
数学Ⅰ・A基礎問題精講○、青チャート○、1対1対応演習○(例題)
・2次方程式の定義域が与えられた時の定数aの決定
数学Ⅰ・A基礎問題精講○、青チャート○、1対1対応演習(△)(例題)
・正12角形の頂点を結んでできる三角形の数
数学Ⅰ・A基礎問題精講△、青チャート○、1対1対応演習○(例題)
・f(x)に条件が与えられた時の命題の真偽と必要条件、十分条件
数学Ⅰ・A基礎問題精講×、青チャート×、1対1対応演習×(例題)
・2次関数が与えられた条件を満たす場合の定数aの範囲
数学Ⅰ・A基礎問題精講×、青チャート○、1対1対応演習△(例題)
〔大問〕確率 2枚のコインを投げた時、立方体の辺上を動く点
数学Ⅰ・A基礎問題精講(×)、青チャート(×)、1対1対応演習(×)(例題)
〔大問〕2次関数の最小値(定数aが変化する時)
x=0、2との交点の最小値
数学Ⅰ・A基礎問題精講(×)、青チャート(×)、1対1対応演習(×)(例題)
x=sとの交点の最小値
数学Ⅰ・A基礎問題精講(×)、青チャート(×)、1対1対応演習(×)(例題)
y>0となるxの範囲
数学Ⅰ・A基礎問題精講(×)、青チャート(×)、1対1対応演習(×)(例題)
〔大問〕図形の計量 円に内接する三角形、四角形
内接三角形のsinθの値
数学Ⅰ・A基礎問題精講(×)、青チャート(×)、1対1対応演習(×)(例題)
外接円の面積
数学Ⅰ・A基礎問題精講(×)、青チャート(×)、1対1対応演習(×)(例題)
三角形の辺の長さ
数学Ⅰ・A基礎問題精講(×)、青チャート○、1対1対応演習(×)(例題)
内接四角形の対角線の長さ
数学Ⅰ・A基礎問題精講○、青チャート○、1対1対応演習○(例題)
内接四角形の内部の三角形のsinθの値
数学Ⅰ・A基礎問題精講×、青チャート×、1対1対応演習×(例題)
・もうひとつの2次関数の不等式問題と図形の性質の問題は選択しなかったので分析省略
今回、1対1対応の演習(例題)で、一見、そのまま対応できないと見られるのは、
①命題と論理の真偽、必要条件・十分条件の問題で、関数の条件が与えられた場合と絡めた問題
②確率で、2枚のコインを投げた時、立方体の辺上を動く点といった初見的な問題
③2次関数の最小値(定数aが変化する時)を求める問題で初見的な問題
であった。
しかしながら、②、③については、とっかかり部分は見慣れないものの、素直に受け止めて解き始めれば、誘導に乗っかっていける。
②は、立体というひねりでスタートだったが、結局は、経路の場合の数とその確率。誘導がとても親切だった。
1対1対応の演習では数学Aの例題8に関係すると思われるが、この例題の方が難しい。
最後の問題には、条件付き確率が加わる。
③は、変数がxからaに置き換えられるひねりでスタートする。
x=0.2を代入すると、p=aの2次式となり、pの最小値を求めれば良い。最小値を求める手順は定型的なもので、1対1対応の演習では数学Ⅰの例題7が関係する。
続いて、x=sを代入すると、s=aの2次式となり、sの最小値を求めれば良い。
aの範囲の縛りがあるため、場合分けが必要となるが、手順は定型的なもので、同じく1対1対応の演習では、数学Ⅰの例題7が関係する。
最後は、sの範囲に応じて求めた最小値の関数について、それぞれグラフを描いて接続する。これもしいて言うなら、1対1対応の演習では数学Ⅰの例題7が関係するか。
息子も、誘導にうまく乗れた。
思うに、バリエーションがある初見的な問題の分野は決まってくるのではないか。
それは、
・場合分けが多いこと
・複雑な構成が可能なこと
・他の分野と融合が可能なこと
である。
今回は、
・確率(場合分け)と立体図形
・2次関数と場合分けとグラフ
で見られた。
以上から、引き続き、1対1対応の演習(数学Ⅰ、数学A)の例題は3周を確保して、完全に近づける。
その後、取り組む問題集は、再度考える。
【国語】
◆現代文
私独自の考えだが、
選択式問題においては、
①明らかにこれだと分かる選択肢が1つだけある場合
②一見選択肢の内容は分かるが、良く良く注意して検討しないと、間違いを掴まされてひっかかって間違ってしまうものが紛れている。
③選択肢を読んでもさっぱり分けがわからないし、どれだか皆目判断がつかない
があると考える。②、③の対策をどうしたらよいかが問題となる。
これに対処するには、まずは、文章を読んだ時の、自分の先入観・スキーマと、著者のスキーマと、さらに出題者のスキーマを一致させなければならない。
自分のスキーマと著者のスキーマの一致までは割と行くと思う。
しかし、その上の、出題者のスキーマに合わせることや、さらには出題者による②、③のような意図的な混乱を目的とした選択肢が出された場合は、どうしてもひっかかってしまうと思うのである。
そして、多くの場合、選択肢は必ずしも文中の字面通りに表現されていない。出題者による言い換えがある。
他方、記述式問題においては、
文章を読んだ時の、自分の先入観・スキーマと、著者のスキーマと、さらに出題者のスキーマを一致させなければならないことは、選択問題と同じである。
その上で、どこの部分の内容を書けばよいのかを見つけ出すことは必須であるが、文章を広範囲にわたり編集したり、最終的に字数以内に整える作業が必要となる。
さらに、
本文内で直接記述されていないことも、補って解答させようと要求しているものもある。
今回の評論文の記述問題の問3がそうだ。
文章の整合性などを保つための調整と解説にあったが、小林秀雄の文章が飛躍気味なところがあるためだと思われる。このことを逆手にとった出題であったとも考えられる。
この飛躍部分を補うことも採点基準に加えられているが、難しく、満点は早々とれない感じがする。
ここまでいくと、非常に技巧的で巧妙なことが要求されているなと思う。
しかし、あれこれ高度なことを考えだしたら何もできなくなってしまうので、
とりあえず、
文章読解の最も基本的なことして、自分自身のスキーマを、著者のスキーマ(文章で述べているイイタイコトの把握)に一致させる修練を積みたい。
そのため、やはり、読解を行う各文章について、意味段落分け、意味段落要約、全文要約、表題付けなどを、息子、自分で行い、問題文との比較表を作って見ることにする。
その後に、出題者のスキーマと出題意図の分析を、まずは、まずは選択問題でやってみようと思う。
一方、小説に対する対策は、今の時点では分からないところが多いのでペンディングとしたい。
問題集例:田村のやさしく語る現代文、現代文トレーニング入門編(堀木)
◆古文
今の段階では、出題される文章の内容により解答の得点が左右されるのは、仕方ないことにする。
当面は、傍線部のみの正確な現代語訳(解釈)ができるようしていくため、古語の語彙を増やし、古典文法を改めて確実に確認しつつ、現代語訳力を、簡単な問題集から着実に伸ばして行く。
問題集例:古典文法10題ドリル 古文基礎編、古文必修問題集(演習編)
◆漢文
基本事項(句形、返り点、書き下し文、漢字の読み・意味)を即刻固めることが先決。
内容に関わる問題は、基本事項を踏まえた解釈はできるようにしておくことにして、現代文演習による文章読解力向上も待つことにする。
問題集例:三羽邦美の漢文教室
4.模試の特徴と受ける意味
(1)特徴
①範囲が広く大雑把。過去問も公開されていない。
⇒具体的に何を勉強していいか分からないことが多い。
②あくまで模擬テスト。実際の大学入試問題ではない。
⇒分析して対策をとり勉強することはあまり意味がないという考え方もあり。
③他方、誘導型設問が多く出題。採点基準も明確。
⇒答案返却後、自分の実力で、どこが足りないかを詳細にチェックすることが可能。
(2)受ける意味
①自ら事前に目標を設定して勉強計画を立てる練習となる。
②勉強実行とその結果の評価過程を自己管理する。
⇒実際の入試に臨む際の訓練となる。
※仕事のように、PDCA(計画→実行→評価→改善)サイクルで、手帳、カレンダーなど、何らかのスケジュール管理ができればベスト。
【駿台模試】内容と対策:関連ページ
・高1:第1回H25.6.9
・高1:第3回H26.2.2
・高2:第1回H26.6.8
≪参考≫
息子の結果
1.主な受験校一覧(人数)
2.模試受験に当たっての勉強方針と実際行った勉強内容
3.私の所感:分析、無駄だった点・失敗だった点
---------------------------------------------
1.主な受験校一覧(人数)
栄東521、市川402、浦和(県立)400、洛南375、渋谷教育学園幕張339、日比谷317、海城286、芝281、攻玉社244、豊島岡女子学園243、巣鴨241、駒場東邦236、鴎友学園女子224、栄光学園178、本郷(東京)123、海陽76、桜蔭74、開成61
2.模試受験に当たっての勉強方針と実際行った勉強内容
(1)勉強方針
【英語】
単語力の強化、文法事項の習得状況確認、速読の練習、和文英訳力の向上を目指した。
学校での英語の教科書はNEW TRESURE(Z会)。
【数学】
前回(第1回H25.6)の教訓から、基本的には、1対1対応の演習の例題をマスターすることを目標にした。基本事項の不安もあるので、併せて数学Ⅰ・A基礎問題精講もやった。
また、今回、図形分野も範囲となるが、相変わらず苦手なので、中学範囲の復習をレベルアップ演習でやった。
【国語】
・現代文(評論文・小説)
どんな問題集などを使って勉強すれば良いか決めきれなかったので、勉強しないことにした。
・古文、漢文
同上
(2)実際行った勉強内容
【英語】
・システム英単語(第2章センターまで)の暗記
・速読英単語(必修編)
・そこが知りたい英文法
・英語リーディング教本
【数学】
・高校への数学(別冊)レベルアップ演習
4 整数、6 場合の数・確率、7 合同&線分比・面積、8 相似、9 三平方の定理、10 円、11 立体
・数学Ⅰ・A基礎問題精講
2次関数、図形と計量、図形の性質
・1対1対応の演習(新訂版)の例題
数学Ⅰ:数と式、2次関数、図形と計量
数学A:場合の数、確率、図形の性質
【国語】
・現代文、古文、漢文 なし
3.私の所感:分析、無駄だった点・失敗だった点
【英語】
・総合力はある。しかし、皆、得点できる文法がいまひとつ。
間違えた問題は、anyの用法、時制、can Iの用法だった。
使用している文法問題集「そこが知りたい英文法」を見ると時制の問題しか説明がなかった。
しかし、学校で参考書としている「総合英語Forest」では、anyの用法と、can Iの用法が解説されていた。
また、内容理解の内容合致の問題(選択式)に失点があった。現代文があまり得意でないことに関係しているのだろう。
【数学】
・全体で7割5分超えたのはよくぞという感じ。
・計算がからむ図形問題(図形と計量分野)は8割5分と頼もしい。
・しかし、小問のところで失点している。
式の値では、理解していないところがあった。
命題と論理では、基本的にわかっていなかったところがあり、ひねられて間違った。
2次関数の定数の範囲を求める問題でも、理解が足りていないところがあった。
確率〔大問〕では、最後の問題が条件付き確率であることが見抜けなかった。
2次関数〔大問〕では、パラメータ範囲の単純な計算ミスで痛恨の12点も失点した。最後の問題は全く歯が立たなかった。
図形と計量・円に内接する四角形〔大問〕では、最後の問題は全く分からず歯が立たなかった。
・2次関数の問題は、難易度が高くなってくると、場合分けとイメージを掴むのが難しいようだ。難易度をあげて鍛錬をつんでいく必要がある。
【国語】
・現代文では、小説がことのほかできていた。他人の意をくまない性質なのに不思議なものだ。
それに対して評論文は…
小林秀雄の文章だから仕方ないのだろうか。今回、出題されたのは「中庸」。
平成25年の大学入試センター試験では、突如「鐔(つば)」が出題されたとのこと。
昭和の時代、小林秀雄は出題されていたが、平成になってからはなかったようだ。
小林秀雄の代表作は、「ドストエフスキイの生活」、「無常といふ事」、「モオツァルト」、「ゴッホの手紙」、「近代絵画」、「考へるヒント」、「本居宣長」など。
正直、難しいと思う。今回の出題文は大人の私が読んでも、一読目は何をいわんとしているか分からなかった。
駿台としては、センター試験で小林秀雄が出題されたこと期に、難文挑戦を復活させたのだろうか。
息子の得点だが、問3傍線部理由説明(記述)75字以内(7点/10点満点)はたまたまか7割と良い点がとれていたものの、息子の解答文章を見て見ると何をいいたいのか分からない文章だった。キーワード的表現が入っていたら加点式で点数をもらえるのだろうか。
・古文は、文法は良くできた。また、現代語訳もできた。
しかし、それ以外の語彙や理由説明(選択も記述も)は散々な結果だった。
本文内容は現代語訳を見ると、夫婦間の感情と姑の感情がからむものだったので、その辺に疎い息子には厳しいだろうし、また興味もないだろう。
息子の実際の解答を見ても、全く的外れで、言いたいことがわからなかった。
邪推ではあるが、すぐ分かる内容だと、皆、解けてしまったテストにならないのだろう。
しかし、どうせなら、大人になってもあの時読んだなーとか、参考になりそうな内容の文章だといいように思う。
・漢文は、現代語訳はできているが、文法事項(返り点、書き下し文)や内容説明もできが悪かった。
文法事項は完成していないからだと思うが、早急に完成させる必要がある。
今回の内容は、国を治める人間は一族など宮中に限って営みを追求し恵みを施すのでなく、広く人民にも恵みを施した方が良い、との内容だった。この程度の内容ならば、小さい子供でも分かりそうなもので、もっと実のある内容を取り上げてもいいと思う。
ただ、国語として内容把握を問題とする場合、内容の程度が同じであれば、現代文<古文<漢文の順に難易度が上がると思われる。古文、漢文はいわば外国語みたいなものと考えてもいいので、漢文の内容把握が一番とっつきにくいのかもしれない。
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋
【駿台模試】内容と対策:関連ページ
・高1:第1回H25.6.9
・高1:第3回H26.2.2
・高2:第1回H26.6.8
≪他のページ≫
・現代文勉強法の考察~各問題集を巡って~【田村のやさしく語る現代文】編
・現代文勉強法の考察~各問題集を巡って~【現代文のトレーニング入門編】編
・【現代文の勉強法01】要約力、文章構造分析力、アイデア創造の発問力の強化-日本語能力試験N2編(1) 問題10(1)
・【東大理系数学】過去問における必須解法・手法の逆算分析~網羅系問題集の該当例題~
・【大学への数学1対1対応の演習】の使い方・勉強法-直観力鍛錬と問題構造分析-数学Ⅰ数と式 例題8
・【能力開発】図形センスを磨き、難問を制覇する-高校への数学「レベルアップ演習」編§7合同&線分比・面積比-
・【システム英単語勉強法】600語を20日間で記憶するためにエクセルを活用した覚え方
・【英語多読】目指せ!大学受験の英文読解で100万語!
★美術展・街歩きのページ
★私の読書メーター(全記録)
★読書日記(受験本)
★ウェブ記事セレクション(H27.1~)
★ウェブ記事セレクション(H26.6~12)
★ウェブ記事セレクション(H26.1~6)



1.出題範囲
2.私が考える対策勉強内容
3.出題内容の詳細と私の出題分析
4.模試の特徴と受ける意味
【駿台模試】内容と対策:関連ページ
・高1:第1回H25.6.9
・高1:第3回H26.2.2
・高2:第1回H26.6.8
◆駿台全国模試:高1(第2回)10月27日(日)実施
1.出題範囲
【英語】
【数学】 小問集合、場合の数と確率、2次関数
※2次不等式、※図形と計量、※図形の性質は選択問題。
【国語】現代文2題、古文1題、漢文1題
2.私が考える対策勉強内容
本来ならば、事前に計画を立て、十分な時間をとって対策をとることが望ましいのだが、
各人の事情により、持ち時間が異なると思われることから、以下のとおり、私なりの対策を考えてみた。
(1)模試の前日にやれること
【英語】
・システム英単語第2章までの1200語の一夜漬け
・ネクステ(Next Stage)Part1文法、Part2語法までの一夜漬け
(英文和訳、英作文、リスニングは諦める)
【数学】
・公式チェックのみ
【現代文】
・必修漢字800選の一夜漬け
【古文】
・文法問題集の一夜漬け
【漢文】
・書き下し文、句形の一夜漬け
(2)模試の1週間前にやれること
【英語】
・システム英単語第2章までの1200語の記憶
・ネクステ(Next Stage)Part1文法、Part2語法までの記憶
(英文和訳、英作文、リスニングは諦める)
【数学】
・公式チェック
・教科書の例題、章末問題のチェック
【現代文】
・必修漢字800選の記憶
・田村のやさしく語る現代文、現代文トレーニング入門編(堀木)の要点を見る。
【古文】
・文法問題集のチェック
【漢文】
・書き下し文、句形を覚える。
(3)模試の1ヵ月前ならできそうなこと
【英語】
・システム英単語第2章までの1200語の3周
・ネクステ(Next Stage)Part1文法、Part2語法までの3周
・英文和訳:英文解釈や英文和訳の問題集の1周
・リスニング 英検準2級、2級のリスニング問題を耳慣らしで聴くのみ
【数学】
・中学分野:平面・立体図形と証明問題の復習
・公式チェック
・教科書の例題、章末問題の3周
・1対1対応の演習 数学Ⅰ、Aの、「数と式」、「2次関数」、「場合の数・確率」、「図形と計量」、「図形の性質」の例題を、読みのみ3周
【現代文】
・必修漢字800選の記憶
・田村のやさしく語る現代文、現代文トレーニング入門編(堀木)の解法を覚える。
【古文】
・文法問題集の3周
(・余裕があったら古文の読解問題集を1周)
【漢文】
・書き下し文、句形の問題集を3周
(4)模試の2ヵ月~数ヵ月前ならできそうなこと
【英語】
・システム英単語第2章までの1200語の3周
・ネクステ(Next Stage)Part1文法、Part2語法、Part3イディオム第20章頻出基本イディオム70までの3周
・英文和訳:英文解釈や英文和訳の問題集の3周
・リスニング 英検準2級、2級のリスニング問題を耳慣らしで聴くのみ
【数学】
・中学分野:平面・立体図形と証明問題の復習
・公式チェック
・教科書の例題、章末問題の3周
・1対1対応の演習 数学Ⅰ、Aの「数と式」、「2次関数」、「場合の数・確率」、「図形と計量」、「図形の性質」の例題の3周
【現代文】
・必修漢字800選の記憶
・田村のやさしく語る現代文、現代文トレーニング入門編(堀木)の解法を覚え、問題を解く。
【古文】
・文法問題集の3周
・古文の読解問題集を3周
【漢文】
・書き下し文、句形の問題集を3周
・漢文の読解問題集を3周
3.出題内容の詳細と私の出題分析
【英語】
・単語は、全問題中を調べてみたところ、システム英単語で言うと、基本レベル(第1章)が41語、センター試験レベル(第2章)が13語、2次試験レベル(第3章)が7個、難語(第4章)2語だった。
システム英単語Basicの第1章とシステム英単語の第1章、第2章までの1200語までをやれば十分だと思われる。
・英文法は、学校で参考書とされてはいるが目を通さず埃がかぶっている「総合英語Forest」も一読しておく。
・総合問題
英文和訳
文章構造がどうなっているか混乱する問題が4題中、1題あった。
その文には、分詞、関係代名詞that、how節が一文に盛り込まれていた。
今使っている「英語リーディング教本」では直接該当する問題はなかったものの、当面は同書を繰り返し、精進する。
参考書・問題集例:ビジュアル英文解釈PART1、英語リーディング教本、英文和訳演習
内容説明
文章読解力は、結局、現代文などと合わせて培っていくしかない。英語独自で鍛錬するには、総合問題集が適当だと思われる。
問題集例:やっておきたい英語長文300、英語長文Rise読解演習1.基礎編、英語総合問題演習
・英作文
引き続き、基本文法事項は確実にすることは当然だが、そこからさらにレベルアップをどう図っていかかが課題であり、変わらず難しいところだ。
使用問題集はペンディングとしたい。
・リスニング
英検のリスニングのスクリプトと比較したところ、会話問題は準2級から2級の間位、長文問題は準1級相当のもので、特に長文問題の方はスクリプトを見る限り、全文を聴きとるのは、かなり聴きこんでいないと難しいように思う。英文音読発音や速読完成の後に、日々の地道な取り組みが必要となってくる。
問題集例:英検準2級、2級リスニング問題、速読英単語(入門編)、速読英単語(必修編)
【数学】
まずは出題内容と手持ちの問題集(数学Ⅰ・A基礎問題精講、青チャート、1対1対応演習)との対応分析について
対応・類題 あり○、一部関連△、なし×:( )は該当しているか分からないもの
〔小問〕
・式の値
数学Ⅰ・A基礎問題精講△、青チャート△、1対1対応演習△(例題)
・2次関数の決定
数学Ⅰ・A基礎問題精講○、青チャート○、1対1対応演習○(例題)
・2次方程式の定義域が与えられた時の定数aの決定
数学Ⅰ・A基礎問題精講○、青チャート○、1対1対応演習(△)(例題)
・正12角形の頂点を結んでできる三角形の数
数学Ⅰ・A基礎問題精講△、青チャート○、1対1対応演習○(例題)
・f(x)に条件が与えられた時の命題の真偽と必要条件、十分条件
数学Ⅰ・A基礎問題精講×、青チャート×、1対1対応演習×(例題)
・2次関数が与えられた条件を満たす場合の定数aの範囲
数学Ⅰ・A基礎問題精講×、青チャート○、1対1対応演習△(例題)
〔大問〕確率 2枚のコインを投げた時、立方体の辺上を動く点
数学Ⅰ・A基礎問題精講(×)、青チャート(×)、1対1対応演習(×)(例題)
〔大問〕2次関数の最小値(定数aが変化する時)
x=0、2との交点の最小値
数学Ⅰ・A基礎問題精講(×)、青チャート(×)、1対1対応演習(×)(例題)
x=sとの交点の最小値
数学Ⅰ・A基礎問題精講(×)、青チャート(×)、1対1対応演習(×)(例題)
y>0となるxの範囲
数学Ⅰ・A基礎問題精講(×)、青チャート(×)、1対1対応演習(×)(例題)
〔大問〕図形の計量 円に内接する三角形、四角形
内接三角形のsinθの値
数学Ⅰ・A基礎問題精講(×)、青チャート(×)、1対1対応演習(×)(例題)
外接円の面積
数学Ⅰ・A基礎問題精講(×)、青チャート(×)、1対1対応演習(×)(例題)
三角形の辺の長さ
数学Ⅰ・A基礎問題精講(×)、青チャート○、1対1対応演習(×)(例題)
内接四角形の対角線の長さ
数学Ⅰ・A基礎問題精講○、青チャート○、1対1対応演習○(例題)
内接四角形の内部の三角形のsinθの値
数学Ⅰ・A基礎問題精講×、青チャート×、1対1対応演習×(例題)
・もうひとつの2次関数の不等式問題と図形の性質の問題は選択しなかったので分析省略
今回、1対1対応の演習(例題)で、一見、そのまま対応できないと見られるのは、
①命題と論理の真偽、必要条件・十分条件の問題で、関数の条件が与えられた場合と絡めた問題
②確率で、2枚のコインを投げた時、立方体の辺上を動く点といった初見的な問題
③2次関数の最小値(定数aが変化する時)を求める問題で初見的な問題
であった。
しかしながら、②、③については、とっかかり部分は見慣れないものの、素直に受け止めて解き始めれば、誘導に乗っかっていける。
②は、立体というひねりでスタートだったが、結局は、経路の場合の数とその確率。誘導がとても親切だった。
1対1対応の演習では数学Aの例題8に関係すると思われるが、この例題の方が難しい。
最後の問題には、条件付き確率が加わる。
③は、変数がxからaに置き換えられるひねりでスタートする。
x=0.2を代入すると、p=aの2次式となり、pの最小値を求めれば良い。最小値を求める手順は定型的なもので、1対1対応の演習では数学Ⅰの例題7が関係する。
続いて、x=sを代入すると、s=aの2次式となり、sの最小値を求めれば良い。
aの範囲の縛りがあるため、場合分けが必要となるが、手順は定型的なもので、同じく1対1対応の演習では、数学Ⅰの例題7が関係する。
最後は、sの範囲に応じて求めた最小値の関数について、それぞれグラフを描いて接続する。これもしいて言うなら、1対1対応の演習では数学Ⅰの例題7が関係するか。
息子も、誘導にうまく乗れた。
思うに、バリエーションがある初見的な問題の分野は決まってくるのではないか。
それは、
・場合分けが多いこと
・複雑な構成が可能なこと
・他の分野と融合が可能なこと
である。
今回は、
・確率(場合分け)と立体図形
・2次関数と場合分けとグラフ
で見られた。
以上から、引き続き、1対1対応の演習(数学Ⅰ、数学A)の例題は3周を確保して、完全に近づける。
その後、取り組む問題集は、再度考える。
【国語】
◆現代文
私独自の考えだが、
選択式問題においては、
①明らかにこれだと分かる選択肢が1つだけある場合
②一見選択肢の内容は分かるが、良く良く注意して検討しないと、間違いを掴まされてひっかかって間違ってしまうものが紛れている。
③選択肢を読んでもさっぱり分けがわからないし、どれだか皆目判断がつかない
があると考える。②、③の対策をどうしたらよいかが問題となる。
これに対処するには、まずは、文章を読んだ時の、自分の先入観・スキーマと、著者のスキーマと、さらに出題者のスキーマを一致させなければならない。
自分のスキーマと著者のスキーマの一致までは割と行くと思う。
しかし、その上の、出題者のスキーマに合わせることや、さらには出題者による②、③のような意図的な混乱を目的とした選択肢が出された場合は、どうしてもひっかかってしまうと思うのである。
そして、多くの場合、選択肢は必ずしも文中の字面通りに表現されていない。出題者による言い換えがある。
他方、記述式問題においては、
文章を読んだ時の、自分の先入観・スキーマと、著者のスキーマと、さらに出題者のスキーマを一致させなければならないことは、選択問題と同じである。
その上で、どこの部分の内容を書けばよいのかを見つけ出すことは必須であるが、文章を広範囲にわたり編集したり、最終的に字数以内に整える作業が必要となる。
さらに、
本文内で直接記述されていないことも、補って解答させようと要求しているものもある。
今回の評論文の記述問題の問3がそうだ。
文章の整合性などを保つための調整と解説にあったが、小林秀雄の文章が飛躍気味なところがあるためだと思われる。このことを逆手にとった出題であったとも考えられる。
この飛躍部分を補うことも採点基準に加えられているが、難しく、満点は早々とれない感じがする。
ここまでいくと、非常に技巧的で巧妙なことが要求されているなと思う。
しかし、あれこれ高度なことを考えだしたら何もできなくなってしまうので、
とりあえず、
文章読解の最も基本的なことして、自分自身のスキーマを、著者のスキーマ(文章で述べているイイタイコトの把握)に一致させる修練を積みたい。
そのため、やはり、読解を行う各文章について、意味段落分け、意味段落要約、全文要約、表題付けなどを、息子、自分で行い、問題文との比較表を作って見ることにする。
その後に、出題者のスキーマと出題意図の分析を、まずは、まずは選択問題でやってみようと思う。
一方、小説に対する対策は、今の時点では分からないところが多いのでペンディングとしたい。
問題集例:田村のやさしく語る現代文、現代文トレーニング入門編(堀木)
◆古文
今の段階では、出題される文章の内容により解答の得点が左右されるのは、仕方ないことにする。
当面は、傍線部のみの正確な現代語訳(解釈)ができるようしていくため、古語の語彙を増やし、古典文法を改めて確実に確認しつつ、現代語訳力を、簡単な問題集から着実に伸ばして行く。
問題集例:古典文法10題ドリル 古文基礎編、古文必修問題集(演習編)
◆漢文
基本事項(句形、返り点、書き下し文、漢字の読み・意味)を即刻固めることが先決。
内容に関わる問題は、基本事項を踏まえた解釈はできるようにしておくことにして、現代文演習による文章読解力向上も待つことにする。
問題集例:三羽邦美の漢文教室
4.模試の特徴と受ける意味
(1)特徴
①範囲が広く大雑把。過去問も公開されていない。
⇒具体的に何を勉強していいか分からないことが多い。
②あくまで模擬テスト。実際の大学入試問題ではない。
⇒分析して対策をとり勉強することはあまり意味がないという考え方もあり。
③他方、誘導型設問が多く出題。採点基準も明確。
⇒答案返却後、自分の実力で、どこが足りないかを詳細にチェックすることが可能。
(2)受ける意味
①自ら事前に目標を設定して勉強計画を立てる練習となる。
②勉強実行とその結果の評価過程を自己管理する。
⇒実際の入試に臨む際の訓練となる。
※仕事のように、PDCA(計画→実行→評価→改善)サイクルで、手帳、カレンダーなど、何らかのスケジュール管理ができればベスト。
【駿台模試】内容と対策:関連ページ
・高1:第1回H25.6.9
・高1:第3回H26.2.2
・高2:第1回H26.6.8
≪参考≫
息子の結果
1.主な受験校一覧(人数)
2.模試受験に当たっての勉強方針と実際行った勉強内容
3.私の所感:分析、無駄だった点・失敗だった点
---------------------------------------------
1.主な受験校一覧(人数)
栄東521、市川402、浦和(県立)400、洛南375、渋谷教育学園幕張339、日比谷317、海城286、芝281、攻玉社244、豊島岡女子学園243、巣鴨241、駒場東邦236、鴎友学園女子224、栄光学園178、本郷(東京)123、海陽76、桜蔭74、開成61
2.模試受験に当たっての勉強方針と実際行った勉強内容
(1)勉強方針
【英語】
単語力の強化、文法事項の習得状況確認、速読の練習、和文英訳力の向上を目指した。
学校での英語の教科書はNEW TRESURE(Z会)。
【数学】
前回(第1回H25.6)の教訓から、基本的には、1対1対応の演習の例題をマスターすることを目標にした。基本事項の不安もあるので、併せて数学Ⅰ・A基礎問題精講もやった。
また、今回、図形分野も範囲となるが、相変わらず苦手なので、中学範囲の復習をレベルアップ演習でやった。
【国語】
・現代文(評論文・小説)
どんな問題集などを使って勉強すれば良いか決めきれなかったので、勉強しないことにした。
・古文、漢文
同上
(2)実際行った勉強内容
【英語】
・システム英単語(第2章センターまで)の暗記
・速読英単語(必修編)
・そこが知りたい英文法
・英語リーディング教本
【数学】
・高校への数学(別冊)レベルアップ演習
4 整数、6 場合の数・確率、7 合同&線分比・面積、8 相似、9 三平方の定理、10 円、11 立体
・数学Ⅰ・A基礎問題精講
2次関数、図形と計量、図形の性質
・1対1対応の演習(新訂版)の例題
数学Ⅰ:数と式、2次関数、図形と計量
数学A:場合の数、確率、図形の性質
【国語】
・現代文、古文、漢文 なし
3.私の所感:分析、無駄だった点・失敗だった点
【英語】
・総合力はある。しかし、皆、得点できる文法がいまひとつ。
間違えた問題は、anyの用法、時制、can Iの用法だった。
使用している文法問題集「そこが知りたい英文法」を見ると時制の問題しか説明がなかった。
しかし、学校で参考書としている「総合英語Forest」では、anyの用法と、can Iの用法が解説されていた。
また、内容理解の内容合致の問題(選択式)に失点があった。現代文があまり得意でないことに関係しているのだろう。
【数学】
・全体で7割5分超えたのはよくぞという感じ。
・計算がからむ図形問題(図形と計量分野)は8割5分と頼もしい。
・しかし、小問のところで失点している。
式の値では、理解していないところがあった。
命題と論理では、基本的にわかっていなかったところがあり、ひねられて間違った。
2次関数の定数の範囲を求める問題でも、理解が足りていないところがあった。
確率〔大問〕では、最後の問題が条件付き確率であることが見抜けなかった。
2次関数〔大問〕では、パラメータ範囲の単純な計算ミスで痛恨の12点も失点した。最後の問題は全く歯が立たなかった。
図形と計量・円に内接する四角形〔大問〕では、最後の問題は全く分からず歯が立たなかった。
・2次関数の問題は、難易度が高くなってくると、場合分けとイメージを掴むのが難しいようだ。難易度をあげて鍛錬をつんでいく必要がある。
【国語】
・現代文では、小説がことのほかできていた。他人の意をくまない性質なのに不思議なものだ。
それに対して評論文は…
小林秀雄の文章だから仕方ないのだろうか。今回、出題されたのは「中庸」。
平成25年の大学入試センター試験では、突如「鐔(つば)」が出題されたとのこと。
昭和の時代、小林秀雄は出題されていたが、平成になってからはなかったようだ。
小林秀雄の代表作は、「ドストエフスキイの生活」、「無常といふ事」、「モオツァルト」、「ゴッホの手紙」、「近代絵画」、「考へるヒント」、「本居宣長」など。
正直、難しいと思う。今回の出題文は大人の私が読んでも、一読目は何をいわんとしているか分からなかった。
駿台としては、センター試験で小林秀雄が出題されたこと期に、難文挑戦を復活させたのだろうか。
息子の得点だが、問3傍線部理由説明(記述)75字以内(7点/10点満点)はたまたまか7割と良い点がとれていたものの、息子の解答文章を見て見ると何をいいたいのか分からない文章だった。キーワード的表現が入っていたら加点式で点数をもらえるのだろうか。
・古文は、文法は良くできた。また、現代語訳もできた。
しかし、それ以外の語彙や理由説明(選択も記述も)は散々な結果だった。
本文内容は現代語訳を見ると、夫婦間の感情と姑の感情がからむものだったので、その辺に疎い息子には厳しいだろうし、また興味もないだろう。
息子の実際の解答を見ても、全く的外れで、言いたいことがわからなかった。
邪推ではあるが、すぐ分かる内容だと、皆、解けてしまったテストにならないのだろう。
しかし、どうせなら、大人になってもあの時読んだなーとか、参考になりそうな内容の文章だといいように思う。
・漢文は、現代語訳はできているが、文法事項(返り点、書き下し文)や内容説明もできが悪かった。
文法事項は完成していないからだと思うが、早急に完成させる必要がある。
今回の内容は、国を治める人間は一族など宮中に限って営みを追求し恵みを施すのでなく、広く人民にも恵みを施した方が良い、との内容だった。この程度の内容ならば、小さい子供でも分かりそうなもので、もっと実のある内容を取り上げてもいいと思う。
ただ、国語として内容把握を問題とする場合、内容の程度が同じであれば、現代文<古文<漢文の順に難易度が上がると思われる。古文、漢文はいわば外国語みたいなものと考えてもいいので、漢文の内容把握が一番とっつきにくいのかもしれない。
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋
【駿台模試】内容と対策:関連ページ
・高1:第1回H25.6.9
・高1:第3回H26.2.2
・高2:第1回H26.6.8
≪他のページ≫
・現代文勉強法の考察~各問題集を巡って~【田村のやさしく語る現代文】編
・現代文勉強法の考察~各問題集を巡って~【現代文のトレーニング入門編】編
・【現代文の勉強法01】要約力、文章構造分析力、アイデア創造の発問力の強化-日本語能力試験N2編(1) 問題10(1)
・【東大理系数学】過去問における必須解法・手法の逆算分析~網羅系問題集の該当例題~
・【大学への数学1対1対応の演習】の使い方・勉強法-直観力鍛錬と問題構造分析-数学Ⅰ数と式 例題8
・【能力開発】図形センスを磨き、難問を制覇する-高校への数学「レベルアップ演習」編§7合同&線分比・面積比-
・【システム英単語勉強法】600語を20日間で記憶するためにエクセルを活用した覚え方
・【英語多読】目指せ!大学受験の英文読解で100万語!
★美術展・街歩きのページ
★私の読書メーター(全記録)
★読書日記(受験本)
★ウェブ記事セレクション(H27.1~)
★ウェブ記事セレクション(H26.6~12)
★ウェブ記事セレクション(H26.1~6)











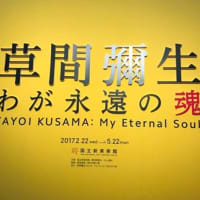






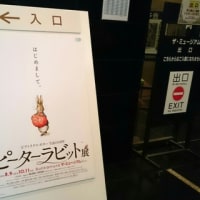

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます