東大理系数学の問題は、一筋縄では行かないと言われているが、それは、解答において、数種類の解法・手法が組み合わされて併存していることが大きな要因であると思う。
このことから、過去問の解答というゴールから、必要となる解法・手法を、逆向きに、各年毎の設問について調べてみたい。
その手順は、
1、模範解答をじっくり吟味する。
1、必要となる解法・手法を同定する。
1、網羅系と呼ばれる問題集で、とりあげられているかどうかを調べる。
1、その解法・手法を知っていることだけでそのまま解けるか、それとも、さらなる別な工夫等が必要となるかどうかを考える。
※当面は、確率、整数、極限等の証明問題等で、典型解法・手法が通用せず、個別的な考察によるもの、または、著しく難易度の高いものは、見送る。
注)略称
1対1:1対1対応の演習(東京出版)
青チャ:青チャート(数研出版)
黒大数:大学への数学(研文書院)絶版
---------------------------------------------------------------------------
★平成20年
【第1問】
座標平面の点(x,y)を移す移動をfとする時、移動される点、直線が描く直線について
(1)移動直線の、x,yの位置の数列による表示
1対1 B 数列 12 p67
青チャ B 数列 121 p185
黒大数 Ⅱ&B 数列 B728 p337
(2)(1)で数列表示された直線により定まる領域の図示
~前半部分~
1対1 B 数列 10 p65
青チャ B 数列 123、124 p188、189
黒大数 Ⅱ&B 数列 B725 p334
~後半部分~
いずれも該当なし。
⇒自ら考える。
【第3問】
(1)正8面体を台に置いて、真上から見た図の描画
いずれも該当なし。
⇒自ら考える。
(2)正8面体の平行な面の重心同士を通る直線を軸に、回転させた時の立体の体積
※関係 1対1 Ⅲ 微積分編 積分法(体積・弧長) 11 p138
他は、いずれも該当なし。
【第4問】
放物線y=x2と放物線上の2点及びその中点のy座標について
(1)2点の長さとその傾きでhを表す。
易問なので、略。
(2)2点の長さを固定した時の、hの最小値。
1対1 Ⅲ 微積分編 微分法とその応用 7 p42
青チャ Ⅲ 微分法の応用 160、161 p258、259
黒大数 Ⅲ&C 微分法の応用 B606、607、608 p226、227、228
【第6問】
媒介変数表示された曲線が囲む面積
※関係 1対1 Ⅲ 微積分編 積分法(面積) 11 p114
青チャ Ⅲ 積分法の応用 重要245 p388
黒大数 Ⅲ&C 積分法の応用 B804 p317
---------------------------------------------------------------------------
★平成21年
【第4問】
(1)円柱の回転体(aをパラメータに含む)の、xyz空間における、x≧0内の共通部分の体積
1対1 Ⅲ 微積分編 積分法(体積・弧長) 11 p138
青チャ Ⅲ 積分法 重要263 p404
黒大数 Ⅲ&C 積分法の応用 B808 p321
(2)円柱の回転体(aをパラメータに含む)の、a→∞の極限値
1対1 Ⅲ 微積分編 積分法(体積・弧長) 11 p138
青チャ Ⅲ 積分法 重要263 p404
黒大数 Ⅲ&C 積分法の応用 B808 p321
+長方形の面積による近似式
+はさみうちの原理を用いて極限値を求める
【第5問】
(1)xの1次式のべき乗の不等式の証明
1対1 Ⅲ 微積分編 微分法とその応用 15 p50
青チャ Ⅲ 微分法の応用 178 p282
黒大数 Ⅲ&C 微分法の応用 B631 p248
(2)ある小数値のべき乗に関する不等式の証明
式変形+場合分け
1対1 Ⅲ 微積分編 微分法とその応用 15演習題(イ)(2) p50
青チャ なし
黒大数 なし
【第6問】
三角形の内部の3点のベクトルについて、時刻ごとに直進させて
(1)内部の点の距離が≦1の時の、なす角をθとした時のsinθの不等式
いずれも該当なし。
⇒自ら考える。
(2)なす角を3つ定義した時の、2つのなす角の和の範囲
いずれも該当なし。
⇒自ら考える。
(3)ある時刻に内部の点の距離が≦1が成立した時、ある時刻Tに≦3が成立することの証明
いずれも該当なし。
⇒自ら考える。
---------------------------------------------------------------------------
★平成22年(2010年)
【第1問】
(1)回転体の体積の考察
(2)上記体積(多変数関数)の最大・最小
~前半部分~
1対1 Ⅰ 2次関数 14 p47 予選決勝法(1文字固定法)
青チャ Ⅰ 2次関数 重要83 p129 予選決勝法(1文字固定法)
黒大数 Ⅰ 2次関数・2次不等式 B319# p117 予選決勝法(1文字固定法)
~後半部分~
1対1 Ⅱ 微分法とその応用 2 p115
青チャ Ⅱ 微分法 206 p304
黒大数 Ⅱ&B 微分・積分 B618 p260
【第2問】
(1)定積分と不等式
1対1 Ⅲ 曲線・複素数編 数Ⅲ総合演習 9(2) p84
1対1 Ⅲ 微積分編 積分法(数式) 1(2) p74
青チャ Ⅲ 積分法 重要232 p361
青チャ Ⅲ 積分法 基本204 p320
黒大数 Ⅲ&C 積分法の応用 B831 p341
黒大数 Ⅲ&C 積分法の基礎 B703(1)(2) p281
(2)式変形(定積分、数列)の考察
【第4問】
(1)座標平面上の座標から三角形の面積を求める。
1対1 Ⅱ 座標 5 p84
青チャ Ⅱ 図形と方程式 87 検討 p131
黒大数 該当なし
(2)曲線(1次関数と2次無理関数の和)とy=xとで囲まれる図形の面積(定積分)
平面図形としての面積の相同に関する考察+
1対1 Ⅲ 微積分編 積分法(面積) 6 p109
青チャ Ⅲ 積分法 240 p375
黒大数 該当なし
【第6問】
(1)四面体の頂点から1面に下した垂線の足のベクトル
間接的に関係
1対1 B 空間のベクトル 3 演習題(2) p36
青チャ B 空間のベクトル 66 p102
黒大数 Ⅱ&B ベクトル B826 p387
(2)四面体の平面による切り口の面積(1辺の内分比 tがパラメータ値)
~前半~
1対1 B 平面のベクトル 1 p8
青チャ B 平面上のベクトル 36 p60
黒大数 Ⅱ&B ベクトル B807 p370
~後半~
四面体の切り口の面積をパラメータ値により場合分け
(三角形の相似比を用いて)
(3)(2)の面積の最大値
間接的に関係
1対1 Ⅰ 2次関数 7 p40
青チャ Ⅰ 2次関数 74 p118
黒大数 Ⅰ 2次関数と2次不等式 B311 p109
❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋
≪他のページ≫
★美術展・街歩きのページ
★私のTwitter
★私の読書メーター(全記録)
★読書日記(受験本)
・現代文勉強法の考察~各問題集を巡って~【田村のやさしく語る現代文】編
・現代文勉強法の考察~各問題集を巡って~【現代文のトレーニング入門編】編
・【現代文の勉強法01】要約力、文章構造分析力、アイデア創造の発問力の強化-日本語能力試験N2編(1) 問題10(1)
・【大学への数学1対1対応の演習】の使い方・勉強法-直観力鍛錬と問題構造分析-数学Ⅰ数と式 例題8
・【能力開発】図形センスを磨き、難問を制覇する-高校への数学「レベルアップ演習」編§7合同&線分比・面積比-
・【システム英単語勉強法】600語を20日間で記憶するためにエクセルを活用した覚え方
・【英語多読】目指せ!大学受験の英文読解で100万語!
【駿台模試】受ける意味と対策勉強内容:関連ページ
・高1:第1回H25.6.9
・高2:第1回H26.6.8











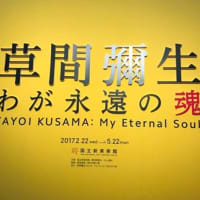






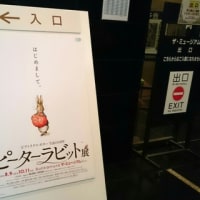

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます