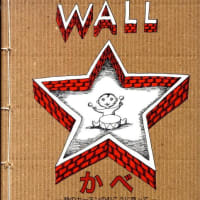富岡多恵子編『釈迢空歌集」を読みふける。
お多恵さんに、「釋迢空ノート」なんて詩人論があるのは知らなかった。
釋迢空とは、まだ中学生のころ、犀星の『わが愛する詩人の伝記』と、太宰への散文詩風の追悼文で出会い、その呪文のような詩の不思議な調べにはまった。
エッセイも素晴らしい。谷崎の女たちと、自分の姉たちの思い出を重ねた文章は、いい文章だった。
折口信夫『歌の話・歌の円寂する時』も読み進む。
冒頭の「歌の話」は児童向けで、『歌・俳句・諺』というタイトルの、高浜虚子・柳田国男との共著だったそうだ。
高浜虚子はどうでもいいが、この豪華な取り合わせ。こんな時は戦前の小中学生がうらやましい。
「女流短歌史」では、折口は晶子になかなか手厳しい。
「歌の円寂する時」は、何度読み返してもいい文章だと思う。夢枕獏の『陰陽師』に今さらながらはまっている身には、こんな文章が突き刺さる。
何物も、生まれ落ちると同時に、
「ことほぎ」を浴びると共に、
「のろい」を負って来ないものはない。
「短詩国の日本に特有の、読者のいない文学」というフレーズも、印象に残った。
「心をつなぐ左翼の言葉」の辻井喬さんが本当に言いたかったことも、そういうことではないのかなと思ったりした。
折口は厳しい学究の徒であるがゆえに、「歌人における学問ばやりの傾向」を憂えている。
文学の絶えざる源泉は古典であったとしても、「宗匠的な態度」「啓蒙知識の誇示」にとどまるのか。
先輩の跡をたどりながらも、若きがゆえの賚(たまもの)なる鮮やかな感覚を自由に迸らそう、となぜ努めないのか、と。
若き日のこの歌論は、「短歌否定論」といわれながら、歌人・釈迢空自身は、一生涯歌うことをやめなかった。
われ歌う、故にわれあり。
歌とはこの世に生まれいでたことに対する「ことほぎ」であると同時に、この世に生きなければならない「のろい」でもある。
どうして歌うことをやめることができるだろう。
「歌の話」では、少年少女たちに向けて、文学の力とは、自分の経験をいつまでも忘れずに握りしめ、それを機会があれば文章に表す能力のことだと折口はいっている。
「物を単純に考える人は、
悲観的だ涙脆い気持ちだといって、
いけないものとしているが、
人間はいつもにこにこ笑っているものばかりの
ものではありません。
さびしく或は悲しい気持ちになった時に、
はじめてほんとうの自分というものを考えてみるものです。」
もはやどんな言葉も通用しない、自己の「死」の極北をくぐり抜けない限り、「歌」も「思想」も「左翼も、よみがえることなんてできないだろう(絶望するにも知性が必要なのさ)。
お多恵さんに、「釋迢空ノート」なんて詩人論があるのは知らなかった。
釋迢空とは、まだ中学生のころ、犀星の『わが愛する詩人の伝記』と、太宰への散文詩風の追悼文で出会い、その呪文のような詩の不思議な調べにはまった。
エッセイも素晴らしい。谷崎の女たちと、自分の姉たちの思い出を重ねた文章は、いい文章だった。
折口信夫『歌の話・歌の円寂する時』も読み進む。
冒頭の「歌の話」は児童向けで、『歌・俳句・諺』というタイトルの、高浜虚子・柳田国男との共著だったそうだ。
高浜虚子はどうでもいいが、この豪華な取り合わせ。こんな時は戦前の小中学生がうらやましい。
「女流短歌史」では、折口は晶子になかなか手厳しい。
「歌の円寂する時」は、何度読み返してもいい文章だと思う。夢枕獏の『陰陽師』に今さらながらはまっている身には、こんな文章が突き刺さる。
何物も、生まれ落ちると同時に、
「ことほぎ」を浴びると共に、
「のろい」を負って来ないものはない。
「短詩国の日本に特有の、読者のいない文学」というフレーズも、印象に残った。
「心をつなぐ左翼の言葉」の辻井喬さんが本当に言いたかったことも、そういうことではないのかなと思ったりした。
折口は厳しい学究の徒であるがゆえに、「歌人における学問ばやりの傾向」を憂えている。
文学の絶えざる源泉は古典であったとしても、「宗匠的な態度」「啓蒙知識の誇示」にとどまるのか。
先輩の跡をたどりながらも、若きがゆえの賚(たまもの)なる鮮やかな感覚を自由に迸らそう、となぜ努めないのか、と。
若き日のこの歌論は、「短歌否定論」といわれながら、歌人・釈迢空自身は、一生涯歌うことをやめなかった。
われ歌う、故にわれあり。
歌とはこの世に生まれいでたことに対する「ことほぎ」であると同時に、この世に生きなければならない「のろい」でもある。
どうして歌うことをやめることができるだろう。
「歌の話」では、少年少女たちに向けて、文学の力とは、自分の経験をいつまでも忘れずに握りしめ、それを機会があれば文章に表す能力のことだと折口はいっている。
「物を単純に考える人は、
悲観的だ涙脆い気持ちだといって、
いけないものとしているが、
人間はいつもにこにこ笑っているものばかりの
ものではありません。
さびしく或は悲しい気持ちになった時に、
はじめてほんとうの自分というものを考えてみるものです。」
もはやどんな言葉も通用しない、自己の「死」の極北をくぐり抜けない限り、「歌」も「思想」も「左翼も、よみがえることなんてできないだろう(絶望するにも知性が必要なのさ)。