「後藤奇壹の湖國浪漫風土記」に、ようこそおいでくださいました
今回の園城寺余話は、馬場町遊廓(ばんばちょうゆうかく)についてご紹介したいと存じます。

西日本最大の風俗街としてその名を欲しいままにした雄琴(おごと)が大津に位置することは今でも多くの人が知り得るところ。
しかし、かつて大津に国内有数の遊廓(ゆうかく/公許の遊女屋を集め周囲を塀や堀などで囲った区画)が戦後間もない頃まで存在したことは以外と知られていません。
この地に遊廓が設けられた確たる時期は判然と致しませんが、大津宿に隣接して、江戸時代初期に現在の長等3丁目辺りに整備されたものと思われます。延宝6(1678)年に藤本箕山によって著された『色道大鑑』によれば遊廓は全国で25箇所存在し、ここはそのうちの1つとされています。
とはいえ「宿場町に隣接しているとはいえ、何故園城寺の門前町に?」という下衆な詮索をせずにはいられません。

またこの界隈は柴屋町(しばやまち)とも呼ばれ、柴屋町遊廓とも称しました。
その他にも大津宿周辺には、真野(長等1丁目)・四の宮(京町3丁目)・稲荷新地(松本2丁目)にも遊里は存在しました。
ですが、井原西鶴の『好色一代男』にも登場するこの遊廓は、当時“東の吉原、西の柴屋町”とも言われる程の格式と隆盛を誇っていたようです。
街の東西南北の入口に大門を設け、最盛期には廓内に約30軒の遊女屋が存在しました。

明治以降、芸娼妓解放令の発令、内務省令娼妓取締規則の制定、そして大東亜戦争後のGHQの公娼制度廃止と様々な規制が成されるものの、バーやスナック、料亭などと看板を変え、遊廓はほぼそのまま赤線の通称で呼ばれて存続しました。
しかし、昭和33(1958)年4月1日に施行された売春防止法。昭和46(1971)年に開業したトルコ風呂(現在のソープランド)“花影”を皮切りとする雄琴温泉の風俗街化が、この花街の衰退を決定的なものとしてしまいました。
流石に江戸時代の建物は残っていませんが、近世から近代へと移行した時期の花街の情景を今でも色濃く残しています。
つい最近まで大津スチームバスセンターというソープランドが存在し、花街の残り香的存在として君臨していましたが、近年廃業し、現在は料理屋が建っています。

かつて隆盛を誇った馬場町遊廓も、都市開発の波に押され、そのよすがは今や風前の灯です。
遊廓・遊里・花街の話題はとかく忌むべきものとして排除されがちですが、かつての日本の文化の一端としてその足跡だけでも残して欲しいと思うのは小生だけではないと思います。
(園城寺余話、続くかな?・・・)












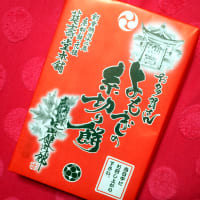







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます